2014/07/10 石川文洋「戦場カメラマン」(朝日文庫)-1
1972年のパリ会談のあと、アメリカ軍の撤退が発表される。それと軌を一にして、北ヴェトナム政府が西側諸国のジャーナリストを招待した。その一員になったことから、しばらく南ヴェトナムの取材が許可されなかった。再訪したのは、1975年のサイゴン陥落以降。それからしばらくの間、ヴェトナムとカンボジア、ラオスは鎖国状態になり、一般観光客はもちろん政府関係者でも入国する機会が少なかった。記者は数少ない訪問可能な記者だった。このルポにあるカンボジア大虐殺の報道は、この国ではほとんど最初のものではなかったかな。

ベトナム解放とその後 ・・・ 1975年、1985年の再訪。社会主義になったヴェトナムのレポート。どうしても取材の制限があるので、先方の見せたいものしかみることができない。やはり南ヴェトナムの軍人、華僑などが社会的に不適合を起こしているみたい。こういう階層がボートピープルになっているようだ。あと、1984年時点では、製造業サービス業が不十分で、若者の失業率が高いようであるという。
ベトミン軍旧日本兵の帰還沖縄 ・・・ 沖縄出身で昭和19年に徴兵。カンボジアに派遣され、その後ヴェトナム解放戦争に参加した旧日本兵。長らくヴェトナムで仕事をしていたが、1977年ころにヴェトナム政府から帰国要請(ほとんど命令)がでた兵士の半生を概略。
ベトナム・カンボジア国境紛争 ・・・ 1978年に中国の支援するポル・ポト政権にたいし、ヴェトナム軍が進攻し、親ヴェトナム政権をカンボジアに樹立した。このとき、カンボジア革命軍が自国内のヴェトナム人を虐殺した報道があり、その検証にいった。
中越戦争 ・・・ 1979年中越戦争の停戦会談のルポ。これもまた共産主義者を震撼させた事件で、動揺した。前年に中国の支援するカンボジアのポル・ポト政権をヴェトナム軍が倒したので、その報復とみなされている。戦争に習熟したヴェトナム軍は地方軍と民兵で中国の人海戦術に勝利した。
カンボジア大虐殺 ・・・ 1980年の虐殺検証の旅。カンボジアの国民はロン・ノル政権時代700万人といわれていたが、ポル・ポト打倒後には400-450万人とされた。若者、知識人、技術者が優先的に殺された。あまりに陰惨な内容は個々に書き写せない。この情報はヴェトナム経由で伝えられたが、このルポの出た当時、社会主義者・共産主義者はデマとみなしていた。
アンコール・ワットへの道 ・・・ カンボジアの遺跡アンコール・ワットは1970年から封鎖。その後の鎖国政策で観光することができなくなった。観光再開後の最初の訪問。1980年6月。多くの仏像の顔が盗まれたと書いてあるが、それは頭部を切断することで異教の神を象徴的に殺したのだ。顔を削られたり切断されたりした仏像や神像はボロブドゥールでもみることができるし、タリヴァンも行った。
戦場のカメラマンたち ・・・ ヴェトナム戦争を取材した記者やカメラマンの記憶。取材中に亡くなった沢田教一(「泥まみれの死」講談社文庫))、嶋元啓三郎、一ノ瀬泰造(「地雷を踏んだらサヨウナラ」講談社文庫)の三氏の追悼文を含む。戦場を駆け回ったということで、同士というか戦友のような特別な感情、連帯感をもつらしい。
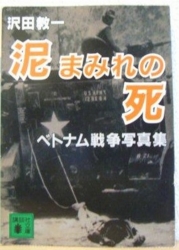

それに東南アジアの国々の関係が分かりにくいのは、どうやらそれぞれの民族が互いに憎悪と差別の感情をもっているらしいこと。それこそ三国志の昔から中国はヴェトナムへの侵略、支配を繰り返してきたし、東アジアから東南アジアにかけては商業・生産資本を華僑がほぼ一手に独占していて国外に移動しているから地元に還元しないで資本は蓄積しないし(経済成長が抑えられている)、複数の宗教があって互いの宗教に不寛容であったりしたし、とどうにもややこしい関係がある。ホー・チミンは中国に悪感情をもっていたし(生井英考「ジャングル・クルーズにうってつけの日」ちくま学芸文庫)、ヴェトナムはカンボジアを実効支配しようとしてカンボジア人を差別していたし、カンボジア人は対抗するようにヴェトナム人を憎悪していたし。さらに高地の少数民族がいるとなっては、その関係の複雑さはその場所にいないし、とりあえず直接の利害関係を持たないわれわれのような読者からするとなんともわからない。それがこの本の後半にある戦争と虐殺のわかりにくさになっている。
この地域では、たしか過去数百年は民族間の憎悪が戦争になり、虐殺になるほどまでには高まらない時代であったのではないかと思う(それ以前に民族間や宗教間の戦争や虐殺が頻発していた)。そういう多民族共存の優れた実績があったのが崩れたのは、19世紀にフランスが植民地支配をして、少数の人々を優遇し、大多数を差別するようになってからか。月並みな感想しかないが、民族が独立していること、主権をもっていることが戦争や虐殺を回避する方法なのだなあと思う。われながら浅はかであるが、それ以上を考えていないので、ここまで。お笑いください。

