2016/02/01 大江健三郎「洪水はわが魂に及び 上」(新潮社)-1
2016/01/29 大江健三郎「洪水はわが魂に及び 上」(新潮社)-2
2016/01/28 大江健三郎「洪水はわが魂に及び 下」(新潮社)-1
の続き。
発表された1973年には、「自由航海団」の無軌道かつ暴力的な行動が連合赤軍のいくつかの事件との類比で語られたようだ。作家によると、小説の発想は1972年冬の事件の前であり、関係はないという。むしろ現実の事件が小説の構想通りに進むのに、唖然としたそうだ(どこかのエッセイかインタビューでいっていた)。
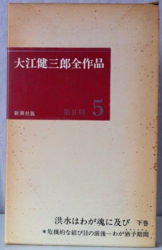
まあ実際に、「自由航海団」は連合赤軍ほかの左翼組織とは違う。
1)組織のビジョンやミッションは必ずしも共有されていない。「世界の大崩壊」のときの「自由」な活動と国籍離脱したの外洋「航海」まで。構成員はそれぞれのビジョンを積み重ねて、好き勝手なイメージをもっている。多麻吉はライフルによる銃撃戦に取りつかれ、「ボオイ」と「赤面」はクルーザーの設計と運転に夢中で、伊奈子は性的な解放をめざし、という具合。リーダーはメンバーの勝手な意味づけを放置している。
2)強力なリーダーシップと上位下達の権威主義組織にはなっていない。喬木はビジョンとミッションを示すのに優れているが、現実の問題解決を引っ張るリーダーシップを持っていない。とくに「縮む男」の査問とリンチにおいて。「縮む男」の裏切りにたいして激しい怒りを持つのは多麻吉であり、暴力をふるうのであるが、喬木は制止しない。籠城戦の最終局面においても、「自由航海団」の説明のために投降しろという多麻吉の提案を受け入れる(最後に残ったのは多麻吉と勇魚の二名)。局面において、特技を持つ専門家の意見を尊重し、リーダーであっても覆すことはできないし、リーダーも命令できない「民主的」な組織。
3)「縮む男」が査問されるのは、本人がそうされたいという思惑に基づく。きわめて些細なふるまいや語りによって、あるいはリーダーの気まぐれで拘留や査問が行われたのではない。そのうえ、「縮む男」は弁明の機会をもたされ、喬木などはむしろ査問するよりも「縮む男」の回心を望む風でもあった。結果として、「縮む男」は死を迎えたが、傍目には他人の手を借りた自死とも思える奇妙な死であった。
連合赤軍事件の詳細や意味づけなどはパトリシア・スタインホフ「死へのイデオロギー」(岩波現代文庫)のエントリーなどを参照してください。
パトリシア・スタインホフ「死へのイデオロギー」(岩波現代文庫)-1
パトリシア・スタインホフ「死へのイデオロギー」(岩波現代文庫)-2
とまあ、新左翼批判、連合赤軍事件批判としてこの小説を読むのはできなかった。むしろカルト教団の暴走とかストックホルム症候群あたりに思いを向けたほうがよいかもしれない(wikiによると、ストックホルム症候群のもとになった事件が起きたのは1973年8月のことで、この小説はそれに先んじているのか!)
昭和40年代のこの国の若者の運動(全共闘運動など)は、存在革命・政治革命・文化革命の3つのモチーフをもっていたと自分は考える。それに照らせば、「自由航海団」と大木勇魚の運動はもっぱら存在革命にフォーカスしていて、その神秘主義的なあり方に執着していたようだ。世界の崩壊の予感と自分の生の終わりの可能性が同じくらいに重要になっていて、その間にある人々とか社会とか公共などは不問。あるいは嫌悪するか排除するべきもの。なので、政治革命にはほぼ無関心で、文化革命でも他者の啓蒙や意識変革には興味を持たない。なるほど、達成不可能なビジョンやミッションをもって、現実では絶対に実現しない「夢」に向かって自らのあり方をかえていこうというのはロマン主義そのもの。「自由航海団」と大木勇魚の運動はあらかじめ挫折することになっているわけだ。このロマン主義においては、全共闘などの当時の若者の運動と共通するところはあっただろう。詳細をみれば、一致点はほぼなくて、やはりカルト運動に見えてくる。
あとは、いくつかの文学作品の引用が小説のテーマにかかわっているところ。外洋にでる「自由航海団」のために勇魚が英語を教えるが、テキストにしたのがドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟」であり、その「prayer」に関する記述が、のちの自由航海団放送のコールサインに使われる。祈ることを忘れるなというメッセージは、作者の解説がなければ伝わりにくそうであるが、どこかのエッセイで解説していたと思う。
タイトルは旧訳聖書ヨナ書2章5節から。魚に飲まれたヨナが腹の中からその神、主に祈った言葉。
「2:4 わたしは言った、/『わたしはあなたの前から追われてしまった、/どうして再びあなたの聖なる宮を望みえようか』。/2:5 水がわたしをめぐって魂にまでおよび、/淵はわたしを取り囲み、/海草は山の根元でわたしの頭にまといついた。(略)2:9 しかしわたしは感謝の声をもって、/あなたに犠牲をささげ、わたしの誓いをはたす。/救は主にある」。/2:10 主は魚にお命じになったので、魚はヨナを陸に吐き出した。」
口語訳聖書 - ヨナ書
このモチーフも上記の指摘に一致する。「あなたに犠牲をささげ、わたしの誓いをはたす」という自己回心、ないし存在の革命が「主」との回路を開き、救済につながるというところ。「文学ノート」新潮社の「消すことによって書く」によると、「かれの最後の聴覚に響くはずであった声の響きは(略)ヨナ書の、鯨の腹の中からの祈りの声の、ある凛凛たる響きを聞き取っている模様なのである(P155)」という。大水にあって沈みつつあって祈る者、そのような彼の魂の強い叫び声。
「すべては宙ぶらりんで、そのむこうに無が露出している。「樹木の魂」「鯨の魂」にむけて、かれは最後の挨拶をおくる、すべてよし!あらゆる人間をついにおとずれるものが、かれをおとずれる。(文庫下巻P299-300)」
(上掲の「文学ノート」によると、ヨナ書をもとにした詩編を小説家は最初にイメージしていたとのこと。
「69:1 神よ、わたしをお救いください。/大水が流れ来て、わたしの首にまで達しました。/69:2 わたしは足がかりもない深い泥の中に沈みました。/わたしは深い水に陥り、/大水がわたしの上を流れ過ぎました。/69:3 わたしは叫びによって疲れ、わたしののどはかわき、/わたしの目は神を待ちわびて衰えました。」
口語訳聖書 - 詩篇
うーん。世界の破滅が神や主の怒りによるもので人間の回心が危機の回避になるというのであれば祈りを忘れまい、真摯に祈ろうというのは破滅に抗するためのスローガンになるだろう。でも、核や環境汚染や戦争などの人間の愚かしさや人間の作ったシステムエラーによって予想される危機に対して皆で祈ろう、宇宙的な意志と交感しようというのは、さて危機回避の方法として適切なのだろうか。民主主義やセイフティネットなどの人間の作ったツールをできる限り使用するほうが先なのではないかなあ。
作者は、大木勇魚という社会から離れた三十男の目で見ることで、新しい自分になるように自律的に自己批判するものの魂の響きを読み取って、勇魚を社会化することを期待しているようだ。そこまでにはいたらず、むしろ自分が20歳頃に読んだ時のように、死の可能性に自ら飛び込み、社会の暴力に抗いながら大水と銃弾にまみれながらも「すべてよし」と充実感にまみれながら死に至るというヒロイズムと自己犠牲に酔ってしまうのではないかな。そのように生きえない自分の代わりに勇魚が死ぬことで、彼に感情移入した自分のありさまを棚上げにする踏み台にしてしまっているのかもしれない。
(ここは思いつきなのだけど、「洪水は我が魂に及び」のラストシーンは、三島由紀夫「豊饒の海」とくに4作目の「天人五衰」のネガないし批判であるのかも。最後に現実に敗北した末に純粋天皇を幻視して法悦境に入るのに対し、世界と生に「すべてよし」の全肯定を投げかける。まあ、三島由紀夫「豊饒の海」を読む気持ちはないので、あくまで妄想レベルということで。)