1958年を同時代としてみる。そうすると、敗戦から12年、占領開放から5年を経過している。この国は自立して戦争の債務を返すために若く健康になっているはずであった。とはいえ、朝鮮戦争から占領軍は名前を変えてこの国に駐留し、保守政党は占領軍の顔色を窺っていて、野党は教条化した社会主義運動の狭隘な道に押し込まれている。若くて健康どころか、不正と詭弁のまかり通る世界。自由や友情の「市民」生活を送るどころか、拘束と孤独に覆われて縮こまって青年は退屈に生きている。その象徴が「絶望あそび」と「拷問あそび」だ。
なぜなら、その時代の若者は決定的な瞬間に立ち会うことができなくなった「遅れてきた青年」だから。彼らが夢想するのは戦争の時代に灼熱するような苦痛を体験して死ぬこと。その一瞬の時に、青年の生まれてきた価値と意味が輝きわたり、永遠を獲得するから。そのような死にかたをできたのは、彼ら若者の兄や父の世代。でも生き延びた兄や父の世代は、あの至高の時代の輝きを持っていない。すっかり消耗しているか、プチ市民のけちな生活に落ちぶれているから。ああ、遅れてきた青年にはもはや脱出の機会はない。

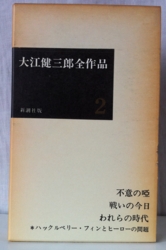
というのが、主人公のひとり南靖男23歳。たぶん東大の仏文科大学院に進学している。彼は級友や政治運動家とは関わらず、孤立している。上のような意識をもっているとき、大学のようなコミュニティにも学問の世界にも全霊を打ち込むほどの熱情を持てないからだ。かれは中年の外国人相手の娼婦のところに入り浸り、娼婦が仕事するとき以外はずっと性向している。退屈で自堕落な性交。それを逃れるすべはなく、彼が期待しているのはフランス政府の募集したフランス語論文の審査結果。トップの成績になれば、数年間のフランス留学と帰国後の助教授の道が開ける。それはあの至高の体験とは真逆のものであるが、このずぶずぶの日常から脱出する契機にはなるだろう。
そういう受け身な青年の夏のできごと(前作「芽むしり仔撃ち」の冬との対比が強烈)。淡い期待であった論文は一等になる。出発のまえに、ふたつの困難が現れる。ひとつは中年の娼婦・頼子が妊娠したこと。すでに数回の堕胎をしていて、もはや中絶できない。頼子は仕事をやめて靖男と所帯を持つことを望む。もうひとつは八木沢という民学同(民主主義学生同盟とでもいう学生運動団体というか秘密結社。全学連や共産党などの公式組織とは別の組織を構想)をつくる年下の運動家から紹介されたアラブ人(こうやって民族名で書くのは当時の著者のやり方)。アルジェリア出身で、解放闘争で家族を失っている男。現地を逃れて日本に来て現地の独立・解放闘争と連帯する組織を探している。彼の強烈な体験に靖男は影響される(小説中ではあまり書かれないが、アルジェリアの独立・解放闘争に靖男の夢想する体験があると思われたため。そこに行けば「遅れてきた」という意識から逃れられる)。
靖男に突然、脱出・連帯・妊娠が突き付けられる。影響されやすく、受け身の靖男は夏の日差しに焼かれながら、決断をしなければならない。「遅れてきた」という意識は、自分が主体的であることを要請しない。あの至高の体験ですら「天皇」の命令に応じることで、死の象徴である「天皇」の観念と合一しようというものだ。そこには自己懲罰や自己破壊の念望が入り込んでいる。だから靖男は自分が最も損をするような決断をする。とはいえ、この問題の突きつけは少しあとの20代後半に体験するものを比べれば、煩悶の度合いは少ない(などとそんな決断を迫られたことのない自分がいうのはおこがましいが)。とはいえ、彼の孤独孤立はさらに深まる(教授やクラスメイトは相手にしないし、金づるはなくなるし、アラブ人は強制送還されて最悪殺される可能性があるし)。靖男は孤独孤立の深みに置いて、唯一自分のもっている自由は自殺することだと観照する。生活においても、思想においても、青臭く、無責任で、他人の物言いの借り物だというしかない。でもそれが、1958年当時のインテリエリートの共感した自由と連帯の不可能性の問題。
2017/02/09 大江健三郎「われらの時代」(新潮文庫)-2 1959年に続く。