大杉栄は1884年生まれ。軍人の家庭に生まれたが、どうも子供のころから無鉄砲でやんちゃだったようだ。長じて陸軍幼年学校に入校したが、ここで権威に従えない自分を発見し、種々の問題を起こした挙句に放校となる。幼年学校で教師や同級生などとずいぶん角突合せ、喧嘩を躊躇しなかったようである。東京に出て外国語学校に通ううち、日露戦争前の騒然とした空気のなかで無政府主義に飲み込まれ(万朝報の報道と足尾鉱毒事件すなわち谷中村事件につよく影響される)、終生の思想とした。もともとは万朝報は反戦論に傾斜していたのであるが、開戦論に移った後、秋水・堺らとともに脱退し、「平民新聞」や「近代思想」などを創刊する。この自叙伝は大杉34歳の時に、雑誌「改造」に連載された。34歳で自伝を書くというのも豪儀。この自信はどこに由来するのかな。

以後、運動家としての活動を行うのであるが、当時のこととて6回検挙されて合計3年間の獄舎で過ごす。のちにパリでも投獄されるが、獄舎を故郷と思うくらいの余裕を持っていた。いまより人権意識の低い時代、囚人はひどい扱いを受けたわけではあるが、そこにも楽しみを見出している。獄中に起こる出来事は、のちのいくつかの監獄映画(「網走番外地」「暴力脱獄」「アルカトラズからの脱出」など)にみられるエピソードに酷似していて、なるほど監獄のシステムは似たようなものだと微笑ましい。それに一回入獄するごとに一つの外国語を習得するという目標を立てて、複数の言語の読み書きができるようになるというのも、生活の知恵か。出獄後は翻訳で食って行けたというのだし。まあ、このころにはひどい扱いを受けても、獄死するまでの危険はなかったのだから(それが1930年代になると、一気に生命の危機に直面するほどひどい処遇になる)。
あわせて、大杉は無鉄砲であると同時に、女好きでもあって、中学生のころから、幼なじみの多分いとこの「令子」に憧れるのも早熟であはあるが(いや明治のころであれば10代後半で結婚というのもざらであるから当然か)、活動家となってから複数の女性と三角関係に入る。結局、年下の若い女性と結婚するのであるが、直前まで付き合っていた年上の女性に就寝中に刺されるという事件を起こす(1916年、32歳の時)。事件の直前には、この三人が一緒に温泉旅行に出かけたりもする。若い女性を先に返した後の」刺した女性との会話が何とも秀逸で、恐ろしい。すなわち、
「しばらくして、彼女がやって来た。顔色も態度も、さっきとはまるで別人のように、落ちついていた。/『私、あなたを殺すことに決心しましたから。』/彼女は僕の前に立って勝利者のような態度で言った。/『うん、それもよかろう。が、殺すんなら、今までのお馴染甲斐に、せめては一息で死ぬように殺してくれ。』/僕はその『殺す』という言葉を聞くと同時に、急に彼女に対する敵意の湧いて来るのを感じたのであったが、戯談半分にそれを受け流した。/『その時になって卑怯なまねはしないようにね。』/『ええ、ええ、一息にさえ殺していただければね。』/二人はそんな言葉を言いかわしながら、しかしもう、お互いの顔には隠しきれない微笑みがもれていた。(P252)」
となる。この情念は自分の想像の範囲外。論評することもできず、それこそ乱歩の探偵小説にはありそうなどろどろさが実際にあったことに口をぽかんとあけるしかない。
さて、この国に社会主義が紹介された時には、アナキズムが先であった。なので、幸徳秋水、堺利彦、著者などの最初の社会主義者はみなアナキスト系の考えを持っている。しかし、1918年のロシア革命はボルシェビズムを優位にして、彼らより年下の人たちに熱烈に支持されたのだった。そこでこの国の社会主義者の間にはアナキストかボルシェビキかの論争もあった(アナボル論争というやつ。日本共産党が結成されたときには、古い社会主義者も参加したが、1年たたずに脱退した)。
1923年春にパリでアナキストの国際大会があったとき、大杉は視察を兼ねて洋行する。もとよりヴィザの出るはずもなく、中国人名を名乗っての密入国なのであった。1923年、フランスでは右派内閣が誕生。この本では詳細が分からないが、インフレと失業が進んでいたようだ。都会の貧困女性はミディネット(大杉は「裁縫女工」と訳している)がデモをしていた。当然それは官憲に弾圧にあうが、同時に男性による差別もみられる。大杉の報告。
「この紳士等の望み通りにミディネットに『往来をぶらぶら』させるためには、そしてやがてそれを本職にさせるためには、彼女等の賃金は決して上げてはならないのだ。/そしてこの紳士等の淑女は、往来やキャフェをぶらつく若い綺麗な女どもとその容色をきそうためには、決して子供を生んではならない。貧乏人の、あるいは乞食のような風をしたあるいは淑女のような風をした、どちらの女も、これまただんだん高くなってくるその生活のためには、決して子供を生んではならない。(P323)」
とはいえ、大杉が反差別主義であるかというとそうでもなく、パリや船中で安南人や中国人にあうと露骨に差別の言辞を吐く。時代の制約といえばそうなのだろうが、「内には民本主義、外には帝国主義」というのはこの人にも見られたのだった。
都度書かれた滞在記が「日本脱出記」にまとめられる。パリ近郊のメーデーで演説していることろを逮捕され、強制送還される。帰国は同年8月。9月に関東大震災があり、どさくさまぎれに憲兵によって妻と甥といっしょに虐殺された。享年39歳。
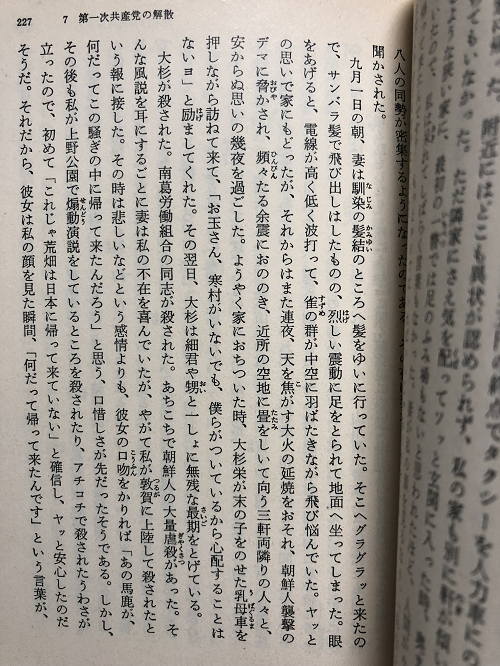
(荒畑寒村「自伝 下」から)
大杉栄の文章は21世紀に読んでも古びていない。この国の文体はいくつかの転換があったのだが、明治半ばころの言文一致運動がもっとも大きな変化をもたらした。大杉より前に生まれた人たちは、言文一致の文章を書くのに四苦八苦したものだが、彼が文学に熱中したとき(10代半ばころ)には、おおよそ文体が確立していた。それを読んでのせいか、大杉の文体は自在で若々しく、読みやすい。同時代の文章の中では、もっとも斬新ではないかな。内容よりも文体のほうに注意が向いた。(文体とか女性遍歴とかパリへの「脱出」などから、金子光晴を連想しましたよ。大杉は金子の精神的な兄でメンターのように思った。)
同じアナキストに堺利彦がいて、この人も自伝を書いている。ずいぶん昔に読んだので細部は覚えていないが、大杉ほどの自信はなかったように記憶している。あと、荒畑寒村も「自伝」をだしている。これらにあわせて、田中正造の論文集と荒畑寒村「谷中村滅亡史」を読むと、20世紀前半のこの国のアナキスト、社会主義運動の概略がわかりそう。