事務所で無聊を囲っているポアロのもとに電話がかかる。秘書のミス・レモン(「ヒッコリー・ロードの殺人」に登場)がとると、女声探偵作家のアリアドニ・オリヴァから「すぐ来て」とメッセージが入って、切れてしまう。ポワロはため息をついて、ロンドン近郊の田舎町に出かける。
その街には、フォリオット卿の邸があったが、夫と息子に先だたれ(先の戦争のため)、未亡人になった夫人がジョージ・スタッグス卿に屋敷と土地を売ったのだった。スタッグス卿には20歳の年の離れた妻ハティがいる。この妻、ファッションとジュエリーのことしか興味がなく、周りには頭が温かい人と思われている。入居して一年目、スタッグス卿は屋敷を開放して祭りをおこない、「殺人ゲーム」を開くことにした。参加者にカードを配り、どういう関係者かを教える。カードをもった参加者は屋敷の中にある手がかりを見つけながら、殺人現場に行き、犯人・方法・動機などをカードに書いて提出。あたった人には賞金を出すというもの。ゲームのスタッフは屋敷の勤め人にエキストラ(こういうゲームは今ではマネジメント研修に取り入れられている)。
さて、当日。ハティは屋敷の関係者の思惑に関係なく、ふらふらしている。そのうえ、近くのユースホテルから外国人観光客が勝手に屋敷に入るので、敷地内はごたごたしている。「殺人ゲーム」は難しすぎたか、参加者はうろうろ。ポワロも筋書きを描いた探偵作家とスタッフに問題がないかチェックすると、「死体」のあるボート小屋に行く。鍵のかかった部屋の中には、死体役の14歳の「少女団(と田村隆一はやくしているがガールスカウトのこと。訳出時にはこの国にはガールスカウト組織がなかったのか?)の女の子が扼殺されていた。なぜ数日前に選ばれた少女は殺されたのか。そのうえ、ハティは失踪し、数日後には少女の祖父にあたる爺さんが酒を飲んで足を滑らし、おぼれ死んでしまった。
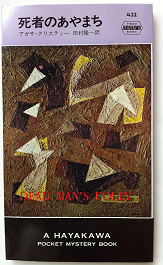
1956年作。このころには戦後復興問題は解決していたようだが、戦後は続いていた。この作品からすると、問題は貴族に起きていて、相続税や固定資産税などで貴族の生活はアップアップ。商才にたけている人はまだしも、そうでない場合、資産を売却しないと生きていけない。そこを付け込まれることがおきる。もうひとつは国境があいまいになって、人の移動が頻繁におきる。ここでは北欧の大学生によるバックパッカーの増加。貴族の敷地だったところにユースホテルができて、ホットパンツとTシャツ姿の若者は田舎者の眉を顰めさせる(ほぼ同時期のベルイマン監督「野いちご」にも若者のバックパッカー、ヒッチハイカーが登場していた)。そういう社会の変化が押し寄せてきたころ。
そういうのを背景にして、変形の劇場ものの探偵小説をやっている。なので、ポワロは劇場にあたるスタッグス家の楽屋を歩き回る。通常では警察の尋問などがつづくところが、ポワロと関係者とのおしゃべりになる。この会話が軽妙で、人物描写は少ないのに、キャラクターが見えてくるという優れた話術。その結果、スタッグスに憎悪と愛情を示すものがいるとか、ハティはその奇行で嫌われているとか、ハティも人嫌いがあるとみえて従兄には会いたくないと言い出すとか、屋敷の周辺の人はスタッグス卿の前のフォリアット家を懐かしんでいるとか、スタッグスも子供じみた軽挙妄動をするとかがわかる。死体が見つかるまでのおしゃべりのほんの一言が真相の手がかりになっているので、十分に注意して読むべき。
事件が起きて5週間目にはお宮入りとおもわれたが、もう一度村を訪れたポワロが死者の家族の話を聞くことで、真相に至る。なるほど、そちらの側が隠していたのですか。真相が個人の思惑にちんまりとまとまってしまうのが印象を薄くするのだが、意外性は十分。なぜ少女を殺したのかの理由の背後にあるもののどす黒さがよいです。
原題は「Dead Man's Folly」。Follyはあやまりとかバカげたことだけど、同時に「大金をかけたばかげた大建築」も意味する。建築家が自分の設計しなければならない建物をそう呼んでいた。さらに、Dead Manも誰をさすかで、二重の意味がある。都合4種類の解釈があるわけ。原題はみごとなダブル・ミーニング。日本語にすると凡庸になってしまう(でもほかに訳しようがない)。