原題「Death in the Clouds」は、創元推理文庫では「大空の死」、ハヤカワ文庫では「雲をつかむ死」、新潮文庫は「~~殺人事件」でまとめようとしたのかこのようなタイトル。cloudのダブルミーニングをどう汲むかがタイトルをつけるときのポイントになるが、邦訳すると間延びしてしまうね。くわえて21世紀には「クラウド」が新しい意味を持つようになったので、これも使えない。うーむ。といって別のアイデアがあるわけではありません。
訳者解説によると、パリ=ロンドン間の定期旅客便は1920年に運航を開始し、この小説の舞台になった飛行機プロミシュース号は実在するインペリアル航空会社のもの(この会社はギリシャ神話からとった名を飛行機につけていたという)という。ライト兄弟のグライダーにエンジンを載せただけの飛行機(1903年)が20年後には商業飛行に至っているのに驚く。この技術の可能性にかけた人たち数万人(適当な数字)がいっせいに開発競争すると、このスピードで進化するのだ。それが商業ベースに乗り、利用者が増え、知っている人が増えると、エンターテインメント小説は貪欲に消化する。これもそういう例(とはいえ、飛行中の機内での殺人事件というのは他に例があったかしら)。
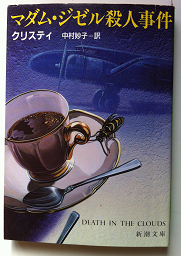
さて、この「マダム・ジゼル殺人事件(大空の死、雲をつかむ死)」1935年は前年の「オリエント急行の殺人」と対になった作品。後者が長距離列車のコンパートメントだったのが、こんどは飛行機の機内。どちらも移動中は人の出入りができず、容疑者は機内の客か添乗員に限られる。しかもどちらでも機内の客は不吉な数字の13人。うち一人が被害者で、もう一人が探偵(エルキュール・ポワロ)。被害者は金貸しのオールド・ミス「マダム・ジゼル」。列車は個人ごとの部屋が用意されているので、出入りは容易であるが、飛行機内では近づくのは難しい。奇妙なのは蜂が飛び(客のひとりが殺した)、吹矢の筒が見つかり、被害者の首元に刺された痕がついていたこと。そのうえ紅茶のスプーンが二本あった(結婚を意味するとか)。なんとも不可解な状況。でも、カーやクイーンなら舌なめずりするように詳細に描きそうな状況はほぼスルーされる。
かわりに被害者の女性にフォーカスする。彼女は捜査すると恐喝まがいのことまでして、がめつく金を儲けていた。巧妙な手口を駆使したらしく、マダム・ジゼルに金を借りていたり、脅迫されているような人は見当たらない。殺人の理由を持っていそうな人が見当たらない。多少関係ありそうなのは、彼女は若い時に娘を出産しているが、その事実を隠していた。現在は友人なし、親類なし、恋人なし、私生活なし(避暑兼任のメイドと二人暮らし)。ここまで過去を捨てている。小説終盤には行方不明の娘が名乗りを上げたが、警察と接触する前に毒殺されていた。
とまあ事件に関するストーリーをまとめると以上。それだけだと退屈になるので、筆は同乗した客の描写に及び、それぞれの事件の影響をみる。雇用人と交渉してサラリーをあげる者もいれば、評判が落ちて店じまいを考える自営業もいる。なぜかポワロはその中からカップルになりそうな若い男女を選んで、捜査に協力させたりする。カーだとカップルを主人公にしてスクリューボールコメディにすることがあるが、クリスティはそこまでドタバタが好きなわけではないので、冒険させたりはしない。
シチュエーションは似ていても「オリエント急行の殺人」には遠く及ばない。なにしろトリックがちゃち(しかも現実味がなく)。そのうえ、機内の描写は冒頭の10ページ足らずで、あとはロンドンとパリを往復して、尋問と会議をするだけ。雪で閉じ込められ、正体不明の殺人者と同室という緊迫感がまったくない。風俗や政治など背景で見いだせるもののないし、まあクリスティにしてはめずらしい駄作でした。
訳者あとがきによると、この5年後の「杉の棺」と設定に共通点があるということだが、未読なのでわかりません。もしも「杉の棺」に出会えたら思い出しましょう。