2016年。ピケティ「21世紀の資本」がよく売れたので、マルクス「資本論」の可能性を見てみよう、という志で書かれたらしい。
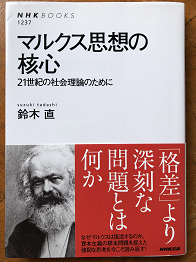
第1章 マルクスはいかに受容されてきたか―四つの断面 ・・・ マルクスは主著が未完であったし、運動や革命の展望を語らなかったので、死後、さまざまな解釈が現れた。史的唯物論と科学的社会主義を標榜するエンゲルスとカウツキー、秘密結社と革命家を育てるレーニンとスターリン(と毛沢東も?)、主体と実践を重視するルカーチとコルシュとフランクフルト学派など。1960年代にスターリニズムへの批判が行われると、革命論より疎外論でマルクスの重要性を見るようになる。21世紀には資本主義経済の批判者として再度脚光を浴びる。なお戦後の社会民主主義は利益集団間の協調主義圧力とみなされるようになって、人気が落ちた。
第2章 現代資本主義の危機 ・・・ 新自由主義批判。経済危機を貨幣・国債・民債の発行で先送りしてきた資本主義。資本の要請を政策にする国民国家によって民主主義が支配され、社会保障が削減され、労働分配率が低下している。資本は緩やかな連帯を取ることで新自由主義を推進するが、労働者は対抗しえないし、むしろ積極的に新自由主義の強化に参加している。
(ここはかなり荒い新自由主義批判なので、ほかの経済書で補完するようにしておこう。著者は労働者も緩やかな連帯で資本に対抗しようというが、実際に起きていることをあまり知らないようなので観念的であいまいな主張にとどまる。)
第3章 近代社会哲学の出発点 ・・・ である社会契約説の批判。論点は、この説にある超越論的構成、演繹的推論、私的利益の正当化(ジョン・ロックの市民政府論からすでにブルジョア擁護の言説が紛れ込んでいるとのこと。すなわち労働による私的所有が国家より優先され、自然の収奪を正当化し推進しているところ)。17-18世紀の政治哲学で、政治主体(シトワイヤン)と経済主体(ブルジョア)が分けられるようになった。
(追記: シトワイヤンとブルジョアはヘーゲル「法哲学」に説明があるらしい。解説書を読むと、マルクスは公民(シトワヤン)と市民(ブルジョア)を区別する。前者は国家の試験で選抜したり任命したりした成員、後者は職業団体や同業組合(ギルド)の構成員でたぶん後には資本家も加わる。)
第4章 自由主義批判と疎外論 ・・・ 自由主義での政治的解放は人間的解放にならないということと、賃労働での疎外について(「経哲草稿」「ドイツ・イデオロギー」「フォイエルバッハ・テーゼ」の紹介)。
(マルクスがよく使う「類的存在」は群れとして生きている人間というくらいの意味。そこからさまざまに疎外されているのが資本主義なので、コミューン主義・共同体主義になりましょう、というのがこの章のまとめ。でもここには権力の問題が抜けているし、国民国家になることで問題が解決されるというアイデアがあるので、まったく乗れない。さらに反ユダヤ主義に対するマルクスの見解もダメ。労働者による国民国家の成立で宗教対立、すなわち民族差別が解消するとしているので。この考えを実行したレーニン、スターリンはエスニックマイノリティへの差別や迫害を行ったのだ。ここでも権力論、ことに権力勾配が抜けている。)
第5章 賃金労働の本質 ・・・ 労働価値説。労働力という商品は、使用・消費によって減価されない、剰余価値が資本家に搾取される、労働者は生産活動から疎外(自分の自由にならない)されている。労働力の売買は非対称。
(労働価値説は21世紀には魅力がないし、支持者も少ないと著者はいう。それでも・・・と著者はいう。ここでもW-G-W'の説明はない。この説はもう使い物にならないわけだ。)
第6章 実体論から関係論へ ・・・ 「因果律の呪縛」を受けた哲学は破綻。ホッブスの社会契約説、ヘーゲルの歴史哲学、マルクスの価値形態説をダメ出し。
第7章 現代社会理論の条件 ・・・ 19世紀までの哲学はダメなので、20世紀の科学を考察しよう。進化論的認識の方法を検討。それを使ってカント「永久平和論」を検討。
(「哲学から科学へ」などと「科学的」であることにこだわる必要なんかないのに。それに「進化論的認識」なるものも誤解やトンデモが隠れているようだ。)
おかしなことしか書いていないなあ、読み取るべきところがどこにもないなあとあくびをこらえながら読んだ。後半になると、目が滑る。第5章以下はもう読めない。「マルクス主義」はここまでダメになったのだなあとしか感想が出てこない。久々に読んだ「壁に投げつけたい本」。