自分が知っている日本の19世紀の歴史は1960年代の研究で止まっているので、比較的最近の研究をまとめたものを読む(初出は2006年)。これまでは「日本の歴史」として記述してきたが、当時の世界情勢(ウィーン体制、ルイ・ボナパルト即位、阿片戦争、クリミア戦争、産業革命など)を反映した世界史の一部分としてとらえるのが本書の特長。あわせて「維新」を近代化・発展史としてみない視点もある。これらは日本と特権化しないで、相対化する重要なみかた。そうすると、日本の「維新」を他国の国民国家創世と比較することができる。
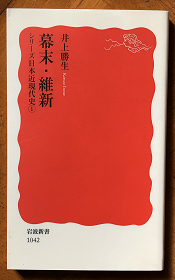
第1章 江戸湾の外交1852-1856 ・・・ 海外情報を収集していた幕府は、1852年のペリー来航を事前に知っていた。当時の国際法は先進国、半未開国、未開国を区別し、日本は半未開国とみなされていた。ペリーの強圧外交は当時の国際法を逸脱。幕府はしたたかな外交を展開。ペリーの要求の一部をはねのけた(とくに外国人の遊歩制限は国内産業保護に貢献)。同時期にロシアも開国と領土交渉を開始。幕府は開国と保護貿易の方針で動く。諸藩も開国前提の殖産興業を始める。
(阿片戦争1842年の結果はすでに伝えられていて、統治者には大きな恐怖になっていた。それが交渉などに反映。いっぽう、諸外国からすると、日本は市場が小さく、植民地とする意思はなかった。とはいえこれらの情報や意見を幕府や諸藩が共有するには、当時の伝達手段やメディアは不充分。なお、日露交渉ではカラフト、北方四島などの領土問題が発生。そこにはアイヌが散在していたが国家をもっていない。そのためにこれらの土地の帰属はあいまいなままになり、帝国主義国家が後に占領した。)
第2章 尊攘・討幕の時代1857-1862 ・・・ 幕府は通商条約締結で一致し、ルールとおり朝廷の裁可を求めたら孝明天皇に拒否された(たぶん前代未聞)。幕府の条約推進派(かつ幕政改革派)が失脚し、諸藩抑圧政策を敷き諸藩の反発になる。朝廷は反幕府運動を扇動。結果、諸藩は攘夷と開国、倒幕と佐幕に分裂。以後、幕府、朝廷、雄藩のヘゲモニー争い。諸藩の中でも改革と現状維持に分裂。比較的早期にまとまったのが長州と薩摩。藩を抜けて政治運動に参加する下級武士や豪家の若者が多数でてくる。
(封建制は経済が安定し秩序を求める社会にはあっているが、経済が混乱し政治や社会が変革を求めているときには対応できない。幕府も朝廷も改革派は有志の人を加えた会議や評議会、フォーラムつくりを目指したが、失敗する。日本型の統治システムではグループ間の調整が必要だが、有事のときにはグループの反目が大きくなってしまうから。で末端では切った張ったの乱暴狼藉、テロリズム。あと「草莽の士」には民間人もいて、そのネットワークは開国後の貿易で活躍した。)
第3章 開港と日本社会1863-1867 ・・・ 混乱期。幕府、朝廷、雄藩の意見が一致せず、その内部でも抗争があった。問題は朝廷。孝明天皇の攘夷とさらに強い攘夷を求める激派があり、幕府の開国策に抵抗する(幕府もは攘夷の命令を適当に受け流す)。慶喜が次期将軍とみなされたが、彼も攘夷論者。朝廷と仲良くなろうとするが天皇が死ぬ(16歳の明治天皇が即位)。朝廷の命令で攘夷をやろうとした薩摩や長州は英国と戦闘になり、大ショックを受ける。ここから幕府に代わる政権奪取の構想が生まれる。幕府は慶喜の指示で改革を開始。
(長州の藩政改革は現実に切迫していない対外的危機を誇大に強調して民衆を動員するというもの。奇兵隊にみられるような階級制の否定と常備兵制度。俺の見立てでは、長州のやったことは大衆運動による全体主義国家の策定だ。薩摩は階級制を否定することはなかったが、カリスマをトップにおく全体主義の制度を作った。その制度が明治政府に引き継がれて、設立当初から明治政府は全体主義国家として生まれたのだった。)
(尊王攘夷運動は朝廷のクーデターのあと打ちこわし一揆で終末を迎えた。いっぽう、いくつかの港を外国に開いたことで、地元や地方の豪商・百姓がビジネスに参加。外国人相手にしたたかな交渉をして経済活動を活発にした。民衆が開国をゆっくり定着させ、外国商人の侵入を断念させ日本の植民地化の危機を防いだ。前の「偽りの現実」を信じ込ませて排外主義を扇動するやり方は必ず失敗するというわけだ。)
(この外国人嫌悪や排斥の感情が国民全体で共有されるようになったのは、明治政府ができてから生まれた、というのが本書に書かれている。維新前の大衆は外国人に対して物おじしないし、恐怖や不審をもつこともない。それは当時の外国人の手記や写真などからわかること。また百姓一揆が頻発していたが
「鎌は武器ではなく、百姓の誇り高いシンボル」で「百姓一揆は『あえて人命を損なう得物は持たず』非暴力的蜂起という点が、江戸日本に普遍的な原則であった(P107)」
「江戸幕府の支配の強さは、訴訟を厳禁し、百姓を力で圧倒したところにあるのではなかった。訴願を受け付け、献策を容れる『柔軟性のある支配』に、その持続の秘密があった(P108)」。「圧政に呻吟する農民の暴力的な蜂起という百姓一揆像も、事実と違っていることが分かってきた(P106)」。
というわけで、日本人が持つ外国人イメージは近世と近代で大きな違いがあった。その理由は、朝廷や武士などの一部がもった危機意識(ことに阿片戦争の結果)からの外国人恐怖と嫌悪が政府を通じて国民に浸透していった。その際に、長州藩などに端を発する全体主義国家体制が大きく働いたのだった。日本のレイシズムは国家神道イデオロギーや朝鮮併合などで形成されると思っていたが、それ以前に端を発していたわけだった。日本の近代批判はもの凄く射程を長くしないといけないのだね。大日本帝国憲法発布などを起点にしてはとらえきれないのだ。)
これを読んで思うのは、あれ外交政策では幕府のほうがよりよい方法でいたのじゃない、孝明天皇や徳川慶喜の狂信的な排外主義に煽られた攘夷運動によって社会と外交を混乱に陥らせたのじゃねえ、ということ。通商条約においてアメリカやイギリス、ロシアなどに最恵国待遇を与えたにしても、他の条件をつけて国内市場を荒らされないようにしたし、近代化も遅れてはいたが規模を大きくして行われていたのだし。むしろ自藩の都合を優先させて動いた排外主義政策の長州と薩摩がこれらの改革運動を疎外したのではないか。ことに、朝廷の命令で攘夷を実行した薩英戦争や下関戦争によって、諸外国との関係を悪化させたのではないか。諸外国は中国進出をめぐって競争していたが、日本は市場の魅力がないので植民地化するような意志はなかった。そこを読めず、攘夷イデオロギーに固執し、「偽りの現実」で物事を見るようになったことが事態を悪化させた。
この攘夷という排外主義イデオロギーはいつ生まれたのか。恐らくは19世紀初頭からの西洋の帝国主義化。それがインド洋経由で中国に到着し、大陸経由で日本海に到達し、太平洋航海を可能にして、軍事大国である「外国」を意識するようになってから。それまでのオランダとの狭い外交しかしていないので経験に乏しい列島の為政者たちは外国を脅威としてみた(孝明天皇などの朝廷も徳川慶喜なども外国人と話したことはなさそう)。それはかつて倭寇や朝鮮遠征などで外国を侵略・略奪してきた自分らの歴史を見ることになっただろう。自分がやったことが他人や他国にやり返されると思うようになる。ことにアヘン戦争の顛末はこの国の為政者のトラウマになった。という具合に、日本の外国人嫌悪や恐怖は明治政府になってからと思っていたが、それより前に始まっていたのだという発見があった。
(この後、古事記や日本書紀などの本を読んだので、排外主義イデオロギーは大和朝廷のときからあったと考えるようになった。)
この外国人恐怖や嫌悪の「偽りの現実」で政治運動を進めたのが長州。この外国人恐怖・侵略デマを藩内に醸成させ(そこには吉田松陰のようなレイシストの影響が大きそう。彼の弟子とされる高杉晋作、久坂玄瑞、木戸孝允、伊藤博文、山縣有朋などという連中はそろって排外主義者で、藩の政治にかかわった)、大衆運動を組織する。藩政は国政方と国用方にまとめられ、用談役に木戸がついて独裁体制になる。これらの改革の最大の成果が奇兵隊のような「国民国家」の常備兵の整備。この政策は階級をなくすことになったが、大衆の命を消耗品とみなした。「幕末の長州藩には百姓一揆がない」といわれ、「蒙古襲来の神風神話での民衆動員が行われていた(P140)」というような大衆運動があった。この政策が政権奪取後に引き継がれ、全国を統治する体制の基本になる。
長州藩が根に持ったのは下関砲撃事件。英国との戦争に敗北した。この時の屈辱がのちの東アジアへの侵略・植民地獲得の運動になったのではないかと妄想した。大日本帝国は「不敗」という神話をつくったのも、薩英戦争や下関砲撃事件の敗北にとらわれてのことではないかとも思う。
2023/02/06 井上勝生「幕末・維新」(岩波新書)-2 2006年に続く