2020年からのコロナ禍は、この小説を「再発見」した。ペストが流行し、都市が閉鎖され、市民が非日常を生きるという設定が、「ステイ・ホーム」や「三密(密閉・密集・密接)を避けろ」、「消毒とマスク着用」などを推奨され、外に出ることが憚られる状況と一致したと思われたのだ。直接コミュニケーションを取ることと移動することが制限され、自宅と職場だけしか居場所がないような状況になる。死者のうわさが聞こえ、いつか災厄が自分を訪れ突然の死を迎えるかもしれない。感染症の蔓延時には、このような恐怖と不安に駆られながら、狭い空間に閉じこもらなければならない。その時にどのように対処すればよいのか。この国の小説には、感染症や都市封鎖を記録したものはない。幽閉された(と感じている)人びとがどのように生きるか、正気を保つかの規範や手がかりを見出すには、外国の小説を参照しなければならなかった。なので、本書が売れた。
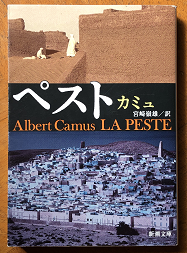
カミュの「ペスト」は1941年ころから1947年にかけて書かれた(解説による)。当時20代後半から30代にかけてのカミュはアルジェリアのオラン市(小説の舞台)で教師をしていた。
1.アルジェリアの都市オラン、某年4月16日。一匹の鼠が血を吐いて死んでしまった。死んだ鼠はリンパ腺が腫れ、膿を出していた。死んだ鼠は町のいたるところで見られ、市は回収を急ぐ。そして最初に死んだ鼠を見つけ塵芥箱に捨てた老人の門番が鼠と似た症状を発症し、2日と立たずに死んでしまった。医師も見たことがない症状なので診断がつかない。半月もすると、一日の死者は30人にもなる。そこにいたって知事はオランの町を閉鎖することに決めた。
(オランの町は「一個の中性の場所」とされて無機質なところ。歴史のない人工的な都市にみえる(というのはヨーロッパ人の傲慢に思える。オランは国民国家ができた後にフランスが占領した植民地の都市だ)。人は分断されて孤立化アトム化している。そこに訪れる感染症は、この時点では抽象的。外部から入り込み、中の人間には責任がなく、それなのに2か月以内に市民の半分が死亡すると予測される。死体や死臭に鈍感なところもあって、ペストは戦争に似ている。むしろ戦争の総力戦のメタファーのように見えるのだ。)
(というのも、同じ感染症や都市封鎖を扱ったトーマス・マン「ベニスに死す」では、うわさが広まる前に消毒液や煙のにおいがするようになる。不安と恐怖の感情がまず生まれ、パニックが広がるものだが、オランの町ではずっと平静を保っていられる。)
(1947年時点では、ペストの研究は進んでいなかったと思われる。最近の流行は20年前だったので、医師たちにも知識や体験がない。とりあえずの対抗策は予防と隔離。しかし死者が出ているうわさのために、病人は隠れ、統計が役に立たない。)
2.閉鎖命令がでてからは、都市への人の出入りは禁止される(必需品の入荷のみ許可)。出入り口は封鎖され、兵士が監視している。郵便、電話は停止され、電報だけが許される。ビジネスは停止され、食糧が制限され、ガソリンも配給制になる。突然の命令だったので、観光客は足止めされ、街の外に出て行ったものは入ることができない。こうしてオランの町は世界から切り離され、追放されてしまった。いつまでなのか期限がわからない幽閉であり、世界に見放され、死の兆候がそこかしこにある。ある日突然、死の兆候が訪れ、家族や友人から引き離される(隔離されると面会禁止になるのだ)。
(この小説は1941-47年に書かれたので、オランの町はナチスに占領されたパリのよう。閉鎖命令の出たオランの運営は、ほとんど占領地や収容所であるのだ。そこでは人体や人権が管理され制限されている。ペストは外部の侵略者や避難先の強大な権力暗喩のようである。なのでこの小説は「外」から来た異物をいかに排除するかが問題になる。本書に近いのはデフォーの「ペスト」ではなく(未読)、ウェルズの「宇宙戦争」だ。)
人びとの感情は、恐怖や追放の苦痛、別離から始まり、次第に状況になれるにつれて退廃や不機嫌、消沈などに移る。夏の暑さに耐えかね、アルコールに耽溺するものがでてくるし、密輸で儲けるものが生まれ、闇ルートで脱出するものもいる。
(その状況は2020年からのコロナ禍に似ているのだが、異なるのはオランの外には「健康」な地域が広大に広がっていて脱出することやいつか復帰できるという可能性を見ることができるのだが、コロナ禍は地球全体を覆っているので脱出先がなく沈静した時には以前の状態には戻れないということ。コロナ禍の地球が近いのは難民収容所なのではないか。閉鎖状態に無理やり入れられた人びとという共通点はあっても、生まれた感情は異なる。)
医療はひっ迫しているし、市のサービスだけでは間に合わないので、保健隊というボランティア組織が生まれる。市内の清掃や消毒、患者の運搬、死体の処理などを担当する。
(ナチスに占領された都市、あるいは「火星人」に侵略された地球という暗喩を延長すれば、この保健隊はパルチザンやレジスタンスとみなせそう。さすがフランス革命の国。政治に参加することが自由であると考える共和主義の模範だと思った。なぜ保健隊に参加するか、なぜ多くの死者が出て自分が感染するかもしれないリスクをあえて犯すかとの問いに、自分の職務に誠実であるから、と医師が答える。誠実であるという美徳は内面にあるのではなく、行為で現れるのだ。これは重要な考え。日本だといいわけのあげく、他者利益を理解してもなにもしないか、上からの命令でないと動かないものだ。)
なので訳者解説では、キャラがどう動いたかにフォーカスしているが、個々人の動きの違いをみてもあまり参考にはならない。そこではなく、閉鎖都市で市民がいかに活動@アーレントを行うかのほうが重要。解説ではカミュが「コンミュニスムとキリスト教とのあいだに、より人間的な第三の道を求めようとしている」と書いている(1969年)が、彼は共和主義のことを知らなかったようだね。フランス革命や「レ・ミゼラブル」をみれば、フランスの民主制は共和主義に基づいているのがわかるのだ。
カミュは「不条理の哲学」なるものを提唱しているらしい(「シーシュポスの神話」は昔々に読んだが、中身は忘れた)。半世紀前を思いだせば、人間がコントロールできない事態に遭遇させられると、生や存在の意味がむき出しになる、あるいは生や存在の無根拠性があきらかになるというような内容だったかしら。たしかに強制収容所の拷問や虐殺、秘密警察の突然の逮捕などは「不条理」と言っていいかもしれないが、感染症や戦争、全体主義運動は不条理ではない。予兆、前兆があり、人びとが適切に対処することによって回避したり被害を小さくすることが可能だ。それをでコントロールできないものとして、「不条理」に棚上げして内面の問題にするのは筋のよくない考えに見える。カミュの「不条理の哲学」は「ペスト」の登場人物、とくに医師によって覆されているのではないか。どんなに困難な場面に直面しても自分の職務に誠実であろう、コモンに関係して活動@アーレントすることで生や存在の意味や価値はおのずと立ち現れてくるのだ、と。そういう人物がいると、脱出して自分だけ安全になりたいと願う人も残って活動を始めるのだ。
(思い付きだが、不条理の哲学は、近代や科学技術に反発するものの、それらは世界を覆う大きな力になっているから「死の哲学」で対抗しようとするハイデガーに近いものになってしまうのではないか。)
2023/03/07 アルベール・カミュ「ペスト」(新潮文庫)-2 1947年に続く