第2章
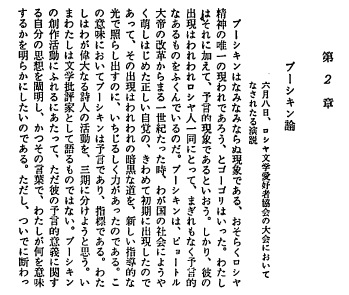
プーシキン論
六月八日、ロシヤ文学愛好者協会の大会においてなされたる演説
プーシキンはなみなみならぬ現象である、おそらくロシヤ精神の唯一の現われであろう、とゴーゴリはいった。わたしはそれに加えて、予言的現象であるといおう。しかり、彼の出現はわれわれロシヤ人一同にとって、まぎれもなく予言的なあるものをふくんでいるのだ。プーシキンは、ピョートル大帝の改革からまる一世紀たった時、わが国の社会にようやく萌しはじめた正しい自覚の、きわめて初期に出現したのであって、その出現はわれわれの暗黒な道を、新しい指導的な光で照らし出すのに、いちじるしく力があったのである。この意味においてプーシキンは予言であり、指標である。わたしはわが偉大なる詩人の活動を、三期に分けようと思う。いまわたしは文学批評家として語るものではない。プーシキンの創作活動にふれるにあたって、ただ彼の予言的意義に関する自分の思想を闡明(せんめい)し、かつその言葉で、わたしが何を意味するかを明らかにしたいのである。ただし、ついでに断わっておくが、プーシキンの活動の各時期は、はっきりした境界を持っていないように思う。たとえば、『オネーギン』の初めの部分は、わたしの考えによると、詩人の活動の第一期に属しているけれども、『オネーギン』の終わりのほうは、プーシキンがすでにおのれの理想を生みの国土に発見して、その愛と洞察に満ちた魂をもって、これを完全に受け入れ、かつ熱愛するようになった第二期のものである。またブーシキンはその活動の第一期においては、ヨーロッパの詩人たち、パルニ(ルイ16世時代のフランスの古典派詩人)、アンドレ・シェニエ、その他、ことにバイロンを模倣したといわれている。なるほど、疑いもなくヨーロッパの詩人たちは、彼の天才の発達に偉大なる影響をあたえ、かつその影響は生涯保存されていたのである。にもかかわらず、プーシキンのきわめて初期に属する諸作ですら、単なる模倣ではなく、そこには早くも彼の天才の異常なる独立性が現われていた。
たとえば、『ジプシーの群れ』――わたしはこの叙事詩――を、まだ彼の創作活動の第一期に属するものと認めるが、プーシキンがこの作の中に示したような、ああいう苦悩の独自性と、あのような自意識の深さは、しょせん模倣の中に現われるものではない。もし彼が単に模倣のみをこれ事としたのであったならば、あれほどの創造力と、激しい推進力が現われるはずがない、などということはもはや喋々すまい。叙事詩『ジプシーの群れ』の主人公アレーコの典型の中には、その後『オネーギン』で見事に完成された調和の中に表現された、あの力強い、深刻な、完全にロシヤ的な思想がうかがわれる。『オネーギン』になると、アレーコとほとんど同じ人間が、もはや幻想的な光に包まれず、手に触れ得るほど現実的な、理解しやすい姿をとって登場するのである。プーシキンは早くもアレーコにおいて、かの不幸な放浪者をわが祖国に見いだして、これを天才的に輪郭づけたのである。それは民衆から分離したわが国の社会に、歴史的必然性をもって現われた、歴史的なロシヤの受難者なのである。プーシキンがこれを発見したのは、もちろん、単にバイロンの作品からばかりではない。この典型は正確なものであり、しかも誤りなく把握されてい、後に長くわがロシヤの土地に住みつくこととなった不断のタイプである。これらの家なきロシヤの放浪者たちは、今日までもその放浪をつづけて、まだ長くその姿を消しそうもない。
彼らは現代において、もはや自分の世界的理想を、ジプシーの野性的な独自の生活形態の中に発見したり、躓きの多い矛盾したわがロシヤ・インテリゲンチャの生活からのやすらいを、自然のふところに求めんがために、ジプシーの群れに身を投じたりしないまでも、結局はそれと同じことで、アレーコ時代にはまだなかった社会主義に飛び込んで行き、新しい信仰を持って別の耕地におもむいて、そこで孜々(しし)として働いている。しかも、アレーコと同じように、この架空的な仕事の中に自分の目的を達し、おのれ自身のみならず、全世界の幸福をも獲得できるものと信じているのだ。なぜなら、ロシヤの放浪者にとっては、心の平安を得るためには、ほかならぬこの全世界的幸福が必要だからである。それより安い値では決して妥協しない、もちろん、それは目下のところ、理論だけの話ではあるが。とにかく、これとても要するに、同じロシヤ人であって、ただ異なった時代に現われたばかりである。この種の人間は、くり返していうが、ピョートル大帝の大改革後、ちょうど二百年をへた頃に、民衆と民衆の力から分離したわがインテリ社会に誕生したのである。おお、ロシヤ・インテリゲンチャの大多数は、プーシキン時代も現代も同様に、官吏として国庫に勤めたり、あるいは鉄道や銀行におとなしく奉職したり、さもなくばいろいろな手段で金を儲けたり、あるいは科学にすら従事して、大学で講義をしている者もある。これらはすべて規則的に、怠惰に、平和に行なわれて、俸給をもらい、カルタ遊びをしながら、ジプシーの群れにもせよ、またもっと現代にふさわしいところにもせよ、どこかへ逃げ出そうなどという野望は、いっさい持ちあわさないのである。まあ、たかだか「ヨーロッパ的社会主義の陰影を持った」自由主義を振りまわすくらいなものだが、それにも若干、ロシヤ人らしいお人好しの性格が加わっているのである。――しかし、これはすべて要するに、ただ時の問題である。一人はまだ不安を感じはじめもしないのに、もう一人は早くも閉ざされた扉に行きあたって、額をしたたかぶつつけたからといって、それになんの意味があろう。民衆とのつつましい合流という救いの道に出ないかぎり、だれでもそれぞれの時代時代に、同じ運命が待ち伏せしているのだ。よしんば、すべての人をこうした運命が待ち伏せしていないまでも、ただ少数の「選ばれたる人」つまり不安を感じはじめた人々の十分の一だけでもたくさんである。それだけでも残余の大多数はおかげで、平安を知らないことになるのである。
アレーコはもちろん、自分の悩みを正確に表現するすべを知らない、彼に見られるすべてのものは、まだなんとなく抽象的で、ただ自然に対する憧れとか、社交界に対する不満とか、世界的憧憬とか、どこかでだれかの失った真理、彼のどうしてもさがし出すことのできない真理に対する哀泣とか、そういったものにすぎない。そこには少々ばかり、ジャン・ジャック・ルソー臭いものがある。その真理はなんであるか、どこでいかなる形式をとって現われるか、またどこで失われたか、彼はもちろん、自分ではそれをいわないけれども、心から苦しんではいるのである。幻想的なせっかちなこの男は、今のところまだ主として、外部現象からの救いを渇望しているにすぎない。またそれが当然なのである。「真理はどこか自分の外にある、おそらくほかの国、たとえば、確固たる歴史的組織と、固定した社会的・公民的生活を有するヨーロッパにあるのかもしれない」。真理が何よりもまず彼自身の内部にあることを、彼はとうてい知ることはできないだろう。またどうしてそれが知れよう。なにしろ、彼は自分の国におりながら、自分の国の人間でないようなありさまである。彼はすでに代々長い間、労働というものから切り離され、文化を持たず、女学生のように、閉じこめられた壁の中に成長し、ロシヤの教養階級が分かたれている十四の官等のうちどれに属しているかに準じて、奇妙なわけのわからぬ職務を履行しているのだ。彼は目下のところ、風にもぎ取られて空中を漂っている草の葉にすぎない。彼はそれを感じて、そのために苦しんでいる。そして、しばしばなんともいえないほど悩むのである!ところで、おそらく世襲の貴族階級に属し、たしかに農奴さえ所有していたに違いない彼が、その貴族らしいわがままから、ちょっとした空想をおこし、「法律の外に」住んでいる人々に誘惑されて、一時、ジプシーの群れにまじって、見世物の熊を引きまわしたからといって、それがいったいどうしたのか?そのとき一人の女、ある詩人の言莱にしたがえば「野生の女」が、何よりもまっさきに彼の悩みを癒やす希望を与えたので、彼は軽はずみではあるけれども、熱烈な信仰をいだいて、ゼムフィーラ(『ジプシーの群れ』の女主人公、ジプシー女)に飛びかかって行った。「ここにおれの救いの道がある、世間から遠く離れた自然のふところの中、文化も法律も持たない人々の間、ここにこそおれの幸福があり得るのだ!」といったわけである。ところが、その結果はどうだろう。この野生的な自然の条件と、はじめて衝突するが早いか、彼はもう我慢しきれないで、自分の両手を血に染めるのである。世界的調和どころか、ジプシーの群れにとってさえ、この不幸な空想家は役に立たないものであるとわかって、彼らは彼を追い出してしまう、――しかし、復讐感も憤りもなく、荘重にしかも単純に。
われらのもとを去れ、倣れる人よ
われらは野の民、掟をもたず
されども人を苦しめ、罰することなし
これらはすべて幻想的なことに相違ないが、「倣れる人」はリアリスチックであり、的確に把握されている。それこそわが国では、プーシキンによって初めて捉えられたものであって、この点を記憶しなければならない。実に、実に、何かちょっとでも自分の気に入らないことがあると、彼はたちまち毒々しい自分の憤りのために相手を八つ裂きにし、刑罰しなければ承知しない。さもなければ(このほうがもっと好都合なのだが)、自分が十四の官等のうちの一つに所属していることを思い出して、相手を苦しめ罰する法律を、大声に呼び招くかもしれない。そういうことも往々おこったのである。ただ自分の個人的侮辱感の復讐さえできればいいのだ。いな、この天才的な叙事詩は決して模放ではない!そこには早くも民衆的信仰と真理によって、問題を、「呪われたる問題」をロシヤ的に解決せんとする試みがほの見えている。「謙遜になれ、倣慢なる男よ、何よりもまず慢心の角を折れ。謙抑であれ、無為の男よ、まず何よりも生みの田野で働くがいい」これが民衆的真実と、民衆的叡知による解決である。「真理は汝以外でなく、汝自身の内にある、おのれ自身の内にみずからを見いだせ、おのれ自身にみずからを服従させ、みずからを制御せよ、さすれば真理を見るであろう。この真理は物の中にもなければ、汝以外にあるものでもなく、またどこか海のかなたにあるのでもない。それは何よりもまず、自分自身に対する汝の労苦の中に存するのだ。おのれを克服し、おのれを鎮撫せよ、さすれば、かつて想像したこともないほど自由な身となって、偉大な仕事をはじめ、他人をも自由にして、やがては幸福を望むことができるだろう。なぜなら、汝の生活が充実して、ついには自国の民衆と、その聖なる真実を理解するからである。もし、汝自身が第一にそれに値しない、意地わるな、傲慢な人間であって、ただ生命を要求し、それに値をはらわなければならぬことさえ知らずにいるならば、世界的調和はジプシーの群れにも、またそのほかのどこにも見いださないだろう」問題のかかる解決は、プーシキンのこの叙事詩の中に、もうはっきりと暗示されているが、それは『エヴゲーニイ・オネーギン』の中にさらに明瞭に表現されている。これはもはや幻想的なものでなく、手にふれ得るがごとく現実的な叙事詩で、その中にはロシヤのほんとうの生活が、プーシキン以前には見られなかったような、またおそらくその以後にも見られないであろうような創造力と、完成味をもって具象されているのである。
オネーギンは、ペテルブルグからやって来る、――これは必ずペテルブルグからでなければならない。これは一編の叙事詩の中に、ぜひとも必須な事柄であって、プーシキンは、自分の主人公の伝記におけるかほど重要な現実的特質を、見のがすわけにゆかなかったのである。もういちどくり返すが、これは依然たるかのアレーコであって、ことにその後、彼が憂愁に駆られながら、
なぜおれはトゥーラの議員のように
中風にやられて臥つかないのか?
と叫ぶところなどは、とくにしかりである。
しかし、いま物語のはじめにあたっては、彼はまだ半分伊達者で、社交界の紳士であり、十分この人生に幻滅を感じるには、まだあまりにも生活経験が少なかった。しかし、彼のところへもまた早くも
ひそかなる倦怠のお上品な悪魔
が訪れて、不安を感じさせるようになるのである。祖国の中心ともいうべき僻陬(へきすう)の地に閉じこもっても、彼はもちろん、わが家におちついているような気がしない。彼はそこで何をしていいかわからず、われながら自分の家にいて、客にでも来ているような気がするのだ。その後、憂愁に駆られて、故郷や外国の土地土地をさまよいはじめた時も、疑いもなく聡明で、疑いもなく誠実な人間である彼は、なおさら自分がわれながら他人であるように感じたものである。もっとも、彼とても故郷を愛してはいるけれど、それを信頼しないのである。もちろん、祖国の理想についてもうわさは聞いたが、それを信じようとはしない。彼が信じているのは、何事にもあれ祖国の耕地で仕事をするのは完全に不可能だ、ということばかりである。この可能を信じているものがあれば、――それは当時も今と同様に少数ではあったが、――彼はもの悲しい嘲笑を浮かべて、それらの人々を眺めるのであった。彼がレンスキイを殺したのは、ただただふさぎの虫のせいにすぎなかった。もっとも、それは世界的理想に憧れるふさぎの虫だったかもしれない。――それはあまりにもロシヤ的で、大いにあり得る話なのである。
タチヤナはそのような人間ではない、これは自分の地盤の上にしっかと立っている、毅然たるタイプである。彼女はオネーギンより深みがあり、むろん、彼より聡明である。彼女はすでに自分の気高い本能によって、どこに、また何に真理があるかを予感しており、それが詩の結末に表現されている。もしプーシキンがこの叙事詩の名をオネーギンでなく、タチヤナのほうからとったら、むしろそのほうがよかったのではないかと思われる。なぜなら、彼女のほうが疑いもなく一編の女主人公だからである。これは消極的でなく積極的な典型である。これは積極的な美の典型であり、ロシヤの女性に対する讃歌である。したがって詩人は、タチヤナとオネーギンが最後に邂逅するあの有名な場面で、彼女に一編の思想を述べる任務を与えたのである。かかる美しさを持ったロシヤ女性の積極的典型は、わずかにツルゲーネフの『貴族の巣』のリーザをのぞいては、その後ほとんどわが文学中に二度とくり返されなかった、とさえいうことができる。けれど、人を高見から見下ろす癖のために、オネーギンは淋しい田舎ではじめてタチヤナに出会った時、まったくその本質を見分けることができなかった。純で無垢なつつましい姿をした彼女は、はじめて彼の前へ出ると、すっかりおどおどしてしまったのである。彼は見すぼらしい小娘の中に、完璧と完成とを見分けることができず、おそらく彼女を「道徳的胚子」と見なしたのかもしれない。いったい彼女が胚子なのだろうか?しかもそれは、彼女がオネーギンに宛てて手紙をおくった後のことである!もしこの叙事詩の中に、だれにもあれ道徳的胚子があるとしたら、それはもちろん、彼オネーギン自身である。それは論ずるまでもない。しかり、彼はまったく彼女を見分けることができなかったのである。またどうして彼に人間の魂を知ることができよう?彼は抽象的な人間であり、一生を通じて不安な夢想家であった。その後ペテルブルグに出て、名家の貴夫人となった彼女の姿を見、彼がタチヤナに宛てた手紙の文句にしたがえば、「心の底から彼女の完成美を残りなく悟った」時でさえ、彼は彼女を見分け得なかったのだ。それはただ言葉にすぎなかったのである。彼女は彼の生活において、認識されず、評価されないままで、彼のかたわらを通り過ぎたのである。そこに彼らのローマンスの悲劇が存するのだ。おお、もしあの時、田舎ではじめて出会った時、ちょうどそこへイギリスからチャイルド・ハロルドか、さもなくば何かのわけでバイロン卿自身がやってきて、彼女の臆病げなつつましい美を認め、それを彼にさし示したとしたら、――おお、その時はオネーギンも立ちどころにはっとして、驚嘆したに相違ない。なぜなら、こうした世界苦の受難者には、性々にして下男根性がひそんでいるからである。しかし、そういうことはおこらなかったので、世界的調和の探求者は、彼女に一場の教訓を授け、なんといっても潔白な態度をとった後、かの世界苦を胸にいだき、愚かな憤りに流された血に手を染めたまま、祖国を放浪すべく旅立ったのである。しかし、その祖国を認めるでもなく、体は健康と力に湧き立ちながら、呪詛の叫びを発するのである。
おれは若くて、内なる命はすこやかなのに
何を待ったらよいのやら、憂悶、憂悶!
タチヤナはそれを悟った。詩人はこの物語の不朽の詩句において、彼女が自分にとってかくも不思議な、依然として謎のような男の家を訪れる場面を描いている。これらの詩句の芸術的なことや、常人の達し得べからざる美しさや深みについては、今さら喋々しまい。さて、彼女は彼の書斎にはいって、彼の本、持ち物、調度品などを眺めまわし、それによって彼の魂を察し、自分の謎を解こうと努めている。やがて「遊徳的胚子」は、ついに謎の解決の近きを感じて、不思議なほほ笑みを浮かべながら、じっと手をとめる。そして、彼女の唇は静かにささやくのである。
ああ、彼はただパロディではないかしら?
そうだ、彼女は当然これをささやくべきであった。彼女は謎を解いたのだ。その後だいぶたって、ペテルブルグで再会した時、彼女はもう完全に相手を知りつくしていた。ついでながら、宮中にも出入りする社交界の腐敗した空気が彼女の魂にふれて、上流貴婦人としての地位と、新しい社交界的な観念が部分的には、彼女がオネーギンをこばむ理由となったのだ、などといったのは、いったいだれだろう?いな、それは見当ちがいである。いな、それは依然たるターニャである。依然たる田舎娘のターニャである!彼女はそこなわれはしなかった。むしろ彼女は、このけばけばしいペテルプルグの生活に圧倒され、眩暈(めまい)を感じ、苦しんでいるのだ。上流貴婦人としての自分の位置を悩んでいるのだ。彼女についてこれ以外の解釈をするものは、プーシキンのいわんと欲したことを、ぜんぜん理解していないのである。現に彼女はきっぱりと、オネーギンにいっているではないか。
けれどわたしはほかの男に許した身です
もう永久にその人に操を立てるつもりです
彼女はまさしくロシヤの女性としてこれをいったので、そこにこそ彼女の讃美さるべきゆえんがあるのだ。彼女はこの詩の真実を表現したのである。おお、わたしは彼女の宗教的信念や、婚姻の神秘に関する見解などについては、一言もいわないことにする。――いな、その問題にはあえてふれまい。しかし、いったいどうしたことだろう、彼女はみずから彼に向かって、「わたしはあなたを愛しています」といったにもかかわらず、なぜ彼について行くことをこばんだのか?それは、彼女が「ロシヤの女性として」(南方の女やフランス婦人などとはわけがちがって)大胆な一歩を踏み出す力がなく、自分の絆を断ち切って、名誉、財産、社交界の位置、美徳の条件などが有している魅力を、犠牲にすることができなかったからであろうか?いな、ロシヤの女性は大胆である。ロシヤの女性は、いったん自分の信じた人の後には、敢然と従って行くものである。彼女もすでにそれを証明した。しかし、彼女は「他の男に許した身であるから、永久にその人に操を立てます」という。そもそもだれに、何に、操を立てようとするのか?それはいったいどういう義務であるのか?あの年とった夫の将軍に対する義務なのか?しかし、彼女は彼を愛するわけにはゆかないではないか。なぜなら、彼女はオネーギンを愛しているからである。彼女が老将軍に嫁したのは、「母が涙を流して哀願した」からにすぎず、傷つけられ、辱しめられた彼女の心には、そのとき絶望のほかなんの希望も、光明もなかったのである。しかり、彼女はこの将軍に、――彼女を愛し、尊敬し、彼女を誇りとする潔白な夫に対して貞節なのである。よしや「母が哀願した」としても、同意したのはほかのだれでもなく、彼女自身ではないか。彼女自身が彼に向かって、貞節な妻となることを誓ったのではないか。たとえ結婚した動機は絶望であったにもせよ、いま彼は彼女の夫であり、彼女の裏切りは彼を汚辱と羞恥に包み、彼を殺すに違いない。ところで、人はおのれの幸福を、他人の不幸の上にきずくことができるであろうか?幸福はただ愛の歓楽のみでなく、精神の最高の調和の中にも存するのである。もし自分の背後に不純、無情、非人間的な行為があるとしたら、何をもって精神を静めることができよう?そこに自分の幸福があるというだけの理由で、彼女はいきなり逃げ出していいものだろうか?もし幸福が他人の不幸の上にきずかれるならば、それがなんの幸福であり得ようぞ?ひとつこういうことを想像してみていただきたい。諸君が究極において人々を幸福にし、ついには彼らに平和と安静を与える目的をもって、みずから人間の運命の建物を築くとしよう。そこで、このためには必ず不可避的に、一人の人間を苦しめなければならないと仮定する。しかも、それはあまりたいした存在ではなく、見る人の目によっては滑稽に見えるくらいで、シェイクスピアとかなんとかいったような偉人ではなく、たかが潔白な老人というだけのことである。それは、若い妻の夫で、その妻の愛を盲目的に信じ、その心はまったく知らないながらも彼女を尊敬し、彼女を誇りとし、彼女によって幸福であり、平安なのである。つまり、こういった人間ひとりだけを辱しめ、穢し、苦しめて、この穢されたる老人の涙の上に自分の建物を築くのだ!はたして諸君はかような条件において、かかる建物の建築技師となることをいさぎよしとせられるか?これが疑問である。もしその土台に、たといつまらない存在であるとはいい条、不正に容赦なく苦しめられた人間の苦痛がこめられているならば、かかる建物を建ててもらった人々自身が、はたしてかような幸福を受け取ることに同意するだろうか。またその幸福を受け取ったにもせよ、永久に幸福でいられるなどという思想を、ただの一瞬間でも認めることができるだろうか?あれほど高尚な魂を持ち、あれほど苦しんだ心を持つタチヤナが、あれ以外の決心をすることができたかどうか、伺いたいものである。いな、純なロシヤの魂は、次のように決心するのである。「たとえ、たとえわたくし一人が幸福を失ってもかまわない、たといわたくしの不幸のほうが、この老人の不幸よりはかり知れぬほど大きかろうと、またこの老人をはじめだれ一人として、永久にわたくしの犠牲に気づかず、しかもその値を知ってくれなくとも、わたしは他人を滅ぼしてまで幸福になりたくない!」ここに悲劇が存するので、この悲劇はついに完成される。最後の境界を越えることはできない、時はすでにおそい。かくして、タチヤナはオネーギンを立ち去らせたのである。
人あるいはいうであろう、オネーギンとても不幸なのではないか。結局、彼女は一人を救って他の一人を滅ぼしたのである!と。なるほど、それは別の問題であって、あるいはこの叙事詩の中で、最も重大なものでさえあるかもしれない。ついでながら、なぜタチヤナがオネーギンと、手をたずさえて去らなかったかという疑問は、少なくともわが文学界において、一種きわめて特色的な歴史を持っているので、そのためにわたしはあえてこの問題を敷衍する次第である。しかも、この問題の道徳的解決が、わが国ではあれほど長く疑問の種になっていたのは、最も特質的な点である。ところで、わたしはこう思う。もしタチヤナが夫の死によって寡婦となり、自分の身の上になったとしても、その時ですら彼女は、オネーギンのもとにおもむかなかったであろう。この性格の真髄を十分に理解しなければならない。なにぶん、彼女は男がいかなる人間であるかを見抜いているのだ。この永遠の放浪者は、自分の歯牙にもかけなかった女を、華々しい、およびもつかぬような、新しい環境の中に、突如として見いだした。つまり、この新しい環境の中にこそ、おそらく問題の全核心が存するだろう。かつて彼が軽蔑せんばかりであったあの小娘に、今や全社交界が跪拝している。オネーギンにとっては、彼の世界的な憧憬にもかかわらず、この社交界は恐ろしい権威なのであった。つまり、それゆえにこそ、彼は眼(まなこ)くらんで、彼女に飛びかかって行ったのである!これがおれの理想だ、これがおれの救いだ、これがおれの憂愁からの逃げ道だ、おれはそれを見落としていた、しかも「幸福はこれほど可能であり、これほど近く寄っていたのだ!」と彼は叫。ぶ。以前アレーコがゼムフィーラに向かったように、彼も新しい気まぐれな幻想の中に、いっさいの解決を求めながら、タチヤナに向かって行ったのである。しかし、タチヤナはこうした彼の内部の気持ちを、はたして悟らなかったであろうか、はたしてすでに久しい前から、彼という人間を見透していなかっただろうか?彼が実際において、ただ自分の新しい幻想を愛しているのみで、依然としてつつましやかな彼女、タチヤナを愛しているのではないということを、彼女ははっきり知っていたのだ!彼は彼女を実際とは違ったなにものかのように取り違えているので、実際は彼女を愛してすらもいない、それを彼女は知っていた。おそらく彼は何人をも愛していないのかもしれぬ、またあれほど悩み苦しんでいるにもかかわらず、なにものにもあれ、人を愛する能力がないのかもしれぬ!彼は幻想を愛しているのだ。が、彼自身も幻想なのである。まったく、もし彼女が彼に従って行ったならば、彼は明日にも幻滅を感じて、自分の一時の熱中を冷笑の目で見るだろう。彼にはなんの地盤もない、これは風に漂う草の葉なのである。
ところが、彼女はまるで違う。絶望の中にあっても、自分の生涯は滅びたという悩ましい意識の中にも、彼女にはなんといっても、魂の寄りかかる強固なゆるぎなきなにものかがある。それは彼女の少女時代の追憶である。彼女のつつましい清らかな生活の始まった、淋しい田舎にある故郷の思い出である。それは「彼女の哀れな乳母の墓の上なる十字架と、木立の陰」である。ああ、これらの思い出と、昔のさまざまな人の姿は、今や彼女にとって何よりも尊いものであり、彼女に残された唯一のものであるが、これが彼女の魂をどんづまりの絶望から救っているのである。これは決して些少なことではない。いな、そこには多くのものがふくまれている。なぜなら、それは完全な土台であり、一種ゆるぎのない、破壊しがたいなにものかである。そこには故郷、郷土の民衆、その聖物との接触がある。しかるに、彼には何があるか、また彼はなにものであるか?彼女としては、ただ彼を慰めんがためのみに、明日にもすぐ彼がこの幸福を冷嘲の目で見ることをあらかじめはっきり承知しながら、無限な愛の憐憫のために、ほんのひとどき幸福の幻影を与えんがために、同情の念から、彼の後に従うわけにはゆかないではないか。いな、たとえ限りなき同情のためにもせよ、おのれの聖なるものを意識的に穢すことのできない、深い毅然たる魂があるものである。いな、タチヤナはオネーギンの後に従うわけにはゆかなかった。
かくして、この及びがたい不滅の詩『オネーギン』の中で、プーシキンは彼以前の何人もかつてなかったような、偉大なる国民的文学者となったのである。彼はその洞察に満ちた的確な形象によって、一挙にしてわれわれの、民衆の上に立っているわが上流社会の、最も深い本質を剔抉したのである。過去および現在にわたるロシヤの放浪者の典型を示し、その歴史的運命と、わが国の将来におけるその偉大な意義を、天才的直覚によって、最初に明察するとともに、ロシヤ婦人の形をとったまぎれもない肯定的な美の典型をそれに平行させたプーシキンは、なおこの時期に属するその他の作品において、ロシヤ民衆の中から発見した多くの美しき肯定的なロシヤ人の典型を示した点からいっても、もちろん、ロシヤ作家の第一人者である。これらの典型のおもな美しさは、その真実さ、争う余地のない、手にふれ得るがごとき哀実さに存するのであって、もはやそれを秀定することはできない。彼らは彫刻のごとく、われわれの前に立っているのだ。もういちどいっておくが、わたしは文学批評家として話をしているのではないから、わが詩人の天才的諸作品を詳細に、文学的に考究することによって、自分の思想を闡明(せんめい)しようとはしない。たとえば、ロシヤの年代記者である修遊僧(『ボリス・ゴドウノフ』の登場人物)にしても、プーシキンによってロシヤの土地から探し出され、彼によって彫刻され表現された、この荘重なるロシヤ的形象の重大さと、深い意義を明らかにするためには、優に一冊の書物を書くにたるほどである。今やこの形象は、かくのごとく争う余地のない真実の所有者を生み出し得る国民生活の力強い精神の証明として、まぎれもない謙抑かつ荘重な精神美を示しながら、永久にわれわれのまえに打ち立てられたのである。この典型はプーシキンによって与えられ、すでに現存しているのであるから、これに論駁して、あれは考え出したものだ、あれは詩人の空想であり、理想化である、といい棄てることは不可能である。諸君みずから静かに瞑想してみるならば、しかり、これは現存する、と同意されるだろう。したがって、これを創造した民衆の精神も存在するわけであり、したがって、この精神の生ける力も存在し、かつ偉大で無限なものであることも承認されるだろう。プーシキンの作品には到るところ、ロシヤ的性格に対する信仰と、その精神力に対する信念がひびいている。信仰がある以上、当然、希望、――ロシヤ人に対する伸大なる希望もなければならない。
光栄と善き行ないの望みに燃えて
われは行く手を見やるなり、恐れげもなく
と詩人みずから他のことに関連していっているが、この言葉はただちに、彼の国民的創作活動の全般にあてはめることができる。プーシキンのごとく、あれほど心から親密に、おのが民衆と融合したロシヤの作家は、彼以前にも彼以後にも、かつて一人としていなかった。おお、わが国の作家の中には、民衆に関して実に上手に、実に正確に、愛情をこめて書いた人情通はたくさんある。けれど、プーシキンにくらべると、最近に現われた彼の後継者のうち、せいぜい一人二人を例外にして、今日までだれもかれもが、ただ民衆のことを書いた「旦那方」にすぎない。彼らの中で最も才能のある人々でさえ、いまわたしが挙げた二人の例外でさえも、ちょっとどうかすると、なにかしら尊大な、別の生活、別の世界から来たようなものが顔をのぞけ、民衆を自分たちのところまで引きあげてやろう、引きあげて幸福にしてやろう、と望むようななにものかが閃くのである。ところが、ブーシキンにおいては、まったく心底から民衆と融合しきったところがあって、それはほとんど素朴な喜びにまで達している。百姓が自分の奥方である牝熊を殺したことを物語った『牝熊の話』を取りあげてみても、また、
おい、イヴァン、仲人役、うんと飲もうじゃないか
という詩を思い出しても、諸君はわたしのいわんと欲するところを諒解されるであろう。
芸術と芸術的洞察の至宝ともいうべきこれらの作品はどれも、あたかも将来の芸術家、――いわば、同じ畑に働く未来の労働者に対する師表として、わが偉大なる詩人が残していったかの感がある。もしプーシキンがいなかったら、彼の後継者となった多くの才能も、現われなかったに相違ないとは、断言してはばからないところである。少なくとも、彼らの偉大なる天賦の資質にもかかわらず、その後、現代にいたって発揮することができたような、あれほどの力と明瞭さは、示されなかったに違いない。これは単に詩や芸術的創造の問題ばかりではない。もしプーシキンなかりせば、わがロシヤの独立性に対するわれわれの信仰も、現在ではすでに意識的になったわが国民力に対するわれわれの期待も、ひいてはヨーロッパ各国間におけるわが将来の自主的使命に対する信念も、これほど強固な力をもって確立されなかったかもしれない(これはまだ全部の人でなく、きわめて少数の人に見られるにすぎないとはいえ、その後、明瞭になった事実である)。このプーシキンの偉業は、わたしが彼の芸術活動の第三期と名づけるものを分析してみると、さらに明らかになるであろう。
――――――――――――――――――――――
もう一度、さらにもういちどくり返していうが、これら三つの時期は、さして画然たる境目を持っていない。たとえば、第三期の作品のあるものは、われらの詩人の詩的活動の、きわめて初期に現われ得るものということさえできるほどである。なぜならば、プーシキンは自分のあらゆる芸術的胚子を、外部から取るのでなく、はじめからちゃんと内部に蔵している、そういったふうの常に渾然とまとまった、全一的オルガニズムだったからである。外界は、すでに彼がその魂の奥底にふくんでいたものを、単に呼びさますだけにすぎなかった。しかしこのオルガニズムは発達を遂げていったので、この発連の各期間を明示することもできれば、その各々にそれぞれ独自の性格を指摘することもでき、一つの時期から他の時期へ移って行く、その経路さえ追うことができるのである。かくして、第三期には主として、全世界的理念が輝きはじめ、他国民の詩的形象が反映し、彼らの天才が具顕されている一系列の作品を、編入することができる。これらの作品の中には、プーシキンの死後はじめて発表されたものもある。わが詩人は、芸術活動のこの時期において、彼以前どこのいかなる作家にもかつて聞いたことがなく、見たこともないような、ほとんど奇跡的なものであるかのごとく感じられる。なるほど、ヨーロッパの文学には、シェイクスピア、セルバンテス、シルレルのごとき、巨大な芸術上の天才がいた。しかし、わがプーシキンのごとく、世界的共鳴の才能を有していたものが、これらの伸大な天才たちの中に、一人でもあったろうか、あれば指摘していただきたい。わが国民性の最もおもな特色であるこの能力を、彼はわが民衆とともにわかち持っているのであって、これこそ主として彼が国民詩人たるゆえんである。ヨーロッパの詩人中もっとも偉大なるものですらも、プーシキンの現わしたような力をもって、よしんばつい隣国のものであろうとも、他国の天才と、その精神と、この精神の中に秘められている深みと、その使命の悩みとを、自己一身に具象し得た例はかってないのである。むしろ反対に、ヨーロッパの詩人たちは他国民に対する場合、しばしば彼らをおのれの国民性に融合させ、自己流に理解したものである。シェイクスピアについてみてさえも、たとえば、彼の描いたイタリア人は、ほとんどぜんぶイギリス人なのである。プーシキンのみは、すべての世界的詩人の中でただ一人、完全に他の国民性に融合し、変態する特性を有していた。現に『ファウストの一場面』、『吝嗇なる騎士』、譚詩『昔世に一人の貧しき騎士ありき』などがその例である。『ドン・ジュアン』を読んでみても、もしプーシキンの署名がなかったならば、これがスペイン人の筆になったものでないということを、とうてい知ることはできなかったであろう。『死の酒もり』の中のファンタスチックな形象は、なんという深みを持っていることか!しかし、これらのファンタスチックな形象の中には、イギリスの天才が感じられる。叙事詩の主人公の歌う素晴らしい黒死病の歌、それから、
騒がしき子らの声々は
学びの庭に響き渡りぬ
の二行をふくんでいるメリーの歌、これはまさしくイギリスの歌である。これはブリテンの天才の悩みであり、その嘆きであり、おのれの未来に対する悩ましい予感である。それから、次の奇怪な詩を思いおこしていただきたい。
あるときよ、荒れたる谷間をさまよいながら
これはあるイギリスの古い宗派の信徒が散文で書いた、不思識な、神秘の書の最初の三ページを、ほとんど文字どおりに翻訳して、詩形に直したものであるが、これがはたして単なる翻訳であろうか?これらの詩の憂鬱な歓喜に満ちた音楽には、北方のプロテスタンチズム、イギリスの異端者、限りなき神秘派の魂そのものが、鈍く、憂鬱な、やむにやまれぬ憧れと、神秘的空想の激しい力とともに、名ごりなく表現されている。この奇怪な詩を読むと、さながら宗教改革時代の精神が耳に響く思いがし、当時ようやく始まったプロテスタンチズムの、焔のごとき闘争精神が理解し得るのみならず、ついには歴史そのものまでがわかってくる。しかも、それは単に思想のうえばかりでなく、あたかも自分がそこに居合わせて、武装した宗派の信徒たちの陣営のかたわらを通り過ぎ、彼らとともに讃美歌を唱え、彼らの神秘的な歓喜に包まれながら、あいともに泣き、彼らの信ずるところをともに信じているかのごとき、気持ちがしてくる。ついでながら、この宗教上の神秘主義とならんで、コーランからとった同じく宗教上の詩の一節、すなわち『コーランを倣(まね)びて』がある。はたしてこれが回教徒の歌でないだろうか、コーランの緒神そのものではないだろうか。その剣、素朴な信仰の荘重味、そのものすごく血なまぐさい力が感じられないだろうか?それから、今度は古代の世界として『エジプトの夜』がある。そこには、民衆の上にどっかとすわっている地上の神々がある。彼らはすでに国民的天才とその憧れを蔑視し、もはや民衆を信ぜず、まったく孤立せる神々となって、おのれの孤独のために発狂し、死滅のまえの倦怠と憂愁のために、ファンタスチックな残虐や、虫けらにひとしい淫楽、――雄をくい殺す雌蜘蛛のような淫楽で、おのれを慰めている神々である。いや、わたしは断固としていうが、プーシキンのような世界的共鳴の天才を持った詩人は、またとほかになかった。しかしこの際、問題は単なる共鳴ということばかりでなく、その驚嘆すべき深みと、他国民の緒神におのれの精神を同化さす力に存するのだ。その同化は、ほとんど完全無欠であるがゆえに奇跡的であり、世界じゅうのいかなる詩人にも、かような現象はくり返されなかったほどである。これはまったくプーシキンにのみ見られることであって、この意味において、くり返しいうが、彼は前代未聞の現象であり、われわれにいわせれば、予言的なものである。なんとなれば……なんとなれば、そこには彼のロシヤ国民的な力が表現されているからである。まさしく彼の詩魂の国民性、その向後の発展における国民性、現在にひそんでいるわが未来の国民性が、予言的に表現されているからである。実際、究極の目的において、全世界性と全人類性に対する希求にあらずして、はたして何がロシヤ国民の精神力であるか?完全に国民詩人となって、民衆の力にふれるやいなや、プーシキンはただちに、その力の偉大なる未来の使命を予感したのである。ここにおいて、彼は洞察者である。ここにおいて、彼は予言者である。実際、ピョートル大帝の改革はわれわれにとってなんであるか?単に将来についてのみならず、すでに過去となったこと、われわれの目前に出現したことについてもいうのであるが、この改革はわれわれにとって、はたして何を意味するか?それはわれわれにとって、ただヨーロッパ風の衣服や、習慣や、発明や、科学を摂取したということばかりではあるまい。事の真相を熟視して、その核心に徹しようではないか。しかり、あるいはピョートルもはじめはこの意味で、すなわち、ただそういった手近な功利的な意味だけで、改革を実施しはじめたのかもしれないが、その後、自分の理想が漸次発展するにつれて、ピョートルは疑いもなく、おのれの内部にひそんでいるある直覚にしたがって、単なる手近な功利主義より、まぎれもなく偉大な未来の目的に向かって、自分の仕事を進めて行ったに連いない。それとまったく同様に、ロシヤの民衆も、単なる功利主義から改革を受け入れたのではなく、手近な功利主義よりさらに遠大な、比較にならぬほど高邁な目的を、ほとんどただちに予感したに相違ない。目的を直感したといっても、またもやくり返すようだが、もちろん、無意識的にである。しかし、それは直接的であり、まったく生命的な感受なのである。事実、ロシヤ人はそのとき一挙にして、生命的な大同団結に向かって、全人類的結合に向かって突進して行ったのだ!われわれは敵意を持たずして(それは一見したところ、そうなりそうなことではあったけれども)、その反対に友諠的な気持ちで、完全なる愛をもって、われわれの魂の中に他国民の天才を受け入れたのである。しかも、民族上の優先的差別をせず、ほとんど第一歩から、本能によって矛盾を見分けて、これを取りのぞき、各々の相違をゆるし、かつ和解させながら、すべてのものを一様に取り入れ、それによって、われわれ自身にもその時はじめて明瞭になった傾向、すなわち偉大なるアーリア人種に属するすべての民族を、全人類的に結合しようというわれわれの傾向と、それに対する用意とを表示したのである。しかり、ロシヤ人の使命は、疑いもなく全ヨーロッパ的であり、全世界的である。真のロシヤ人になること、完全にロシヤ人になりきることは(この点をはっきり銘記していただきたい)、とりも直さず、すべての人々の同胞となることである。もしお望みなら、全人になることだと申しあげてもよい。おお、わが国のスラヴ主義とか西欧主義とかいうものは、歴史的に必然なものであったとはいえ、要するに、すべて大きな誤解にすぎないのである。真のロシヤ人にとってはヨーロッパも、偉大なるアーリア人種ぜんたいの運命も、ロシヤそのもののごとく、わが生みの国土の運命のごとく尊いものである。なぜなら、われらの運命は全世界性だからである。それも剣の力によるものでなく、われわれの人類同胞性と、全人類結合に対するわれわれの同胞的努力によって、獲得されたものである。もし諸君がピョートル大帝改革以後の、わが国の歴史の真意に透徹しようとするならば、その中にこの思想の痕跡と、わたしのこの空想の指示を見いだされるであろう。さらにお望みとあらば、わが国とヨーロッパ諸民族との交通の特質にも、またわが帝国の政策にさえも、それを発見することができるのである。この政策を行ないはじめた最近二世紀間に、ロシヤはなにをしただろうか、ロシヤは自分自身に奉仕するよりもおそらくはるか以上に、ヨーロッパに奉仕してきたのではないか?それは単にわが国の政治家たちの無能のために生じた、とばかりは考えられない。おお、ヨーロッパ各国民は、彼らがわれわれにとっていかに尊いかを知らないのだ!わたしはかたく信ずるが、後日われわれは、いや、もちろん、われわれではなく未来のロシヤ人は、すべて一人のこらず悟るであろう。――すなわち、真のロシヤ人なることは、とりもなおさず、ヨーロッパの矛盾に最後的な和解をもたらし、いっさいを結合する全人間的なおのれの魂の中に、ヨーロッパの悩みの捌け口をさし示し、同胞的な愛を。もってすべての同胞をその中に収め入れ、ついにはおそらくすべての民族を、キリストの福音にしめされた掟によって充全に同胞として結合さすにたる、伸大なる一般調和の決定的な言葉を発するという、かかる目的に向かって努力することを意味するのである!わたしは承知している、わたしの言葉は右頂天な、誇張した、幻想的なものに聞こえるかもしれないということを、あまりにもよく承知しているのである。しかし、かまわない、わたしはそれを口外したことを悔まない。これは当然、口外さるべきことだったので、ことに今、まさしくこの思想を芸術の力をもって具象化した、われらの偉大なる天才を追慕するこの盛大なる祭典にあたっては、なおさらこれをいう必要があったのである。この思想は、すでに一度ならず表白されたもので、わたしの言葉はもうとう新しいものではない。第一、これらのことは、あまりに思いあがった言葉に聞こえるかもしれない。「それはいったい、われわれの貧しい国についていっているのか、われわれの粗野な国土にそんな運命が授けられているのか?はたしてわれわれが、人類に新しき言葉を発する使命を有しているのか?」といわれるかもしれない。しかし、そこにはなにも不思議はないので、わたしは経済的方面の光栄や、剣や科学の光栄のことをいっているのではない。わたしはただ人間の同胞愛のことと、全世界人類の同胞的結合のためには、ロシヤ人の心がおそらくあらゆる国民の中で、最も適した素質を持っているだろう、という話をしたまでである。わたしはその形跡をわが国の歴史に、わが国の天分ある人々に、プーシキンの芸術的天才の中に見いだすものである。よしやわが国土がまずしいものであろうと、この国土は「キリストが奴隷の姿をかりて、祝福しながら遍歴された」ものである。どうしてわれわれが彼の最後の言葉を、内部に蔵しているはずがないといわれよう?またキリスト自身も秣槽(まぐさおけ)の中で誕生したのではないか?くり返していうが、少なくともわれわれはすでにプーシキンと、その天才の全世界性・全人類性を指示することができるのだ。事実、彼は他国の天才をさながら肉親のもののごとく、自分の魂に納め入れることができたではないか。芸術においては、少なくとも芸術的創作においては、彼はロシヤ精神の希求が全世界的であるということを、疑う余地もないほどに表現して見せたが、ここにもう偉大なる啓示があるのだ。よしんばわれわれの思想が夢であるとしても、プーシキンという人がある以上、少なくともこの夢の根拠となるべきところは存するのである。もし彼がもっと長くこの世に生きていたならば、あるいはヨーロッパの同胞に完全に理解されるような、偉大にして不滅なロシヤ魂の形象を創造して、今よりもさらに強く、さらに近く彼らを引き寄せ、われらの希求の真実さを残りなく、彼らに闡明(せんめい)したかもしれない。そうすれば、彼らも今よりずっとわれわれを理解し、われわれの気持ちを察して、今なお彼らが持しているような不信と、傲慢の態度をとらなくなったであろう。もしプーシキンがいま少し長命したならば、現在見受けられるような、われわれ相互の間の誤解と争いは、少なくなっていたに相違ない。しかし、神の裁きは別様であった。プーシキンはその力の延び行く最中にたおれて、疑いもなくある偉大な秘密を、墓の中に持ち去ったのである。かくして、今やわれわれは彼なき後にこの秘密を解かんとしているのである。
「作家の日記」1880年8月
河出書房「ドストエフスキー全集 15」作家の日記 下
昭和45年7月20日初版
昭和52年6月25日9版