作者の1961年のデビューから1974年までの短編を収録したもの。これに「オルシニア国物語」を加えると、初期のほぼすべての短編を読むことができる。70年代後半−80年代の短編は「コンパス・ローズ」で読める。
タイトルの「風の十二方位 The Wind's Twelve Quaters」は、いささか奇妙。というのは、方位は4、8、16、32で表示されるから。でも、wikiをみると、東洋では十二支による12方向の方位を用いていたとのことなので、それを採用したのだろう。なるほど、いくつかの短編には禅の思想(らしきもの)も含まれていて、著者が親近感をもっていたのだろう。ともあれ、風の全方位がここにあると示すことで、著者の短編の多様性と関連性を暗示しているのだと納得する。
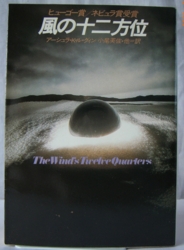
1.「セリムの首飾り」(1964) ・・・ 第一長編「ロカノンの世界」の第1章。
2.「4月は巴里」(1962) ・・・ 15世紀の錬金術師が黒魔術の呪文を使ったら、現代(1960年代)の古典文学者を呼び寄せてしまった。学芸の問題を楽しく話し、落ち着いた共同生活を楽しむ。さらに黒魔術を使ってみると。ハートウォーミングなファンタジー。
3.「マスターズ」(1962) ・・・ 若い修道僧が修士の院に入団する。そこでは無の数字や太陽が天を移動する理由などを考えていた。数十年ぶりに太陽が見えたとき、その院は異端の容疑で捜査される。知を求める自由が権力と衝突し、しかし知を求める自由は消えない。
4.「暗闇の箱」(1962) ・・・ 王位継承権を守るためには、兄弟とて容赦してはならない。兄が挑んできた戦いに勝利した王子は、海から流れ着いた箱をもらう。それは先王が海に捨てた「闇」を閉じ込める箱であった。その箱が開き、闇が現れる(シャミッソーの「影を無くした男」の再話かなあ)。
5.「解放の呪文」(1964) ・・・ 魔術と巨人に襲撃されている村と森を守るために王子は戦ったが、いまは城に幽閉されている。脱出の試みは失敗し、最後の解放の呪文を唱えた。どこかロード・ダンセイニの幻想譚を思わせる。
6.「名前の掟」(1964) ・・・ 真の名前を人に教えてはいけない孤島にはできの悪い魔法使い住んでいる。ある日、一人も魔法使いが閉じこもっている島の魔法使いに挑みに来た。不思議なオチの付け方だなあ。
7.「冬の王」(1969) ・・・ 「闇の左手」の前史。惑星<冬>の王が失踪し敵対する勢力から脅迫される。2週間後に発見された王は、自らに心理的な「爆弾」を仕掛けられ、敵対勢力のいうがままになることを知らされる。彼女(この惑星の住民は両性具有だ)がこの罠からすり抜けるために取った行動は?
8.「グッド・トリップ」(1970) ・・・ LSDでトリップするカップル。
9.「九つのいのち」(1969) ・・・ 辺境の開拓惑星に派遣されたのはクローン人間20人。彼らは同じ性格と思考で「社会的人間」として存在している。頻発する地震で19人が死亡した。残された一人の恐怖と孤独。テイラー「人間に未来はあるか」(みすず書房)のクローンの話題に感化されて書いたという。完全な複製生物は、行動パターンや知能が同じになるという強力な遺伝子決定論がその頃(1960年代)の主流の考えだった。その反映。
10.「もの」(1970) ・・・ 世界の破滅が迫り、人々は生産をやめ、都市を捨てた。一人残る煉瓦職人は、見えない島につながる道を作るために海辺に煉瓦を沈める。それを手伝うやもめと最後の子供。島に向かう日に起きた奇蹟。「明日世界が終わるとも、私は林檎の苗を植える」という言葉の変奏なのだろうなあ。心理的な神話と作者は言うがそういう趣き。
11.「記憶への旅」(1970) ・・・ 記憶のない男たちが放浪している。名前を思い出した時(アイデンティティを獲得した時)、男は仲間を失っている。
12.「帝国よりも大きくゆるやかに」(ヒューゴー賞候補、1971) ・・・ 恒星間飛行は片道なので、志願するのは精神疾患を抱えた人たちばかり。その中にエンパシー(人の感情を読む:言語や意見はわからない)能力をもつ自閉症患者がいた。彼は隊員の悪意を常に感じているので、それを鏡のように跳ね返し、誰とも仲良くなれない。到着した惑星は、植物だけがある。調査開始後一週間、隊員は森で恐怖を感じる。それは群体で完結している生物が初めて他者と接触したときの恐怖。自閉症患者は森との交信と試みる。隊員たちのコミュニケーション不全と森と人間の間のコミュニケーション不全が鏡のようにあわさり、互いに互いのメタファーになって無限の像を作る。そういう物語。これ一作で完結していると同時に、他の小説との連結もあるようなすばらしい傑作。たぶん「世界の合言葉は森」との関連を考察する学者もいるだろう。またルーマニアのSF作品であるアラーマ「アイクサよ永遠なれ」@深見弾編「東欧SF傑作集 下」(創元推理文庫)も生態系が一つの巨大な有機体であるという発想で共通点がある。
13.「地底の星」(1974) ・・・ 地動説を唱えたために異端にされ追われた老天文学者が使われなくなった坑道にはいる。そこの労働者は老人が何者かを知ったうえで受け入れた。天文学者はこんどは地下の星を観察する。ケプラーやガリレオの時代にあったかもしれない物語。
14.「視野」(1973) ・・・ 火星探検で<部屋>を発見し、そこに滞在した飛行士=研究者たちは帰還の途中で気が狂ってしまった。彼らの治療の様子から、<部屋>の体験があきらかになる。われわれの理解を超えた存在物と接触したとき、人間の認識はどのように変化するか、それは神的体験と区別がつくか、あたりが主題か。大江健三郎「治療塔惑星」、ストルガツキー「ストーカー」などと共通する。でも、一歩踏み間違えると映画「ミッション・トゥ・マーズ」になってしまう。
15.「相対性」(1973) ・・・ 裁判にかけられる樫の樹の独白。人間が持ち込んだ自動車が「相対性」をいかに失わせたか、彼らがいかに超越的存在を誤って理解しているか。
16.「オメラスから歩み去る人々」(ヒューゴー賞受賞、1973) ・・・ そのユートピア的な非資本主義的な幸福の都には一つの秘密がある。それは痴呆の子供が地下室に監禁されていること。幸福の都のすべての住人は子供のことを知っていて、境遇に憤激するが、子供がいるからわれわれの幸福が成り立つといずれ納得する。そうでないごく少数の人々は都を去る。なるほど序にあるように「カラマーゾフの兄弟」(大審問官)の主題の変奏。これは難問だ。
<追記2014.10.09>
「カラマーゾフの兄弟」の主題はイワンの告発に当たる以下のセリフ。
「さあ、答えてみろ。いいか、かりにおまえが、自分の手で人間の運命という建物を建てるとする。最終的に人々を幸せにし、ついには平和と平安を与えるのが目的だ。ところがそのためには、まだほんのちっぽけな子を何がなんでも、そう、あの、小さなこぶしで自分の胸を叩いていた女の子でもいい、その子を苦しめなければならない。そして、その子の無償の涙のうえにこの建物の礎を築くことになるとする。で、おまえはそうした条件のもとで、その建物の建築家になることに同意するのか、言ってみろ、うそはつくな!(カラマーゾフの兄弟 2」光文社古典文庫P248」
アリョーシャはしずかに「いいえ、しないでしょうね」と答えるが、オメラスは建物を建てたのだった。
17.「革命前夜」(ネビュラ賞受賞・ヒューゴー賞候補、1974) ・・・ 「所有せざる人びと」の前史。オドーというアナキズム(政府のない社会、ここでは組合他の自助組織が人々を緩やかに結合する政治形態を構想するもの)の思想家がいた。彼女の人生は革命の準備とアナキズムの理論化。そして明日ゼネストが予定され、政府が打倒される可能性のあるとき、彼女は72歳で、脳梗塞を患っている。生涯をかけて追及したものから疎外された人の老年の孤独。序によるとオドーは「オメラスから歩み去る人々」のひとりとのこと。
デビューからしばらくまでのはリーダビリティに乏しいのか、こちらの体調に問題があるのか、なかなか読み進むことができない。8の「グッド・トリップ」までは大変だった。「ロカノンの世界」「闇の左手」の長編に通じるストーリーもあったのに。ファンタジー色の強いもの(人に言わせると「少女マンガ的」)なものがどうも苦手だ。
後半の「九つのいのち」と「帝国よりも大きくゆるやかに」以降の6編は傑作揃い。途中でやめようかと思っていたのを我慢してよかった。ここにいたって短編は独立した物語になって(それ以前は長編の一部かスケッチみたいだった)、それ自体で主張と個性をもっている。解説によると、著者の思想は内外のさまざま人に研究されていて、いくつかの主要点を取り上げれば「孤独と愛」「科学的思考への憧れ」「ユング心理学の活用」「保守性と進歩性の二重構造」「非唯心論的(スピリチュアリズム)なロマンチスト」「理性への信頼」など。自分にはもはや付け加えることはないな。
アーシュラ・ル・グィン「ロカノンの世界」(ハヤカワ文庫)→ https://amzn.to/3IpMX6A
アーシュラ・ル・グィン「辺境の惑星」(ハヤカワ文庫)→ https://amzn.to/4342pig
アーシュラ・ル・グィン「幻影の都市」(ハヤカワ文庫)→ https://amzn.to/3v0yefj
アーシュラ・ル・グィン「闇の左手」(ハヤカワ文庫)→ https://amzn.to/4350Ale
アーシュラ・ル・グィン「オルシニア物語」(ハヤカワ文庫)→ https://amzn.to/3v4W7SU
アーシュラ・ル・グィン「世界の合言葉は森」(ハヤカワ文庫)→ https://amzn.to/48C9ZC0
アーシュラ・ル・グィン「天のろくろ」(サンリオSF文庫)→ https://amzn.to/3uYvPBM https://amzn.to/3V60HLf
アーシュラ・ル・グィン「風の十二方位」(ハヤカワ文庫)→ https://amzn.to/434P6y2
アーシュラ・ル・グィン「コンパス・ローズ」(サンリオSF文庫)→ https://amzn.to/3IrpZfi https://amzn.to/4a0d1Rz
アーシュラ・ル・グィン「所有せざる人々」(早川書房)→ https://amzn.to/4aiwHR1
<追記 2014/5/30> 「オメラスから歩み去る人々」の感想をいくつか紹介します。
一人の「見せしめ」を作ることでそれ以外の生徒に何かを教えられると謂うメソッドは、多くの生徒に何かを教える為に一人の無辜の犠牲を要求する方法論だと謂うことだ。人間は本当にそんな不合理な方法でしか何かを行い得ないのかと謂う問い掛けが「オメラスから歩み去る人々」のテーマだよ。
— knt(黒猫亭) (@chronekotei) 2013, 1月 19まあ、そうです。オメラスは普遍的な物語 RT @Ra_koyama: ル・グイン「オメラスから歩み去る人々」か。RT @kikumaco 1割の不幸な人を見ないことにすれば、9割の人は幸福と答える
— 菊池誠 (@kikumaco) 2012, 7月 20『きょうも上天気』に収録されてた「オメラスから歩み去る人々」、読んでみたけど、これ、共同体主義への批判にもなりかねないような…? 『これからの「正義」の話をしよう』ももう一度読んでみなきゃダメだな、これ。
— MaliS (@MaliSNacht) 2013, 8月 4たとえば、安い牛丼が販売されていて、多くの人は利便を得ているが、それは一人のアルバイトがワンオペレーションの過酷な労働を強いられることで提供されているとする。多数の顧客の利便をとるために現状を維持するのか、顧客が不便になるようにアルバイトの労働条件を変えるかということにつながるな。ちなみにこの思考実験では、アルバイトは辞めてほかの仕事をすることはできず、顧客はその店でしか牛丼を食べることができないという前提になっています。
<追記2018/12/6>
ドストエフスキー「プーシキン論」(作家の日記1880年8月)から抜粋(米川正夫訳)
もし幸福が他人の不幸の上にきずかれるならば、それがなんの幸福であり得ようぞ?ひとつこういうことを想像してみていただきたい。諸君が究極において人々を幸福にし、ついには彼らに平和と安静を与える目的をもって、みずから人間の運命の建物を築くとしよう。そこで、このためには必ず不可避的に、一人の人間を苦しめなければならないと仮定する。しかも、それはあまりたいした存在ではなく、見る人の目によっては滑稽に見えるくらいで、シェイクスピアとかなんとかいったような偉人ではなく、たかが潔白な老人というだけのことである。それは、若い妻の夫で、その妻の愛を盲目的に信じ、その心はまったく知らないながらも彼女を尊敬し、彼女を誇りとし、彼女によって幸福であり、平安なのである。つまり、こういった人間ひとりだけを辱しめ、穢し、苦しめて、この穢されたる老人の涙の上に自分の建物を築くのだ!はたして諸君はかような条件において、かかる建物の建築技師となることをいさぎよしとせられるか?これが疑問である。もしその土台に、たといつまらない存在であるとはいい条、不正に容赦なく苦しめられた人間の苦痛がこめられているならば、かかる建物を建ててもらった人々自身が、はたしてかような幸福を受け取ることに同意するだろうか。またその幸福を受け取ったにもせよ、永久に幸福でいられるなどという思想を、ただの一瞬間でも認めることができるだろうか?あれほど高尚な魂を持ち、あれほど苦しんだ心を持つタチヤナが、あれ以外の決心をすることができたかどうか、伺いたいものである。いな、純なロシヤの魂は、次のように決心するのである。「たとえ、たとえわたくし一人が幸福を失ってもかまわない、たといわたくしの不幸のほうが、この老人の不幸よりはかり知れぬほど大きかろうと、またこの老人をはじめだれ一人として、永久にわたくしの犠牲に気づかず、しかもその値を知ってくれなくとも、わたしは他人を滅ぼしてまで幸福になりたくない!」
プーシキン「エフゲーニ・オネーギン」におけるタチヤナの選択について述べた部分。
この話、入管問題や外国人技能実習生問題などを思い起こすと、人ごとではない。俺たちの国はこのような不幸な人々の上に建てられていて、存在しないかのように俺たちは暮らしている。俺たちは「わたしは他人を滅ぼしてまで幸福になりたくない」と言えるか。言っているか。
2019/11/28 フョードル・ドストエフスキー「作家の日記 下」(河出書房)-3(1880年)