1972年初出。すでにべ平連の運動が数年間継続。その間に、定例デモ、雑誌の刊行、さまざまな集会、雑誌新聞への反戦広告、アメリカ脱走兵支援などいろいろやってきた。病気で入院したので、そのときにまとめたのがこの本。
運動すること、社会の不正をただすことなど、自分の身にときとして危険になるかもしれない世直しに参加するのはどういうことか。その倫理を「無数のひとりの人間」から展開していき、運動の仕方(というか心構え)の論理を考えようということ。
背景にあるのは、1972年当時の風俗。すなわち、著者らのべ平連運動もあれば、新左翼と全共闘の反戦・反安保そして革命運動があり、継続中のベトナム反戦運動があり、中国では「文化大革命」があり、佐藤栄作の最後の任期中で、三島由紀夫の切腹があり…。新左翼の機関紙や雑誌は簡単に入手でき、ビラで彼らの主張を見るのも簡単。もしかしたら、みうちに逮捕者がいたかもしれない。連合赤軍とあさま山荘は店頭にこの本が並んだ頃に起きたし、中核と革マルの内ゲバが盛んになるのもこのちょっとあと。
当時の読者はこれらの出来事と、新左翼や旧左翼に組合の運動方法はよく知っていたし、同時にデモの現場での機動隊の暴力も知っていた。マルクス主義がどういう主張であるかも知っていたし、東欧ロシア東アジアその他の社会主義諸国で何かおかしなことが起きているということも知っていた。ソルジェニツィンやサハロフなど批判的文化人のソ連による弾圧も知られるようになっていた。
以上はこの本の中では自明なこととして書かれているので、40年もたつと、映像と注釈がないとわからないかもしれない。
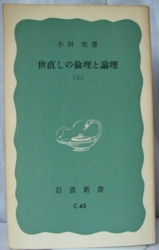
無数のひとりの人間 ・・・ 一人の人間=この<私>・だれも代替できないで生も死も一人で引き受けなければならない存在、が物事を考えるスタート。その<私>が世界や社会に参画して、問題にぶち当たったり、他者への暴力や理不尽に怒るところから「運動」=世直しが始まる。それは巻き込まれながら、まき込むこと。一人の運動の総体が「運動」とまとめられるかもしれないけど、実際にあるのは、ないし見えるのは一人ごとのそれぞれの個々の運動だけ。個々の運動では全体をと荒れることはできないが、運動している人とのかかわりから全体が見えるときがある。
(マルクス主義の社会分析の方法や組織論は影響力があるけど、ひとりの人間=この<私>の運動の子とはとらえることはできていないね。代わりに「革命」とか「党」とかの理念からスタートするので、スターリニズムや官僚主義や収容所群島や査問や内ゲバや「総括」殺人など、のこの<私>を裏切ることを平気でやらかすね。というマルクス主義運動の批判。)
「生きもの」としての人間から ・・・ この<私>は「生きている」という実感から「生きる」という概念がつくられていて、重要なのは実感のほう。「生きている」という実感には前置き(肩書とか職業とか思想とか所属とか)はなくて、根源的に平等であり、根源的に連帯している(ここでマルクスの生産様式の連鎖を想起してもよい)。でふつうは「人並みに安楽に生きたい」が願い出あるが、他人を押しのけたり押さえつけたりしている。さまざま理由で人並みや安楽ができなかったり、他人のことを慮ったりしたとき、この<私>は暮らしに切れ目を入れて「運動」=世直しを起こすことになる。それは英雄的でもなんでもなく、転向はごくありふれたこと。運動から弾き退くことがあるが、どこまで戻るかの歯止めが必要。敵の協力者、手先になるのではなく、敵に非協力になるくらいのところを確保しよう。それに運動で勝ったことに執着することはない。デモの勝ち負けで運動がきまるわけではないから。というのも人はなかなか死ぬものではないし、生き続けるのだから。運動(ことに勝ち負け)を続けることを目的にすると、非常事を装うことになり、「死を生きる」という倒錯が生まれる(まあ、なんてハイデガー、三島由紀夫、レーニン?)。そういう仕方で「死」を固有名詞で考えると、普段の暮らしからずれるよ。それより「死ぬ覚悟」という動きの中で考えるほうがよい。
くらしと「人間の都合」 ・・・ 「生きる」には、いのちとしごととあそびの3つからなる。このうちしごとをみると、ある時期(敗戦後とか開拓期とか)にはしごとはみんなのいのちを生きながらえる「たつき」であった。そこでは会社と働き手の間に境や垣根なんかはなかった。で人は暮らしが楽になると「マイホーム主義」になり、会社は成績と利益のことばかりを要求するようになり、しごとは「はたらき」になった。それが貫徹すると、マイホーム主義は会社の言いなりになることであり、会社の利益のためにマイホームを手放すようになってしまう。そこで抜けているのは「人間の都合」であって、会社や国家など暮らしから離れたところにある場所に対しては人間の都合を要求すべき。たとえば自主管理工場・民主経営会社などに消費者や材料供給会社を入れるように考えよう(ここは目からウロコの指摘!)。
「まき込まれた」歴史、「まき込まれる」現実 ・・・ 会社や国家が大きくなってくると、それが持つ「公」がこの<私>の一部である「公」を合わせるように強制される。困るのは国家の「公」が民主主義の公であると表現されていることで、民主主義という言葉がこの<私>の公にまではいっている。そこで国家=会社=この<私>の「公」がトライアングルになって、この<私>が会社や国家の公に抗するのが難しくなる。それは端的には会社や国家のピラミッドにあって、公に抗するときピラミッドがせり出してきて上にまでいけないしくみになっている。そのうえピラミッドの長には「大元帥」と「やさしい私人」の二つの顔があり、TPOにあわせて使い分けるので、ピラミッドがあること、現状維持することを肯定するように仕掛ける。
「しくみ」をかたちづくるくらしのなかで ・・・ この<私>は仕事や遊びを通じて経済や文化のしくみをつくっているし、まきこまれているし、区別を受けている。国家の顔を持つ人は暴力をふるったり示威行為をするのが認められていて、私人はやめさせられるか逮捕させられる。そのとき国家の顔を持つ人(軍人、警官、公務員など)が不正義を行ったとき、この<私>の追求を鈍らせる論理を国家や会社はもっている。それでも/だからこそ、この<私>は「人間の都合」から不正義を追及して、生きることが楽しくなるように世の中を変えていく。
(そのとき当時の自称革命家や警世人みたいに安易に死んで後の人にまかすなどというな、やるならまっとうしろ。世直しは生きるのが楽しくなるようにするのが目的だろ!と叱咤する。その通り。)
他に代替しようのないこの<私>という言い方は柄谷行人にもあって(たしか「探究」)、ここで借用した。この本には別の本の引用とか参考文献一覧はないので(病室にもちこめなかったのだろう)、たぶんとつけないといけないが、デカルト、ロックからアダム・スミス、マルクスなどの西洋哲学が見事にまとめられている感じ。この<私>から出発し、無数のひとりの人間との関係を見出し、関係(マルクス的には「交通」)からモラルやエシックスが浮かび上がってくるという展開が上の系譜の思想家のたどった道だものね。そして関係する諸個人から「しくみ」ができて、諸個人の「人間の都合」が無視されて、仕組みの都合が押し付けられるというのはマルクスの疎外論にあたるだろう。重要なのは、彼らの権威ある言葉を使わないで、著者のこの<私>の言葉で書くこと。さらには、他人の思想を顧慮することなく、自力で再発見すること。その時、書斎で考えに耽るのではなく、運動の現場で動きながら考えるというのが重要。次に何が起こるかわからない現場で、頭をくるくる回転させなければいけない、無数のひとりの人間の群れで全体が把握できない状況で、この<私>が試され、試していることが思想を深めて、実践的にしている。(なるほど機動隊の盾を目前にしたり、ヘイトの言葉を投げかけられる現場では、一瞬ごとが過去の事例のない新規な出来事ばかりが起こり、すばやく判断し決断しないといけない。そこでは本を読んだり、文句を暗証したりする余裕はない。一瞬ごとに自分のことばで考えなければならない。)
それを通じて、思想(というか考えとか運動とか世直しとか)は血肉化されるわけだ。のちの著者の本もこの本の延長にあり、いわば同じところをぐるぐるしているのだが、それは思想がちゃんとこの<私>のものになっているから。