前作「ミシェル 城館の人」で16世紀フランスを描いた次作「ラ・ロシュフーコー公爵傳説」では17世紀フランスを取り上げる。この博識な観察家によると、ばらばらだった断片が一つにつながる快感を得られる。箴言(マキシム)で高名なラ・ロシュフーコー公がデカルトやパスカルの同時代人であることを本書で知って驚くという具合に。
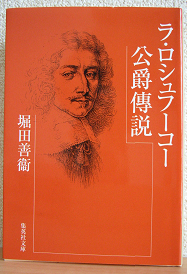
公爵の評伝に入る前に、社会や歴史などで教えてもらったことをメモしておこう。
・フランスは森の国であって15世紀までは森の収穫で年間に必要なものの3分の1を賄えた。それが17世紀にはいると、突如開墾の手が入る。牧場と小麦と葡萄畑。この時の人為によってフランスの景観が一変する。それは産業構造を変えることであり、政体にも影響する。隣国イギリスでは清教徒革命が起こっている。
・開墾によって自給自足体制になったので、貿易や植民地には関心を持たない。そのため国庫の収入は周辺国(イタリア、オランダ、スペイン、イギリスなど)に及ばず、王室の経営は常に危うい。
・前世紀の宗教戦争は継続。ルイ13世の時代にはリシュリュウ枢機卿が実権を握り、有名貴族と組んで、内外の戦争を継続する。途中、プロテスタントの牙城を制圧し、スペインとの戦いにも勝つ。おおよそカソリックが主権を得ることに成功。とはいえ外交の進捗は遅く、内戦が頻発するので、王室の財政はいつもからっぽ。諸外国に借金することで対応していたが足りなくなり、さまざまな税金を課していたので、民衆の不満は高まっていたのだった。
・それを鎮められない理由は王権の不安定さにあり、王と外国から嫁いだ王妃との関係はよくなく、枢機卿が政権運営をするのを王が統制するのも難しい。王妃は枢機卿を蹴落とす陰謀を企み、貴族は誰につくかをしょっちゅう変えていた。もはや政治を動かすのは、貴族とその集まりの高等法院ではなく、枢機卿のまわりにいる官僚の側になっているのだった。
・17世紀(のフランス)は女性の時代。陰謀をすることで政治にかかわるものが出て、貴族の女性は屋敷にサロンを設けて、文芸・文学の徒を集める。男性のみだった舞台俳優に女性がなることが許された、など。
・1642年に、リシュリュウ卿、ルイ13世が相次いで亡くなる。王権は4歳のルイ14世にうつるが、リシュリュウが後を継がせたのはイタリア出身のマザラン枢機卿。王が政務をとれない時、取り巻きが権力を代行し、その権力を獲得する闘争も起こる。1648年のフロンドの乱がそれであるが、新しいのは民衆が税務をつかさどる官僚に反抗し、古い権力である貴族らの高等法院を支持したこと。民衆(ただしパリ市民くらい)が政治に関与するようになる端緒。
このあと1650年のボルドオの乱があり、マザランが失脚、ルイ14世も権限を失うわと混乱は続く。でも主人公のラ・ロシュフーコー公爵は老年(40歳)になり痛風に悩まされ、政治と軍事の一線からは退く。どうやらこの後30年ほどたった1680年にはルイ王朝に権力が集中し、絶対王政が確立する。あと重要なのは、ルイ14世の宗教寛容令が出てもプロテスタントへの迫害、差別は続き、プロテスタントは周辺諸国やアメリカなどに脱出移住するようになった。
堀田善衛「歯車・至福千年」(講談社文芸文庫)→ https://amzn.to/3TzIzHm
堀田善衛「広場の孤独」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3TyWLk4 https://amzn.to/3vunHt2
堀田善衛「歴史」(新潮文庫)→ https://amzn.to/4aukzfv
堀田善衛「記念碑」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3vwOipy
堀田善衛「時間」(新潮文庫)→ https://amzn.to/43EXW6a
堀田善衛「奇妙な青春」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3vvIBbi
堀田善衛「インドで考えたこと」(岩波新書)→ https://amzn.to/4cwhiOP
堀田善衛「鬼無鬼島」(新潮日本文学47)→ https://amzn.to/3xoefrC https://amzn.to/3TDmlnO
堀田善衛「上海にて」(筑摩書房)→ https://amzn.to/3PJCGWX
堀田善衛「海鳴りの底から」(新潮文庫)→ https://amzn.to/4axgGX8 https://amzn.to/3TVq5Th https://amzn.to/3TVEq1G
堀田善衛「審判 上」(集英社文庫)→ https://amzn.to/43ANAUB
堀田善衛「審判 下」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IWDkN5
堀田善衛「スフィンクス」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3TUfg3G
堀田善衛「キューバ紀行」(岩波新書)→ https://amzn.to/4cwhvBB
堀田善衛「若き日の詩人たちの肖像 上」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3vwEPOW
堀田善衛「若き日の詩人たちの肖像 下」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3TCxbKR
堀田善衛「美しきもの見し人は」(新潮文庫)→ https://amzn.to/4cvGTat
堀田善衛「橋上幻像」(集英社文庫)→ https://amzn.to/49jslYK
堀田善衛「方丈記私記」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3IUqfDR
堀田善衛「19階日本横町」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3TB9PoT
堀田善衛「ゴヤ 1」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3TzknEX
堀田善衛「ゴヤ 2」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3TTnXLs
堀田善衛「ゴヤ 3」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3IRZj7U
堀田善衛「ゴヤ 4」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3vwOogU
堀田善衛「ゴヤ」全巻セット(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3vwPNE1
堀田善衛「スペイン断章〈上〉歴史の感興 」(岩波新書)→ https://amzn.to/49k7RPr https://amzn.to/3xlcrzG
堀田善衛「スペインの沈黙」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/3J0K508
堀田善衛「スペイン断章〈下〉情熱の行方」(岩波新書)→ https://amzn.to/4ar4JD7
堀田善衛「路上の人」(新潮文庫)→ https://amzn.to/49e9vlJ
堀田善衛/加藤周一「ヨーロッパ二つの窓」(朝日文庫)→ https://amzn.to/3IRZCzA https://amzn.to/43xqSwR
堀田善衛「歴史の長い影」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/4ae0ydy
堀田善衛「定家明月記私抄」(ちくま学芸文庫)→ https://amzn.to/3PE2vaW https://amzn.to/3VU2Muv
堀田善衛「定家明月記私抄 続編」(ちくま学芸文庫)→ https://amzn.to/3PGKWHn
堀田善衛「バルセローナにて」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3PEoI8Q
堀田善衛「誰も不思議に思わない」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/4ai7hDu
堀田善衛「ミシェル 城館の人1」(集英社文庫)→ https://amzn.to/4cBgKHc
堀田善衛/司馬遼太郎/宮崎駿「時代の風音」(朝日文庫)→ https://amzn.to/3IYDbsx
堀田善衛「ミシェル 城館の人2」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IVZ9w5
堀田善衛「めぐりあいし人びと」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IREiKB
堀田善衛「ミシェル 城館の人3」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3PH4tat
堀田善衛「ミシェル 城館の人」全巻セット(集英社文庫)→ https://amzn.to/4acvVVZ
堀田善衛「ラ・ロシュフーコー公爵傳説」(集英社文庫)→ https://amzn.to/49k7DYB
2022/08/01 堀田善衛「ラ・ロシュフーコー公爵傳説」(集英社文庫)-2 1998年に続く