2022/08/02 堀田善衛「ラ・ロシュフーコー公爵傳説」(集英社文庫)-1 1998年の続き
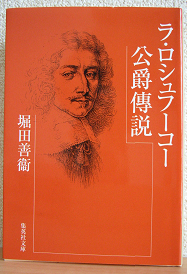
ラ・ロシュフーコー公爵家はフランス南部の名家。この名を持つ土地を所領にして、フランス王の覚えも愛でたかった。本書の主人公フランソア六世・ド・ラ・ロシュフーコー公爵は1613年生まれ。感想1にまとめたフランス王と貴族、あるいはカソリックとプロテスタント、あるいは周辺諸国の横やりや後押しによるいさかいや争いにおいて、コンデ公を支援するように働いた。したがって前半生は戦いの日々であり、当時の貴族の常として支出は多いが領地の収入は減少する一方(戦で人が流動し耕作が滞る)で借金に苦しむ(そこで年若い家令のグールヴィルが全土を神出鬼没して、王の周辺や貴族、聖職者などとの関係を結び、ついにはフランス宮廷の財務担当大臣にまで出世するという愉快な物語がついている)。武弁一方ではなく、読書に励むような知識人でもあり、40代の若さで痛風を発症し家族のほとんどを失ったときに、パリの貴族サロンに招かれるようになった。それは知的な女性が主催し、政治的な情報を得ようとする場でもあったが、眼目は新しい文芸の披露と批評であった。それまでの詩の朗読や劇の上演にかわり、「肖像」という人物デッサンやマキシム(箴言)を読み上げるのである。それを聞いた人々は批評批判しあい、すぐれたものを出版するのであれば支援するような場であった。戦乱と動乱の世にあって、おそらく数百人という少数であっても互いに顔見知りであり長年の付き合いで気心も知れている場で、文芸が育てられたのであった。
(おもいかえせば、貴族のような知的人物が文芸を切磋琢磨するというサークルやサロンが成立したのは中世日本の宮廷と、17世紀フランスのサロンくらいではないか。)
2016/04/15 堀田善衛「定家明月記私抄」(ちくま学芸文庫) 1986年
2016/04/14 堀田善衛「定家明月記私抄 続編」(ちくま学芸文庫) 1988年
そこにおいてラ・ロシュフーコー公爵はマキシムの名人であった。ずいぶん昔の学生時代にラ・ロシュフェコー(岩波文庫の著者名による)の「箴言と考察」を読んでいる。もちろんそのときには、著者がデカルトやパスカルの同時代人であることも、「フロンドの乱」と呼ばれる宮廷の内輪もめに端を発する内乱に参加していたことも知らなかった。ただ、この人のひどくペシミスティックで辛らつな文章と意見にはとても興味を持った。手元にある文庫を持ってきて、当時の自分が印をつけたものを書き置くと、
「太陽と死とは、じっとして見てはいられない。」
「われわれの美徳は、ほとんど常に、仮装した悪徳にすぎない。」
「ほんとうに愛しなくなったものを、またあらためて愛することは不可能だ。」
という具合に、よく知られているものに反応する凡庸な若者だった。それに同じ主題や内容の箴言がページを変えて繰り返される。ひとつにまとめて体系化することも可能だろうと考えたことがある。あいにくPCのカード型データベースを知らなかったのでとん挫した(同様の集約化をする論文がどこかにあったと記憶)。しかし、同じテーマの繰り返しは作者の意図であることを知り不遜な考えであったことを知る。マキシムは文脈(コンテキスト)を持たず自己完結したもので、それ自体を味わうものであり、分散しているところに価値がある(その点和歌に似ているな)。重要なのは人間を観察すること。神さまと照らし合わせることなく、人間の言動をみましょう。というわけで公爵が関心をもつのは虚栄心、情熱、自己愛など。公爵の手法は「〇〇は△△に過ぎぬ」という否定的断定法(という名前がついているんだ、へえ)。それは受けたけど、人間に対して厳しすぎる、単刀直入に過ぎる、寛容に書ける、復讐心がある、虚無的であるなどの批判批評がサロンであったらしい。(若いころには公爵の否定的断定法に驚かされたものだけど、理屈っぽい自分としては体系だった政治哲学で考えたい。人間を突き放した公爵のマキシムをそのまま受け取ると、他人の価値を低くしてしまいそうだ。そこから正義や善のまとまった考えをもたらさないとなると、モッブの冷笑と政治への無関心を生みそうだ。)
作者堀田善衛はこれまでに藤原定家、ゴヤ、モンテーニュ等の評伝-小説を書いていたのだが、そこでは作者と対称の人物は離されている。彼らの感情を書くときには、作品を読み上げて、そこから掬い取るようにしていた。しかし作者最晩年の作である本書では、語り手は公爵その人になる。なので、感情や心理は独白として地の文として描かれる。すると記述者である作者堀田善衛の姿が消える。というかいうべきことが失われる。最後あたりの章でマキシムを並べるとき、注釈・解釈は書かれず(モンテーニュや定家ではあれほど言葉を費やしたのに)、ひとことの慨嘆くらいしか追記されない。マキシムで十分に語りつくした自己完結した者なので、もはやなにも付け加えることはない。語り手の存在がなくてもよい文芸形式なのだ。
あとは、公爵はラ・ファイエット夫人(21歳年下)と懇意であり、彼女の書いた「クレーブの奥方」の出版に尽力したことを追加しておこう。公爵はデカルトやパスカルをよく知っていたのみならず、モリエールやラ・フォンテーヌらも知っていた。公爵を描くことで、17世紀フランスのサロンの広がりや知識人たちのつながりが見えてくる。
堀田善衛「歯車・至福千年」(講談社文芸文庫)→ https://amzn.to/3TzIzHm
堀田善衛「広場の孤独」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3TyWLk4 https://amzn.to/3vunHt2
堀田善衛「歴史」(新潮文庫)→ https://amzn.to/4aukzfv
堀田善衛「記念碑」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3vwOipy
堀田善衛「時間」(新潮文庫)→ https://amzn.to/43EXW6a
堀田善衛「奇妙な青春」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3vvIBbi
堀田善衛「インドで考えたこと」(岩波新書)→ https://amzn.to/4cwhiOP
堀田善衛「鬼無鬼島」(新潮日本文学47)→ https://amzn.to/3xoefrC https://amzn.to/3TDmlnO
堀田善衛「上海にて」(筑摩書房)→ https://amzn.to/3PJCGWX
堀田善衛「海鳴りの底から」(新潮文庫)→ https://amzn.to/4axgGX8 https://amzn.to/3TVq5Th https://amzn.to/3TVEq1G
堀田善衛「審判 上」(集英社文庫)→ https://amzn.to/43ANAUB
堀田善衛「審判 下」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IWDkN5
堀田善衛「スフィンクス」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3TUfg3G
堀田善衛「キューバ紀行」(岩波新書)→ https://amzn.to/4cwhvBB
堀田善衛「若き日の詩人たちの肖像 上」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3vwEPOW
堀田善衛「若き日の詩人たちの肖像 下」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3TCxbKR
堀田善衛「美しきもの見し人は」(新潮文庫)→ https://amzn.to/4cvGTat
堀田善衛「橋上幻像」(集英社文庫)→ https://amzn.to/49jslYK
堀田善衛「方丈記私記」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3IUqfDR
堀田善衛「19階日本横町」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3TB9PoT
堀田善衛「ゴヤ 1」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3TzknEX
堀田善衛「ゴヤ 2」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3TTnXLs
堀田善衛「ゴヤ 3」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3IRZj7U
堀田善衛「ゴヤ 4」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3vwOogU
堀田善衛「ゴヤ」全巻セット(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3vwPNE1
堀田善衛「スペイン断章〈上〉歴史の感興 」(岩波新書)→ https://amzn.to/49k7RPr https://amzn.to/3xlcrzG
堀田善衛「スペインの沈黙」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/3J0K508
堀田善衛「スペイン断章〈下〉情熱の行方」(岩波新書)→ https://amzn.to/4ar4JD7
堀田善衛「路上の人」(新潮文庫)→ https://amzn.to/49e9vlJ
堀田善衛/加藤周一「ヨーロッパ二つの窓」(朝日文庫)→ https://amzn.to/3IRZCzA https://amzn.to/43xqSwR
堀田善衛「歴史の長い影」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/4ae0ydy
堀田善衛「定家明月記私抄」(ちくま学芸文庫)→ https://amzn.to/3PE2vaW https://amzn.to/3VU2Muv
堀田善衛「定家明月記私抄 続編」(ちくま学芸文庫)→ https://amzn.to/3PGKWHn
堀田善衛「バルセローナにて」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3PEoI8Q
堀田善衛「誰も不思議に思わない」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/4ai7hDu
堀田善衛「ミシェル 城館の人1」(集英社文庫)→ https://amzn.to/4cBgKHc
堀田善衛/司馬遼太郎/宮崎駿「時代の風音」(朝日文庫)→ https://amzn.to/3IYDbsx
堀田善衛「ミシェル 城館の人2」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IVZ9w5
堀田善衛「めぐりあいし人びと」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IREiKB
堀田善衛「ミシェル 城館の人3」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3PH4tat
堀田善衛「ミシェル 城館の人」全巻セット(集英社文庫)→ https://amzn.to/4acvVVZ
堀田善衛「ラ・ロシュフーコー公爵傳説」(集英社文庫)→ https://amzn.to/49k7DYB
長い時間がかかった堀田善衛の作品読み直しもこれで終了。楽しませていただいたし、おしえていただきました。ありがとう。