続けて第2巻。アディスンとスティールはこの本以外で名前をきいたことがないや。
「第3編 アディソンおよびスティールと常識文学
1 常識/2 訓戒的傾向/3 ヒューモアとウイット
第4編 スウィフトと厭世文学
風刺家としてのスウィフト/スウィフトの伝記研究の必要/「桶物語」/「ガリヴァー旅行記」
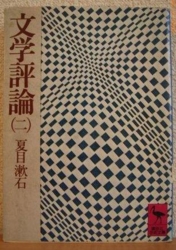
背景を確認すると、1668-69年の名誉革命によって統治の権利が国王から議会に委譲された。そこから選挙権とか被選挙権(立候補して国政をやるぞという決意表明)を人々がもつようになって(もちろん今日の目から見れば非常に制限されたもの)、生活の余裕を持つ人たちが政治に意見を持ち始めた。そこにはたぶん、利権を獲得するとか、自分に有利な税制や規制をしろなど底意があったはず。その一方には、こういう人々の勝手な主張とか縄張り争いなどに目をひそめる人もいて、百家騒乱状態になっていたのだろう。この「民主主義」に腐敗というのは、そういう制度にした後、一度は起こるものらしく、その後どのように改革していくかが重要なのだろう。漱石の記述によれば、18世紀初頭において、政治的寛容が重要という意見があったり風潮になっていたとのこと。英国の革命ではほとんど流血騒ぎもなく、たしかカソリックと英国国教会の確執でも死者は出ていなかったと思う。このあたりの自由と寛容と規律というのは重要で、勉強しておいたほうがよい。隣国フランスが17世紀の宗教戦争や18世紀の革命でひどい流血騒ぎを起こしているとか、スペインほかカソリックの異端審問、宗教裁判で多くの死者をだしていることを思い出しておきたい。とりあえずこの国と比較すると、英国では18世紀で民主主義があったが、こちらでは17世紀にようやく中央集権の封建体制になっていた(それまでは二重三重の権力がアマルガム状態になっていたのだった)。この違いは頭に入れておこう。
あと、英国というけど「イングランド」「ウェールズ」「スコットランド」「アイルランド」はそれぞれ異なる意識を持っていて必ずしも一枚岩の国家ではないことに注意。イングランド以外の場所にいる人にとって は、ときには腹にすえかねるようなことをイングランドに感じているらしい。スウィフトがアイルランド出身であって、栄達や名声とは無縁に過ごしたことが、「ガリヴァー旅行記」の風刺につながってるのではないか、と漱石の意図以上の深読みをしておく。
さて、第3編と第4編は対になっていて、前者はイングランドの常識文学家で、後者はアイルランド出身の厭世・風刺・皮肉の文学。現在のこの国では前者の文章を読むのは困難。漱石のまとめをさらにまとめると、議会の権限が拡大し、かつヨーロッパの中では安定した政情と軽工業の発展でイギリスは反映 繁栄していた(しまったインドの植民地経営の成功で利益が流れ込んでいたのを忘れていた)。そこで「満足した階層」が生まれて、彼らが徳やマナーを啓蒙する役をになうことにした(誰かが頼んだわけではない)。そのときにアディソンおよびスティールがおもに雑誌や新聞の記事、小文を発表した。そのときに、自分のことをいったん棚に上げて(ないし上から目線のところに自分をおいて)、世間に小言を言ったのであった。それで常識文学。対象になるのは都会で頻繁に見られることで、とくに想像力を必要とするわけではない。
スウィフトについては説明不要だな。せいぜいガリヴァー旅行記の小人国、大人国、飛行国、馬の国が著者の想像力の産物であることが強調されるけど、前世紀からこの時代の博物学では不思議な人種が図版でもって表現されていたのだ(荒俣宏「目玉と脳の冒険」(筑摩書房)など)。
この第3、4編のキーワードは「愉快」。この「愉快」について生活上の、文学上の、などさまざまな場合について説明している。
夏目漱石「倫敦塔・幻影の盾」→ https://amzn.to/4d1PiCH https://amzn.to/4aAAedK https://amzn.to/3xKkpTu
夏目漱石「吾輩は猫である」→ https://amzn.to/3xGC7ae https://amzn.to/3UlzIdR
夏目漱石「坊ちゃん」→ https://amzn.to/49CnsKp
夏目漱石「草枕」→ https://amzn.to/49MESE9 https://amzn.to/3U4zVRr
夏目漱石「二百十日・野分」→ https://amzn.to/3W4fhDQ
夏目漱石「虞美人草」→ https://amzn.to/3Ulwh75
夏目漱石「坑夫」→ https://amzn.to/3JpZUxY
夏目漱石「文鳥・夢十夜」→ https://amzn.to/3w0gAcb https://amzn.to/3UjH2a2 https://amzn.to/3Q9iDRX https://amzn.to/3U4zOW1 https://amzn.to/3xE8pmr
夏目漱石「三四郎」→
夏目漱石「それから」→ https://amzn.to/49FGwYn
夏目漱石「文学評論」→ https://amzn.to/3W2HCdm https://amzn.to/3Q9kxlD https://amzn.to/4aAGjaj
夏目漱石「門」→ https://amzn.to/3UjH3L8
夏目漱石「彼岸過迄」→ https://amzn.to/4cVqqgd
夏目漱石「行人」→ https://amzn.to/3VWNhSq https://amzn.to/3VY9uQ1
夏目漱石「こころ」→ https://amzn.to/49AZOhu https://amzn.to/4420IlS https://amzn.to/3U279ku https://amzn.to/3vXiKJs
夏目漱石「私の個人主義」→ https://amzn.to/3Jo4Zqw https://amzn.to/49FQU2i
夏目漱石「硝子戸の中」→ https://amzn.to/3w0ggtZ
夏目漱石「道草」→ https://amzn.to/3UlwuqT https://amzn.to/49GVJYY
夏目漱石「明暗」→ https://amzn.to/3VYzfQf https://amzn.to/3TZzYy1
水村美苗「続 明暗」→ https://amzn.to/3UncMv1
島田荘司「漱石と倫敦ミイラ殺人事件」(光文社文庫)→ https://amzn.to/3vWFw4h
柳広司「贋作『坊っちゃん』殺人事件 」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3vVappQ
柳広司「漱石先生の事件簿 猫の巻」(角川文庫)→ https://amzn.to/49FRcGq
奥泉光「『吾輩は猫である』殺人事件」(新潮文庫)→ https://amzn.to/4b1C1rZ
小山慶太「漱石が見た物理学」(中公新書)→ https://amzn.to/3UmudM6
