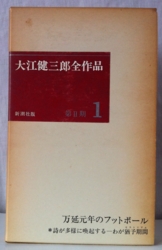2017/01/17 大江健三郎「万延元年のフットボール」(講談社文庫)-1 1967年
2017/01/16 大江健三郎「万延元年のフットボール」(講談社文庫)-2 1967年の続き。
蜜と鷹が帰る四国の山の中の村。周囲は森に囲まれ、隠遁者ギーという老人のほかは村人でさえ迷うことのあるほど鬱蒼としている。森の直前には敷石道があり、村の「御霊」はこの道を通る。一本の川が流れ、最も下流は「窪地」と呼ばれほとんどの村人が住む。その上流には「在」と呼ばれる地域があり、村の中心ではない人たち(新参者である根所家や住職など)が住む。大竹藪があり、御霊はここから登場する。さらに奥まった住むのによくない土地には強制連行された朝鮮人部落があった。この村は「大窪村」と呼ばれる(村に固有名がついているのはこの作品くらい)。
これまでとそのあとの「村(あるいは村=国家=小宇宙)」は、村は日本という国家や権力の外にあって、「天皇制」とまとめられるシステムを批判ないしオルタナティブになる場所であった。ところがこの小説での「村」にはそのモチーフはあっても強調されない。なるほど万延元年の一揆があって、藩権力と対峙はしたのである(なおもうひとつの反権力闘争があったことがわかる)。しかしむしろここでは村の権力の在り方に注目する。すなわち江戸時代の楮の生産と卸で巨富を得ながら明治維新後は衰退するばかりであり、15年戦争時には朝鮮人部落を作り差別する(一方で部落が生産するものにも依拠する)。内部には不可視の中心があり、新参者やよそ者を排除する差別の階層がある。差別される側には根所家と住職と蔵屋敷の住人ジン一家がある。住職は妻に逃げられたので、村人の嘲笑の的。ジンはもともと村の雑用を押し付けられるもの。大食症で太りあがったのちは、村人が支援するようになる(異形のものには排除と聖化が同時に起こるのだ)。外に大きな権力があれば反感と不平を持ちつつ従順であり、内の被差別階層には厳しくあたる。その典型が敗戦直前の朝鮮人部落襲撃であり(死者が出て、朝鮮人の物資を強奪する)、戦後のスーパーマーケットに対する服従である。この「村」を自分は20世紀の「日本」とみた。無名にされた村人と青年会の言動は、この国の政治と大衆に合致している。
鷹四の結果として「たった一人の反抗」もまた、リーダの不祥事で総スカンをうけ、自殺の追いやるような陰湿ないじめが行われる。この反応もまた「日本的」。とはいえ自分は鷹四の行動に同意や賛同するわけではない。彼の自己破壊的な、他人を手段として利用する機会主義的な運動、一時的な熱狂で蜂起にむかわせる扇動と自分以外に指導者を作らない独裁的な方法、これらもまた「日本的」。これらの醜悪な「日本」を描き出す。「村」の歴史はこの日本のありえたかもしれない(しかし実勢としてはほぼ同じ)歴史である。
(そういうところは「遅れてきた青年」や「治療塔」などに通じるはず)。
(とはいえ、この「村」の歴史でいやな気分になるのは、「スーパーマーケットの天皇」が襲撃された朝鮮人であるという設定かな。なるほど差別されたものが復活して権力者となって、村=日本に復讐するというのは、15年戦争の対戦国であるアメリカの暗喩になるのだろう。そうは読み取っても、戦後の在日朝鮮人から生産や商人資本家になったものがいたという事実があるのを知っても、在日朝鮮人のこの描き方は実際と離れすぎていてありえないよなあという気分になる。「スーパーマーケットの天皇」の一存で、村の象徴的な建築物であった蔵屋敷が破壊されるというのものねえ。ドラマの必要に応じたアクションであるのは読み取れるが、ないよなあという感じ。)
2017/01/12 大江健三郎「万延元年のフットボール」(講談社文庫)-4 1967年に続く。