2020/01/28 チェルヌイシェフスキー「何をなすべきか 上」(岩波文庫) 1863年
2020/01/27 チェルヌイシェフスキー「何をなすべきか 下」(岩波文庫)-1 1863年 1863年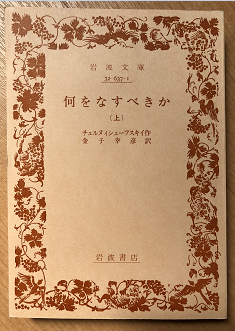

「宮殿」の比喩が二回出てくる。この比喩には同時代のドスト氏が「地下室の手記(地下生活者の手記)」で批判しているので注目。
一回目は、第3章の終わりに出てくるラフメートフの人となりにおいて。ヴェーラの前に現れた男は、軍人や医学生などロシア帝国の上流階級。帝国のシステムが維持される限り、大きな失敗をしない限りは、それなりに「豊かな生活@ガルブレイス」が保証された身分。このラフメートフは地方の中産階級の出で、父の代までに没落している。そこで国内およびヨーロッパ各地を放浪し、下層階級の中でもまれてきた(チェ・ゲバラや主徳、ホー・チミンらの経歴に似ている)。そこから「民衆の中へ」と決意し、自身を「革命家」と規定して、定住地を持たない暮らしを選択する(おそらく家族も作らないから、ラフメートフはボリシェヴィキの「革命家」第一号にあたる。レーニンが熱狂したのはここかな?)。そのようなラフメートフを著者は「宮殿を作る人」、英雄と呼ぶ。なんとなれば、ほとんどの人は地下のひとであり(ヴェーラの最初のパートナーであるロプホーフはヴェーラを「地下室からでられる」といって求愛したのだった)、そこから脱出できてもせいぜい「地面の人」である。そのような地面の上に建てるのが「宮殿」なのだ。
その宮殿が具体的になるのは、第4章でヴェーラが見る夢において。過去とも未来ともつかないのは夢だから。どこかの町。女神に案内される街は生活と労働の苦労がない。男女同権が実現されていて、各人が平等で自由。すなわち女が男の「所有物」「奴隷」「純潔な処女」であることがなくなったので。町の中心には鉄とかガラスでできた透明「宮殿」がある。人々はそこにはいないが、劇場・図書館・美術館などにいて、自分の好きなことをしてよい。すなわち他人に強制される労働はなく、自分に必要な応分の生産作業をすればよく(多くの作業は機械が行っている)、それ以外は各人の自由になるから。このユートピア幻想は具体性に乏しく詩的なイメージで書かれている。ユートピアの運営にさほど拘泥しないのは、このユートピアがヴェーラの共同経営や生産消費協同組合の延長にあるからだろう。他のところで運営に関する議論はすましているからだ。
ロシアは資本主義の黎明期であるとか、経済学は古典派しかないとか、著者が参照できる情報は少ないので、ユートピアの構想が空想的になってしまうのは仕方ない。そのうえ、人間の心理に対する考察もないので、集団化された人間の動向を楽天的に考えているのも不十分(そこはイギリスやフランスの革命を見て、ポピュリズムについて考えてほしかった(カール・マルクス「ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日」が1852年にでているが、さすがにロシアでは読めなかっただろう)。
21世紀の読者は、本書がでてからの150年の間に、全体主義の監視社会やマイノリティへのホロコーストが行われたり、ポピュリズムによる社会の不安定を見たりしているので、著者の提起した社会変革のプログラムにはさまざまな不備があることを知っている。著者が「宮殿の人」と呼んだラフメートフのような革命家がいかに民衆を嫌悪したかも知っている。もはや、これを読んで革命運動に参加することはないだろうし、ラフメートフをロールモデルにする人もいないだろう(彼の放浪癖はドスト氏のスタヴローギン@悪霊に似ている。いずれ彼と同じ民衆嫌悪に至るのではないかと危惧)。
むしろ可能性は不十分にしか書かれていない共同経営と生活消費協同組合にみたほうがよいか。これもまた150年の間に実験と失敗、弾圧の繰り返しなので、成功の可能性はとても低い。それでも資本主義ではない経済を構想するとき、魅惑的にみえるのだよなあ。
もう一つの論点は、「地下生活者の手記」にはあらわれず、ずっとのちの「カラマーゾフの兄弟」での告発だろう。イワンの以下のセリフ。
「さあ、答えてみろ。いいか、かりにおまえが、自分の手で人間の運命という建物を建てるとする。最終的に人々を幸せにし、ついには平和と平安を与えるのが目的だ。ところがそのためには、まだほんのちっぽけな子を何がなんでも、そう、あの、小さなこぶしで自分の胸を叩いていた女の子でもいい、その子を苦しめなければならない。そして、その子の無償の涙のうえにこの建物の礎を築くことになるとする。で、おまえはそうした条件のもとで、その建物の建築家になることに同意するのか、言ってみろ、うそはつくな!(カラマーゾフの兄弟 2」光文社古典文庫P248」
チェルヌイシェフスキーの小説には「宮殿」のなかに「小さなこぶしで自分の胸を叩いていた女の子」はいないようにみえる。なにしろ「地下室」に住む人は宮殿ができるまでにいなくなってしまったからだ。社会変革が隅々まで行き届くと、すべての人は地上にでてくると考えているわけだ。
しかし、「地下室」に生活するドストエフスキーはそのような子供を幻視する。あるいは領主に鞭打たれる農民や馬であるかもしれない(でもドスト氏はロシア社会のマイノリティであるユダヤ人には冷淡。どころか差別的)。彼らのような辱められ虐げられた人々が宮殿の地下室に閉じ込められている。彼らは革命家にもなれず、革命から取り残される人々だ。革命家になった人たちは宮殿で優雅に過ごすことができる。しかし足元の床の下にいる取り残された人々はみえない(床からは上にいる人々を見ることができる。マイノリティとマジョリティの関係には非対称性があるわけ)。
イワンは「建物の建築家になることに同意するのか」と問い詰める。アリョーシャはしずかに「いいえ、しないでしょうね」と答える。ここでは、チェルヌイシェフスキーの希望や理想をイワンやアリョーシャは引き継がないことを宣言している。ではどうするか。それにこたえるにはドスト氏の時間がなかった。もしかしたら「カラマーゾフの兄弟」第2部が回答になったかもしれない。
<参考エントリー>
亀山郁夫「『カラマーゾフの兄弟』続編を空想する」(光文社新書)
チェルヌイシェフスキー「何をなすべきか 上」(岩波文庫)→ https://amzn.to/4c3Qq8L https://amzn.to/3ORLfPe
チェルヌイシェフスキー「何をなすべきか 下」(岩波文庫)→ https://amzn.to/3OVoGJm
(追記。読み落としていたのは、チェルヌイシェフスキーの「水晶宮」はベンサムやミルの「最大多数の最大幸福」を実現する功利主義の理想化であること。社会の構成員の幸福の総和がおおきいほど、社会が幸福になるという考え。でも、この考えの欠点はマイノリティの幸福が-1のときに、マジョリティの幸福が+10くらいになると、幸福の総和は、マイノリティとマジョリティの幸福が+1だったときよりも大きくなるので、より良いと判断されること。それはマイノリティを不幸にすることで、マジョリティが幸福になる。そういうありかたは社会の正義や公共の善と照らしてみるとおかしいのではないか。在住する外国人を貧困・過重労働のままにするとか、公害被害者を放置して公害除去の施策をとらないとか、弱者の介護を女性や若者に押し付けるとか、よくない事例には事欠かない。仮に国内の幸福が公正に最大化されたとしても、他国の人権侵害や搾取の上にあったのでは、国内の幸福が正当であるとはいえない。これは功利主義の欠点。
そこにおいて、ドストエフスキーの弾劾に正当な意味が生まれる。ドスト氏の弾劾はまさに功利主義に対する批判であるわけなのだ。ただ、ドスト氏は功利主義に代わる正義や善を提示していない(「カラマーゾフの兄弟」を読み返せば、彼が構想するキリスト教社会主義がみえてくるかもしれないが)。イワンやドスト氏の批判の先で正義や善を構想することは市民社会の課題になる。チェルヌイシェフスキーやドストエフスキーの指摘から150年以上たっても回答は生まれていないが(ロールズやサンデルの議論は参考になる)。
<参考エントリー>
2019/11/28 フョードル・ドストエフスキー「作家の日記 下」(河出書房)-3(1880年) 1880年
サンデルの功利主義批判は、「道徳性とリベラルの理想」(「公共哲学」所収)に書いてあるのが、わかりやすい。以下のエントリーではサンデルの考えをまとめなかったが、一応参考まで。