タイトルは米川正夫がつけたもの。江川卓訳(新潮文庫)では「地下室の手記」。原題に即すると「地下室」が正しいというが、本書がチェルヌイシェフスキー「何をなすべきか」批判の書というとき、同書(岩波文庫版)に出てくる「地下室の人」の意味を持っている「地下生活者」の方がいいと自分は思う。それに、主人公の「ぼく」は地下室ではなく、普通の部屋に住んでいるのだし。
(米川訳と江川訳の二冊を読んだが、最近読んだ江川訳で感想を書く。)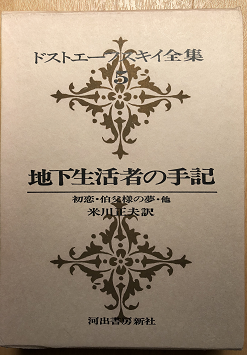

「ぼく(米川訳では「わたし」)」は40歳。元役人だったが、6000ルーブリの小金を遺産相続でもらったので、退職して引きこもることにした。自分は何も始めず、何もやりとげなかった、何にもなれない、病んだ、意地の悪い人間。それでもなお自意識はあるし、しゃべることはできる。とうわけで、「ぼく」の内にこもった呪詛やひねくれを書きつけよう。(書いている間は)存在しない読者のつっこみに煙幕を張り、何もしない時には滅入る気持ちも書くことで晴れてくるからと正当化も隠さない。そのような独身男のモノローグを聞こうじゃないか。
何に対する呪詛やひねくれであるかは小説だけを読んでいるとわからないが、前年(1863年)に出版されたチェルヌイシェフスキーの小説「何をなすべきか」を並べると見えてくる。
ドスト氏は流刑前にはチェルヌイシェフスキーも参加していたペトラシェフスキー・サークルに所属していた。米川正夫によると、流刑から帰ったドスト氏は
「いっさいの社会主義学説に対して、烈しい憎悪をいだき、社会主義の説くところの理論による合理的な社会統制ということを、個人の奴隷化・個性の蹂躙ということと同一視していたのである(全集P453)」。
そういうところからすると、ドスト氏のチェルヌイシェフスキー批判、社会主義批判は筋がよくない。ドスト氏の脳裏にあって、そのようなことを言っていない社会主義理論や「水晶宮」を批判している。一種の藁人形論法をつかっている。そのことは米川正夫も全集の解説で指摘している。チェルヌイシェフスキーの小説の中では、「個人の奴隷化・個性の蹂躙」を行うような言説はないものな。ドスト氏のいう「水晶宮」だって、「何をなすべきか」ではシンボルとしてあるが、人がそこには集まらない場所になっている。なにしろ「何をなすべきか」の共同経営や生活消費協同組合には代表やまとめ役はいても、指導者・リーダーはいない。ほかにもドスト氏の指摘はチェルヌイシェフスキーや社会主義には刺さらない(まあ、のちのボリシェヴィキによる個人の奴隷化・個性の蹂躙を19世紀なかばで見出したのは慧眼であると思う。ああ、フランス革命の記憶があるか)。
(「ぼく」のいう「水晶宮」は、「夏象冬記」をみると、パリ万博の「水晶宮」と混同している節がある。ドスト氏は「水晶宮」をブルジョア精神の象徴とみていたようだ。チェルヌイシェフスキーの「宮殿」はブルジョアなき後に建てられるものであるので、ドスト氏の批判はどうも的外れに見える。)
思うに、チェルヌイシェフスキーは共同体(共同経営や組合など)の規範や組織化について語り、「ぼく」は自意識や内面の個人(の自由)について語る。彼らの思考には複数の共同体が並立していて、それぞれが独自の規範や道徳を持っていて、共同体の間で規範や道徳が衝突しあうという公共の空間(交通空間@柄谷行人)を想定していない。資本主義や貨幣経済が十分にいきわたっていないので、市場も小さい(「何をなすべきか」にはイギリス資本がロシアに投資することが書かれていたが)。互いに規範や道徳を異にする人がであうようになっていない。なので、「何をなすべきか」には個人(とりわけ貧困層)の内面には無頓着であるし(これものちのボリシェヴィキの指導する前衛と教育される大衆の構図をみていいかも)、地下室住人の「ぼく」はひきこもりであるせいか、役人であったにもかかわらず社会の構造には無知。これでは話が通じるわけはない。
「水晶宮」批判で「ぼく」は人間を啓蒙して正しい真の利益に目を開けてやれば、汚らわしい行為をやめて善良で高潔な存在になるのはうそっぱちだという(チェルヌイシェフスキーは、共同経営や協同組合に参加すると正しい行為をするようになるといっているだけ。ドスト氏は結果と原因を混同していない?)。さらに利益は幸福・富・自由だというが(チェル(略))、もう一つ別の利益があると宣言して、ずっと明かさない。これもよくない議論。それに利益や富という経済学の指標と幸福や自由という別の概念をごっちゃにする議論もよろしくない。で、もうひとつの利益があいまいに提示されるが、どうやら愚行権を認めろということのようです。
ドスト氏の「ぼく」の激烈な批判、のごときもの、は藁人形論法といい、個人の体験を法則にするような拡大化といい、ネトウヨや冷笑家の言い草によく似ていて、なるほど150年以上前から似たような連中はいたのだなあと嘆息する。
フョードル・ドストエフスキー「貧しき人々」→ https://amzn.to/43yCoYT https://amzn.to/3Tv4iQI https://amzn.to/3IMUH2V
フョードル・ドストエフスキー「分身(二重人格)」→ https://amzn.to/3TzBDKa https://amzn.to/3ISA99i
フョードル・ドストエフスキー「前期短編集」→ https://amzn.to/4a3khfS
フョードル・ドストエフスキー「鰐 ドストエフスキー ユーモア小説集」 (講談社文芸文庫)→ https://amzn.to/43w8AMd
フョードル・ドストエフスキー「家主の妻(主婦、女主人)」→ https://amzn.to/4989lML
フョードル・ドストエフスキー「白夜」→ https://amzn.to/3TvpbeG https://amzn.to/3JbxtDT https://amzn.to/3IP71zF https://amzn.to/3xjzJ92 https://amzn.to/3x9yLfE
フョードル・ドストエフスキー「ネートチカ・ネズヴァーノヴァ」→ https://amzn.to/3TwqMRl
フョードル・ドストエフスキー「スチェパンチコヴォ村とその住人」→ https://amzn.to/43tM2vL https://amzn.to/3PDci14
フョードル・ドストエフスキー「死の家の記録」→ https://amzn.to/3PC80Hf https://amzn.to/3vxtiib
フョードル・ドストエフスキー「虐げられし人々」→ https://amzn.to/43vXLtC https://amzn.to/3TPaMew https://amzn.to/3Vuohla
フョードル・ドストエフスキー「伯父様の夢」→ https://amzn.to/49hPfQs
フョードル・ドストエフスキー「地下室の手記」→ https://amzn.to/43wWfYg https://amzn.to/3vpVBiF https://amzn.to/3Vv3aiA https://amzn.to/3vmK9V5
フョードル・ドストエフスキー「論文・記録 上」→ https://amzn.to/3VxSShM
フョードル・ドストエフスキー「論文・記録 下」→ https://amzn.to/3VwvP79
フョードル・ドストエフスキー「賭博者」→ https://amzn.to/43Nl96h https://amzn.to/3x2hJju
フョードル・ドストエフスキー「永遠の夫」→ https://amzn.to/3IPQtY7 https://amzn.to/43u4h4f
フョードル・ドストエフスキー「後期短編集」→ https://amzn.to/49bVN2X
フョードル・ドストエフスキー「作家の日記」→ https://amzn.to/3vpDN7d https://amzn.to/3TSb1Wt https://amzn.to/4a5ncVz
レフ・シェストフ「悲劇の哲学」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3TR758q https://amzn.to/3x2hMvG
フョードル・ドストエフスキー「ドストエーフスキイ研究」(河出書房)→ https://amzn.to/4avYJIN
河出文芸読本「ドストエーフスキイ」(河出書房)→ https://amzn.to/4a4mVSx
江川卓「謎解き「罪と罰」」(新潮社)→ https://amzn.to/493Gnxy
江川卓「謎解き「カラマーゾフの兄弟」」(新潮社)→ https://amzn.to/3VygEKG
亀山郁夫「『カラマーゾフの兄弟』続編を空想する」(光文社新書)→ https://amzn.to/493GqcI
(追記。古い読書メモを見た。第1部の批判先は、水晶宮(チェルヌイシェフスキー)、美にして崇高なるもの(カント)、自然と真理の人(ルソー)、ロックやヒュームの功利的人間(市民社会の理念)、フランス革命の普遍的人間(近代国家の理念)であるとのこと。たぶん誰かの指摘したことのメモ。水晶宮にとらわれて、ドスト氏の18世紀思想批判をすっかり読み落としました。次回の再読のときに、ここに注目するようにしよう。)
(追記2。地下生活者による「水晶宮」の功利主義批判は、以下のエントリーに書いてみた。)
チェルヌイシェフスキー「何をなすべきか 下」(岩波文庫)-2
2020/01/21 フョードル・ドストエフスキー「地下生活者の手記(地下室の手記)(河出書房)-2 1864年
2020/01/20 フョードル・ドストエフスキー「地下生活者の手記(地下室の手記)(河出書房)-3 1864年
2020/01/17 フョードル・ドストエフスキー「地下生活者の手記(地下室の手記)(河出書房)-4 1864年