2023/10/02 ジェイムズ・ジョイス「若い芸術家の肖像」(岩波文庫)-I、II スティーブンは優等生で、作文がうまいが、コミュニケーションはうまくいってなさそう。 1914年の続き
スティーブン・デダラスのミドルからハイティーンの時代。一貫して寄宿学校で暮らしている。友人や教師との親密な交友が全く現れない。いわゆる青春の時代なのに、誰ともつるんだりしない。娼館通いにしろ、修業にしろ、他の生徒が行うようなことではなく、一人で孤独に行うものだ。学友たちは彼を奇怪なものを見るように接していたのだろうか。

(俺もこの年齢のころは学校で誰かとつるむことは少なく、孤独にすごしていたので、スティーブンの気分はよくわかる。)
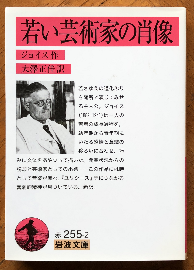
III.ディーダラス14歳から16歳まで。
娼館通いは習い性になり、スティーブンは止めることができない(前の感想にも書いたがよく発覚しなかったものだ)。唇、やわらかい肌、匂い、そうしたものがスティーブンにまとわりつく。そのうちに、隣の女の子エマと聖母マイアが一緒になる幻想をもつまでになり、快楽は彼の体の一部になる。でもその日々は続かない。学寮がフランシスコ・ザビエルの誕生日を記念する静修に参加することになる。日曜の礼拝とは別に週末の3日間、静かな沈黙の日々をすごし、自分の罪を悔い改めるよう心を覗けという日々だ。そして3日間にわたって神父が説教する。死と審判と地獄と天国について。ことに地獄の微細な描写(苦痛と恐怖と永遠のイメージがことに刺激的)を聞いて、自分の存在が全否定され、救済される可能性がないのではと絶望する。
(その絶望の時期にスティーブンはこんなことを考える。「The Dead(死者たち)」につながる述懐。)
「みんな死んでしまった。みんなすべて裁きを受けたのだ。「人、全世界ラ得ルトモ、己ガ魂ラ損セバ、何ノ益アランヤ?」やっとわかった。人間の生活はぼくのまわりにも平和な野のようにひろがり、そこでは蟻のような人びとが仲よく働き、死者たちは静かな塚の下で眠っているのだ。(P234)」
そして、市内の教会で告解し、さいわい老いた神父は彼を激高せず叱責せず、悔い改めよと穏やかに諫めるにとどめる(これが校内の告解であれば、第1部にあったような折檻や退学などの処分があっただろう。スティーブンはそこまで考えていたかどうかは知らないが、校内では告解できないと決めていたのは賢明な判断だった)。
と、この部は頽落にあったものが改心して救済されるまでの物語。まことにキリスト教文学にふさわしい流れをもっている。でも、と異教徒である俺は思う。スティーブンは自分の汚れを娼館の娘たちに押し付ける。あるいは、蛇に誘惑されたイブの末裔である女たちに。彼が存在を認めるのは聖母マリアのみ。それ以外の女性は汚らわしいし、救済に値しないとみなすのだ。そこにおいてスティーブンは「ぼくもほかの人々と一つになろう。神と共にあろう。隣人を愛そう(P265)」と決意する。この隣人に女性がいるとは思えない。スティーブンは幼い時から家族から離れて男性しかいない社会にずっと属していた。娼館に出入りしていた経験はこの悔い改めで封印され、女性には蔑視の感情だけが残った。この女性嫌悪の感情は22歳になった時の「ユリシーズ」でもあり(むしろ人嫌いと他人の蔑視は強化された感じ)、克服の機会は訪れそうにない。
IV.ディーダラス16歳から17歳まで。
16歳の神秘体験、至高体験、純粋経験はとんでもない高みまで自分を押し上げた。そこでスティーブンはその時の体験を継続するために修業に励むのであり、ときに聖師や学校が要求する以上のルールを自分に科すのである。しかし、この体験・経験は一度限りのことであり、長続きしない。そのために、懐疑やためらい、確信のゆらぎが生まれる。
「現に聖体を拝領しても、これまで秘蹟にあずかった際に時折り感じられたあの霊的な交感といった純潔な自己放棄の溶け入るような恍惚の瞬間はおとずれなかった。(P283)」
そうなのだよなあ。神秘体験、至高体験、純粋経験は一度限りであり、それを思いだすことはできても、繰り返すことはできない。他人とのかかわりには堕落への誘惑が潜んでいる。そのうえ、日常のルーティンは心身に重力がかかり、上昇する機会がない。なのでパウロや聖フランシスコやフランシスコ・ザビエル、あるいはカタリ派の異端修行者(堀田善衛「路上の人」)らが厳しい修行に堪え、過酷なルールを実践し続けたのはとても珍しいのである(彼らの改心や神秘体験は大人になってからのことなので、16歳の少年には過酷すぎたといえるのだ)。
一方、外見からはスティーブンはまじめで禁欲的なので、校長に目をかけられる。ひとつの学年で数名しか選ばれない特待生コースに進むことを勧めるのだ。それも一つの誘惑。すなわち、「こちらに入りたまえ」、そうすれば智恵を授けよう、というもの。ひとつの共同体に入り、その成員になることで、さまざまな特典が得られるというものだ。でも、上のような懐疑と観照を行っているスティーブンには誘惑にはならない。
「今はもう自分の魂がその声を聞いて迎えいれる気配もなくなっているし、先ほど耳を傾けていた勧告もすでに虚しく形ばかりのおしゃべりにすぎなくなっているのを彼は知った。ぼくは決して聖櫃の前で司祭として香炉を振ったりはしないだろう。ぼくの運命はどうやら社会や家族の秩序から巧みに身をかわすことのようだ。校長の知恵に満ちた訴えもぼくの急所には触れてこない。ぼくは他人から離れて自分独自の知恵を身につけるか、それともこの世のさまざまな罠のあいだをさまよいながら、他人の知恵を自分ひとりで学びとるよう運命づけられているのだ。この世のさまざまな罠とは、そこに設けられたさまざまな罪の道のことだ。ぼくは堕ちてゆくだろう。まだ堕ちてはいないけれど、やがて音もなく、一瞬にして堕ちてゆくだろう。堕ちずにいることはあまりにも難しい、そう、あまりにも(P300)」
というわけで単独者として生きることを選ぶ。その際に「他人の知恵を自分ひとりで学びとるよう運命づけられている」という自己評価を夜郎自大とみるか、それとも天才の先触れと見るか。それは彼の果たした成果に置いて評価するべきであり、22歳までしか生涯を知られていない青年はどうにも評価しようがない。
でもこの精神の遍歴と高揚の末に自分の運命を見出し、途中に彼をインスパイアする
「少女のイメージはすでにぼくの魂に永久に溶け込んでいる」(P317)
というとき、そこに独我論のおごり、自己中心的なうぬぼれが入り込んでいないか。
odd-hatch.hatenablog.jp
途中でデダラスの意識の流れが句読点のない文章でつづられる。この翻訳では、文の間にスペースを入れている。たぶん「and」でつないでいるところをこう処理した。こちらの分かち書きの方が日本語の読者には親切。「ユリシーズ」の「18.ペネロペイア」もこうするほうが原文にあっているのじゃないか。
このように単独で、孤独に暮らすことはディーダラスから共感を失わせたように思う。「ユリシーズ」の「2.ネストル」で22歳のディーダラスは15歳前後の生徒を教えたのだが、彼らのことを大事にする感覚がほとんど見られない(まあ、勉強のできない子供に課外で教えはしたのだが)。やはり突然、古典や教義書を引用して難しいことを言い出す奇妙で気難しい近寄りがたい人と見られていたのではないか。
ジェイムズ・ジョイス「若い芸術家の肖像」(中橋一夫訳)→ https://amzn.to/3OOW6cB
ジェイムズ・ジョイス「若い芸術家の肖像」(講談社文庫)→ https://amzn.to/3SPjl7H
ジェイムズ・ジョイス「若い芸術家の肖像」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3uQFDxA
2023/09/28 ジェイムズ・ジョイス「若い芸術家の肖像」(岩波文庫)-V 「知的半可通」「つむじまがりのインテリ」は独学で世界に打って出られるか? 1914年に続く