2023/10/26 ジェイムズ・ジョイス「ユリシーズ I」(集英社文庫)1.2.3 第1部は何者にもなっていないし何もしないディーダラスの青春の一日。 1922年の続き

第2部が始まる。第2部は第4挿話から第15挿話までで、「ユリシーズの放浪」というタイトルがついているから、このパートの主要な語り手・視点の持ち主がユリシーズ(オデュッセウス)ということになる。

第2部 ユリシーズの放浪
4.カリュプソ
同じ日の午前8時に時刻は巻き戻され、レオポルド·ブルーム(38歳、広告取り)が目覚める。以後、劇場歌手の妻モリーのために朝食を用意し、自分のために腎臓を買いに行き、バターと一緒に炒める。ベッドの中のモリーと会話し、離れのトイレで踏ん張る。1904年なので(日露戦争の話題が新聞にのっている)、家電製品はないし、ガスのレンジもない。というわけで、ブルームは自分で石炭を焚いて火をおこさなければならない。電灯もないのでトイレ(当然水洗ではない)のドアを閉めたら中はほぼまっくらになる。読者は自分の環境を古い小説に当てはめがちなので、よしなしごとを書いてみた。
ブルームは娘ミリーのおしゃまやなまいきに閉口しながらも目を細めるのだが、彼のオブセッションになっているのは息子が誕生後すぐに亡くなったこと。死児の齢を数えるのは東西を問わずにあるらしい。そのうえ、今日は誰かの葬儀に出なければならない。人はあっという間に死に、死ぬことは日常であるので、死を恐れるのであった。それがゆえの生の快楽への執着や祭事への熱狂がある。
あとブルームは東方移民のユダヤ人の息子。自身はカソリックとプロテスタントで洗礼しているが(可能なんだ!)、周囲からはユダヤ人とみられている。プロテスタントのイギリス人>カソリックのアイルランド人>ユダヤ人もしくは東方移民という差別のヒエラルキーで、もっとも攻撃を受けやすい属性にあるのだ。
ここはずっとブルームのモノローグ。それこそ内的に生まれた言葉をそのまま書きつけたかのような文章。この前の章でディーダラスのモノローグが語られたが、ブルームとディーダラスでは語彙も関心事項も感嘆の仕方も異なる。途中出てくる15歳の娘ミリーの手紙も、その年齢の女の子の筆であることがすぐにわかる。世代や境遇の違いがすぐ分かるように翻訳しているが、原文もそうだったのだろう。
5.食蓮人
午前10時。ブルームは知人の葬式に出席するために喪服に着替えて、街を歩く。郵便局、教会のミサ、薬局に立ち寄り、手紙を受け取ったり、石鹸を買ったり。俺らもそうするような大した用事もないのに街をぶらつく、無為で怠惰な時間だ。その間に、ブルームはいろんなことを考える。ディーダラスと異なるのは所帯を持っているので、発想は日常あるいは下世話なことに終始すること。偽名でどこかの女と文通していて(なので郵便局留めで手紙を出している、たぶん相手も偽名)、とりあえず関わりのできた女を妄想したり、風呂に入りたいと思って連想したり。ミサを眺めていても神のことなどこれっぽちも考えず、神父やミサボーイのふるまいに意識を向けるだけ。なんとも怠惰な次第。
喪服を着てめだつためか、歩いている最中に、知り合いに声をかけられる。どうでもいい話をしたり、競馬のことを振られたり。この町に住んでいて、こどものころからの知り合いがそのまま町に居残っているのだ。こどもや独身時代のことをいつまでも覚えていて、現在の趣味趣向まで知られている。そういう閉ざされた世界に「ある」のはWW2以降の転居がつねにあり、卒業と同時に居場所を変える生き方からはなかなか理解不能。きついねえ。
ブルームは妻に隠れて見知らぬ女と文通していて、いつか会って性交したいと思っている。女の手紙(タイプライターで書かれていた。1904年にすでに商用化されていたんだ)をみて、妄想を逞しくし、同封された押し花の花言葉を考える。21世紀ならSNSで似たようなことをする男はたくさんいそうだ。
6.ハデス
午前11時。冥界の支配者ハデスを章題にするように、ブルームらは冥界巡りをする。待ち合わせ場所に集まった数人と一緒に馬車にのって教会へ。死者のためのミサを聞き(あいかわらずブルームはうわの空で、別のことを考えている)、墓所にいって死者を入れた棺を埋めるのを見守る(映画「第三の男」にあるように、神父が祈祷文を称える中の土葬)。
ブルームが葬儀に集中できないのは、彼がユダヤ人であるので、死者の知り合い・友人の集まりにあってなお、疎外された気分をもっているため(他が名を呼び合っているのに、ブルームだけ姓で呼ばれるところだし、カソリックの儀式に参列させられているなど)。そのうえ、死者の噂話が聞かされる中で、自殺をほのめかす会話があり、ブルームは父が自殺しているので(そのうえ息子を亡くしている)、深い心の傷を抉られた気持ちになっている。そりゃ、身近な人々にいる死者に気持ちが向かうし、いま-ここにいることがいたたまれなくなるわな。解説などをみるとブルームがオデュッセイアに模されているというが、その話に違和を感じていたが、ここでようやく合点がいった。オデュッセイアとおなじく、ブルームも異邦の地で一人ぼっちの気分をあじわっているところで共通するのだね。それにブルームも、いま-ここにいない女のことを思慕するのだ(そして妻が不倫しているのではないかと疑惑している)。
死者を悼む集まりの中に、サイモン・ディーダラスがいる。かれはスティーブンの父であり、ブルームは馬車で移動中に街を歩いているスティーブンを見つけている。二人の主人公が邂逅しそうな予感、しかしすでに顔なじみである二人が街中で出会うことはとくに珍しいことではない。
解説にこのような指摘があった。6.ハデスでのエピソードから。
「墓堀りたちが鋤を取り上げて棺の上に土を落とし始める。ブルームは顔をそむけながら、ふと思った。/ 『もしも彼がまだ生きていたら?』/ まだ息があるとして、生きながらに埋められていることに気がついたら。――すぐさまブルームは解決策を考えた。棺桶のなかに「電気時計か電話を入れる」、あるいは帆布で通気孔をつくっておく。遭難を伝える信号旗の役まわり。/ 荒唐無稽の想念ではないのである。仮死状態のまま葬られるといったことが、たしかにあった。それも、ひんぴんと報告されていた。用心深い者たちは、万一のために合図を送ることのできる「信号旗」つきの棺を遺言した。/ 『ユリシーズ』が書かれていたのは(注:1914年から1922年にかけて)、おりしも電話が普及しはじめていたころで、電話会社がしきりに電話の便利さ、さまざまな使用法を広告していた。そのうちの大きな一つが「死からの復活」だった。電話があると、死の国からよみがえることができる。墓の中から電話をすればいい。電話さえあれば、心やすらかに死を迎えることができる。」
池内紀「ジェイムズ・ジョイス語積木箱」(@ジェイムズ・ジョイス「ユリシーズ I」(集英社文庫、P636)
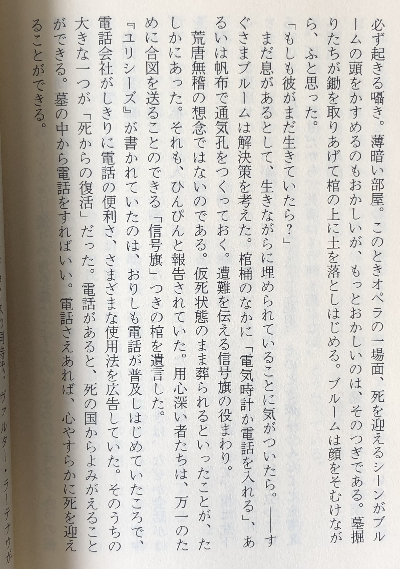
電話にこのような需要・受容があったのだね。1920-30年代の英米探偵小説に電話のついた棺が登場するのがあったと思うが、実用化されていたのか。20世紀の怪談でも死者や冥界から電話がかかってくるというのがよくあった。この事実を知ると、以下のフィクションにおける棺や電話の意味がまた違って見えてくる。
2019/05/24 エドガー・A・ポー「ポー全集 3」(創元推理文庫)-3「陥穿と振子」「早まった埋葬」ほか
2014/05/21 小栗虫太郎「黒死館殺人事件」(ハヤカワポケットミステリ) 黒死館殺人事件2
2020/06/04 夢野久作「ドグラ・マグラ 上」(角川文庫)-2 1935年
2021/06/15 埴谷雄高「死霊 II」(講談社文芸文庫)「第五章 夢魔の世界」-1「死者の電話箱」 1975年
ジェイムズ・ジョイス「ユリシーズ」全4冊(集英社文庫)→ https://amzn.to/3OMKfMb
ジェイムズ・ジョイス「ユリシーズ I」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3I5Qw1B
ジェイムズ・ジョイス「ユリシーズ II」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IrlmlL
ジェイムズ・ジョイス「ユリシーズ III」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3I7A3df
ジェイムズ・ジョイス「ユリシーズ VI」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3uHgJAA
ジェイムズ・ジョイス「ユリシーズ 1-12」(河出消防新社)→ https://amzn.to/3UIng8M
2023/10/23 ジェイムズ・ジョイス「ユリシーズ I」(集英社文庫)7.8 文体パロディの始まり。内面描写よりも言葉遊びに関心が移る。 1922年に続く