2023/09/29 ジェイムズ・ジョイス「若い芸術家の肖像」(岩波文庫)-III、IV スティーブンはまじめで禁欲的な外見と常習的な娼館通いの堕落に分裂している。 1914年の続き
ジョイスの「若い芸術家の肖像」は、同年齢だった自分の感情を記録しているかのような稀有な小説。前回でも、今回の再読でも、スティーブンの言動を通じてその年齢の時の自分がどうだったかを見ているような気がした。老年になってからのふり返りだから、自分のこととはいえほとんど他人のようなものだ。

高校から大学に変わって、とまどうのは自分が自由に過ごせる時間がいきなり増えたこと。どの時間にどの講義を聞くかは自分で決めることになる。一日中いっしょにいるクラスメイトはいなくなり、席も決まっていないから隣にいる人はいつも違う。その結果、どこかの大学や学部に所属はしていても、孤独を強く感じるものだ。そのとまどいは3か月もすると消えて、こんどはスティーブンのような傲岸不遜、傍若無人な態度になり、大人もクラスメイトも小馬鹿にするような気分になっていく。
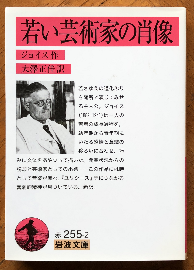
V.ディーダラス18から20歳
そういう気分、気持ちを感じた老年者の視点で若僧のスティーブンをみると、たしかに彼自身の自己評価の通り「知的半可通」だ。「つむじまがりのインテリ」だ。大学の講義をそのまま勉強するより、独自の勉強や創作をする方を優先している。当然、誰もその評価ができないから、彼の態度は傲岸不遜、傍若無人になっていく。慇懃な口の利き方をしても、年上の学監生のイギリス人に敬意を払わないとか、自分の関心事項に興味を持たないクラスメイトを小馬鹿にするとかにみられる(ああ、俺もそうだったなあ)。
そうしているうちに、スティーブンは自分を拘束しているものがうっとうしくなってしかたがない。カソリックの教義だし、聖餐の秘儀を受けろと強要する母や子供に無関心な父にたくさんの兄弟姉妹たちだし、イギリスの植民地であることを意識させられる祖国だ。そういう束縛にあることが不自由でたまらない。そこでこう考える。
「魂のゆっくりした暗い誕生は、肉体の誕生以上に神秘的だ。人間の魂がこの国に生まれると、網がいくつも投げかけられて、その飛翔を妨げようとする。きみはいつも国民性とか、国語とか、宗教とかについて話してくれるね。ぼくはそうした網の目をすり抜けて飛び立ってみせたいのだ(P379)
ここらへんはスティーブンの自立の意識と読みたい気分もあるが、再読では「中二病」のような自意識過剰と努力不足から生まれていると読んだ。ナショナリズムや宗教、家族から抜け出せる特別な場所があり、そのような場所を自分で作ることができるという妄想じみた確信なのだ。たぶんそれはスティーブンが他者とあっていないから。他人と共同作業をしてうまくいかなくなることを経験していないから。奨学金や親の仕送りで食べていけるので、生活や仕事、労働、活動において他人にもまれることがない。だから、
「ぼくは自分が信じていないものに仕えたくない。たとえそれがぼくの家庭だろうと、祖国だろうと、教会だろうとね。ぼくがやりたいのは自分自身を表現すること、生活または芸術の何かの様式を通して可能な限り自由に、可能な限り完全に表現したいんだ。そして自分を守るためにぼくがあえて使用する唯一の武器、それは沈黙と、流浪と、そして狡智。(P464)
という宣言にいたる。心意気やよし。とはいえ極東の老年者からすると一抹の不安が残るが、この先の人生は彼が決めることだ。心配なのは、彼が離脱したがっている国家、宗教、家族の桎梏はとても強いもので、そこから逃れ違った人たちが再びそこに戻ってきてしまうこと。よくあることだ。若い時にインターナショナルやコスモポリタンを目指した人がいつのまにか宗教右翼になって他人を束縛する扇動をしたりする。ことにインテリに多発する。その一端は、「ユリシーズ」の「第1部 テレマキア」で判明する。スティーブンは母危篤の知らせを受けて帰郷したが、母が求める祈りの儀式を拒否した。それが強いトラウマになって彼を苦しめる。そのような離脱したものの逆襲がいずれ起こるに違いない。離脱したい国家、宗教、家族はスティーブンを構成する一部分になっているから、彼からそれらを取り除くことはできない。
スティーブンにはどうも辛らつになってしまう。この小説とだいたい同じ時期に、似たような自意識をもっていてその後の生活の不満をぶちまける青年がいたことを知っているから(加えて俺もスティーブンに似た行動性向を持っていて、彼と同じ失敗をいろいろやらかしているから。同族嫌悪みたいな感情がある)。
石川啄木「雲は天才である」(角川文庫) 1906年
スティーブンはジェイムズ・ジョイスのような作家になったか、世界的な名声を得ることができたか。こういう疑問が生まれるのは、一人の天才がいるジャンルには途中で挫折したたくさんの人がいる。モーツァルトの天才の影には、親の英才教育でつぶれた音楽少年が無数にいる。挫折者がたくさんいるからそのジャンルは長続きしていて、天才の仕事を下支えしている。スティーブンがどっちになったのかはわからない。
あと気に入らなかったのは、詩の霊感を女のイメージから喚起されるように説明するところ。女のイメージがステロタイプ(純潔、貞節、働き者、母性など)で描かれる。ここは今日的でない。ジョイスは性表現の開拓者、先駆者として評価されているようだけど、もう十分に賞賛されたから、ダメなところは指摘しないと。
途中でスティーブンは美学論を語る。あまり熱心に検討しなかったが、ヘーゲル流の観念にイギリスの経験論をまぶしたもの、という印象。WW1のあとにはこういう議論は主流ではなくなったのではないかな(まあ、日本の音楽評論では1980年代ころまでは流通していたようだ)。彼の主張のいちいちに「そりゃ違うだろ」とツッコんでいたので、記憶に残っていない。
ジェイムズ・ジョイス「若い芸術家の肖像」(中橋一夫訳)→ https://amzn.to/3OOW6cB
ジェイムズ・ジョイス「若い芸術家の肖像」(講談社文庫)→ https://amzn.to/3SPjl7H
ジェイムズ・ジョイス「若い芸術家の肖像」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3uQFDxA