雑誌「世界」に1984-85年に連載されたエッセイ。その10年まえに「状況へ」というエッセイを連載していて、その続きになるのかな。ほかのところでも書いたように、1980年代前半は、核戦争の恐怖、軍拡競争の激化、日米英で保守政権が誕生などがあって、センシティブな人には憂鬱な時代だった。著者の個人的な状況に思いをはせると、50歳を目前にしていることと障害を持つ息子が成人になり学校を卒業することになったというのもうっとうしいことであったとおもう。
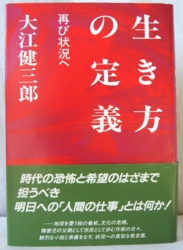
「優しさ」の定義 ・・・ 定義を求めるとすると、1)人間が優しくあることを不可能にする仕組みや制度と戦っていくということ(社会的な条件)、2)精神の自由と文化のもっとも繊細なもの(@ヴァレリー)、になる。これを実現する条件にディーセンシーが必要ということであるが、同じ言葉をリリアン・ヘルマンが使っていることに注意。
「考えられないこと」を下準備する ・・・ 西ドイツがアメリカの核配備を容認する、ソ連が核軍縮会議から退席する、米ソの警戒発射システム(まあ、敵国から核ミサイルが発射されたら指導者の指示なしに自動的に迎撃・反撃する仕組みだ)の開発が始まる。そのような熱核戦争の現実化において、「考えられないこと」として核廃絶を闘おう。
乱世の菫、カキツバタ ・・・ 原爆を描いた小説のアンソロジー。後半は西欧が日本の企業経営を研究していることへの文学的な提案。
百年の、「迷路」と「新時代」 ・・・ ディーセンシー(品格の良い)作家としての野上弥生子。後半はブレイクを経由した、物質主義と科学主義としての近代批判をする「新時代(ニューエイジャー)」への応援。
資産としての悲しみ ・・・ 過去の償いがたい出来事に源はあるのだが、自分の現在の人間としての資質に生きている悲しみを「資産としての悲しみ」とする。スタイロン「ソフィーの選択」、林京子「空缶」。
破壊していい最後のもの ・・・ 武田泰淳「滅亡について」。あとは人類は滅びたほうが地球の生物には好ましいのではないかという愚かで鈍感な樋に対する反論。
教育される能力 ・・・ 教育するものと教育されるものを子規とその弟子、ソクラテスとその弟子で考える。最後のフォークナーの小説で「おまえは人類の仕事をやらなきゃいけないよ」。
「ある楽しさ」とその反対 ・・・ 「ある楽しさ」は中野重治の小説のタイトル。時に人は無知で孤独で不幸で自死に至ってしまうこともあるけど、その反対に生を楽しむことができて、それは悲惨の極みみたいな、あるいは差別された悲嘆の底にでも楽しみはあるよ。でもそれに反対する生き方をする人も多いよ。
恐怖と希望 ・・・ 文学は時代の精神、恐怖と希望を何らかの形で反映していなければならない。そのような文学を構想するときに、道化や祭り、何よりも想像力が重要。
多面的に読む ・・・ 文学(小説)は、現実のある様態について、それを可能な限り多面的に読み取り、そのうえであらためて統合する人間の行為の、モデルとして効用を持ち、役割を持つ(P195)。例は金芝河。
戦闘的なユマニスム ・・・ 戦争をしかけたがっているもっとも浅はかなオプティミストに対抗する、断乎として進むペシミスト=戦闘的なユマニスト。例は中野重治と渡辺一夫。1983年当時のスターウォーズ計画批判。(個人的にはこのような「文学」的な批判や活動意思は好かないなあ。経済と軍事で利得で考えるようにしたほうがすっきりするのではないかな)
「この項つづく」 ・・・ 死んでいったもの、現在悲嘆にくれているものたちのそれぞれの「生き方の定義」を見聞し、自分の生き方と世界へのコミットの仕方を考えよう。ブレイクやイエーツなどの神秘思想に共鳴する人々の詩を引用し、すでに流行りを過ぎた「水瓶座の時代」「新時代(ニュー・エイジ)」が登場するとなると、この文学的・作家的想像力は危ういところを持っている。
小説とのかかわりでいうと、第1章や5章の経験がのちに小説となる。第1章=「静かな生活」、5章=「懐かしい人への手紙」という具合。個人的な体験を繰り返し反復想起することから、普遍的な意味を見出そうとフィクショナルな改変をするのに数年かかるのか、とその持続力には感嘆。
とはいえ、政治的な実践を呼びかけるとき、このような小説的な想像力は有効であるかというと、そうではない。むしろ早とちりと混乱をもたらすのではないかな。「乱世の菫、カキツバタ」みたいに、個人の日常生活の気づきから想像力をもって、世界の危機や不安を認識し、「人間が優しくあることを不可能にする仕組みや制度と戦っていく」ことを選択しよう、それが小説的な想像力の仕組みだという。そのときに、類推思考や象徴思考などが入り込んで、個人の気づきと世界の危機や不安の結びつき方が論理的か、実装可能なのか、他者の検証が可能かどうかが問われていない。著者は、大量の本を読み、専門家や知識人の援助を得られ、意見を公開するまでに時間をかけているので、そこは担保できるだろう。でも、市井の読者がそこまでの検証や他者評価に時間を割けるのか、検証や他者評価で気づきや意見が誤っていたときにそれを訂正する動機や仕組みをこの小説的な想像力は持っているのか。このあたりが疑問。著者が誠実であるのはわかるとして、その善意の行動の「正しさ」が担保されるわけではないからね。そういう危うさをこの本の呼びかけは持っている。
もうひとつの危うさは、「この項つづく」に書いたこと。個人的な体験はその人に重要であってもそれが普遍的であるかは慎重であるべきだし、その種のことを強調する考えはときに人の健康や資産を破壊することもある。そういう運動に取り込まれたり、みこしにのったりすることに反省とか懐疑する契機をもっていないようだ。