本書に書かれる倫理(社会的)は、野間易通「実録・レイシストをしばき隊」(河出書房新社)の「正義」にとても良く似ている。後者の実践の根拠を与えるのが本書であると思えるくらい。ただし後者は賃労働の廃棄とかアソシエーショナリズムの実践とかの本書の提言にはまったくかかわらない。
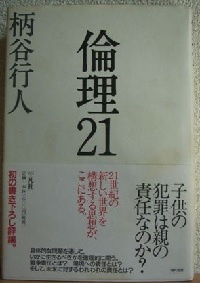
第七章 幸福主義(功利主義)には「自由」がない ・・・ カントの「他人を手段としてのみならず目的として扱え」には、他人を手段として扱わざるを得ないところがある。資本制経済ではことに。なので、カントの倫理を実践する際には資本制経済を変えることも射程にある。「自由であれ」には他人の自由を含む。この他者には死者や未来の人間がいる。自由であれには未来の人間を自由であることを要求される。幸福主義(功利主義)ではこのような他者、特に未来の人間を排除する。なので自由であることができない。他者(ことに未来の人間)がわれわれ現在の人間に感謝するのをあてにすることなく考慮しないといけない。
(他者との関係は、たいてい非対称的(売る-買う、教える-教わる)。でも対話はレスポンスがすぐにある間にげんていされるわけではない。あと、「死者はいつも生者のダシに使われている。死者はそれにも抗議できない」。ことに戦争責任において。)
第八章 責任の四つの区別と根本的形而上性 ・・・ ヤスパースの指摘する戦争の罪。1)刑事上の罪(戦争犯罪)、2)政治上の罪(責任)、3)道徳上の罪(しなかったことの罪)、4)形而上の罪(「なぜここにいて自分は助かり、あそこにいた人は死んだのか」など)。4の形而上の罪は高邁なものではない。
(哲学者は民族の危機に現れて国民の精神的統合を主張する。フィヒテ、ヤスパース、ハイデガー。日本にもいたが(田辺元など)、原因を追究しなかったので影響力を失った、とのこと。こういう哲学者のふるまいを文学者が肩代わりする必要はない。ああ、10年代には「百田尚樹」みたいな「文学者」がいる。)
第九章 戦争における天皇の刑事的責任 ・・・ 戦争責任は国際法の観点からのみ生じる。15年戦争では日本の刑事上の罪が十分に問われなかった。その原因は、天皇が政治的理由で免責されたこと。資料は天皇が戦争に加担し、地位の保全に画策したことが明らか。それが免責されたので、国民や個々人の責任が問われない。「天皇の責任がないのに、その代わりに責任を問われるのは嫌だ(不当だ)」という意識が過去の半生が不十分なせいで、国家の謝罪が受け入れられない理由。また天皇の免責が、この国の「無責任の体系@丸山真男」の始まり。
(天皇退位論は戦後にはあったし、それが一般的な予測になっていた。日の丸や君が代の「問題」も天皇の免責に端を発している。「天皇のご聖断」という神話がつくられた。)
2015/04/03 井上清「天皇の戦争責任」(岩波現代文庫)
第十章 非転向共産党員の「政治的責任」 ・・・ 獄中非転向の共産党員が党の中枢になったので、神聖化と党の権威の源泉になった。その結果、党の政治的責任、道徳的責任が問われなかった(たとえば、政治指導のミスで逮捕者を出したとか、ファシズム体制を阻止できなかったとかの)。
(ここでは「何もしなかった」「無知であった」ことの責任が問われる。「自由であれ」の義務はそのような責任や罪も問う。)
第十一章 死せる他者とわれわれの関係 ・・・ 過去(歴史)の見直しは必要。死者との関係を変化させることで、死者とわれわれの関係は完結していない。戦争犯罪が法廷で裁かれたことによって、戦勝国もそれに規制されるようになった(1990年以降はさまざまな戦争責任を問う国際法廷が開かれている)。日本が世界史でひとつの一を占めるには、戦争責任を明確にすることとそれを不変化することが必要。いずれ原爆、植民地主義の責任を問われることになるだろう。
(過去の見直しは新たな視点による現在の批判を含む。従軍慰安婦問題は戦争責任のみならず女性差別の告発でもあるように。2000年には将来の歴史見直しは倫理的、正義の実現に行くという希望があったが、実際は歴史の捏造になり、死者を都合よく利用することに終始するようになった。現状維持のレイシストがのさばる、とても駄目な時代。)
第十二章 生れざる他者への倫理的義務 ・・・ カントの「他人を手段としてのみならず目的として扱え」は生産関係の他人を必然的に手段にすることを変更することも要請する。具体的には賃労働の廃棄。それができると、私有財産=国家の廃棄になる。この賃労働の廃棄はマルク主義者のいうような必然性はない。倫理的な介入であり、自由の次元からのみ来ること。その倫理的な介入では、被搾取者との合意のみならず、未来の人々との合意を得なければならない。
「資本制段階からコミュニズムへの発展はけっして歴史的必然ではないということです。それはただ、『自由であれ』、『他者を手段としてのみならず、同時に目的として扱え』という、倫理的な義務からのみ生じます。歴史には意味も目的もありません。しかし、それは、実践的(倫理的)にのみあるのです。」
(「持続可能な循環的な社会をグローバルに形成すること、それは、資本制でないような生産と消費の形態を作り出すことであ」る賃労働の廃棄、資本制経済の変更の可能性は生産-消費協同組合(アソシエーション)のみにある、という提言になる。これは「可能なるコミュニズム」の主題になるので、ここでは割愛。)
本書では倫理的に生きることの具体例は出てこない。読者の認識を変えることはできても、どのような行動が倫理てきであるかはほのめかされるにとどまる。その点では、「自由であれ」の義務に応えようとしても、自発的・自律的に自由であることはきわめて困難であるのがわかる。自由であると思っていることが、他人の欲望を反復することや共同体からの要請であることがよくわかる。自由は困難。でもやりがいがある。
具体的な行動の参考になるのは、10年代の本だと
木下ちがや「ポピュリズムと「民意」の政治学 3・11以後の民主主義」(大月書店)
野間易通「実録・レイシストをしばき隊」(河出書房新社)
これらの本が面白いのは、痛快なのは、爽快なのは、「反撃」であり、成功事例が書かれていること。それ以前の社会運動の本は敗北と悲壮感が強くて、読んでてめいってしまうし、萎縮してしまうんだよね。上記二書にはそんなことがない。