ペトラシェフスキー事件のあとに発表された作品を読む。ざっと8年のブランクのあとの作品。すでにドスト氏は30代半ば。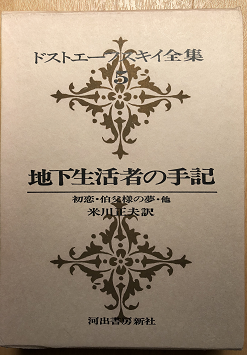
初恋(小英雄) 1857 ・・・ ペトラシェフスキー事件以前に書かれたが、事件のために発表は1857年と遅れた。兄が原稿を保管していて、ドスト氏は発表にやきもきしていたらしい。「ネートチカ・ネズヴァーノヴァ」で少女の心理を書いたドスト氏、ここでは11歳の男の子の心理を描く。貴族だかブルジョアだかの夏の避暑に同行。大人が気になる年ごろの「わたし」はブロンド夫人とM婦人の眼にとまり、彼女らのいたずらが「わたし」の自尊心をちくちく騒がせる。小英雄は大人が乗り越せなかった荒馬を乗りこなしたこと、M婦人のなくした手紙をトリックで返してあげたこと(褒美は初の接吻)。この時代には思春期という概念がなかったのかな。少年のはかない初恋(と初体験)は1950年代以降映画や小説のテーマになったから、ドスト氏のはとてもはやい。ただ米川正夫の訳文は堅くて。福永武彦のような文体(「夢みる少年の昼と夜」「沼」「夜の寂しい顔」「温室事件」など)だったらなあ。
(「初恋(小英雄)」から「白夜」と続く文庫本があったらなあと妄想。そのつぎにくるのは「地下生活者(地下室)の手記」か。)
伯父様の夢 1859 ・・・ シベリヤ流刑後にドストエフスキーの名前で発表されたものとしては、最初の作品。1858年発表。モルダーソフ村の社交界はマリア・アレクサンドロヴィナおばさんが仕切っていた。気になるのは娘ジーナが23歳と婚期を逸しているのに、許嫁のモズグリャコフ青年がいるのになかなか結婚しないこと。なにしろ青年は空想癖が強くて、どうにも頼りにならない。そこに、K公爵が村にやってくることになった。家の資産をバカ騒ぎで失ったのだが、最近さらに大きな遺産を手に入れた。長年の放蕩は健康を衰えさせ、しかもアルコール多飲は体にいいわけない。K公爵は長くないとみてとったマリア・アレクサンドロヴィナはいっそのことジーナとK公爵を結婚させてしまおう、すぐに亡くなるから遺産を手に入れたらモズグリャコフ青年と再婚させればいい。そうすえば家は安泰、わたしも楽隠居ができる。マリアはしぶるジーナを説得し、激昂するモズグリャコフ青年をなだめすかし、自宅に招いたK公爵に酒をのませ、ジーナに歌わせ、愛想を振りまいた。機嫌のよくなったK公爵は意識もうろうとしながら、「あの娘と結婚したい」と口ばしる。マリアの計略が成功したとたんに、それを崩すようなできごとが次から次へと巻き起こる。ここでくじけてはダメと、マリアは体に鞭打って、村中を駆け回り、言葉巧みに場をとりつくろわねばならない・・・
ドスト氏が10年弱の経験で変わったなと思うのは、これまで地の文で説明過多、情報量満載、物語を進めすぎというところがあったのが消え、とても読みやすくなったこと。説明は人物の語りにまかせ、地の文は人物の感情や心理を語る代わりに行動を描写し、物語は人物の出入りで進める(作者は舞台化も考えていたようだ。実現しなかった)。技術の転換がリーダビリティを生み、さらに人物の深みを増す。ジーナやマリア、モズグリャコフらの心理はほとんど書かれないのに、その存在感は以前の作品とは大違いになった。それが、マリアおばさんの大変な一週間という喜劇で実現するとはねえ。そう、もうひとつ変わったのはドスト氏のユーモアが満載になったこと。細部はリアリズムなのに、それがつながると爆笑必至の珍場面になってしまう。低劣極まりないものが高貴な尋常を吐露したり、上流階級が下劣なことをして笑われたり、上にあげたり下にさげたりの皮肉で冷静な人間観察が披露される。(マリアおばさんのアクションを作者は「大審問官」と2回名付けていて、のちの作中作を予感させる。ただし、そこまでのものとは思わないくてよい。)
その最たるところがジーナの造形か。最初は母に操られる自尊心の少ない女性であったのが、マリアの計略が露見されるとK公爵の前に跪いて許しを乞う。楚々として切々とした陳謝はのちのソーニャ(@罪と罰)を思い出しましたよ。その改心もエピローグでは鼻持ちならない高慢な女性になっているのが知れるというのも、ドスト氏の皮肉な観察の眼。
作者も大方の評論家も駄作ないし失敗作と位置付ける。まあ、そうかもしれないが、思想の深みは気にしないで、ドスト氏の技術を楽しむにはいいんじゃない。例によって、冗長にすぎるけど。
ドスト氏の小説を読み続けると奇妙なことに気付く。どこかから人がやってくる、あるいは長年その地に居なかったものが帰ってくる、そうすると一見平穏無事にみえたその村や都会の一隅で、物事が動き始めるのだ。やってきた/帰ってきた人物が動かすのではない。異邦人もしくは異邦にふれた人が来ることが物語のきっかけになる。「白痴」がムイシュキン公爵の到着で始まり、「悪霊」がスタグロービンの帰還から始まり、「カラマーゾフの兄弟」がイワンの帰郷から始まる。「ネートチカ・ネズヴァーノヴァ」だって、バイオリニストがペテルブルグに来ることが父の錯乱のきっかけ。一方で、町や村の中での出会いは没落や喪失になる。「貧しき人々」「分身(二重人格)」「白夜」「地下生活者の手記」など。この思い付きは何も生まないな。メモするだけにしておく(堀田善衛「若き日の詩人たちの肖像」では「白痴」を例に入ってくると出ていくを考察しているので、興味のある人はどうぞ)。
フョードル・ドストエフスキー「貧しき人々」→ https://amzn.to/43yCoYT https://amzn.to/3Tv4iQI https://amzn.to/3IMUH2V
フョードル・ドストエフスキー「分身(二重人格)」→ https://amzn.to/3TzBDKa https://amzn.to/3ISA99i
フョードル・ドストエフスキー「前期短編集」→ https://amzn.to/4a3khfS
フョードル・ドストエフスキー「鰐 ドストエフスキー ユーモア小説集」 (講談社文芸文庫)→ https://amzn.to/43w8AMd
フョードル・ドストエフスキー「家主の妻(主婦、女主人)」→ https://amzn.to/4989lML
フョードル・ドストエフスキー「白夜」→ https://amzn.to/3TvpbeG https://amzn.to/3JbxtDT https://amzn.to/3IP71zF https://amzn.to/3xjzJ92 https://amzn.to/3x9yLfE
フョードル・ドストエフスキー「ネートチカ・ネズヴァーノヴァ」→ https://amzn.to/3TwqMRl
フョードル・ドストエフスキー「スチェパンチコヴォ村とその住人」→ https://amzn.to/43tM2vL https://amzn.to/3PDci14
フョードル・ドストエフスキー「死の家の記録」→ https://amzn.to/3PC80Hf https://amzn.to/3vxtiib
フョードル・ドストエフスキー「虐げられし人々」→ https://amzn.to/43vXLtC https://amzn.to/3TPaMew https://amzn.to/3Vuohla
フョードル・ドストエフスキー「伯父様の夢」→ https://amzn.to/49hPfQs
フョードル・ドストエフスキー「地下室の手記」→ https://amzn.to/43wWfYg https://amzn.to/3vpVBiF https://amzn.to/3Vv3aiA https://amzn.to/3vmK9V5
フョードル・ドストエフスキー「論文・記録 上」→ https://amzn.to/3VxSShM
フョードル・ドストエフスキー「論文・記録 下」→ https://amzn.to/3VwvP79
フョードル・ドストエフスキー「賭博者」→ https://amzn.to/43Nl96h https://amzn.to/3x2hJju
フョードル・ドストエフスキー「永遠の夫」→ https://amzn.to/3IPQtY7 https://amzn.to/43u4h4f
フョードル・ドストエフスキー「後期短編集」→ https://amzn.to/49bVN2X
フョードル・ドストエフスキー「作家の日記」→ https://amzn.to/3vpDN7d https://amzn.to/3TSb1Wt https://amzn.to/4a5ncVz
レフ・シェストフ「悲劇の哲学」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3TR758q https://amzn.to/3x2hMvG
フョードル・ドストエフスキー「ドストエーフスキイ研究」(河出書房)→ https://amzn.to/4avYJIN
河出文芸読本「ドストエーフスキイ」(河出書房)→ https://amzn.to/4a4mVSx
江川卓「謎解き「罪と罰」」(新潮社)→ https://amzn.to/493Gnxy
江川卓「謎解き「カラマーゾフの兄弟」」(新潮社)→ https://amzn.to/3VygEKG
亀山郁夫「『カラマーゾフの兄弟』続編を空想する」(光文社新書)→ https://amzn.to/493GqcI