2020/01/23 フョードル・ドストエフスキー「地下生活者の手記(地下室の手記)(河出書房)-1 1864年
2020/01/21 フョードル・ドストエフスキー「地下生活者の手記(地下室の手記)(河出書房)-2 1864年
2020/01/20 フョードル・ドストエフスキー「地下生活者の手記(地下室の手記)(河出書房)-3 1864年
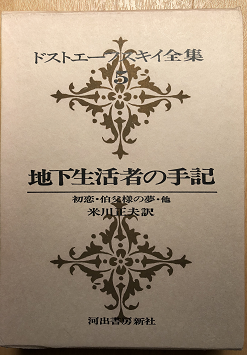

本書をチェルヌイシェフスキー「何をなすべきか」の反論の書としてみるとき、いくつか気の付くところがある。
例えば、リーザへの説教では夫婦の対立があり、子供へのDVがあることを強調する。これはヴェーラの過程ではあまり現れてこなかった事態。ヴェーラと母マーリアは対立していたが、口喧嘩くらいで互いに手は出さなかった。「ぼく」は「自分が学んでから人を責めるべき」というが、これも学ぶことと同時に人へ介入するヴェーラのやり方に対する批判をみてもよいかも。「ぼく」はリーザを「穴倉の一番奥におしこめられている」と指摘する。これはラフマートフを形容する中ででてくる「地下室の人」をさらに細かく見た指摘。「地下室の人」は地下室において一様な存在なのではなく、その中で葛藤や分離、敵対、差別などが起きていることを見ている。また、チェルヌイシェフスキー「何をなすべきか」では議論(または講義)が行われる。双方のやり取りが保証された対等の場がある。ドスト氏の「地下室の手記」ではひとりごとか説教。聞き手の反応を無視した一方的な発信。相手がどう思っているのかかまわずにしゃべりまくるのだが、それでいて聞き手の「高貴な感情をよびおこす」のだと「ぼく」が思い込むのは滑稽。
(バフチンはドスト氏の小説をポリフォニーという。それは登場人物の会話において、それぞれが独立した思想を持っていて、たくさんの主張が「交響的」に読めるのであるが、個々人の話は案外と「説教」とひとりごとではなかったかと思い出す。「手記」であるこの小説では、人物のポリフォニーはまだ聞こえない。)
チェルヌイシェフスキー「何をなすべきか」は平等や公正などが実現されている(あるいは実現を目指している)のに、ドスト氏の「地下生活者の手記(地下室の手記)」ではそれはないし、どころか対等な関係すらない。みじめだと自認している「ぼく」ではあるが、その下(娼婦リーザ、下男アポロン)を見出して、見下しの対象にする。こういう構造は事実。そこをみるドスト氏の冷徹な眼(チェルヌイシェフスキーは見たいものをみるロマンティストの眼)。
この小説を読み直す前に、後期長編を読んでいたのだが、その記憶を掘り起こすと、本書は後期長編のモチーフの先取りがたくさんある。「ぼく」の年齢は24歳であるが、イワン@カラマーゾフと同い年。リーザへの説教で「ぼくは幼い子供が好き」というとき、大審問官への道がここにあるのがわかる。何しろ、リーザへの長広舌もアリョーシャにむけた大説教の前触れに他ならない。。
「ぼく」と下男アポロンの関係は、イワンとスメルジャコフか。アポロンは下からのぞきこむように「ぼく」をみて圧迫する。この下男は饒舌ではなかったが、スメルジャコフになると、卑屈さと虚栄心のないまざった複雑な男になり、彼を見下すものを操ったりするようになる。そういう「邪悪」さはこの男にもみられる。
娼婦リーザと「ぼく」の関係はラスコーリニコフ(彼は23歳だ)とソーニャに重ねることができるか。おとなしく話を聞くリーザに「待ち伏せたり君の前でひざまついたりする」というのは、後にラスコーリニコフがおなじことをした。
金がないのに歓送会に割り込んで参加し、馬車に乗ってペテルブルクの町中を走り回らせ、娼館に乗り込むというのは、ミーチャ・カラマーゾフと同じ。これには「分身(二重人格)」に先例がある。
シェストフのように「ドストエフスキーの全作品を解く鍵」であるかどうかは俺にはわからないが、ドスト氏43歳で書いたこの小さな作品が、のちの大作のモチーフを作っているのはよくわかる。この小説を読んでから、後期長編に挑むと、細部が読み取りやすくなるのではないかな。
フョードル・ドストエフスキー「貧しき人々」→ https://amzn.to/43yCoYT https://amzn.to/3Tv4iQI https://amzn.to/3IMUH2V
フョードル・ドストエフスキー「分身(二重人格)」→ https://amzn.to/3TzBDKa https://amzn.to/3ISA99i
フョードル・ドストエフスキー「前期短編集」→ https://amzn.to/4a3khfS
フョードル・ドストエフスキー「鰐 ドストエフスキー ユーモア小説集」 (講談社文芸文庫)→ https://amzn.to/43w8AMd
フョードル・ドストエフスキー「家主の妻(主婦、女主人)」→ https://amzn.to/4989lML
フョードル・ドストエフスキー「白夜」→ https://amzn.to/3TvpbeG https://amzn.to/3JbxtDT https://amzn.to/3IP71zF https://amzn.to/3xjzJ92 https://amzn.to/3x9yLfE
フョードル・ドストエフスキー「ネートチカ・ネズヴァーノヴァ」→ https://amzn.to/3TwqMRl
フョードル・ドストエフスキー「スチェパンチコヴォ村とその住人」→ https://amzn.to/43tM2vL https://amzn.to/3PDci14
フョードル・ドストエフスキー「死の家の記録」→ https://amzn.to/3PC80Hf https://amzn.to/3vxtiib
フョードル・ドストエフスキー「虐げられし人々」→ https://amzn.to/43vXLtC https://amzn.to/3TPaMew https://amzn.to/3Vuohla
フョードル・ドストエフスキー「伯父様の夢」→ https://amzn.to/49hPfQs
フョードル・ドストエフスキー「地下室の手記」→ https://amzn.to/43wWfYg https://amzn.to/3vpVBiF https://amzn.to/3Vv3aiA https://amzn.to/3vmK9V5
フョードル・ドストエフスキー「論文・記録 上」→ https://amzn.to/3VxSShM
フョードル・ドストエフスキー「論文・記録 下」→ https://amzn.to/3VwvP79
フョードル・ドストエフスキー「賭博者」→ https://amzn.to/43Nl96h https://amzn.to/3x2hJju
フョードル・ドストエフスキー「永遠の夫」→ https://amzn.to/3IPQtY7 https://amzn.to/43u4h4f
フョードル・ドストエフスキー「後期短編集」→ https://amzn.to/49bVN2X
フョードル・ドストエフスキー「作家の日記」→ https://amzn.to/3vpDN7d https://amzn.to/3TSb1Wt https://amzn.to/4a5ncVz
レフ・シェストフ「悲劇の哲学」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3TR758q https://amzn.to/3x2hMvG
フョードル・ドストエフスキー「ドストエーフスキイ研究」(河出書房)→ https://amzn.to/4avYJIN
河出文芸読本「ドストエーフスキイ」(河出書房)→ https://amzn.to/4a4mVSx
江川卓「謎解き「罪と罰」」(新潮社)→ https://amzn.to/493Gnxy
江川卓「謎解き「カラマーゾフの兄弟」」(新潮社)→ https://amzn.to/3VygEKG
亀山郁夫「『カラマーゾフの兄弟』続編を空想する」(光文社新書)→ https://amzn.to/493GqcI