2024/06/04 川北稔「世界システム論講義」(ちくま学芸文庫)-1 世界システム論は、近代世界を一つの生き物のように考え、象徴としての「コロンブス」以降の世界はヨーロッパ世界システムの展開である 2016年
2024/06/03 川北稔「世界システム論講義」(ちくま学芸文庫)-2 ヨーロッパは政治的統合体を作らなかったから世界システムを作れた 2016年の続き
世界システムのヘゲモニー国も、せいぜい50年ほどしか覇権をとれない。生活水準があがり賃金が上昇すると生産性が低くなる。まず工業の優位がなくなり、商業・海運が衰え、金融は最後まで残る。オランダ、イギリス、アメリカのヘゲモニー国はこのようにして衰退した(日本は1980年代に世界第2位のGDPまで上ったが、次の30年でまさにこの順に衰えていった。歴史に学ぶというのはまさにこういうこと)。
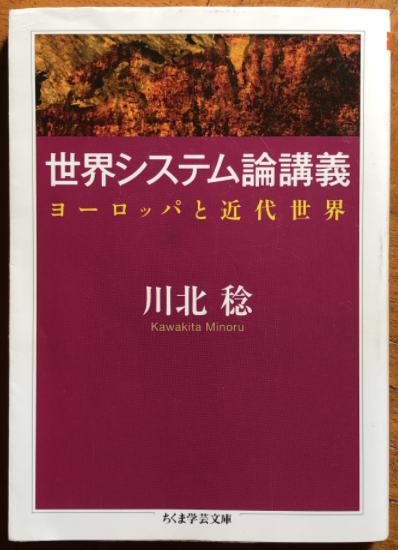
奴隷解放と産業革命 ・・・ ヨーロッパの農業を考えるとき、国内の生産様式だけを考えてしまうが誤り。イギリスの食生活をみると、17世紀半ばから大転換した。工業化と都市化で自給ができなくなり、時間管理が厳しくなって食事の時間が短くなった。そのために簡易外食、および紅茶と砂糖の食事になった。紅茶のカフェインと砂糖の高カロリーが好まれた。絶対王政は消費者保護のために輸入制限をしていたが、市民政府は生産者保護で輸入規制を撤廃した。イギリスには輸入食物が席巻し、農業人口と自給率が激減した。砂糖をみると、独占企業(東インド会社など)の保護のために極めて高価。19世紀にイギリス植民地は奴隷制を廃止したが、これは人道的見地からではなく、経済対策のためだった。アメリカの奴隷制廃止後も、イギリス植民地には奴隷制が残った(キューバなど)。
(大西洋の奴隷貿易と奴隷経営は資料が不足しているようで、調査の仕方によっては正反対のことがいえてしまう。貿易は高収益-低収益、奴隷経営は人権侵害-合理的。そのときに、アフリカやイギリスから見た視点が欠けていることが多いので、本書のように環大西洋の商業ネットワークとする見方が重要。)
ポテト飢饉と「移民」の世紀 ・・・ ジャガイモは貧民の食事として普及し、ヨーロッパ各国の人口増をもたらした。しかし病害を受けやすく、1845-49年にアイルランドで飢饉が起こる。その後80万人以上がアメリカに移住した。19世紀は労働者が世界規模で移動した。東欧、南欧→アメリカ、中国、日本→アメリカ、インド→アフリカ(とくに南アフリカ)。世界システムが地球規模になったので、新規労働力を供給する地域はないので、周辺部への労働力補給が行われた。また中核地域の大都市では雑業のために労働者が移住し、スラムが形成された。
(ガンジーがイギリスに留学し南アフリカで起業した、中国人が拉致されてアメリカで苦力にされた、日本人がハワイやアメリカ西海岸に移住したというのを点でみるのではなく、大きな人口流動としてみることが大事。20世紀に人口流動に、亡命・難民があるが、これは労働力として吸収する周辺も中核もなく、棄てられた人びとになっている。ことに世紀の後半から21世紀になって以降。)
(アイルランドはイギリスの植民地として、すぐ近くにある周辺として搾取を受けてきた。その歴史はジェイムズ・ジョイスの小説に現れる。)
パクス・ブリタニカの表裏 ・・・ イギリスが世界システムのヘゲモニー国になったことを象徴するできごとが、1851年ロンドン万国博と1877年のインド式典。前者は国家威信の発揚と科学技術の展示(これにドスト氏は強く反発)。後者は武力侵略したインドにイギリス風の身分体形を取り入れようとする試み。この式典はのちのイギリスの公式セレモニーの原型になった(植民地の政策が本国に持ち込まれる例のひとつ。王室儀式であってもそれほど古い歴史や伝統をもっているわけではない)。
ヘゲモニー国家の変遷 ・・・ 1870年ころからイギリスの力が衰える。18世紀に適合していたイギリスのインフラ・技術・法・企業などは19世紀の大量生産にあわない。新興国のドイツをアメリカが成長してきた。このころに新しい周辺はなくなり、中核国は帝国主義国家になり領土争奪戦が起きる。次のヘゲモニー争いはWW1とWW2で起こり、アメリカ対ドイツの対決で、アメリカが次のヘゲモニー国となった。この時期はソ連などの反システム運動が起こる。しかしソ連や中国はヨーロッパ近代世界システムと交流を断つことはできず、世界システムのなかの「反システムな政体」でしかなかった。
(21世紀はロシアと中国が次のヘゲモニー国になろうとしている。どちらも反システム的な政体であって、過去に帝国であった。なので21世紀でも領土拡張と周辺からの収奪という19世紀の帝国主義を繰り返そうとしている。)
結びにかえて―近代世界システムとは何であったのか ・・・ WW1とWW2を通じてアメリカがヘゲモニーを取った。広大な土地面積をもち、生産・商業・金融で優位を取った。新たに開拓できる周辺はないので、米ソ間で周辺の支配競争が起こり、戦争で疲弊した。ベトナム戦争終結でアメリカのヘゲモニーはゆるやかに喪失している。資源供給できる周辺が地位を向上している。これからのヘゲモニー国の在り方はまだ見えていない。
(やはり化石燃料が枯渇した時に、物資の輸送と人の移動が制限されるようになり、人口が大幅に減少したときにどうなるか。成長・発展ができなくなったとき、地球を覆う世界システムがなくなるのではないか、と妄想。数百年先ではあるが、すぐ目前に迫っている。)
〈参考エントリー〉
鬼頭昭雄「異常気象と地球温暖化」(岩波新書)
世界システムを言い出したのは、1970年代のウォーラーステインのようだが、そのあとたくさんの研究家がこのアイデアを膨らませ、細部を詰めていった。そういう集合知として「世界システム論」がある。
一国の動きだけでは歴史はとらえきれないし、ヘゲモニー国だけ見ても世界の動きはわからない。
インマニュエル・ウォーラーステイン「新版 史的システムとしての資本主義」(岩波書店)→ https://amzn.to/4bGwK9N https://amzn.to/4bneEKl
川北稔「世界システム論講義」(ちくま学芸文庫)→ https://amzn.to/3wRG5N7