「新版」であるのは1983年にでた「史的システムとしての資本主義」に、「資本主義の文明」二編を追加した版を1995年に出版したため。近代史を「世界システム」の変遷とみるやりかたはだいぶ普及しているが、その嚆矢になった論文。
川北稔「世界システム論講義」(ちくま学芸文庫)を読んだので、そのアイデアのもとになったウォーラーステインの論文を読む。歴史記述は大部な「近代世界システム」で行っているよう。本書はその記述を支える理論をまとめる。この二つの書は相補的なのだろうが、あいにく「近代世界システム」は大部すぎて読めそうにない。川北の本で満足することにします。
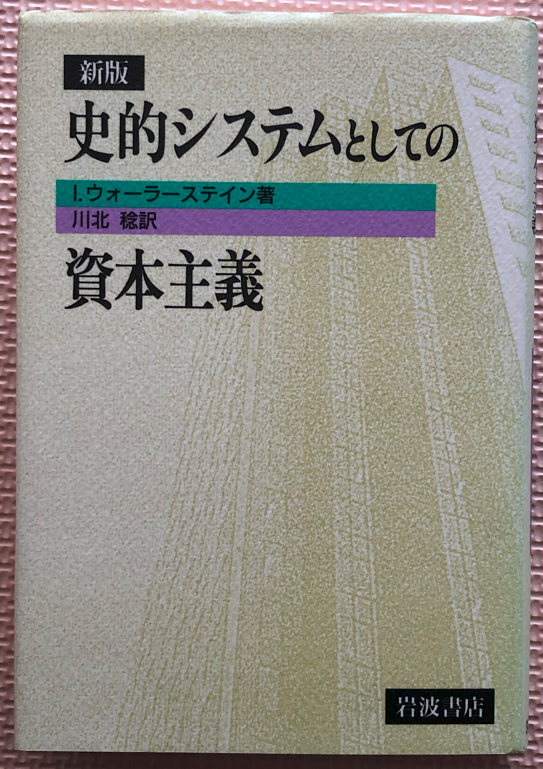
史的システムとしての資本主義
Ⅰ万物の商品化──資本の生産 ・・・ 資本主義は歴史的な社会システム。資本の自己増殖を目的として近代に成立した(15から17世紀の西洋が起源。当時のヨーロッパは最先進地域でも原始的な地域でもないが、社会構造が危機を迎えていた。中世の上層部が作り、近世近代にも上層部であり続けた。19世紀には地球全体を覆いつくした)。生産・投資・交換の各過程が商品化され、市場ができた。中世までは労働力は固定していたが、資本主義以降労働力は流動化した。しかしすべての労働者はプロレタリア化したわけではない。再生産は家族と女性に押し付け、未成年と老人を労働力から除外した。労働の性別分業が強化され固定化された。資本の側からも、賃労働に依存するプロレタリアよりも自給生産できる半プロレタリアのほうが搾取でき低賃金でも生きていけるので半プロレタリアになることを進めた。
上野千鶴子「家父長制と資本制」(岩波現代文庫)
商品連鎖は辺境の余剰の一部を中心(中核)にむかう。そうなるのは不等価根幹を隠蔽したため(とくに上記の労働力で)。余剰の一部を得た中心は強い国家機能をつくり支配を強化した(「これまでは、ある地域にて賃金水準の引き上げがなされると、別の地域において、低い賃金水準での生産者を増やす施策が取られた」という指摘をSNSで見つけて納得)。不等価交換は資本主義の原動力であり、受給バランスではない。また市場は生産者と消費者を直接結ぶのではなく、生産や交換の過程の一部だけを行われる。そのような市場は無数にあり、商品連鎖でつながっている。史的システムとしての資本主義はバランスがとれたものではなく、発展と停滞を繰り返し地理的に再編した。技術革新は資本主義を動かすモーターではなく、動いた結果である(「イギリスは、お金があったから産業革命が起こったのであって、産業革命によって金持ちになったわけではない」というのをSNSで見つけて納得)。資本主義は新たな市場を求めるより、新たな生産物(とくに労働力)を求めて膨張する。
(この資本主義分析はマルクス「資本論」やヒックス「経済史の理論」(講談社学術文庫)より明快ですね。以上は18世紀の終わりまで。)
Ⅱ資本蓄積の政治学──利益獲得競争 ・・・ 近代国家が資本増殖のプレーヤーになる。国家の機能は領土の支配権、国境をまたぐモノと人と金の流れの管理する権利、課税権、軍事力を独占という機能をもっている。国家は個人や集団の消費を増価させるが分配は不平等。特定の個人や集団の利益を増やすが、リスクは社会に負担させる。資本からすると国家は利用できる相手だが、国家が世界帝国になることには抵抗する。単一の国家が他国を征服しつくさないようにする。そこで多国の間でヘゲモニーができ、オランダ(17世紀)→イギリス(19世紀)→アメリカ(20世紀)と移動した。世界戦争によってヘゲモニー国は交代する。農業・工業、商業、金融で優位に立っている国が次のヘゲモニー国となる(海洋国であることも大事かも)。
国家の中では複数の闘争・競争が常に起きている。企業家同士、企業家と労働者、労働者とエスニックマイノリティの闘争が起きている。ここで重要になるのは民族概念。国の労働力形成の過程と民族は結び付いている。階級構成と言語・人種・文化の区分は高い相関性を持つので。資本・企業家は資本蓄積が目的であるように、労働者は自らの生存と負担軽減だけが目的。エスニックマイノリティは労働者と競合し、文化が異なっているので闘争が起きている(ここでは人種差別の起源とはしていないが、アーレントのいうように植民地経営で生まれて本土に持ち込まれたという説明がよさそう。でも東欧の多民族国家の差別を説明できないか)。これは国家内部の闘争であるが、多国家の間でも闘争が起きている。
このような資本主義の世界システムに対抗する運動として、社会主義運動とナショナリズムが生まれた。啓蒙主義のイデオロギー(自由・平等・友愛、人間解放、進歩の必然性など)をまとい、権力奪取を目的にしていて、民衆動員が不可欠であるという共通点をもつ。社会主義運動は〈中核〉の工業労働力が重要な地域で生まれ(イギリス、ドイツが例になるだろう)、ナショナリズム運動は〈周辺〉の権利の分配が不平等・抑圧的・不公平と考える者がいるとことで起こる(ハンガリーを例にする)。反世界システム運動は権力に取り込まれたり、自滅した。ときに周辺で成功することもあったが(ロシア、中国など)、反システムは資本主義の一部を担い続けた。
(資本・企業家は資本蓄積が目的であるように、労働者は自らの生存と負担軽減だけが目的という指摘は衝撃的。個々の人を見れば例外はあるけど、19世紀以降を観察すれば、「労働者」の傾向はそういうものだといえる。なお著者の言う「労働者」はまさに賃金労働にある人のことなので、マルクスの言う「プロレタリア」とは一致しない。マルクスの社会主義を指向するプロレタリアはあくまでイマジナリーな概念だから。もう一つの目からうろこは、社会主義運動とナショナリズム運動には親近性があるという指摘。権力奪取目的と民衆動員が共通しているというのは、20世紀になってどちらも全体主義運動になっていったことをよく説明する。ただ本書の記述だと、ナショナリズムと人種差別の発生をうまく説明できていないように思ったので、アーレントの「全体主義の起源」で補完してもよいのかもと素人考えをした。)
(資本主義の世界システム論だと、ヘゲモニー国家があり、変遷していった、中核と周辺は絶えず移動しているというのは重要なのだが、本書ではついでに説明しているだけ。ここは不思議。)
資本主義の起源は、マルクス「資本論」とヒックス「経済史の理論」を読んだが、ウォーラーステインの本書のほうがピントがあっていて詳細情報をとらえている感じ。前著ではヨーロッパのことばかりをみていて、そこで起きたことだけで記述している。でも15-16世紀のヨーロッパで資本主義が成立したのは、単独の経済発展があったわけではない。地中海貿易に成功と遮断が「革命」を起こしたわけ。そのうえ資本主義をより強力にしグローバルなものにしたのは、新大陸での先住民虐殺と黒人奴隷制だった。国内の工業化による性差別とコモン破壊、国外植民地のレイシズムが資本主義発展の基礎になっていることに注意すべし。
2013/05/23 ジョン・リチャード・ヒックス「経済史の理論」(講談社学術文庫)
2019/02/1 ジョン・リチャード・ヒックス「経済史の理論」(講談社学術文庫)-2 1969年
2019/01/31 ジョン・リチャード・ヒックス「経済史の理論」(講談社学術文庫)-3 1969年
インマニュエル・ウォーラーステイン「新版 史的システムとしての資本主義」(岩波書店)→ https://amzn.to/4bGwK9N https://amzn.to/4bneEKl
川北稔「世界システム論講義」(ちくま学芸文庫)→ https://amzn.to/3wRG5N7
2024/05/28 インマニュエル・ウォーラーステイン「新版 史的システムとしての資本主義」(岩波書店)-2 資本・企業家は資本蓄積だけが目的であるように、労働者は自らの生存と負担軽減だけが目的。反システムの社会主義は資本主義的世界システムの援軍になる。 1995年
2024/05/27 インマニュエル・ウォーラーステイン「新版 史的システムとしての資本主義」(岩波書店)-3 資本主義的世界システムは危機。その先は新封建国家か民主的ファシズムか。 1995年