2024/06/04 川北稔「世界システム論講義」(ちくま学芸文庫)-1 世界システム論は、近代世界を一つの生き物のように考え、象徴としての「コロンブス」以降の世界はヨーロッパ世界システムの展開である 2016年の続き
なぜヨーロッパは世界システムをつくることができ、その他の地域ではできなかったのか。世界システムになりうる「先進性」をもっていたのは、中央アジアやインドやビザンチンや中国などにあった。それらは帝国はつくっても、世界システムにはならなかった。いろいろな説明が行われているが、本書ではヨーロッパが政治的統合体を作らなかったことが重要だとされる。中心の帝国が規格を押し付けることで、発展や革新の機運をつぶしてしまった。西ヨーロッパの資本主義は拡大膨張だけを目的にしたので、発展や革新を継続することができた。その違い。
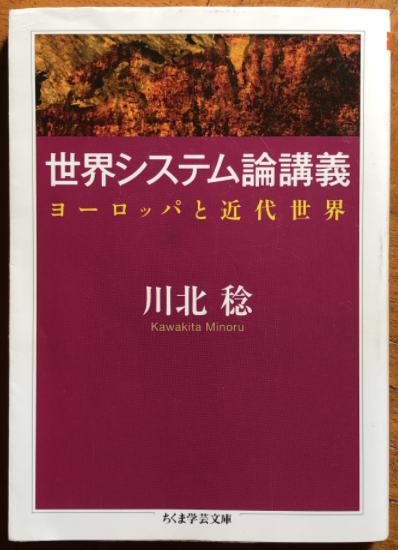
ヨーロッパの生活革命 ・・・ 16世紀の貿易量を1とすると、17世紀に3、18世紀初めに10~20になった。大量の輸入品(煙草、紅茶、砂糖、綿織物など)はイギリスの生活を一変した。これらの舶来品を大量消費することがステイタスシンボルになり、下層に普及した。その結果ますます貿易量が増える。次に輸入品を国産化する代替が起こり、工業革命になる。舶来品の消費は、コーヒーハウスの繁盛になり、そこで政治・商売・文芸・科学が語られた。政治運動や科学革命がコーヒーハウスを基にするネットワークで起きた。これは夏目漱石が「文学評論 1」(講談社学術文庫)で詳述している。
(漱石の評論を読んだときはコーヒーハウスの重要性にはちっとも気づかなかった。まして17~18世紀の科学革命(@バターフィールド)につながるなど、想像すらしなかった。それを記述した漱石は先見性の持ち主。)
砂糖王とタバコ貴族 ・・・ 18世紀のイギリス植民地をみると、カリブ海諸島は砂糖で高収益。ニューイングランドなどのアメリカはたばこで低収益。なので本国は前者を優遇・保護したが、後者は放任した。前者は管理人を雇えるほど高収益なので不在プランターとなり公共インフラ投資をしない。後者は在住プランター(イギリスの移民や官吏など)にならざるを得ず自分の生活のために公共投資を行った。在住プランターは生活や価値意識がイギリス化し、独立志向になった。その結果20世紀になっても前者はイギリスの保護領で「低開発」国となり、後者はイギリスに変わるヘゲモニー国になった。植民地が生産する世界商品の違いが、その後の地域の差になる。
(なお、この時期中国の経済水準はヨーロッパ並みだった。ヨーロッパは政治的に統合されていないが、中国は帝国として統合されていた。原材料を供給する「周辺」も国内にあった。中国の現在の経済格差は、ヨーロッパの本国と植民地の格差に相当するといえる、という。)
奴隷貿易の展開 ・・・ 17-18世紀の三角貿易。西アフリカの黒人→カリブ海プランテーション、カリブ海やアメリカの綿花・砂糖→イギリス、イギリスの綿織物・砂糖→西アフリカ。イギリスでは黒人奴隷売買の囚役が産業革命の財源になった。西アフリカでは労働力が流出し、人身保護のためにイスラム化が進む。カリブ海諸島では単一作物の身の生産なので食料自給ができずイギリス依存の経済になり、インフラ未整備で生産性が上がらず、人種間交流が進まなかった。この三角貿易の傍流にあったアメリカは独自の商業ネットワークをのちに作れた。
だれがアメリカをつくったのか ・・・ アメリカへの移民はイギリスの中産階級という説があるが、これは「神話」。記録を見ると、社会に占めるべき位置のないもの(サーヴァント:使用人、徒弟など)が大半であり、その他の食い詰めものや孤児・捨て子が送られ、死刑を減じられた犯罪者が流刑された。本国の貧困や失業、犯罪などの社会問題の解決の場とされた。それはオーストラリアやニュージーランドも同じ。
(勤勉で信仰心の厚いWASPが移民だったというのは、アメリカがヘゲモニー国になってから作られた。)
「二重革命」の時代 ・・・ 18世紀後半の大きな出来事を世界システム論から検討する。
産業革命:イギリスに起きたのは、イギリスが世界システムのヘゲモニー国だったから。重税だったが、軍事に使い競争国との戦争に勝ち植民地経営を拡大し収益を上げた。なので不満が起きなかった。フランスはイギリスとの競争に負けたので、産業革命は起きなかった。19世紀後半にドイツとアメリカが工業生産をあげるとイギリスはヘゲモニー国から脱落する。
フランス革命:1786年の英仏間自由貿易協定によってイギリス製品に対抗できないフランスの工業が壊滅。その立て直しで89年に「革命」が起きた。とはいえ社会改造の動きとしては革命というほどのものではない。フランスの近代化理念(自由・平等・同胞愛)も世界システムの中核にしか届かない。むしろ平等が能力主義と結びつくことで、新たな差別(人種、性など)がおき高齢者と子供の排除を助長した。人種差別は生物学的な人間の種類による区別ではなく、安価な労働力を抽出するための手段であった。
アメリカ、ハイチなどの独立:世界システムの周辺に起きた隷属状態からの脱却運動。「半周辺化」運動。隷属状態から脱却するためには本国との関係を暴力的に断つ必要がある。
(ハイチは1804年に黒人共和国として独立し奴隷制廃止を実行した。しかし、その後はフランス、ドイツ、アメリカなどが干渉する。20世紀には独裁国家になり、変わった政権でも腐敗が横行し、世界で最も貧困な国になっている。世界システムから離脱する「革命」は自立できる可能性がなかった。)
(ソ連や鎖国の日本が「半周辺」でいられたのは、世界システムから隠遁していたためとみなせる。とすると、21世紀の日本は半中核国だったところから零落して搾取の対象になっているが、それから脱却するには中核国との関係を断つ必要がある、とえるのかも。)
フランス革命とアメリカ独立戦争の評価が、アーレントとかなり異なるのに驚いた。アーレントの議論には経済と政権の情報が洩れているので、世界システム論のほうが事象を説明するのにはふさわしい。アーレントの議論は共和制や活動による政治参加、それによる自由の獲得という政治哲学として傾聴するべきだろう。
2021/11/16 ハンナ・アーレント「革命について」(ちくま学芸文庫)-第1章革命の意味 1963年
2021/11/15 ハンナ・アーレント「革命について」(ちくま学芸文庫)-第2章社会問題 1963年
2021/11/12 ハンナ・アーレント「革命について」(ちくま学芸文庫)-第3章幸福の追求、第4章創設(1)自由の構成 1963年
2021/11/09 ハンナ・アーレント「革命について」(ちくま学芸文庫)-第6章革命的伝統とその失われた宝-1 1963年
2021/11/11 ハンナ・アーレント「革命について」(ちくま学芸文庫)-第4章創設(1)自由の構成(続き)、第5章創設(2)時代の新秩序 1963年
2021/11/08 ハンナ・アーレント「革命について」(ちくま学芸文庫)-第6章革命的伝統とその失われた宝-2 1963年
インマニュエル・ウォーラーステイン「新版 史的システムとしての資本主義」(岩波書店)→ https://amzn.to/4bGwK9N https://amzn.to/4bneEKl
川北稔「世界システム論講義」(ちくま学芸文庫)→ https://amzn.to/3wRG5N7
2024/05/31 川北稔「世界システム論講義」(ちくま学芸文庫)-3 世界システムのヘゲモニー国も、せいぜい50年ほどしか覇権をとれない。次の覇権国はまだ見えてこない。 2016年に続く