歴史をみるときに、国を単位として展開するとみる一国史観と、国は同じ一つのコースに沿って競争するという単線的反転段階史観。これらの見方はやめよう。かわりに、近代世界を一つの生き物のように考え、近代の世界史を有機体の展開道程としてみるシステム史観〈世界システム〉をとる。すると、象徴としての「コロンブス」以降の世界はヨーロッパ世界システムの展開なのである。
一国史観と単線的反転段階史観のサンプルは、 レオポルド・ランケ「世界史概観」(岩波文庫) 1854年。
なお、ここでいうヨーロッパは、イギリス・ベネルクス3国・北フランスなどの西ヨーロッパのことをいう。東欧、ロシアなどは含まれない。下記参照。
クシシトフ・ポミアン「ヨーロッパとは何か」(平凡社ライブラリ)-2
クシシトフ・ポミアン「ヨーロッパとは何か」(平凡社ライブラリ)-3
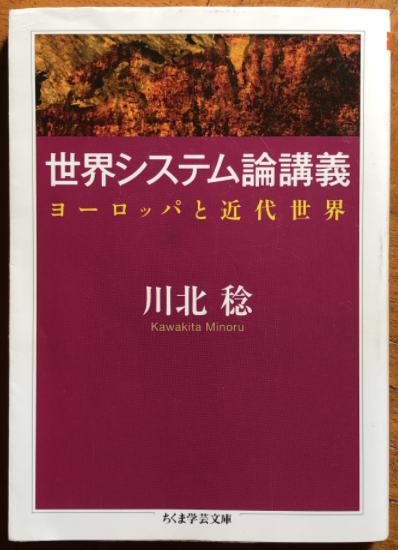
世界システムという考え方 ・・・ 世界システム論から見ると、ヨーロッパなどの北の国が南を開発して世界的な分業体制を作り、経済や社会の在り方をゆがめた。なので「後進国」はひとつのコースに遅れているのではなく、北によって「低開発化」されたのだ。このシステムは世界帝国を目指し、実際にヘゲモニー国家(オランダ、イギリス、アメリカ)を生んだが、ベトナム戦争以後アメリカのヘゲモニーは失われた。
(ヨーロッパの開発によって中心と周辺ができ、開発途中の周辺には奴隷制が生まれる。アメリカやロシアに顕著。そうすると、21世紀の日本で起きているアジア人労働者の奴隷化は日本が中心から周辺に落ち込んだことに理由を見出せそう。)
アジアにあこがれたヨーロッパ人―大航海時代へ ・・・ 15世紀までのヨーロッパは東アジア、中央アジア、ビザンチンなどより人口が少なく生鮮性が低い周辺。14~15世紀は人口減と生産の停滞が起きた危機の時代(村上陽一郎「ペスト大流行」(岩波新書)。16世紀になって危機が克服されると、ヨーロッパは大航海時代になった。同時代の中国も大航海の時代だったが、世界システムを作らなかった。中国は帝国化したので、武力と経済発展の拡大を制限したのが理由と思われる(のちに鎖国化する)。一方ヨーロッパは農民の反乱に対抗するために領主の力が弱くなり国家の権力が強くなった。国家の分業体制ができつつあり諸国家のつながり(インターステートシステム)が強くなって、国家ができることが制限された。でも国家は武力や経済発展を制限しなかったので、ヨーロッパを中核とする世界システムを構築できた。東欧やラテンアメリカでは国家が弱くなり、周辺化して植民地になっていった。
キリスト教徒と香料を求めて ・・・ 最初に対外進出したのは、最西端にあるポルトガル。イスラムからの国土回復を達成していたのに加え、ヨーロッパの広域商業ネットワークの外にあったので、進出する野望があった。ガマ他によるインド航路の開拓。16世紀当時はほかの広域商業ネットワークができていたので参入することが目的であり、イスラムと北イタリアのネットワークを覆すにはいたらない。それに当時のヨーロッパには輸出する産物がなかった。アメリカを除く世界には商業ネットワークと一緒に分業体制ができていた。次第にヨーロッパの世界システムに飲み込まれていったが、最後まで独立していたのは地理的に遠いアジアだった。
スペイン帝国の成立と世界システムの確立 ・・・ スペインはアメリカを植民地化した。商業ネットワークと生産物がないので、プランテーション化した。先住民を奴隷化したが、激減・絶滅した。そこでアフリカの黒人を奴隷にした(利益と利権があって以後数百年続く)。アメリカの銀はヨーロッパの経済発展に貢献し、世界帝国を作ろうとする動きがあったが、スペインとフランスの王室の破産で潰えた。政治的な統合を図る世界帝国はできず、世界経済だけが残れた。
(世界システムはグローバリズムと世界的分業を前提にしていた/いるから、いまさら鎖国やブロック経済はできないし、引き合わない。なお、ユーラシアの広域商業ネットワークは世界的な分業体制ができていたし、「帝国」でも分業体制になっていた。一国内の自給自足体制はまず成り立たなかった。)
「十七世紀の危機」 ・・・ 17世紀にイギリス・フランス・オランダがスペイン・ポルトガルの世界分割に挑戦する。オランダが農業と漁業と造船業の優位によってバルト海貿易(東欧との商業ルート)を独占する。これによって、世界システムの覇権を握るヘゲモニー国家になった。金融・保険の市場となり、オランダの通貨が世界通貨になった。自由貿易を称えたのでリベラルな場所になり、亡命者や芸術家が集まった。なおヘゲモニー国家は生活水準や賃金の上昇などによって生産性が低下し、50年程度しか続かない。
(だからデカルト、スピノザ、ライプニッツなどの学者が集まり、オランダに画家が輩出したのか。バルト海貿易が重要であるのは全く見過ごしてました。)
環大西洋経済圏の成立 ・・・ 16世紀から18世紀までのイギリス。経済危機(インフレ、森林枯渇、人口増、輸出停滞など)にあった「後進国」のイギリスが、カリブ海やアメリカを植民地化することで、17世紀半ばには貿易増に転換した。それは植民地の「世界商品」を使ってアジア・アフリカ・アメリカという新市場に販売することで達成した。イギリスはオランダの金融市場を使って資金を集め、国立銀行と議会制度によって安全な資金運用先と目され、高い税率や軍事費負担で国民から抵抗を受けることが少なかった。それでイギリスは対オランダ、対フランスの戦争に勝つことができた。18世紀のイギリスは地主のジェントリと商人が支配する国になった
(18世紀末からの産業革命より前の時期は、ヨーロッパの輸出品は質に劣っていたので、ビザンチンやインド、中国にはほとんど流通しなかった。かわりに新興市場を席捲した。可能にしたのは、奴隷制によるコスト削減。搾取によって利益を上げた。19世紀ヨーロッパの工場労働者の悲惨な生活は「新大陸」の奴隷制を本国に持ち込んだためにできたのかも。)
2022/06/17 フリードリヒ・エンゲルス「イギリスにおける労働階級の状態」(山形浩生訳)-1 1845年
2022/06/16 フリードリヒ・エンゲルス「イギリスにおける労働階級の状態」(山形浩生訳)-2 1845年
個々の事例や評価は断片的に知っていたことが多いが、この記述によって線につながっていく。本書はエッセンスだけしか書かれていないので、ここに肉付けする勉強は必須。ことに16世紀から18世紀までのヨーロッパを絶対王政として、一国内やヨーロッパ各国の覇権争いとしてみるのはとても狭い見方になってしまう。
インマニュエル・ウォーラーステイン「新版 史的システムとしての資本主義」(岩波書店)→ https://amzn.to/4bGwK9N https://amzn.to/4bneEKl
川北稔「世界システム論講義」(ちくま学芸文庫)→ https://amzn.to/3wRG5N7
2024/06/03 川北稔「世界システム論講義」(ちくま学芸文庫)-2 ヨーロッパは政治的統合体を作らなかったから世界システムを作れた 2016年
2024/05/31 川北稔「世界システム論講義」(ちくま学芸文庫)-3 世界システムのヘゲモニー国も、せいぜい50年ほどしか覇権をとれない。次の覇権国はまだ見えてこない。 2016年に続く