レオポルド・ランケは19世紀ドイツの歴史家。1795年に生まれて1886年に亡くなるという当時としては長命な人だった。この国では戦前から知られていた模様。本書の訳者の林健太郎が主要著作を翻訳している。でも、手軽に入手できたのは岩波文庫にあった「世界史概観」くらい。
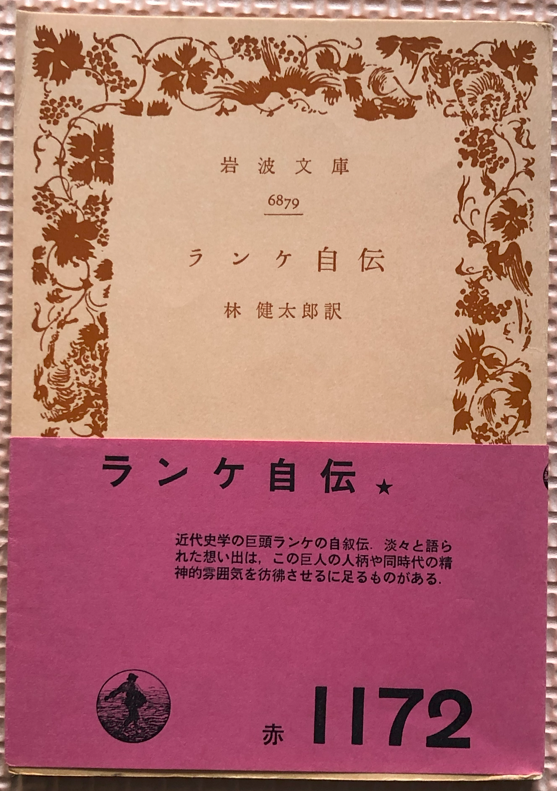
単独で読むと、この自伝は面白いところがまるでない。祖父の代に中流階級になり、父が神学者になる(多くの自伝が祖父からの系譜を書くところを見ると、たいていの人は自分の家の2、3代前までしか知らないらしい)。その息子はティーンエイジに修道院学校に行き、成績が良かったらしくライプチヒ大学に進学した。卒業後しばらく教師をしていたが、校長などの勧めで大学で研究を再開。29歳で書いた論文で認められて教授職を得た。以後91歳で亡くなるまで研究生活を続ける。この間、結婚や子育てなど家庭や個人の話は出てこない。まことに近代ドイツの教育政策をそのまま体現したような人であった。日本で「ランケ自伝」が求められるとすれば、戦前の教養主義が規範とするべき学究に他ならないところ。
〈参考エントリー〉 ランケが規範にしたかもしれないドイツの学究
中島義道「カントの人間学」(講談社現代新書)
というわけでものすごい勢いでページをめくった。でも、いくつかの本と並べてみると、興味がわくところがある。
上山安敏「世紀末ドイツの若者」(講談社学術文庫)は19世紀末のドイツ学生運動を紹介する。この時代の大衆化しつつある大学の学生は、それ以前の学生生活を嫌ったという。彼らが嫌った古いタイプの大学生活を送ったのがランケだった(あとニーチェも)。ランケは学生組合のことを書いていない。残念だが、代わりにかれはTurner(体育会)という学生組織に加入していた。野山に出て身体を鍛錬することでドイツ民族意識を高揚させる目的の組織だという。おりしもランケの大学生時代はナポレオンのロシア遠征の時期にあたり、Turnerは反ナポレオン運動になる(指導者は古ゲルマン崇拝者であったとのこと)。
「解放戦争後はドイツの統一と自由な憲法を求めるブルシェンシャフト運動の中核となり官憲の弾圧を受けた(訳注)」。
ワンダーフォーゲルのような運動はドイツの伝統なのだね。心身の鍛錬が民族運動に回収されるのも、ドイツ学生運動の伝統みたいなものか。
そのランケは自身を保守的と規定する。ドイツ精神を連邦の維持、君主制や身分制、官僚制に見るという。反フランスを明言しているので、民主主義や共和主義などの人々Peopleが政治参加することを嫌う(ここも戦前の日本の歴史学がランケを紹介した理由なのだろう)。この人は、ナポレオンのドイツ占領のあと、1830年と1848年の革命を見ているのだが、自伝を見る限り冷淡。君主に対する慮りが目立つ。ランケの仕事を見ると、自国史・自民族史、教会史(とくにプロテスタント)が主で、彼の歴史研究はナショナリズムに沿って行われたのだった。彼はドイツ語圏内にある図書館や文書庫などを調査して古い文書を大量に集めた。それを参考にして歴史を記述した。解説や訳者が近代的な歴史学の開始者というのは、その方法なのだろう。このやりかたは、19世紀前半の文化活動を担ったディレッタントのもの。ケッヘルの仕事が19世紀後半には批判されたように、ランケが高齢になったころにはその著書も「古めかしい」という評になったのもやむを得ない(解説によると、「世界史概観」がそう評されたそう)。
〈参考〉 同時代のディレッタントの例。モーツァルトの作品番号を作ったケッヘルの生涯とその影響。
岡崎勝世「聖書vs世界史」(講談社現代新書)によると、聖書の通りに世界の歴史を記述する普遍史ユニバーサル・ヒストリーは18世紀の啓蒙時代で終わったという。実際にランケが学生だった1820年年代には歴史学と神学は一応切り離され、普遍史が講義されることはなかった。当然、ランケがのちに書くものにも普遍史や聖書が入り込むことはなかった。本書や「世界史概観」ではランケは近代歴史学の礎という位置づけになっているが、文献を重視する記述は彼の前にすでに確立していたようだ(そこでは18世紀にできた聖書学や古典文献学の方法が反映しているのだろう、と妄想)。
ランケはマルクスとエンゲルスの父にあたる世代。二人の著作をざっと斜め読みする限りでは相互に影響を与え合っている様子はない。言及もたぶんない。まったくすれ違ったのだろう。ランケがマルクス「ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日」、エンゲルス「ドイツ農民戦争」を読んでどういう感想を持ったかを想像するのは楽しい。
という具合で、本書を単独で読んでもなんの感興もわかないが、別の本とリンクを貼ると書かれていないところに「もんだい」があるのを発見できる。こういうのが読書の楽しみ。
レオポルド・ランケ「ランケ自伝」(岩波文庫)→ https://amzn.to/3K8LuCt
ランケ「世界史概観」(岩波文庫)→ https://amzn.to/4dXxXvs