2024/09/24 フョードル・ドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟 3」(光文社古典新訳文庫)第3部第7編「アリョーシャ」 一本の葱が差し出され受け取ったアリョーシャは「生涯変わらない確固とした戦士」に生まれ変わる 1880年に続く
これまでほとんど登場しなかったドミートリー(ミーチャ)が大暴れする。この大きな小説のちょうど半ばにあたり、アクションではクライマックスになる。熱に浮かされたようなミーチャの狂態を口あんぐりと追いかけるのであるが、同時にとんちんかんなユーモアを発揮しているところに注目。ことにミーチャとホフラコーラ夫人との会話。爆笑必死です。
ドミートリー(ミーチャ)は激情家で気分の振幅が激しい。自制できなくて衝動的に行動するのに、しばらくたって自分の行動を恥じて消沈する。そのような行動性向を積極的に評価する向きもあるようだが、居酒屋でであったスネリギョフを叩きのめしたり、実父のフョードルを殺害したいなどと脅迫したりする。これは情状酌量の余地ない悪質な粗暴犯。豪遊しては借金を繰り返し、返済のあてがないので時に踏み倒す(婚約者のカテリーナに借りた金だけは返済する強い意志をもつ)。これも社会性のない甲斐性なし。弱い者には居丈高で暴力をふるい、女性にはこびへつらう。ほんとダメ男。なので、初読でも今回の再読でもドミートリーには同情も共感も持てない。
多少大目にみることができるとすれば、ドミートリーは母に早く死なれ、父の育児ネグレクトを受けてきた。他人に愛される経験がなかったのが、ドミートリーの行動性向を形成する要因になったのだろう。他人と同等に付き合う方法を知らないので、他人への攻撃性と女性への過剰な依存性が生まれてしまった。どんちゃん騒ぎをして金を蕩尽するのも、承認欲求を満たすために攻撃性と依存性が現れたのだろう。カテリーナやグルーシェニカへの態度は恋人に対するそれではなく、母の代理への甘えにみえてしまう。そういう子供大人(チャイルディッシュ)なドミートリーの大冒険。
ドミートリーの恋情は一方的に女性に思いを寄せ、相手の意向にお構いなしに自分の感情を伝え、空想の中で高揚したり落ち込んだりするもの。この「女好き」はドスト氏の小説によく見てきた。リストアップすると、「貧しい人々」「分身(二重人格)」「白夜」「小英雄(初恋)」「虐げられた人々」。これらの男性は好きになるという感情に高揚するだけでなく、相手に傷つけられることを望んでもいる。フラれるかもとおびえたり、相手の些細な行動の意味を勘ぐったり、相手をわざと挑発して泣かせたり反発させたり。恋愛が幸せを構築するのを目的にしていなくて、壊して自己評価を下げたり、苦痛や屈辱を味わうことを目指しているかのよう。他人の感情をうまく読めないひとにありがちな行動性向に見える。ドスト氏の考えをみるときに、女好きと苦痛愛好は面白い視点になるけど、読者が自分の行動のモデルにするのはお勧めできない。
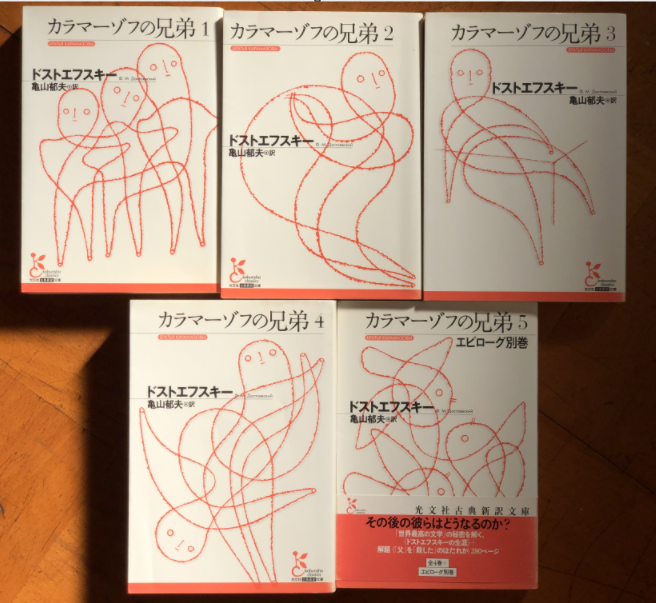
第7編「ミーチャ」 ・・・ 時間は少し巻き戻され、ドミートリーがフョードルの家を出て行ってから。第1部第3編「女好きな男ども」の続き。ドミートリーは焦っている。ライバルである父のフョードルが先にグルーシェニカを手に入れてしまうのではないかと。彼女が「連れて行って」と言ってくれれば、つかまえて世界の果てにつれだしてしまおう、でも婚約破棄したカテリーナに金を返さなければならない。同時にできればすべてが生まれ変わり、新しく歩みだせるのだ(とここまではドスト氏に登場する空想家の思考そのもの。思い付きの妄想がどんどん膨らんでいって、自分の都合がよくなると思い込んでしまう。思い込みは現実よりも実感あるものになり、すぐに実現するものだと未来を楽観してしまう)。
手元に金がないので、ドミートリーはまず商人サムソーノフに借りに行く(グルーシェニカを囲っていた老人が金を出すと思い込むところが滑稽)。チェルマシニャーの森を担保にしようとする(フョードルが売りにだそうとしていることをドミートリーは知らない)。サムソーノフは意地悪をしようと、フョードルの敵になっているリョガーヴイ(猟犬の意)を紹介する。
馬車を仕立ててリョガーヴイの家を訪れると、ウオッカで泥酔したリョガーヴイは起きない。一晩を過ごすと酩酊したリョガーヴイはドミートリーを「悪党」と罵って追い出す。
失意で帰ってきたドミートリーはピストルを担保に金を借りる。今度はホフラコーラ夫人に金を借りに行く(ドミートリーが婚約破棄したカテリーナの世話を見る夫人が金を借すと思い込むところが滑稽)。ホフラコーラ夫人は3000ルーブリくらい何とかなると言い出すので、ドミートリーは有頂天になるが、どうも会話がかみ合わない。なんとホフラコーラ夫人は「金鉱に行け」と言っているのだった。
ドミートリーはグルーシェニカはフョードルの所に行ったと推測し、フョードルの家に行き、秘密のノックをする。ドミートリーはフョードルに人間としての嫌悪を感じる。フョードルの姿を認めたとたんに、ドミートリーの意識は消失。記憶が戻ったのは、塀を乗り越えるとき。目覚めたグレゴーリーが追いすがってきたので、小さな杵で頭を殴り昏倒させる。ドミートリーも血まみれになるが構わない。グルーシェニカの家に行くと下女が「お嬢さんは将校の所に行った」と告げ、ドミートリーへの託も伝える(第7編「アリョーシャ」参照)。そこでようやくドミートリーはグルーシェニカに愛されていなかったことを悟る。
(失恋する経験はすなわち、愛している相手を中心に構成されていた世界から突然中心がなくなり、意味をもっていた世界の表徴が色を失い味気なくなり自分から遠ざかってしまうのである。人々を信じられなくなり、自分が相手を傷つけてきたのではないかと怖れと憎しみが生まれ、自分がひどく傷ついていることに気づき、傷ついている自分には価値や意味がないと思うようになるのである。これは自分に起こったことだが、ドミートリーにも同じことが起きた。なので「身を引くのだ。愛している人と憎んでいる人に道を譲る」「自分は卑怯者だが自分には満足している。卑怯者なのを苦しんでいる」と言い出し、メモに「全人生に対し自分を処刑する。僕の全人生を処罰する」と深い悔悟を持つのだ。)
ドミートリーはピストルを返してもらうとともに、大量の金を見せつけて、酒や肴や菓子を買い込み馬車につめこませる。モークロエという離れた町に向かうことにする。内心ではピストルでけりをつけるとも決めている。
(ドミートリーは御者に「みんなにかわって僕を許してくれるか」「神よ、僕の裏切りを受け入れてください」「僕は自分で自分を裁いた」とかきくどく。)
モークロエの宿場で居酒屋にいたのは、先に出立したグルーシェニカと将校、ほかに数名のポーランド人。ドミートリーは割って入って酒や肴や菓子をふるまい、村人をたたき起こして音楽を演奏させ踊りを踊らせる。それというのもドミートリーがいうには「うじ虫はしばらく地面をはい回ってから消えてなくなる」から。ドミートリーはポーランド人にトランプゲームの賭けを申し込み、手ひどく負ける。別室に将校を呼び込んで手切れ金を渡すからグルーシェニカから切れろと強要する。侮辱だと憤慨する将校たちであった(いったん宿の外に出たドミートリーは今を除いてチャンスはないと覚悟するが生きていたいという強い思いが実行をとどませる)が、宿の主人にいかさまを見破られる。
(将校とポーランド人はみずから一室にこもってしまい、ロシア人だけのどんちゃん騒ぎが続く。ここはドスト氏のレイシズムが垣間見える。「作家の日記」などで国内に住むポーランド人やドイツ人、トルコ人らを虚仮にしバカにするのであるが、ここの記述が最も差別的。ドスト氏のユートピア願望は他民族や他人種を排除することで成り立つ。イワンは幼児や女性らの弱いものを虐待するのを許さないのであるが、弱いものの中には国内在住のエスニックマイノリティは含まれないようだ。)
この醜態をみて、グルーシェニカも自分の本心を見つけるのであった。将校にみそめられ商人に囲われていた五年間は一生の恥で死ぬまで呪ってやるという。ドミートリー以外の人を愛していたのはバカだった、許してくれという。ドミートリー「この一瞬のためなら世界ぜんぶだってくれてやる」。グルーシェニカ「明日は修道院に入る。でも今ははしゃぎまわりたい。私が神さまならみんなを許してあげる。私たちは汚らしいけれど、この世はなにもかもすばらしい。カテリーナの借金は私の金を使えばいい。土を耕しにいきましょう」。ここまで言うと疲れて寝てしまう。すでに夜明けが近いのに、ドミートリーは鈴の音が聞こえ、宿屋の周囲が騒がしくなったのに気づく。警察が踏み込んだのだ。「あなたは昨日起きたフョードル殺害の罪で起訴されている」。
この章のテーマは「許す」。これには「他人を許す」と「自分を許してくれ」のふたつがある。前者は「プロとコントラ」「ロシアの修道僧」で検討していた。他人を許す資格を考えると、イエスしか許すことはできなくなりそう。それに許した他人が再び似たようなことで他者危害を加えたら、許した人には責任があるのか。そんなことも考える。なので、他者を絶対に許さない大審問官やイワンのほうに理屈がありそうにもみえてくる。
さて、この章では「自分を許してくれ」が重要。その発話の前には、自分が他者危害を繰り返してきたという反省がある。実際、このようにいったドミートリーとグルーシェニカはふたりとも過去の自分の言動が誤っていたと自省する。ドミートリーは自分がやってきた放蕩や女性への求愛などの失態を演じてきたこと(父への憎悪やスネリギョフへの暴力などは反省対象にならない。殺人を罪であるとついに思わなかったラスコーリニコフと同じ)。グルーシェニカは将校を愛していたと自分を偽っていたこと(テキストから現れないが、ポーランド人への差別感情があるかもと疑いたくなる)。自分の過去は恥じるものであった。彼らは地上の罪にはあまり関心がなくて、天上に対する罪を感じている。でも、その罪の許しを神にするには、あまりに自分らはおこがましい。彼らの「自分を許してくれ」は、神を信じていないもの、神から遠ざけられたもの、地に呪われたものが言っているように見える。彼らが「自分を許してくれ」と発するのが自己懲罰とセットになっていて、罪の自覚からいっきに罰を引き受けることも発している。「自分を許してくれ」は天上の罪の自覚とそれに対する罰の引き受けが同時にある。
(ラスコーリニコフがソーニャの諭しで自白を引き受けることにしたのと同じことが、どんちゃん騒ぎをしているドミートリーとグルーシェニカに起きたのだった。とてもわかりにくいけど。)
グルーシェニカは改心の証として「いっしょに土を耕しに行きましょう。この手で土を掘ってみたいの、働かなくちゃいけないの」という。それまで労働したことがないし、まして土を耕したことなどない人が実際にできるわけではない。この表現から前の章でアリョーシャが見せた大地へのひれ伏しを思い出してしまう。でもアリョーシャがもった大地、すなわちロシアそのものとの一体化というコンセプトをグルーシェニカはもっていない。それよりも「土を耕す」ことで未来の収穫を期待するという希望をみる。明日なにかすることがある、いつか何事かを造ることができる、そういう自己変容をみよう。そうすると(先取りすると)エピローグでグルーシェニカがシベリアに流刑されるドミートリーの後を追う決心がここに由来していることがわかる。
言い添えれば、ドミートリーもグルーシェニカも体を使って「土を耕す」ことはしない。汗を流して地道なことをこつこつと積み上げることはできない。「土を耕す」ヴィジョンにうっとりとして、いつか実現することを空想するだけ。これはドスト氏の小説にでてくるキャラに共通している。
フョードル・ドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3SEP249 https://amzn.to/3SC1OQW https://amzn.to/3SEYK6x
(光文社古典新訳文庫)→ https://amzn.to/3SExViP https://amzn.to/3ysORSy https://amzn.to/3ysh5Nk https://amzn.to/3SEAPEt https://amzn.to/3SCwYHL
(岩波文庫)→ https://amzn.to/3SDORWZ https://amzn.to/46yo6c8 https://amzn.to/3Yy0vX9 https://amzn.to/3yiZmYO
2024/09/20 フョードル・ドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟 3」(光文社古典新訳文庫)第3部第9編「予審」 好色で金に執着していたドミートリーは逮捕されて神を愛している自分を発見し苦しみを引き受けることを決意する 1880年に続く