宗像冬樹という作家がいる。この呪われた作家は「天啓」シリーズの重要キャラクターであるので、覚えておくこと。現在29歳で2年前に「昏い天使」という小説で新人賞を取り、ベストセラーになっていた。しかし第2作「黄昏の館」はタイトルのみ発表しているものの、アルコールに耽溺し、まったく書くことができない。そこで編集者に勧められるまま、彼の「失われた黄金の時」であるオニコベノゴウにある西洋館を訪ねることにする。
宗像冬樹が書けない理由は、2つの失われた記憶に原因があるらしい。ひとつは数年前のフランス体験。文学研究でフランス留学中に、所持金をすべて失う。そのあとジュリエットという不良少女と同棲していたらしい。というのは消息のしれた時、宗像は精神錯乱の状態にあり、その半年の体験をすっかり忘れているから。
彼の書いた「昏い天使」という小説は、自身のフランス体験を下敷きにしているとされる。すなわち一夜にして所持金と銀行の残高を失い、パリを追い出され、ジュリエットという少女に出会う。彼女は、カンボジア人の幼女を助けるために命がけの冒険を命じ、一方で犯罪を実行させる。この小説では、これは宗像の自己変革を促す悪魔であり天使である存在に振り回される個人の経験として描かれる。でも、見方を変えると、ジュリエットの指令は「バイバイエンジェル」で「赤い死」なる革命組織の女性首魁が結社員に命じることと同じ。すなわち、労働と定住の禁止。社会道徳の拒否と共同体からの離脱。結社員として生涯を(存在)革命にささげる決意を持つこと。「赤い死」の首魁は社会革命から存在革命にいたる道筋を考えたが、ジュリエットは存在革命から社会革命に向かうように促す。そういう点で、「黄昏の館」のジュリエットと「バイバイエンジェル」の女性首魁は表裏をなしている。
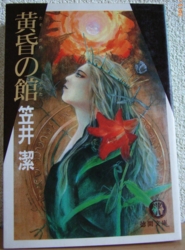
存在革命の道筋に現れるのが、さまざまなオカルティックな説や論。縄文文化が山人に継承されているという1980年代に流行った論に、東北地方の古代文明、古代・神代文字と古文書、義経=ジンギスカン伝説、日猶共同起源説などなど。これらに入れ込んだ人物(西洋館の建造者)が明治から大正のころにかけて外遊するという描写がある。そこで、西洋のオカルティックな研究をして、古代巨石文明、王権論、ケルト文明、古代ルーン文字などなどが登場。さらには当時のオカルト研究者や神秘主義者と会話をしたなど(ユングにシュタイナーに・・・)、ネタの仕込みに手間暇かけていて壮観。まあ自分としては、たとえば酒井勝軍、小谷部全一郎などの昭和初期の奇人を思い出すのだが。
もうひとつの失われた記憶は、9歳の時の西洋館でのできごと。なにか甘美で超越的で決定的な経験をしたようなおぼろげな記憶があるが、まったく思い出せないでいる。いくつかの断片はあるが、現実と結びつかない。
前半は、この記憶を取り戻すための探索。横溝正史的な閉鎖された村での幽霊屋敷物語。途中で出会う人は警告し、警戒し、監視している。カフカの「城」に入るみたいだな。西洋館の中ではうってかわって、丁重に扱われ、しかし監視の目は厳しく、奇怪な出来事が続けざまに起こる。とりわけ、肩に赤い痣を持つ絶世の美女の存在。夢幻のうちに現れ、強烈な印象を残しながら、それを見た人はいない。物語の真ん中で、土地のインテリによって正鵠の一歩手前まで情報が開示され、主人公=探検者が何か特別な使命をもっているとされる。もちろんこのインテリは翌日に殺され、彼に明かす約束をしている秘密ないし渡す予定の文書は失われるのである。ここらもセオリー通り。後半は・・・やめておこう。前半のさまざまな伏線が見事に回収され、もうひとつの巨大な物語が生起するのをみて唖然とするのを楽しもう。
というようなホラー・ミステリーの読み方をしても構わないのだが、どうしてもひっかかるのは、宗像の書きたかった第2作のタイトルが「黄昏の館」であること。小説の中では、すでにフランス語で書かれていて、そこにはここにあるような謎が解明されているとされている。これを第2の「黄昏の館」と呼ぶのは、読者が手にしている小説が「黄昏の館」なのであってそちらを第1の書と呼ぶべきだから。小説で宗像が書きたがっている未着手の、しかしすでに完成している小説(という設定のなんと魅惑的なこと)は、もしかしたら読者が手にしている「黄昏の館」であるかもしれない。作中でフランス語版「黄昏の館」は優秀な翻訳者の手によって訳されるべきであるとされていて、そのとおりに訳出されたのが読者の手にしている本であるのかもしれない。この推測がそれなりに成り立つのは、第1の「黄昏の館」にも宗像9歳のときの「失われた黄金の時」が詳細に書かれているから。ラストシーンで宗像は「決死のジャンプ」を敢行するのだが、それを目撃し記述したのはいったい誰? 宗像は予知夢を見る能力を持っているらしいので、「決死のジャンプ」を予知していて数年後に起こることをあらかじめ書くことができたのかもしれない。とすると、第1の「黄昏の館」は第2の「黄昏の館」と同じものであるのか。しかし、そうしたとき「「決死のジャンプ」はイマジナリーなものであり、宗像は生きているのか?彼が生き延びたとすると、第1=第2の「黄昏の館」に書かれたことは全体としてフィクションになるの? いや「決死のジャンプ」が実際に起きたことだとすると、彼が第1の「黄昏の館」で読んだ第2の「黄昏の館」にはこれから起こることがすでに書かれていたのであるが、その戦慄は第1の「黄昏の館」には書かれていない。とすると、第2の「黄昏の館」はまた別の内容を持っていたのか。そこには第2’ともいえる別の「黄昏の館」があったのか?宗像にとっての事実の確からしさはどこの記述が保証するのだろう。
小説の中に小説が登場することは珍しいことではない。でも、ここでは小説の中の小説の中の・・・という無限入れ子の先で、第n番目の小説は突然入れ子を作る外側の枠になる。小説の内と外が反転。地と図が反転。そこから生まれる幻惑。まあ、ルービンの壺とかメビウスの輪とかウロボロスの環とかそういうものだ。昔の物語には複数の書き手の編集で、そういう趣向になったのはあるというが(「アラビアンナイト」)、近代の小説はその趣向を積極的に開拓してきたなあ。元祖はボルヘスかな。戦前の「黒死館殺人事件」「ドグラ・マグラ」なんかも自己言及的な仕掛けで迷宮を作り出していて、1980年代の作家もそれに挑戦。竹本健治「ウロボロス」シリーズと笠井潔「天啓」シリーズが挑発的な趣向。こちらはその前駆作(1989年)。物語の入れ子構造は隠し味になっているので、わかる人でないとわからないというのがなんとも人を食っている。
でも、怪奇小説・ミステリーとしてよんでも抜群に面白い。
笠井潔「バイバイ、エンジェル」(角川文庫)→ https://amzn.to/48TqZne https://amzn.to/3PkHxh0
笠井潔「熾天使の夏」(講談社文庫)→ https://amzn.to/43dNZwe
笠井潔「アポカリプス殺人事件」(角川文庫)→ https://amzn.to/48MbFZG https://amzn.to/48QRF8q
笠井潔「薔薇の女」(角川文庫)→ https://amzn.to/3PjAu8r
笠井潔「テロルの現象学」(ちくま学芸文庫)→ https://amzn.to/3wTqYCJ https://amzn.to/3wSESF6
笠井潔「ヴァンパイア戦争」(角川ノヴェルス)→ https://amzn.to/3TzXkvc
1 https://amzn.to/49O1RQ1
2 https://amzn.to/3TgB73L
3 https://amzn.to/3Vgx2iH
4 https://amzn.to/3IBpiAa
5 https://amzn.to/3VdTHfq
6 https://amzn.to/43evGqA
7 https://amzn.to/4c9Jmap
8 https://amzn.to/4a5De14
9 https://amzn.to/3vcall9
10 https://amzn.to/4a4WAEd
11 https://amzn.to/3TbwKah
九鬼鴻三郎の冒険
https://amzn.to/3Tihs3g
https://amzn.to/49MsDIT
https://amzn.to/4caCCJr
笠井潔「サイキック戦争」(講談社文庫)→ https://amzn.to/4celyCd https://amzn.to/3IzhKOp
笠井潔「エディプスの市」(ハヤカワ文庫)→ https://amzn.to/3vaFOUO
笠井潔「復讐の白き荒野」(講談社文庫)→ https://amzn.to/43cFiST
笠井潔「黄昏の館」(徳間文庫)→ https://amzn.to/3IxA3DR
笠井潔「哲学者の密室」(光文社)→ https://amzn.to/3IyyOnF
笠井潔「国家民営化論」(知恵の森文庫)→ https://amzn.to/3wSgkMu https://amzn.to/49GiUUh
笠井潔「三匹の猿」(講談社文庫)→ https://amzn.to/49MTGn7
笠井潔「梟の巨なる黄昏」(講談社文庫)→
笠井潔「群衆の悪魔」(講談社)→ https://amzn.to/3IxQb8j https://amzn.to/3Iy6jqg
笠井潔「天啓の宴」(双葉文庫)→ https://amzn.to/3TIMN0R
笠井潔「道 ジェルソミーナ」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3v8nvPZ
笠井潔「天啓の器」(双葉社文庫)→ https://amzn.to/49VWw9K
笠井潔「オイディプス症候群」(光文社)→ https://amzn.to/3T6YgWk https://amzn.to/3TdmuOH https://amzn.to/43mMUSU
笠井潔「魔」(文春文庫)→
笠井潔/野間易通「3.11後の叛乱 反原連・しばき隊・SEALDs」(集英社新書)→ https://amzn.to/4ccUXpe