2023/03/08 アルベール・カミュ「ペスト」(新潮文庫)-1 1947年の続き
感染症が起きたとき、どのような対策をとるかは政治の仕事になる。なので、統計や対策、声明は市が出すものになる。医師や技術者、科学者は政治のサポートにまわる。2020年のグローバルなコロナ禍から見ると、この市の運営はとても理想的に行われている。行政は科学者や医師の意見を尊重し慎重に判断し、市民は行政に不満を持たないし、デマや流言に惑わされることがない。緊張に耐えられなくなったものが市の行政を破壊する行為にでることもない。誰もがリテラシーが高く、理性的に冷静に事態に対応している。市も市民の監視を強化しようとしない。
(あいにくコロナ禍では、行政が医療従事者や専門家の意見を聞かず、緊張に耐えられない市民が愚行を繰り返し、ポピュリストやメディアが妄言やデマを流してしまった。コロナ禍を理由にする差別が起きても、行政や立法は放置していた。この小説のような対策や対応が行われなかった。)
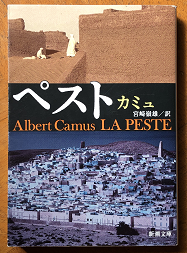
3.8月。ペストが多い尽していた。膨大な死者が簡易的な葬儀で次々埋葬されていた。多くの人びとは感情を喪失し、死者の記憶をすぐになくしていった。未来を失ったように感じ、恋愛や友情を喪失し、無気力状態になっていった。
(この感情の推移は、強制収容所の収容者に近い。ショックのあとに無気力無関心が現れる。)
医師や彼の周辺の人たちは、医療や介護、死者の埋葬など不足するサービスに無償で協力する。その様子を「2+2は4」であることを示す人であると語り手は称する。
(「2+2は4」は、オーウェル「1984年」の主人公ウィンストン・スミスが何度も口にした。この定言は否定しようのない確かさを持っていると考えることで全体主義による人体・人格・人権の棄損に抗おうとした。一方、ドストエフスキーの「地下室の手記」では「2+2は4」は西洋の近代化や合理主義の押し付けに思えていらだたしくてならない。英仏の自由主義は「2+2は4」を理性の証と見る一方、ロシアの汎スラブ主義者は人間らしさを損なう監視や抑圧の象徴とみる。)
4.9月から11月。ペストの患者と死者は上昇して高止まり。人びとはペストに無関心になり投げやりな態度をとるようになった。浪費するものもいたが、それは資産を持っている人たちで、配給の欠乏によって貧乏人や庶民は苦しんでいる。でまかせな予言をするものがでて、人びとが熱中して読んだ。この章では二つの重症者が描かれる。快活な少年が罹患して、大丈夫だろうと思われながら苦しんで死ぬ。詩作に情熱を持つ老人がもはやだめだろうと思われながら熱が引いて快癒する。実際、11月になると、重症者が快癒する例がでてきて、なにより再び鼠が見られるようになった。
(感染症の病原菌やウィルスは致死率が高いものほど、次の宿主に感染する機会をもてないので早晩淘汰される。弱毒性のものは感染力を持つが、やはり淘汰が働いて死滅する。こうして感染症は「自然」に消滅する。その間の感染者を減らすために、隔離やワクチン接種、消毒や防疫などを行う。経済活動が止まるので、行政は市民を支援する。これらが感染症対策の基本。)
(外部からの支援の様子が書かれない。都市の人々は孤立し世界から忘却されているように感じる。無関心や投げやりな態度は、緊張による疲労のせいもあるが、世界に忘れられていることも理由にある。キャラの一人は「愛のない世界」というが、この事態を正確に表している。)
(登場するキャラは仕事と労働に献身的に携わっている。隔離収容所から解放された患者は、施設の介護者として収容所に戻りたいという。他人の複数性(@アーレント)を知ることで、暮らしと生に意味が生まれたのだ。ひとりが「神によらずして聖者になりうるか?」と問う。キリスト教国家の市民ならではの問い。)
5.翌年1月。感染状況が好転していることが知られて、人々に笑顔や微笑みが戻りつつある。25日に市が一定猶予期間ののちに防疫完了することを宣言する。その日には、市民がみな路上に出て、祝祭のようになる。歓喜、喧噪、享楽、祈りなど様々な人々(そのなかで一人の男が銃撃事件を起こし逮捕される)。追放感が消え、祝祭の連帯性を感じる。人びとは人間的な温かみを求めていた。医師はペスト感染は終焉したのではなく、いつでも再び起こるものであると警鐘を鳴らす。
(解放のあと、記録者や作家は感染症や閉鎖の体験から意味や教訓を引き出さない。日本では、耐えた人々を賞賛したり、市や国の対応を批判したり、次に備えよと予言したりするものだが、そういうことをしない。このあとは各人がしゃべりまくって、それぞれが持った疲労や緊張、苦痛や沈鬱、貧困や栄養不良などの意味を個々にとらえるのだ。それは強制収容所から解放された人々に必要な経験だった。前掲フランクル「夜と霧」を参照。)
本書は感染症の対策事例を描いたものではなかった。全体主義に占領された都市や強制収容所の閉鎖空間のレジスタンスの想像的な記録なのだ。作中でもペストに罹患することは悪であるとされ、そこからいかに離脱するかが精神的な問題になったりする。ペストは全体主義のメタファーとみることができる。なので、医師や市当局やボランティアの活動は全体主義に抗する活動にとてもよく似ている。
そのとき、個々人の思想や経歴は問題にならなくなり、さまざまに立ち上がったチームやプロジェクトをどのように組み立て、効果的に運営するかが問題になる。そうすると、医師の周辺にいる人たちはとくに個性的であることは必要でなくなり、彼らの個人的な意思の対立を見る必要はなくなっていく。記述者は自分の周辺にいるものを記述するのだが、とくに彼らが何かを代表しているわけではなく(まあ、神父や脱出できなくなった記者などをある類型に見ることは可能だろうが)、どう参加しているかの方が重要。実際、各人のキャラがたっているということはなく、みな似ていて同じような感情に支配されているのがわかるのだ。それは凡人であるわれわれ読者自身とその周辺の人々の観察から得られる感想と一緒。
ここには世界の苦悩を一身に背負って解決にあたるヒーローはいないし、こういう人になりたいというロールモデルもいない。問題を解決する簡単なやり方もない。そこにおいてすることは、自分の技能や能力をもってできることをすることで、ペスト防疫や医療や行政の補助に参加していこうということだ。ふだんの仕事や労働とは別の責任感を持って、危機に対処し、愚痴は言ってもやると決めたことを簡単には放棄しない。誰かが疲れて離脱することがあっても、それを咎めたり責任を追及することはしない。抜けた穴は別の人で埋めていき(失業者が仕事を求めているから補充は簡単だったようだ)、チームやプロジェクトが滞らないようにしていく。そういう活動(@アーレント)をすることで「自由」になっていく、自分を変えていくのだ。そういうのがフランスの共和主義。このような活動はペストのような感染症にも、全体主義にも対応できるのだ。
おれはそんなふうに読んだ。サマリーにあげたように、本書に近いのはフランクル「夜と霧」だった。
ペストで閉鎖された都市を全体として描くことは難しい。ここでも記述者の事情のために、フォーカスされる場所や階層は制限されている。医師や神父、記者、市の職員などとの付き合いになるので、例えば以下のような人たちが後景に退いて、いないもののようにされる。女性、子供、権力者、貧困層、アルジェリアにいるはずのアフリカ系やイスラム系のマイノリティ。なので、どうしても白い男たちだけの物語にみえてしまう。
(こういう人たちが隠されたのとあわせて、ニヒリストや冷笑、享楽の人たちが徒党を組んで、市や保健隊のじゃまをしたり、デマやヘイトスピーチを流したりすることが描かれなかった。彼らによる分断やマイノリティへの差別が起きなかったのは僥倖だった。酒を飲んで羽目を外すようなものより、誤った情報や信念に基づいて他者の分断や危害を行うものの方がより社会の脅威になる。)
それは1947年に発表された時代の制約だ。女性やエスニックマイノリティの人権を認めるようになるのはこのあとだから。このような弱点を克服する感染症の小説はコロナ禍の後に書かれるだろう。でも、現実ではコロナ禍は格差の拡大やマイノリティ差別の顕在化、権力の拡大などを引き起こしたので、カミュのように希望を書くことはできないだろう。
〈追記2024/2/13〉
都筑道夫がカミュ「ペスト」の小説作法で以下のように指摘していた。
すくない人物で、こういう生きるか、死ぬかの物語を書くのは、もともと、むずかしいのである。すくない人物に、それぞれ性格をあたえ、ときには半数を、殺していかなければならない。その順序がたいせつで、出来ばえを大きく左右する。はたち代で、アルベール·カミュの『ペスト』を読んだとき、私はそれに気がついた。
カミュは、アメリカン·ミステリイのテクニックに学んで、自分の小説作法を完成させた作家だ。それは、私の独断ではなく、名前はわすれたが、フランスの評論家もいっていることだから、『ペスト』の登場人物の殺しかたも、ハメットかチャンドラーに倣ったのかも知れない。とにかく、私は感銘をうけた。(都筑道夫「都筑道夫の読(ドク)ホリデー 下巻」フリースタイル、P80)
読んでから1年しかたっていないのに、「登場人物の殺しかた」はあまり記憶に残っていないなあ。メモをみると、最初死んだネズミが道路でみつかり、門番の老人が発症して最初の死亡者になる。第2章ではすでにパンデミックになって、毎日数百人が発症し、毎日死者がでる(が名前を持たないモブとして死ぬ)。4章で典型的な事例として死なないと思われた少年が死に、老人がもはやだめだろうと思われながら熱が引いて快癒する。すでに町が解放された終章では、冒頭で最初に死んだネズミを発見したタルーが発症して死亡する。ある市民が銃撃事件を起こして警官隊に射殺される。
このようなキャラの退場のさせかたは都筑道夫が指摘するように、「アメリカン·ミステリイのテクニックに学ん」だというのは妥当。