1999年にでた第3短編集。でたばかりのノベルスをすぐ買ったはずなのに、中身をすっかり覚えていなくて、今回の文庫は再読とはいえまったく初読に等しい。何も思いだせなかった。
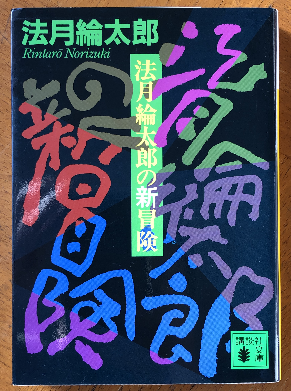
背信の交点 1996.10 ・・・ 信州からの帰りで「あずさ68号」に乗っていると、ある乗客・品野の様子がおかしい。松本をでたあと、容態が悪くなり、アトロピンを飲んで毒殺されたのだ。その男は浮気をしていて、その相手はあづさという。法月は浮気相手が「しなの23号」に乗っていて、男と浮気相手は松本駅でホームを挟んだ車中で相手の顔を見ながら毒を飲み心中したのではないかといいだす。実際そうだった。しかし穂波は、男の妻の態度に不信を感じる。作中「Xファイル」「古畑任三郎」などが出てくる。そのせいか本邦の有名作をパスティーシュしたものとしれる。
世界の神秘を解く男 1997.10 ・・・ テレビ局がポルターガイスト実験のバラエティをすることになり、法月綸太郎は懐疑主義者として立ち会うことになった(そこでタイトルの異名をもらう)。実験の最中、超心理学の教授の姿が消え、ラップ音が聞こえる。しばらくして実験の部屋の下のサロン室で、教授がシャンデリアで圧死しているのが発見された。部屋のドアはテープで密閉されていた。ミステリは懐疑主義と相性がよいので、安易にオカルトに乗らず、むしろデバンキングの立場になる。ここでも不可解状況は合理的に解き明かされ、二つの憑き物落としが行われる。遠隔殺人と超常現象のデバンキングは、 カーター・ディクスン「読者よ欺かれるなかれ」(ハヤカワポケットミステリ)、ヘイク・タルボット「魔の淵」(ハヤカワポケットミステリ)、泡坂妻夫「ヨギガンジーの妖術」、東野圭吾「虚像の道化師 ガリレオ7」(文芸春秋社)など。
身投げ女のブルース 1998.3 ・・・ 警視庁の敏腕刑事が密告者に会いに行く途中、ビルの上に投身自殺を使用としている女をみつける。懸命の説得で救ったのち、女は自宅で男を殺したと告白した。実際、勤め先の上司(悪い噂のある占い師)が告白通りに死んでいた。しかし、上司の死亡時刻は女がビルの上にいるとき。複数が見ている中、どうやって殺人を行ったのか。別の秘書に嫌疑がかかるが、アリバイがある。事件を担当した刑事は焦燥する。迷宮入りかと思うときに、法月警部が現れ、「さてみなさん(とはいわない)」と別の解釈を啓示する。「一人称には注意しろ」案件。
現場から生中継 1998.12 ・・・ 都内のマンションで女子大生が殺された。有力容疑者は彼女と付き合っていたチャラい学生。だが、彼はその日の突発的な生中継に映っていて、しかも直後に友人に携帯電話で通話していた。遠隔殺人の可能性? この年の携帯電話はアナログからデジタルの移行期で、インターネットに接続できず、写真も撮影できない。携帯電話と同時にPHSもそれなりに普及。警察の捜査に応じて通話記録を開示することもあった。2020年代に読むと、化石のようなテクノロジーを記録している。これを21世紀生まれの読者はリアルと感じるだろうか。当時の最先端の技術をトリックに使ったものに、クリスティの某作1926、ヴァン・ダインの某作1929、クイーン「ギリシャ棺の謎」1932があるが、本作はエヴァーグリーンになるだろうか。
リターン・ザ・ギフト 1999 ・・・ ある晩、売れっ子ホステスが自宅で暴漢に襲われた。反撃して逃げ出した男は捻挫してあっけなく逮捕。奇妙なことに男は見ず知らずのホステスを襲ったのは交換殺人を依頼されたからだという。事実、男の妻は以前に殺されていて、それは交換殺人を持ち掛けた男が犯人であるらしい。行方の知らない持ち掛けた男の自宅には数冊の交換殺人ミステリが残されていた。法月はそこに不審の目を向ける。
とてもよく考え抜かれ(ときにおれにはややこしすぎて付いていけなかったり。特に最後の短編)、意外な結末に導かれ、ミステリ読みとしては極上の時間を過ごしたのだった。ここまでの満足をもたらす作家はちょっとほかに思いつかない(いや数名いるけど)。
でも、どうも冷たい風が心のなかを吹くのを止められない。ひとつは、都筑道夫は偉大だったなあ、ということ。探偵は親の警官と事件を議論する。頭のよい二人の会話は手際よく事件の複雑さを説明するものだが、探偵の設定はクイーンでも、語りの趣向は「退職刑事」。上にでてくる事件も都筑道夫が書いていたものに似ている。解決の仕方もそう(とくに人間関係の複雑さがあきらかになると事件が判明するというところ)。で、この作家は数か月に一本ずつのペースで作品を作っていたが、都筑道夫は毎月数本を発表していたなあ。この作家のとても知的なところが多作にならないのだろう。この作家はずっとアマチュアっぽさを感じさせるのだが、その性向が量産に向かないのだろう。
もうひとつは、本格ミステリはパロディやパスティーシュとしてしか成立しない時期にはいったのだなあということ。これはこの作家に限らず21世紀の作品を読むと気にいつも感じることだ。このブログでもさまざまな作品のエントリーでなんども書いている。この短編集に収録されたものでも、全体が都筑道夫を思わせるだけでなく、個々の短編も先行作を意識している。ときには小道具として先行作を登場させる。そうしないと、日本の現代社会であるような舞台で、19世紀末のような犯罪を書くことにリアリティを持たせられない。
作者は探偵の口を借りて、探偵小説は「カール・バルトのいう男性的形式の知的エッセンス」であるという。その指摘は全くその通りだと思い、作者も探偵もそこまで思いを伸ばしながら、男性的形式を反復する。多くの短編は家庭や男女の関係のもつれを暴くことにあるのだが(その点は19世紀末の短編探偵小説の反復)、視点が男性でかつ権力者のものなので、関係者たちの苦悩がよそ事になってしまう。その冷酷さは法の番人としてはいいのかもしれないが、読者のモラルに訴えかけないので、なにごとも「自己責任」で済ます風潮に一致させてしまう。事件のその先にある何ごとかを訴える筆の力を持っていると思うのだが、社会や世間に踏み込まない作者とその作品がもどかしい。作家の知的エネルギーが浪費されているみたいだし、読者は消費しておしまいになるのが残念。
法月綸太郎「密閉教室」(講談社)→ https://amzn.to/3Tnpokb
法月綸太郎「雪密室」(講談社)→ https://amzn.to/4a0Gz1h
法月綸太郎「誰彼」(講談社)→ https://amzn.to/3v0pAxp
法月綸太郎「頼子のために」(講談社)→ https://amzn.to/3P9aI6F
法月綸太郎「一の悲劇」(祥伝社)→ https://amzn.to/3uWliXO
法月綸太郎「ふたたび赤い悪夢」(講談社)→ https://amzn.to/49tW16p
法月綸太郎「二の悲劇」(祥伝社)→ https://amzn.to/3wzOAMi
法月綸太郎「法月倫太郎の新冒険」(講談社文庫)→ https://amzn.to/3ImpTFN
法月綸太郎「生首に聞いてみろ」(角川文庫)→ https://amzn.to/3uWsO53
法月綸太郎「しらみつぶしの時計」(祥伝社)→ https://amzn.to/3P7GctM
法月綸太郎「キングを探せ」(講談社文庫)→ https://amzn.to/49XU2Hd
法月綸太郎「ノックスマシン」(角川文庫)→ https://amzn.to/3uWsR0J