若くして亡くなった科学史家の論文集。彼の関心は物理学史とこの国の科学社会学であったが、ここではそこから外れるテーマの論文が収録されている。内容は濃い。例によって論文のサマリー。
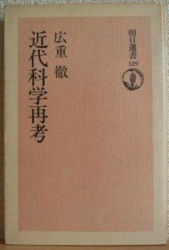
科学のおける近代と現代 ・・・ 科学の開始は16世紀ごろに求められる。とりあえず近代と現代という区分をしたとき、その転換点は17世紀の啓蒙主義の時代にある。それ以前は、(1)科学は自立したものではなくスコラ哲学などの影響下にあった、(2)神は人間に神と同じ認識方法を与えたが人はそれを正しく使っていない、この理性をしっかりと使うことで神と同じ認識を持つことができ、科学はそれを実証することを要求された、(3)空間は真空ではなく何かで充満していて、時間とは独立している、(4)部分を積み上げることによって全体を把握できる、などの考えを持っていた。それが啓蒙主義の時代で変わる。前提になったのはニュートンの自然科学の方法とロックの哲学。いずれも神を必要としない(いるかもしれないが、存在の起源になることで済ませることができ、現在には影響なしとされる)。このような科学がヨーロッパに広がり、社会で制度化される。主要なところは、貴族・ブルジョアの個人的な活動から産業・国家の運営する研究所の団体によって研究されるようになった、科学者が職業化され職能を得るための資格を獲得する制度ができた、述語・単位系などが確立し科学の方法に正解標準が作られた、科学は世界の意味や存在の目的を探ることを目的としなくなり科学の知を集積することが目的になった、など。(このような科学の制度が疲弊し、変革しなければならないと指摘・批判したのが1960年代の学生叛乱であったとされる。)
問い直される科学の意味 ・・・ 戦後の科学の特徴は技術化と制度化。技術化というのは、科学集団も生産性で評価されるようになり、生産性=論文の発表数ということになったから、結果がどうなるか予測しやすい枚挙的な仕事になること。制度化というのは、科学研究の費用を主に負担するのは国家になり、官僚が科学の予算と人事の権限を持つようになり、科学研究の方向も国家や産業の指導のもとに決められるようになったということ。これらの変化は科学者の自立性を失うものであるが、科学者集団は有効な批判や体制変革を行うことができなくなっている。むしろポストと予算の獲得を中心にした自己保持のために、国家や産業に進んで提携したり、科学者集団内部で利権獲得の闘争を行ったりしている。ここらの問題は1960年代の学生運動で摘出されている。吉岡斉(「科学の社会史」解説)でいうとおり、このまとめでは日本の戦後の科学をまとめる視座としては不十分。著者は戦争に加担する科学を批判しているが、それは重要な論点ではない。むしろ科学者と科学官僚の癒着というか科学者の権力への摺り寄りのほうがポイントなのではなかったかしら(1980年前後に学生であった身としては、構内で戦争加担の研究なんぞなかったからね。こんなやり方の科学批判は通じなかった)。
十九世紀の科学思想 ・・・ 18世紀の科学の成功は天文学と力学(あと数学)。啓蒙主義の運動もあって、科学と宗教は分離した。19世紀の科学を特徴つけるものは、要素論と機械論。物理学の原子論、化学の分子論が19世紀に確立し、多くの現象の説明ができるようになる。また熱力学、電磁気学などの多様な現象が引力と同じように説明できることわかり、エネルギー、エントロピーなどの基本概念が成立する。生物学、医学では生気論が後退し、細胞説から始まる機械論が優勢になる。細胞という生物の要素を提案することから細胞学、生理学も生まれ、医学と連動する。全体として19世紀は要素還元主義、数値化、実験と観察からの帰納という科学の基本的なありかたに楽観的であった時代といえる。数学とあわせて大統一理論の可能性も考慮された。科学の中心はイギリス、フランス、ドイツ。その他の国はほとんど発展に寄与していない。
二十世紀の科学思想 ・・・ 20世紀になると、前世紀末の公理主義や大統一理論などの楽観論に水が差される。相対性理論と量子学がそれ。ポイントは、人間の認識に相対的な差異があることと歴史的地域的な思い込みがあるということ。すなわち神の視点と認識は持てないということ。あと科学が巨大化・プロジェクト化していき、個人の創造的発意の領域が狭くなってきた。物理学の栄光とトラブルの一方、化学・生物学では要素論・還元主義が成功し、地球の生物がほぼ同じ仕組みで成り立っていることがわかってきた。生物または生命を要素還元主義で捕らえるというのが今日の情勢で、これは19世紀の生命ないし生物を全体として一度に認識しようとする考えに対立している(これに対する反対、批判は定期的に現れる)。技術と科学を区別しよう。科学は部分ごとの厳密さを要求するが、技術では全体が働くことが必要で、細部にブラックボックスがあることを許容し、機序が不明であっても結果が目的を達成すれば問題がないとされる。このような技術において重要なのがサイバネティクス(とくにフィードバック機構)と電子計算機。いずれも世界を確率論的に捉えようとする。この分野ではデカルト・ニュートン的な絶対空間・絶対時間は存在しない。
日本の大学の理学部 ・・・ 明治時代、日本にはひとつしか理学部はなかった。昭和になって京都大学(文部省の意図のもと)、九州大学、東北大学(後者は古河財閥の出資による)ができた。文科大学は官僚の要請を目的にしていたが、理科大学は産業ブルジョワジーの要請によって作られた。しかし、世界大恐慌によって産業からの要請が途絶える。代わりに国家の要請によって科学研究が進められた。大きな目的は軍事であり、小さい目的は新たな産業の開拓にある。昭和10年以降は理学部および各種研究所が軍事動員されていった。おそらくそのときの制度は現在でも残っているはず。
初読のときは大きな関心と興味、興奮を持った。教科書(著者の指摘によると、教科書は科学教育=科学の職能制度の成果物)には書かれていない歴史認識があったから。教科書では、三田誠広「天才科学者たちの奇跡」のような天才の人物史になってしまい、科学と社会、政治の関係には触れないから。ここにかかれた科学史は哲学や神学の側からも見直しておくとよいだろう(生松敬三/木田元「現代哲学の岐路」、小田垣雅也「キリスト教の歴史」が参考になる)。
ついでだが、ニセ科学・ニセ医療の推進者、信奉者が、誤った科学史、断片的な記述を使って正当性を説明することがある。いわく、ガリレオ・コペルニクス・ウェーゲナーも生存中は正しさを認められなかった、ニュートンは魔術研究を行っていた、科学は哲学・神学の一分野であるのに現代の科学はそれを忘却している、云々。それに惑わされないためにも、この本程度の知識は必要。(ガリレオ以下は十分な理論を持っていたが当時の水準では評価できなかった、ニュートンの個人的な思想と成果はわけるべき、哲学と神学は科学がその配下になることを望んではいない・むしろ積極的に科学の成果を取り入れようとしている、などなど)一応、近代科学になるまでの「科学」の歴史も村上陽一郎「科学史の逆遠近法」で補完しておきたい。上記のような言説に対抗するために必要。