「スティーブンソンが『カトリアナ』のなかで、こういった縛り首の死体をジャンピング・ジャックと呼んでいなかったか。ということは、女性ならジャンピング・ジェニィだろう(P17)」
1920-30年代に地方の閑なアッパークラスの人たちは、互いに招待しあって集まった。ときにゲームをしたり、仮装をしたり。ロアルド・ノックス「サイロの死体」(国書刊行会)1933年でも、こういうパーティがあったな。でもクリスティの小説ではそういうのはなかったので、ゲームは男の発案なのだろうか。付き合う女性もたいへんそう。あと、ラジオに期待されていたのは、パーティのBGMやダンスのための音楽の提供。3分で終わるSPをいちいち取り換えるのは面倒なので、貧弱な音でもダンスが聞こえることが大事だったのだろう。音楽の聴取スタイルがラジオの登場で劇的に変化したことがわかる(そのまえに、20世紀のゼロ年代のSP登場も音楽の聴取スタイルを劇的に変えた。マン「魔の山」を参照)。閑話休題。
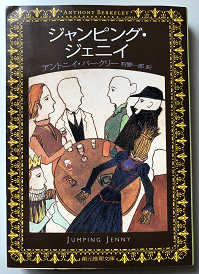
屋上の絞首台に吊された藁製の縛り首の女──小説家ストラットン主催の〈殺人者と犠牲者〉パーティの悪趣味な余興だ。ロジャー・シェリンガムは、有名な殺人者に仮装した招待客のなかの嫌われもの、主催者の義妹イーナに注目する。そして宴が終わる頃、絞首台には人形の代わりに、本物の死体が吊されていた。探偵小説黄金期の雄・バークリーが才を遺憾なく発揮した出色の傑作!
http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488123062
パーティ主催者の弟の妻が招待客の嫌われ者。他人にからんでばかり。自分のことしか語らないし、男に誘惑して、振られると自殺したいとほのめかす。そういうわがままに振り回されてばかりだったので、誰もがいい顔をしない。孤独にされているのがわかると、ますます意固地になるというフィードバックがかかる。パーティが深夜になって皆疲れてきたころ、出版社のサマリーのとおりのできごとが起こる。彼女の言動からして自殺だろう、とりあえず警察に連絡しておくかということになるが、ロジャー・シェリンガムは首つり自殺というのに踏み台がないことに気づく。名探偵を前にしての挑戦か!と闘志をもやされたロジャー、ひとりで探偵を開始する。
ロジャーが困ったことは、証言を突き合わせていくと、どうやらロジャーが犯人であると推定されること。そのことに気づいたのは週刊誌編集者ひとりで、彼は正義を実行するきがないらしいのでひとまず安心。でも早晩警察も同じ結論に達するのではないか。なのでロジャーは警察をだしぬき、編集者の目をごまかし、パーティの参加者の証言を誘導して自殺にもっていこうとするのである。
なんとも人を食った設定。シェリンガムも途中でいくつかの解決を提示するが、その都度推理は粉砕される。探偵が自分より頭の良いキャラクターに翻弄され、しかしめげずに推理するもののことごとく外される。デュパン、ホームズ以来、探偵は理性の輝きによって悪を摘出するのであるが、その約束はここにはない。
しかしお宮入りする前に、作者は短いエピソードを加える。フィリップ・マクドナルド「ゲスリン最後の事件」(創元推理文庫)みたいなエンディング。俺はにやにやしてやりすごしたが、人によっては怒るのじゃないか。そういう感情を起こさせないために、ロジャーをドジでウスノロにしたのかも、と邪推してみる。
1933年初出。