前回は柳瀬尚樹訳の新潮文庫で読んだが、今度は結城英雄訳の岩波文庫で読む。岩波文庫の訳者はジョイス研究者らしい(集英社文庫の「若い芸術家の肖像」「ユリシーズ」で解説を書いている)。より学究的な翻訳になると、読後の感想は変わるだろうか。

本文の前に解説を読む。すると、20世紀初頭のアイルランドは沈滞と堕落と憂鬱と怠惰だったようだ。たんにロマン主義的な気分が漂っているのではなく(なのでジョルジュ・ローデンバック「死都ブリュージュ」(岩波文庫)とは違う)、政治や経済そのものが停滞しているせいだと思えた。前の感想に書いたようにイギリスによるアイルランド支配は1世紀にもなり、パーネルらが指導したナショナリズム運動・独立運動も沈滞していた。イギリス支配のガラスの天井が至る所にある。アイルランドの男は経済停滞から逃げ出せない。なので酒と買春にふける。女性にはくわえて性差別もあり、結婚することですら抑圧からの解放ではなかった。とくに貧困層においてはそう。そうすると、「ダブリンの市民(ダブリナーズ)」は市民社会のスケッチであるというより、植民地文学とみなしたほうがよさそう。沈滞と堕落と憂鬱と怠惰が都市に蔓延するというのは、他国に占領され解放の可能性が少ないと思われている国でよくみられる光景。たとえばベトナム戦争中の南ベトナム。社会主義体制下の東欧。
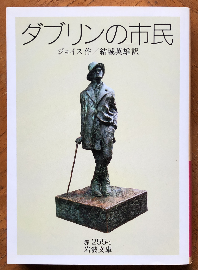
前回の初読で読み落としたところをメモしていこう。結城訳は2004年。
少年期
The Sisters (姉妹) ・・・ 亡くなったフリン牧師は若いころの不注意で聖杯を壊していた。気に病んでいたようだが、中が空っぽなので告解するときに「大きく目を見開き、くすくす笑いをしているようでした」と見られる。そのことは衆目に知ることになっていたのに、誰も指摘せず咎めず。信仰が形式化しているし、共同体の結束にも向かっていない、というところか。語り手の「ぼく」は寄宿制の神学校の優等生。信仰が揺らぐようなできごとになった。
An Encounter (ある出会い) ・・・ 文学愛好を教える大人は、興奮して草むらの中で自慰をする「変態」であるし、少年たちが無礼であればむち打ちしてもよいと主張するのでもあった。こういう矛盾をそのままにしているのが大人であると、「僕」は知る。憧れと幻滅を感じ、彼に言い返せない「ぼく」の弱さの自覚。
Araby (アラビー) ・・・ 「ボーイ・ミーツ・ガール」になり損ねた物語。「行ってみたいわ」のメッセージを読み取れず、叔父から小遣いをもらえず、汽車は遅れに遅れ、閉館まぎわのバザーは閑散とし物売りは飽きていて・・・。やることなすことうまくいかない空回りの一日。だから「いたたまれなさと怒り」を感じる。
青春期
Eveline (イーヴリン) ・・・ 初読では父(こいつはレイシストでDV常習者)への嫌悪と共依存を見たのだが、駆け落ち相手のフランクもいずれは父のようなDV野郎になるのではないかと思った。女性嫌悪の強い所では、だれかが突然変異のようにフェミニストになるわけはないからね。こういう時代だったから主張する女を描いたイプセン「人形の家」が大評判(あるいは大炎上)になったわけだ。
After the Race (レースのあとで) ・・・ フォーカスされているジミー・ドイルという青年が重要。昔は熱心な国民党員(独立運動支持)だったのがやめて、実業界に進出。外国資本企業との協業をもくろむ。レースの後の祝賀会、そのあとのカードゲームでこっぴどく負ける。まるで当時のアイルランドのよう。
Two Gallants (二人の伊達男) ・・・ この詐欺師たちが狙う娘は青い服を着ていて、これは少女が着る服の色。アイルランドの中流層から金を巻き上げる下劣な男たち(巻き上げたのは1ポンドだが、当時の女中の年収は4~7ポンドだそう)。
The Boarding House (下宿屋) ・・・ 冒頭、アルコール耽溺と育児ネグレクトで追い出された夫がのちにタイピストになった娘に会いに来ては無心する。この家族は教会の支援で別居になれたからよいものの、そうでなければ凄絶な家庭になっただろう。女性の自立促進は必要だったし、今でも必要。
青年期
A Little Cloud (小さな雲) ・・・ 小さな雲は成功したジャーナリスト・ギャラハーが立てる葉巻の煙。羨望と軽蔑が入り混じった遠くの光景だ。チャンドラーは帰宅すると不機嫌な妻と泣き叫ぶ子供にいらだち、大声を出す。ここから「下宿屋」の親父までの距離はそんなに遠くない。
Counterparts (対応) ・・・ 中年男の卑屈と逆切れは、夏目漱石の小説でもよく見かけた。モッブの特長だと思う。
Clay (土) ・・・ これも勘違いしていた。訳者解説によると、入寮している施設はプロテスタント系の売春婦更生施設なんだそう。マライアは若い娘ではなく、古顔のひとり。中年になっても独身。なので「a sup of porter」に黒ビール一杯とサポーター(睾丸隠し:ファウルカップ)を同時に聞き取って笑い転げることができる。これは社会的なスティグマを持たされた女性が自己欺瞞を演じている物語。最後の「彼女の誤り」は歌の第2節の求愛の部分を歌わず、シンデレラのような夢を歌う第1節を繰り返したからだそう。米本義孝(ちくま文庫)によると、マライアの容貌は魔女みたいで、万聖節の迷信とおりにさまざまなものが紛失するのだって。
(歌の第1節のような夢は「ユリシーズ」のブルームもみていたなあ。マライア同様に、ブルームの現実逃避であったのかも。)
A Painful Case (痛ましい事故) ・・・ 再読しても男の心理はよくわからない。解説の結城英雄は孤独癖やトリスタン伝説など持ち出しているが、自分からはモッブ@アーレントの典型のように思えた。
(モッブの解説)
社会生活
Ivy Day in the Committee Room (委員会室の蔦の日) ・・・ パーネル亡き後の民族解放運動は当初の理念を失い、現実的な利益誘導に舵を切ろうとしていた。選挙期間中に様々な思惑を持った党員たちが集まる。この現実的な利益のシンボルがスタウトというビール。これを、選挙に立候補している酒屋が事務所に届けることにし、その噂を聞いた党員たちが次々やってくる。分け前をくすねようとしているのが、ジャック爺さんと届けに来た少年(17歳)。後者は成功し、前者はありつけない。
A mother (母親) ・・・ 初読ではステージママの傍若無人さを笑ったのだが、読み返すと男ばかりの「委員会」が契約を反古にし契約金を払わない「犯罪行為」に腹が立った。この動きにアイルランド民族運動の揶揄を読み取ったりもできるらしい(解説)が、それよりも契約違反の加害者が被害者母娘を嘲笑するありかたに腹が立った。ジョイスの意図はこのような男性優位に対する批判なのじゃない?
Grace (恩寵) ・・・ 説得されたカーナン氏は「ユリシーズ」に再登場。この短編でカソリックに改宗したが、「ユリシーズ」の時代になっても酒飲みはやめられずジンを愛飲していたとの由(「ユリシーズ」の登場場面の記憶がないよ、困った)。教会批判は彼の説得の時に、教皇や枢機卿などが不信心の暮らしをしていると噂話をしたところか。
少年期、青春期、青年期、社会生活はジョイス自身の解説による区分け。
ジェイムズ・ジョイス「ダブリナーズ」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3wvJSPA
ジェイムズ・ジョイス「ダブリンの市民」(岩波文庫)→ https://amzn.to/42JTJ0v
ジェイムズ・ジョイス「ダブリンの人びと」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/42ODW09
2023/10/03 ジェイムズ・ジョイス「ダブリンの市民」(岩波文庫)-2 男性の女性支配欲と女性のアイルランド愛国主義。 1914年に続く
〈追記2023/10/31〉
朝日新聞天声人語に「Clay (土)」が登場していたので、その部分だけを抜粋。
アイルランドの文豪ジョイスは、短編『土』(結城英雄訳)で大衆が祝うハロウィーンを描いた。主人公はダブリンの女性更施設で働くマライア。かつて乳母をした男性の一家が彼女をパーティーに招待する。1906年の執筆で、当時の迷信や習慣がわかる▼たとえば、マライアが家で興じたのはハロウィーンには定番のゲームだった。目隠しをして皿にのった物を選び、指輪なら結婚、水は移民、上は死を意味するとされた。施設で出された干しぶどう入りケーキも、この日には欠かせない菓子だ▼ジョイスの物語には仮装もカボチャも出てこない。静かで少し不穏な空気が漂っている。死や魔女、火といった象徴はうかがえるが、百年余でこれほど変わるのかと驚く。
「仮装もカボチャも出てこない」とありますが、これらの意匠はアメリカのハロウィーンで追加されました。なので、ヨーロッパのハロウィーンにはもともとありません。
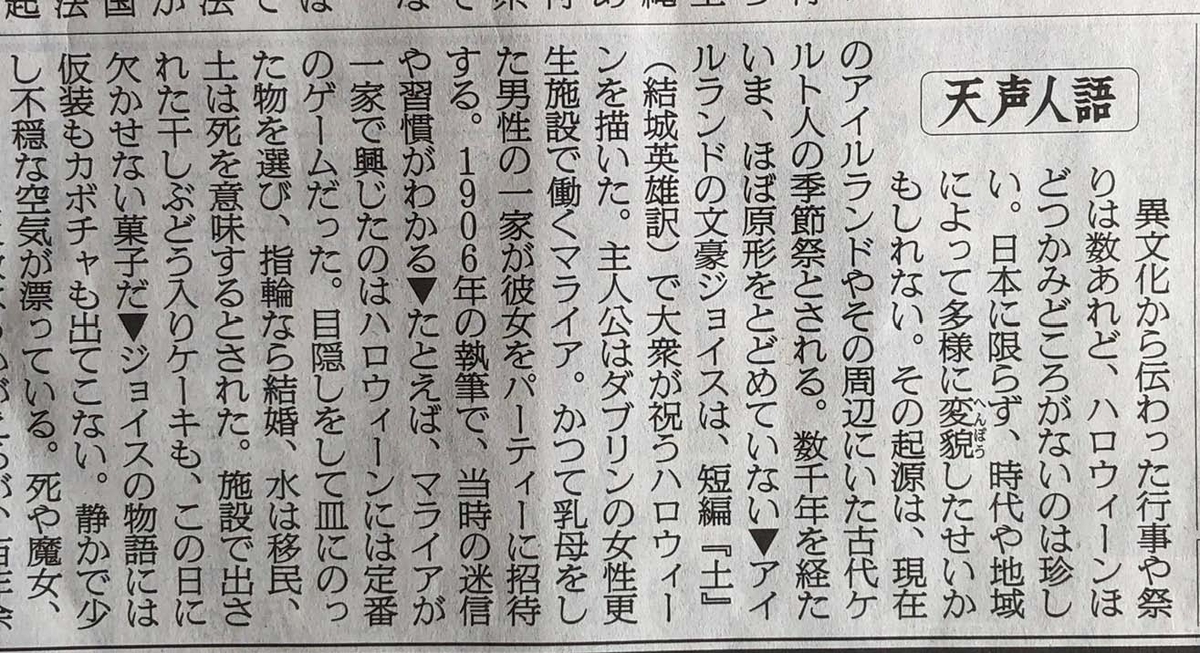
1回目の読みの感想