2014/11/19 ジュール・ヴァレース「パリ・コミューン」(中央公論社)-1
後半の150ページが1871年の「パリ・コミューン」のドキュメント。小説を見る前に、このできごとをまとめておこう。
遡ると1789年のフランス革命まで行ってしまうが、そこまで行くのはこらえると、プロシャが北ドイツを統一し、当時その一帯の覇権を持っていたオーストリアとの争いに勝利したところ(普墺戦争1866年)から始まる。ここでメッテルニヒ体制が崩れ、新たな強国プロシャが生まれたので、ナポレオン三世支配下のフランスが反発。プロシャの宰相ビスマルクはフランスとの戦争が不可欠と判断。空位となったスペイン国王の跡継ぎ問題にドイツとフランスがかかわり、ある事件をきっかけに1870年普仏戦争が開始される。この争いにおいて、フランスは劣勢。セダンの戦いでナポレオン三世が捕虜になるという失態を演じてしまう。そこにおいて穏健的共和派の議員により1870年9月4日に臨時国防政府が樹立。戦争を継続するも、プロシャ軍は優勢。パリ攻囲を132日間続け、1871年1月28日、国防政府は極秘にすすめていたプロイセンとの三週間の休戦協定に調印。2月8日国民議会選挙、2月12日穏健的共和派のティエールを首相とする臨時政府が誕生。1871年3月1日にパリに入場。
この小説によると、臨時政府樹立後に、パリにはコミューン(市民の集まりで、政治要求を認めさせようという組織くらいの意味かな。物資不足とインフレで生活困窮になった市民の組合的な機能ももったみたい)ができていた。臨時政府はパリをプロシャに解放する手続きを取っていたが、市民とコミューンは反発。3月18日に総決起。臨時政府はヴェルサイユに退避。
この結果、パリは無政府状態になり、市民は国民衛兵中央委員会を組織して、自立した。3月28日に市庁舎前でパリ・コミューンが宣言され、以後5月20日までパリを統治することとなる。以下の政治政策を実施。教育改革、行政の民主化、集会の自由、労働組合の設立、女性参政権、言論の自由、信教の自由、政教分離、常備軍の廃止、失業や破産などによる社会保障。この時代にここまで幅広い自由と民主を認める政策と政治組織はなかった。
ヴェルサイユの臨時政府は、プロシャとボス交して、軍隊を再組織。4月2日からパリの国民衛兵に攻撃開始。5月21日、ヴェルサイユ軍がパリ入場。以後1週間の市街戦。国民衛兵の兵力不足と政府軍の焼夷弾と榴弾でコミューン側は敗退する。このときに、コミューン軍とは無関係の市民がバリケードを築き、自警団を組織して、コミューン軍を援助した。この小説でも、商人、職人、女性、子供らがほぼ素手でバリケード防衛に参加している様子が描かれる。ヴェルサイユ軍は国民衛兵とコミューン関係者に殺戮を繰り返す。その数3万人とも。5月28日、パリが鎮圧される。コミューンの政治委員は逮捕、銃殺され、多くの人が亡命した。
コミューンには文学者、学者も参加。この小説にでてくる有名どころは、ユーゴー、クールベ(画家)、ジュール・ミシュレ(歴史家)、ヴィリエ・ド・リラダン、マキシム・ドゥカンなど。登場しないが、ランボーとヴェルレーヌもパリ・コミューンのパリにいた。ランボー「酔いどれ船」は1871年の出版という具合。あと、1848年2月革命の参加者が20年後の蜂起にも参加している(ブランキなど)のに驚きと感動をもつ。
以上は、wikiの「普仏戦争」「パリ・コミューン」のページを参考にしました。
wiki普仏戦争
wikiパリ・コミューン
前史にあたる1848年パリ革命は、カール・マルクス「ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日」(岩波文庫)、笠井潔「群衆の悪魔」(講談社文庫→創元推理文庫)のエントリーを参考に。
1871年のパリ・コミューンは、同時代のマルクスや30年後のレーニンらの希望であった。なるほど19世紀後半のさまざまな都市の革命はすべて失敗し、叩き潰されたわけだが、72日間とはいえど自主管理・自主運営の自治組織ができ、革新的な政策を打ち出していったのはこれひとつしかない。となると、そこにしかすがれる可能性はなかったのだといえるだろう。しかし、20世紀のさまざまな革命や政権の転覆をみてきたとなると、パリ・コミューンにはサバイバルの可能性はなかった。成功の条件を二つ欠いていたと思う。ひとつは、周辺地方の支持。蜂起したコミューンがヴェルサイユ軍に包囲されたとき、それに呼応する地方蜂起がなかったというので明らか。もうひとつは、政府や常備軍から蜂起したコミューンの支持者がでなかったこと。市民の側にたつ行政官、司法官、軍人、兵士などがいなかったことが、コミューンの敗北を決定付けたし、市民の虐殺・粛清になったのだった。革命や政権の転覆が都市蜂起を重要な契機にしているのは間違いないが、それは十分条件であっても必要条件ではないだろう、と歴史を見て思う。となると、後付ではあるが、パリ・コミューンの政治的な成功の可能性はなかった。
革命家の煽動やオルグには全く反応しないのに、蜂起の瞬間、バリケードの中でおっさん、おばさん、坊やに老人が生き生きと生死をかけた行動に赴き、革命家や運動家の思惑を超えてしまうことがある。そこにある「存在の革命」「生の燃焼」に意義があるとする立場もある。まあ、そうかもしれないし、祝祭的な熱狂において自分が自分の制限を超えた感じを持つことは体験したことはあるので共感するところもあるのだが、この年齢になるとねえ。現在の社会において、公共財を破壊し、生死をかけるのはコストが高くつきすぎないかい。と、保守的な自分を見つけてしまう。彼らの無償な行動がのちの国民国家を寛容にし、社会民主主義政策を取らせたことにつながったので、そこには感謝します。
(社会運動で、何を達成目標にするかは難しい。19-20世紀の社会改革運動では、政治要求の実現を掲げ、政府や国家に突き付ける。拒否されると徹底抗戦じさず、逮捕上等、死ぬことも覚悟してるぜと、暴力や武装も辞さない。そのような強硬な運動方法は、政府や国家の暴力にかなわず、ステークホルダーの支持も得られず、孤立して敗北した。しかし、事後に政府や国家は政治要求を受け入れて、人々の権利を拡大していった。となると、社会運動の達成目標は何かということになる。この二つの指摘が腑に落ちた。
要求を突きつけて達成を撤退条件にする社会運動は、撤退戦略につまづく。その達成自体は社会運動の役割ではない、と最初から規定しておいた方がいい。
— bulldozexxx (@bcxxx) 2014, 11月 12問題を社会の表舞台に出し、世論を喚起して先に社会を変え、政治をそれについて来させるべき。政治に直接変化を迫ってもそれは実現しない。その実現を撤退条件にすればつまづく。
— bulldozexxx (@bcxxx) 2014, 11月 12「世論喚起」「社会の変化」を測定するかは難しいと思うが、経験を積むうちに見極めができるようになるでしょう。少なくとも、国家や企業などが強硬な対抗策を示唆してきたら(不当逮捕者が続出するとか強制排除するとか機動隊出動を示唆するとか)、撤退するのはなんら問題ない。そこで対抗・対決するのは目標達成を遠ざけ、リソースを失い、ステークホルダーの支持を失う。でも世論喚起ができていないときは、非暴力でも強硬姿勢を見せる場合がある。うーん、レーニン「共産主義における左翼小児病」は駄本と思うが、読み直したほうがよいかなあ。)
ようやく、小説について語るときになったが、語ることはほとんどない。まず、著者は以上の経緯をほとんど記述していない。この小説からは普仏戦争の様子はわからないし、臨時政府の樹立も、コミューンのさまざまな政策の中身もまるでかかれない。あるのは、著者の個人的な体験と感情だけ。それも皮相で、シニカルで、センチメンタルで、プライドの高さだけがめだつような。記憶しておきたい記述はそれこそバリケードを作る親父やおかみさんの様子くらいだ。ジュール・ヴァレース「パリ・コミューン」(中央公論社)-1エントリーの挿絵を参考に。革命や蜂起の記述としては、リード「世界を揺るがした十日間」、オーウェル「カタルニア讃歌」に劣ること数等という出来栄え。好事家だけが読めばいいや。
この本には初版の挿絵が復刻されている。普仏戦争に敗北続きの政府に対する反対集会の様子。
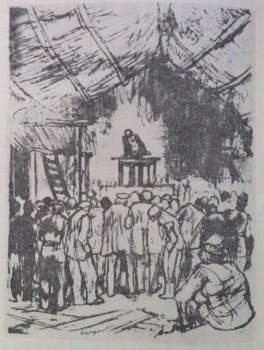
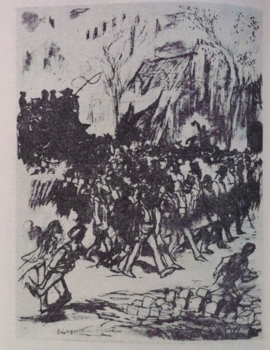
次は臨時政府樹立後の市民の反発と総決起だと思う。


次は3月のパリ・コミューン宣言のころと思う。


次は5月のヴェルサイユ軍との市街戦。右の挿絵の下の黒いのは血。

