オペラはこの国ではなかなか理解がむずかしいところがあって、聴衆にも演奏家にも評論でも、どこか手の届かないいらだたしさを感じていた。交響曲や弦楽四重奏曲やピアノ曲などを主に演奏・鑑賞する教養主義では扱いかねる「夾雑物」みたいなものがあるのだ。たとえば、小林秀雄「モオツァルト」や河上徹太郎「ドン・ジョバンニ」のようなこの国の最初期のオペラ評論など。吉田秀和のようなディレッタントもオペラの難しさを書いていた。
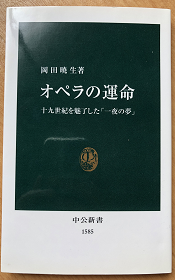
21世紀になってでた本書によって、そのいらだたしさやもどかしさの理由がわかる。著者によると、オペラは、
1.18世紀の絶対王政期以降に、
2.中央ヨーロッパのカソリック文化圏で、
3.宮廷文化を背景に作られ、
4.フランス革命後ブルジョア階級と結合し、
5.19世紀に黄金期を迎え、
6.第1次世界大戦終了と同時に歴史的使命を終えた、
7.音楽劇の一ジャンルであるとする。
この宮廷文化とブルジョア階級との結合があるので、オペレッタやミュージカルはオペラに含まれないという慣習が続いていた。また、第1次世界大戦の後にも「オペラ」は作られたが、それは上のように範囲を限定すると、オペラではないことになり、同時にバロック以前の17世紀までに作られた音楽劇(たとえばモンテヴェルディなど)もオペラからは外れることになる。オペラを作曲家や作品、オペラハウスとしてとらえると、19世紀ロマン派の天才、改革、実験などの価値観を持ち込んで考えることになる。そこに、王侯、貴族、ブルジョア、庶民などのステークホルダーを加えて、さらに社会的な動向(政治や経済、国家独立など)を加える。そうすると、オペラの成り立つ「場」が浮かび上がってくる。
そのような「場」を共有していない日本では、自国作曲家による祝典オペラや国民オペラなどに熱狂しない。あくまでも中央ヨーロッパの文化理解という基準でオペラを受容しようとしていたのだ。そのあたりがいらだたしさやもどかしさをオペラに感じていたのだろう。
したがって、オペラの歴史は同じ著者の岡田暁生「西洋音楽史」(中公新書)とは違った地域を対象にする。すなわち西洋音楽史では18-19世紀の西洋古典音楽の中心はドイツになるが、オペラというジャンルではイタリアが断然たる中心(もうひとつはフランス・パリ)になる。オペラが宮廷文化の中で作られた経緯があり、そこでの国際語がイタリア語であったという事情から。なので、通常のオペラ書では重視される作品や歌劇場はほとんど触れられない(ベートーヴェン「フィデリオ」やチャイコフスキー。ウィーンやプラハなど)。かわりになかなか体験することが難しいオペラ(フランスのグランドオペラや異国オペラ、東欧の国民オペラなど)に筆が割かれる。
とりわけ、フランス革命とウィーン会議以降の反動の影響の記述は目からうろこ。フランス革命後パリでは救出オペラが盛んに作られ、ベートーヴェンの「苦悩を経て歓喜に至れ」はこの影響を受けている。「救出オペラ」の説明はリンクを参照。
1814年のウィーン会議で王政復古の政治になってから政治運動への弾圧が始まるので、ベートーヴェンは高揚の音楽(革命を連想させる)をやめて孤独と省察の音楽に変貌した。これまでのベートーヴェン像を覆す衝撃の指摘。ベートーヴェンと世界史とのかかわりは以下を参照。
2023/03/22 片山杜秀「ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる」(文春新書) 2018年
また、グランドオペラの章では、オペラのパトロンが貴族からブルジョアに代わり、聴衆が生まれる過程の記述がさえている(アドルノが「音楽社会学序説」に書いた聴衆の類型はこの時代から生まれているのだ。あと1920年以降の大衆社会で誕生)。
(オペラのパトロンが貴族からブルジョアに代わり、聴衆が生まれる過程は、小宮正安「モーツァルトを『造った』男」(講談社現代新書)を参照。ここでディレッタントという存在が重要になる。その後、市民階級に音楽が普及すると高等遊民のディレッタントの影響力がなくなり、プロの学者や批評家が音楽の評価をつけるようになる。)
(グランドオペラ以降は浅井香織「音楽の<現代>が始まったとき」(中公新書) で補完しよう。19世紀後半にパリの聴衆はオペラに熱中するものだから、この不見識に憤慨して、ベートーヴェン協会を作りシンフォニーの啓蒙に励む演奏家や作曲家がいた。こういうのはたいていの「西洋音楽史」には出てこないので貴重。で、19世紀末には、こんどは彼らの努力によるベートーヴェン理解を揶揄するサティやドビュッシーなんかがでてくる。)
この後のワーグナーも面白い。絶対王政時代にオペラは王の権力の誇示に寄与するものであったが、ワーグナーは自身を「オペラの王」であると演出した。自身を誇示するだけでなく、作品の崇拝を求め芸術に格上げさせた。そこから、総合芸術は、1.哲学や宗教に匹敵する深遠さをもつ、2.作品を記念碑として保存する、3.絶えざる伝統批判と実験、であり、作品や演出を鑑賞するものとした(古典芸能化)。ああ、なるほど、ドイツの教養主義やロマン派の芸術観がここに由来しているのだなあ、とあたりを付けられる。
さらにオペラの歴史的使命は第1次大戦で終わったが、オペラの手法(ことにグランドオペラやワーグナーのやりかた)はコルンゴルドやスタイナーを通じてハリウッドの映画に継承された。ニーノ・ロータやジョン・ウィリアムズも、オペラを書きまくった19世紀前半の作曲家との類似があるとされる。こういうのも。
(私見だが、20世紀半ばまでのフランスの映画音楽は、6人組のひとりオーリックが作曲していたのもあって、ドビュッシーやラベルの影響がある。それをさかのぼるとムソルグスキーやボロディン、リムスキー=コルサコフらのロシア音楽の影響が認められる。参考例はコクトー「美女と野獣」。ハリウッド映画とは異なる系譜になるはず。まあ、1950年代のヌーベル・バーグでジャズにとってかわられたのだが。)
オペラは映画の台頭でとってかわられたという。なるほど、初期の無声映画の大作は歴史的なイベントを扱い、スペクタクル(視覚効果)をふんだんに使い、国民意識を高揚させる目的のものが多かった(デミル「国民の創生」「イントレランス」、ガンス「ナポレオン」、ラング「ニーベルンゲン」、エイゼンシュタイン「戦艦ポチョムキン」。各種の西部劇、史劇映画もそういう役割)。好況期の1920年代には観客を1000人以上収容できる映画館ができ、内外装はオペラハウス並みの豪華なもので、正装した観客がオーケストラ伴奏付きで映画をみた。トーキーになって、映画館の規模は縮小し内外装も質素になる。世界不況でブルジョア階級がいなくなり、大衆相手のビジネスになったためだろう。)
自分がオペラを聞き始めた時にもった違和感は著者の問題意識とかさなっている。なので、本書にはあまり驚かなかった。むしろ。これまでの視聴や読書で培ってきた体験や知識に重なるという確認の感じがつよい。あるいは断片的な知識にリンクが張りまくられて、ヨーロッパが少しは良く見えてきたという思い。
オペラにとってかわった無声映画大作