まず諸言で、「ザ・ヒヌマ・マーダー」「尾を食らう蛇(ウロボロス)I」「尾を食らう蛇(ウロボロス)II」に相当する読者の物理現実に存在する本を読んでおくといいとすすめられる。それぞれ、中井英夫「虚無への供物」1964年、竹本健治「ウロボロスの偽書」1991年、「ウロボロスの基礎論」1995年。初出の1998年はこれらは容易に入手しえたはずだが、いまとなっては後者が入手困難になってしまった。そのうえ「ウロボロスの偽書」には当時大人気のUWFのプロレス論が書かれているなど、その時代を知らないと理解が困難な話題も出てくる。それらを読んだうえでないと、「天啓の器」で議論されること、言及されることがわかりにくい。時の流れと、資本主義における商品の回転の速さに目がくらまされる。まあ、諸言で作中の固有名が読者の物理現実の固有名とリンクされることは、そのあとの「トリック」に関わる重要な伏線になっている。そこには注意すること。
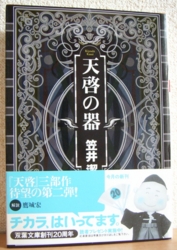
さて、本文になると、数字で分けられた42の章でできていることがわかる。
3で割ったときに余りが1になる数字の章は、天童直己の物語。これは前作「天啓の宴」の続きであるようなないような。とりあえず前作(「天啓の宴」)で失踪したことになっている作家と同じ名前の作家が「ウロボロスIII」を書くことになっているが書けないでいる。それは作家の宗像冬樹が「ウロボロスII」において大文字の作者が消失していないからで、それにこたえる構想を見いだせないでいるため。そのとき、宗像と編集者の三笠が「ザ・ヒヌマ・マーダー」の作者が殺されたのではないかという疑惑を聞く。そこで天童が素人調査を始めると、作者である仲居の周囲にヒヌマ家のソウジや初版の筆名である「トウアキオ」と同名のものがいたのを知る。現在の仲居さん殺人疑惑に、1956年のヒヌマ家の火事と首を切断された死体の事件が浮かび上がり、さらに敗戦前後に大連にいたヒヌメ家と謎のロシア人の関係も調べなければならない。そしてソウジが書いた≪ザ・ヒヌマ・マーダー」≫の存在を知る。
3で割ったときに余りが2になる数字の章は、仲居の視点で書かれた手記。戦後文学がはなばなしく活動しているころ(1950年ころから)、20歳で敗戦を迎えた仲居は自身の戦争体験と大量死を小説にできない。洞爺丸事件の新聞記事をみたときに、いっきに物語が細部まで出来上がったが、原稿用紙に文字を埋める作業ができない。そこに、敗戦直後の同人誌に載せた短編のファンという「トウアキオ」少年が来て、二人で構想を練る。「トウアキオ」が【ザ・ヒヌマ・マーダー】前半を書き上げて、仲居に見せる。
3で割ったときに余りが0になる数字の章は、「トウアキオ」の視点で書かれた手記。父母が相次いで若くして死に、残された家にほぼ引きこもっている少年(高校生をそう呼ぶのはどうかとも思うが、描写から浮かび上がるのは少年だ)。仲居作の短編を見つけ、すべての作品を読もうと決心する。そして、仲居に近づき自分の書いた<ザ・ヒヌマ・マーダー>を仲居に差し出す。(という話は、実在する探偵小説家にもあり、それが雑誌「幻影城」のデビューにいたったのであって、上記3作を既読の読者には周知であるので、これもめくらましのひとつ。)
とりあえずそれぞれの手記の「現在」でまとめてみた。そこには天童直己のところに書いたように、過去の因縁があり、情報は必ずしも時間継起順にだされるわけではないので、読者がプロットを構成しないといけない。また、複数の書き手の手記が交互に配置され、事件をそれぞれの視点で書いている。ここでも細部をチェックしておかないと、そこに書かれた微妙な証拠や複線を見逃すことになる。なので、メモを取りながら、ゆっくりと時間をかけて読み、時に振り返ることを推奨。それでもなお、混乱するのは、年月日がかくされていることと、同じ人物が複数の名前を持っていて使い分けていることと、日本語には同音異字がたくさんあること。そこらは「作者(どの?)」の意図的、恣意的なものなので、許容しつつ、注意深くなることが必要。
2016/03/15 笠井潔「天啓の器」(双葉社文庫)-2 に続く
笠井潔「バイバイ、エンジェル」(角川文庫)→ https://amzn.to/48TqZne https://amzn.to/3PkHxh0
笠井潔「熾天使の夏」(講談社文庫)→ https://amzn.to/43dNZwe
笠井潔「アポカリプス殺人事件」(角川文庫)→ https://amzn.to/48MbFZG https://amzn.to/48QRF8q
笠井潔「薔薇の女」(角川文庫)→ https://amzn.to/3PjAu8r
笠井潔「テロルの現象学」(ちくま学芸文庫)→ https://amzn.to/3wTqYCJ https://amzn.to/3wSESF6
笠井潔「ヴァンパイア戦争」(角川ノヴェルス)→ https://amzn.to/3TzXkvc
1 https://amzn.to/49O1RQ1
2 https://amzn.to/3TgB73L
3 https://amzn.to/3Vgx2iH
4 https://amzn.to/3IBpiAa
5 https://amzn.to/3VdTHfq
6 https://amzn.to/43evGqA
7 https://amzn.to/4c9Jmap
8 https://amzn.to/4a5De14
9 https://amzn.to/3vcall9
10 https://amzn.to/4a4WAEd
11 https://amzn.to/3TbwKah
九鬼鴻三郎の冒険
https://amzn.to/3Tihs3g
https://amzn.to/49MsDIT
https://amzn.to/4caCCJr
笠井潔「サイキック戦争」(講談社文庫)→ https://amzn.to/4celyCd https://amzn.to/3IzhKOp
笠井潔「エディプスの市」(ハヤカワ文庫)→ https://amzn.to/3vaFOUO
笠井潔「復讐の白き荒野」(講談社文庫)→ https://amzn.to/43cFiST
笠井潔「黄昏の館」(徳間文庫)→ https://amzn.to/3IxA3DR
笠井潔「哲学者の密室」(光文社)→ https://amzn.to/3IyyOnF
笠井潔「国家民営化論」(知恵の森文庫)→ https://amzn.to/3wSgkMu https://amzn.to/49GiUUh
笠井潔「三匹の猿」(講談社文庫)→ https://amzn.to/49MTGn7
笠井潔「梟の巨なる黄昏」(講談社文庫)→
笠井潔「群衆の悪魔」(講談社)→ https://amzn.to/3IxQb8j https://amzn.to/3Iy6jqg
笠井潔「天啓の宴」(双葉文庫)→ https://amzn.to/3TIMN0R
笠井潔「道 ジェルソミーナ」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3v8nvPZ
笠井潔「天啓の器」(双葉社文庫)→ https://amzn.to/49VWw9K
笠井潔「オイディプス症候群」(光文社)→ https://amzn.to/3T6YgWk https://amzn.to/3TdmuOH https://amzn.to/43mMUSU
笠井潔「魔」(文春文庫)→
笠井潔/野間易通「3.11後の叛乱 反原連・しばき隊・SEALDs」(集英社新書)→ https://amzn.to/4ccUXpe