2020/01/23 フョードル・ドストエフスキー「地下生活者の手記(地下室の手記)(河出書房)-1 1864年
2020/01/21 フョードル・ドストエフスキー「地下生活者の手記(地下室の手記)(河出書房)-2 1864年
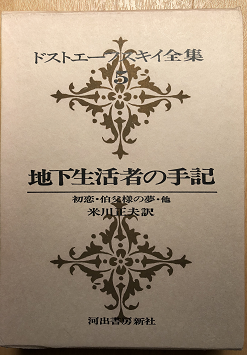

第2部「ぼた雪にちなんで(米川訳では「べた雪の連想から」:米川はべた雪という造語にしたことをどこかのエッセイにほこらしげに書いていた。追記:河出文芸読本「ドストエーフスキイ」1976年所収の「翻訳の苦心を通じて」)。
書き手の「ぼく」が24歳(この年齢は重要)の時のできごとを回想する。「美を意識するときに見苦しい行動をしでかす」男のドタバタ騒ぎ。いやストーカー的嫌がらせとセクハラの告白。これは気分の良い読み物ではない。知的には発達していて虚栄心と他者への軽蔑心を持っている男が、他人に無視されている・無関心にされている・バカにされていると思い込んで、交流をしないでいる。それが虚栄心と軽蔑心が高じて、他人を軽蔑し、軽はずみな行為をする。その結果は女性や下男などへのハラスメントになるという次第。かつての「貧しい人々」「白夜」もそんな感じであったが、まだ純情であった。ここでは差別とハラスメントが爆発する。いやな話だ。
「ぼく」のうっくつは止まることがない。下男の目つきが気にくわないと給料の支払いを故意に遅らせたり、ペテルブルクの娼館を経めぐっての女遊びをしたり。しかし、役所では卑屈に悶々としている。さて、レストランで学校時代の知り合いが出世頭の歓送会を開くのを聞く。招待されていないし、なにより彼らに嫌われているのに、無理やり参加する。案の定、歓送会では彼らに無視され、バカにされ、腹を立てたのに借金するという体たらく。女遊びに行くというので、別に向かったらはぐれて、一人で娼館にはいる。そこでついた嬢は20歳の見るからに疲れた女。軽蔑と哀れみがいっしょになって長時間の説教をする(こういう客は嫌がられるのに)。なぜか嬢のリーザは感激し、かつてもらった恋文を見せる(彼女の誇りの象徴であり、「ぼく」への信頼の証)。リーザに住所を教えたので訪問するかもしれないと待つがなかなか来ない(感情の浮き沈みの描写はみごと)。下男アポロンに八つ当たり。それをリーザにみられ、釈明するうちに自分の本心を告白していた。それに気づくと泣きながらリーザを罵倒する。ようやくしゃべり終えた後、リーザは「恐怖と屈辱が悲しげな驚愕に」になる。「ぼく」は「善良な人間になれない」といいながら、リーザに情欲を感じる。15分後リーザは別室で泣いている(「ぼく」がレイプしたことが暗示されている)。「さようなら」といった出て行ったあと、渡したはずの5ルーブリ紙幣が椅子に残されている(拒絶のシンボル)。追いかけたがリーザはペテルブルクの雑踏でみつからない。
「ぼく」はひどいやつだ、というしかない。自分をみじめな存在だ、何もしでかしたことのない男だと卑下しながら、実際にはマイノリティへのマウントとハラスメントを止めない。これは読者のロールモデルにはならない。
しかし不快な気持ちになりながら、ページを繰る手が止まらないのは、このどうしようもない男が読んでいる本人(男性読者の場合)にほかならないと、「ぼく」の心理と行動を克明に記述しているから。自分の感じる不快さは、まさに自分がこれまでにしでかした行為によって不快にされた人たちの感じていたものであると、心が寒くなるからだ。しかも小説の最後のように、謝罪する方法がないとすると(どこにいるのかわからないのだし)、自分への嫌悪となって帰ってくるのである。この小説で示した文章の力は、これまでのドスト氏の小説にはなかったもので、なるほどシェストフのいうように作家の転換点を示すものであろう。
フョードル・ドストエフスキー「貧しき人々」→ https://amzn.to/43yCoYT https://amzn.to/3Tv4iQI https://amzn.to/3IMUH2V
フョードル・ドストエフスキー「分身(二重人格)」→ https://amzn.to/3TzBDKa https://amzn.to/3ISA99i
フョードル・ドストエフスキー「前期短編集」→ https://amzn.to/4a3khfS
フョードル・ドストエフスキー「鰐 ドストエフスキー ユーモア小説集」 (講談社文芸文庫)→ https://amzn.to/43w8AMd
フョードル・ドストエフスキー「家主の妻(主婦、女主人)」→ https://amzn.to/4989lML
フョードル・ドストエフスキー「白夜」→ https://amzn.to/3TvpbeG https://amzn.to/3JbxtDT https://amzn.to/3IP71zF https://amzn.to/3xjzJ92 https://amzn.to/3x9yLfE
フョードル・ドストエフスキー「ネートチカ・ネズヴァーノヴァ」→ https://amzn.to/3TwqMRl
フョードル・ドストエフスキー「スチェパンチコヴォ村とその住人」→ https://amzn.to/43tM2vL https://amzn.to/3PDci14
フョードル・ドストエフスキー「死の家の記録」→ https://amzn.to/3PC80Hf https://amzn.to/3vxtiib
フョードル・ドストエフスキー「虐げられし人々」→ https://amzn.to/43vXLtC https://amzn.to/3TPaMew https://amzn.to/3Vuohla
フョードル・ドストエフスキー「伯父様の夢」→ https://amzn.to/49hPfQs
フョードル・ドストエフスキー「地下室の手記」→ https://amzn.to/43wWfYg https://amzn.to/3vpVBiF https://amzn.to/3Vv3aiA https://amzn.to/3vmK9V5
フョードル・ドストエフスキー「論文・記録 上」→ https://amzn.to/3VxSShM
フョードル・ドストエフスキー「論文・記録 下」→ https://amzn.to/3VwvP79
フョードル・ドストエフスキー「賭博者」→ https://amzn.to/43Nl96h https://amzn.to/3x2hJju
フョードル・ドストエフスキー「永遠の夫」→ https://amzn.to/3IPQtY7 https://amzn.to/43u4h4f
フョードル・ドストエフスキー「後期短編集」→ https://amzn.to/49bVN2X
フョードル・ドストエフスキー「作家の日記」→ https://amzn.to/3vpDN7d https://amzn.to/3TSb1Wt https://amzn.to/4a5ncVz
レフ・シェストフ「悲劇の哲学」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3TR758q https://amzn.to/3x2hMvG
フョードル・ドストエフスキー「ドストエーフスキイ研究」(河出書房)→ https://amzn.to/4avYJIN
河出文芸読本「ドストエーフスキイ」(河出書房)→ https://amzn.to/4a4mVSx
江川卓「謎解き「罪と罰」」(新潮社)→ https://amzn.to/493Gnxy
江川卓「謎解き「カラマーゾフの兄弟」」(新潮社)→ https://amzn.to/3VygEKG
亀山郁夫「『カラマーゾフの兄弟』続編を空想する」(光文社新書)→ https://amzn.to/493GqcI
2020/01/17 フョードル・ドストエフスキー「地下生活者の手記(地下室の手記)(河出書房)-4 1864年