何度も「野火」を読んでいるけど、どうにももどかしいというか、はぐらかされているというか、こちらがテーマをつかみきれていないというか、上手く読めない。とりわけ後半の「人肉食い」を巡る禁忌と乗り越えの議論がわからない。
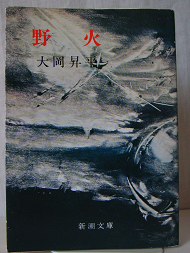
補充兵として召集された「私」は、結核を病んで病院にいかされるが、食料がなくなったところで追い出され、帰隊も拒まれる。どこにも所属しない単独の落伍兵として戦場をさまよい、米軍の襲撃で本隊とはぐれる。死ぬことを意識(なのか覚悟なのか)している「私」は自らを死に追いやる可能性をもつ砲声に哄笑をあげたりもする。「孤独と絶望を見極める」「死ぬまでの時間を思うままに過ごす」というのが心境。山間の捨てられた村で芋畑を見つけ、近くの海で塩をつくり、2週間ほどの飽食を過ごす。十字架を見つけて、そこにたどり着くと、見つけたのは味方の日本兵が殺されている姿。そして磔刑にあっているキリストの彫像。たぶんそれに自分の痩せこけた姿も重ねてみているはず。たまたま比島の男女がカヌーに乗ってやってくる。身を潜めていると、その十字架のある家で女と遭遇。腰溜めにかまえた三八銃で発砲。女を殺してしまう。村と畑を捨てて逃げる途中で、日本兵の集団と遭遇。米軍の監視が緩む夜に街道をこえるときに、待ち伏せに会って再び山野をさまよう。そして病院の落伍兵仲間である安田(煙草の販売)と永松(安田の子分)にであい、永松の持つ「猿の肉」を食う。「猿の肉」がなにかを薄々と知ってはいるものの食うが、永松の「猿の肉」加工現場を見た後、激しい嘔吐。そして安田が殺され、永松ともみあっているうちに「私」は殺してしまったようだ。としか語れないのは、その直前で記憶が途切れているため。俘虜生活のあと帰国した「私」は生活への関心を失い、精神病院に入棟し、この手記を書いている。
埴谷雄高は「野火」について、
「この司令部からも病院からも追いだされてレイテの原野を彷徨する暗号兵の人物と、人肉食と、食前儀礼をする狂人の三人がアマルガメイトされ、そしてそこに、大岡自身の感覚と思索が緊密に注ぎこまれて、あの『野火』ができたわけだ」大岡昇平/埴谷雄高「二つの同時代史」
といっている。さすがに文学の達人は凡人よりもはるかに遠くまで見通し、細かいところまで掘り下げられるものだ。いずれも「俘虜記」に点描される人物とエピソードであって、なるほどこれらの見聞に比島での本人の体験が加わって、「野火」のような作品になったのだというのが腑に落ちた。
そのような支えがあっても、「野火」はよくわからない。というのも、
・十字架のある家で、「私」は比島の女を射殺する。「人間的感情を持たない獣の声」を聴き「怒りを感じ」て銃を撃つ。「すべては銃にかかってい」て「銃は国家が私に持つことを強いた」のであり、「孤独な敗兵として国家にとって無意味な存在となったあとも持ち続けたということに、あの無辜の人が死んだ原因がある」と総括する。うーん。「俘虜記」ではあれほどアメリカの若い白人兵に遭遇したとき銃を発射しなかったことに固執していたのだが。発射するかしないかの違いを説明するのは不可能であるし、「国家が私に強いた」というのは十分な理由になると思うのだが、白人男性は見逃し、比島の女(しかも非武装)を殺したというのにひっかかる。事件のずっと前で落伍兵になったときに、「戦う意思はない」とまでいっいるのに。
・日本兵の人肉食いは小説の発表当時はセンセーショナルな話題であったが、1970-80年代に南方戦線の帰還兵からぼつぼつと証言がでてきた。すでに「俘虜記」でも話題になっている(そこでは作り話と一蹴されていたがね)。なので、その種の事件はあったのだろう。とはいえ、自分のなかでは人肉食い全般を犯罪として告発する気になれないのだ。たぶん子供のころに聞いた「アンデスの聖餐」事件に基づく。そのうえ開高健「最後の晩餐」によると、この事件で生還した人々は祖国(中南米のカソリック国)に帰還したとき訴追されるどころか、英雄として迎えられたという。どのような状況でどのような経緯でそれが行われたかで個別に判断することではないかな。というか文明はその種の飢餓が起こらないように、起きても支援がすぐに差し伸べられるように政策をたてるようになっている。その種の事件を起こさないことが重要。あと、自分がやるかという判断と、他人がやることを認めるかという判断は別物であって、自分の判断を他人に押し付けるのも問題あるだろう。という具合に歯切れ悪くしか考えられない。(「私」が人肉食いを忌避したというのに道義とかタブーとかの内面を持ち出せないように思えるのもある。「左手が止める」「嘔吐した」のような身体の反応が先に会って、それに精神が追い付こうとしているみたいだ。文学でも日常でも、意識が行動を決定すると考えるし、多くの事柄をそのように説明するのだが、この小説の「私」は意識することなく行動が先にでてしまう。そのために文学のやりかたで説明することができない。)
・日本兵の人肉食いを問題にする前に、ロジスティックを築かないで戦線を拡張するばかりの本部とか参謀とか陸軍省・海軍省の無能無策、バカさを大いに批判する必要がある。イギリスはインパール作戦で山岳から帰ってきた兵士に、アメリカは太平洋のどの孤島の兵士にもステーキとビールを配給し、豊富な兵器を供給し、医療設備を設けた。戦争する国民のことをいかにこの国の政府や軍隊(および便乗して騒ぐだけの壮士きどり)が考えていないか。この国の戦争責任者が戦争被害者に無責任であったか。
2012/09/15 森本忠夫「マクロ経営学から見た太平洋戦争」(PHP新書)
2015/01/29 ブライアン・オールディス「兵士は立てり」(サンリオSF文庫)
・この小説では風景が重要な役割を持っている。部隊からはぐれ比島の山中をさまよう「私」のまえに野火がのろしのように上がるのを何度も見る。それは現地の農業で普通のことであるが、このタイミングでは狼煙であって警告や警戒のしるしであるかもしれない。そのような読み取りを敏感に行ううちに、風景は変わってくる。十字架を見るころには、なにごとかの超越性をもって「私」にメッセージを送っているように思える。しかし、「私」はそれをよく解読しえないのであって、次第に「見られている」感覚を持つようになる。そして、臀肉をそぎ落とされた友軍の死体をみるうちに風景が語りかける。狂人は「ここを食べてもいい」、花は「あたし、たべてもいいよ」。しかし、その肉を口にはこぼうとするとき、肉を持った右手を左手が掴みはなさない。「私」の意識は食べることを許容している(らしい)のだが、自然なのか神は「食べるな」と行為で押しとどめる。ここに来ると風景は、「私」と対決対立するものではなくなって(「もの」といってよいのだろうか)、風景と「私」の差異やずれがなくなってくる。しかし、風景や自然の命令することは理解できないまま。という具合の、風景と「私」の関係の仕方が、極限状況になったことのない自分にはよくわからない。
・そのうえ、この硬質な文章。戦後文学の書き手は、体験と見聞と感情と思想を一気にまとめて書こうとして、何とも晦渋で畝くねった文章を書いたものだ。野間宏「暗い絵」、椎名麟三「永遠なる序章」、石川淳「焼跡のイエス」、坂口安吾「不連続殺人事件」などなど。これらの戦後文学の文体にみられる技巧はここにはほとんどない。名詞と動詞のみ。形容詞や副詞はまずない。ひとつの文章も短い。何しろ感情が書かれない。そこにあるのは、行動とその反省のみ。まるで科学の論文のように味気ない文章。にもかかわらず、上記のどれよりも「リアル」を感じさせない異様な感覚が生まれてくる。
あとで見たら初出は1952年。いまあるようにまとめるためには、7年の時間がかかったということか。
自分がふだん考えているテーマにぴったりとあう作品なのだが、自分がフルスイングしても何の手ごたえも持てずに空振りしている感じ。全力でバットを振ったら、星飛雄馬の大リーグボール2号「消える魔球」のようにバットをかいくぐり、「野火」はどこかにふっとずれていってしまう。それでいて「ストライク」の絶好球にみえるのだから、どうにも手に負えない。ともあれ戦後の最重要作のひとつであることは再確認した。
<参考エントリー>
2018/11/22 柄谷行人「倫理21」(平凡社)-1 2000年
2015/04/07 大岡昇平「俘虜記」(新潮文庫)-1
2015/04/08 大岡昇平「俘虜記」(新潮文庫)-2
2015/04/09 大岡昇平「俘虜記」(新潮文庫)-3
大江健三郎が「道化と再生への想像力@言葉によって」で「野火」の主人公をトリックスターとして読んでいる。右手が人肉を取ろうとするのを左手がとめるとか、銃弾ではがれた自分の肉は躊躇なく食うとか、野道を歩いていると「この道は私が生まれて初めて通る道であるにも拘わらず、二度とこの道を歩くことはないだろう」という奇態な想念にとらわれるとか。このような行為や想念(自己の過度な客観視)などがナヴァホインディアン(ママ)のトリックスターにそっくりであるという指摘。
もう少し大江健三郎の言葉を引くと
「敗戦まぢかな混乱のうちになりながら、病人ですらもありながら、自分の部隊からも病院からも拒まれ」「追放されると(略)自由をはっきり受け入れて、したたかな人間的資質を示す。」「レイテ島の日本人に許された軍隊という唯一の社会から追放され反社会化した彼の自然の中の放浪。」
「徹底的に反社会化することによって、宇宙的なものへの交感の道を開いている。」
「自分の肉を食うことによって、人肉嗜食の禁忌を侵すものらとともに、彼自身の内の人肉嗜食を拒み続けようとしてきた倫理との相克までを、すべて批評的に逆転してしまう。」
「軍隊的な束縛の内外を自由に出入りし、敵意ある自然のただなかを放浪して(略)、突然にそして必然的に神の怒りを代行する者となる。」
「天にのぼるかわりに精神病院にあって、しかもトリックスターが地球創造者にあたえられた役割を思い出し(略)」「すなわち神の代行者としてのかれ自身の役割を認識し、なおそれがすでにフィリピンの山野で自分によって実践された役割を追認している。」
(「言葉によって」新潮社P270-272)
なるほど。そういうふうに読むのもありか。そして、このようなトリックスター(社会の束縛から自由になって宇宙的なものと交感してその代弁者となる)が、同じ時期に発表された「ピンチランナー調書」の「森」であるわけだ。彼も「障害を持つ」「子供」として、トリックスターの資格をもっている。「野火」の「私」も、「森」もイエスのような受難を経験しているのだし。森は燃えて天に昇ってしまった。