松田道雄「世界の歴史22 ロシアの革命」(河出文庫)、クリストファー・ヒル「レーニンとロシア革命」(岩波新書)、エドワード・H・カー「ロシア革命」(岩波現代選書)、レフ・トロツキー「ロシア革命史」(岩波文庫)あたりが自分の読んだロシア革命の本。これらに共通するのは、記述のほとんどを1905年(血の日曜日)から1924年(レーニン死去)にあてているということ。これはそれ以前、とくに19世紀のロシア史を革命運動の側からみようという本。
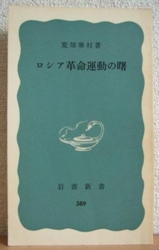
ざっと19世紀のロシア史を振り返ると、開明的なアレキサンドル1世の治世で始まるが、国内統治は圧政で押し通す。まあフランス革命の飛び火を警戒したわけだ。そのため下級仕官や貴族はうだつが上がらないというわけで、上級貴族の排除と国内の民主化をスローガンに「デカブリストの乱」というクーデターを起こす(ネクラーソフ「デカブリストの妻」(岩波文庫)参照)。しかし国民(ブルジョアとかインテリゲンツァとか)の支持を得られず失敗。そのあとのアレクサンドル2世、3世も似たような方針で臨む。海外資本を導入して工業化を図るが、王政は変えず、国内の民主化は徹底して弾圧。この時期に農奴解放を行うが、農奴はもらった土地の代金を49年年賦で支払うことになり、その他の重税(しかも貨幣があまり流通していないのに金納にする)もあって、ますます窮乏。工業化は多少は進展するものの、都市が農村の過剰人員を受け入れることはできず、スラム化する。また官吏といえど薄給で生活が困難(ここら辺はゴーゴリやドストエフスキーの小説にでている)。そんな具合に、社会の不満は鬱屈していた。そこで立ち上がろうとしたのが、おりから西洋ではやっていた社会主義運動(プルードンとかサン=シモンらの初期のもので、マルクスはまだ入っていない)に影響された貴族の息子や娘に学生。彼らは1870年代に「人民の中へ」というヴ・ナロード運動を行った。労働者、農民と同じ労働と生活をし、彼らに知識教育や医療などを行ったのだった。当然、これらの運動も当局の知るところとなり、弾圧を受ける。それがあんまりひどいものだから、このような民衆の啓蒙ではらちがあかん、俺たちが過激な行動をとることにより、政府の重鎮を排除し、人民の蜂起を起こそう、とテロリズムの考えを持つものが生まれ、「人民の意志」党が発足。アレキサンドル2世の暗殺に成功するものの、19世紀中は人民が蜂起することはなかった。結局、「人民の意志」党も解散した。20世紀に近くなると、マルクス主義文献が紹介されるようになり(ロシアの革命家は亡命して、パリ、ロンドン、ジュネーブなどに住居を構え、同じ境遇の人びとと意見交換したり、ロシアに残る組織を指導したりしていた。彼らからマルクス主義は浸透していったのだろう)。
作者の筆は、ナロードニキに同情的。流刑になった運動家(多くは20代、ときには10代も)がどのようなルートでシベリアに送られたか(最終地のひとつはバイカル湖近辺であって、そこは高杉一郎が送られたところに近い(「極光のかげに」(岩波文庫)。当時のこととて、満足な防寒服、暖房装置もなく、食料に乏しいとあって、病気で死亡したり、刑期のあけることがないことに絶望して狂気に陥る人もいた。彼らに対する同情とそこまでする権力への怒りは、全巻に通底している。寒村の生年は1887年。このころがヴ・ナロード運動の最盛期。彼が社会主義運動に参加する1903年になっても、当時流刑にあった人たちの消息が聞かれるのであった。となると寒村にとっては、まさに同時代のことであり、ナロードニキは彼の同世代人なのである(本書の初出は1960年)。
その一方で、ボルシェヴィキには批判的。寒村によると、ロシアの革命運動には二つの傾向があって、ひとつは官僚主義・上位下達の組織運営。もうひとつは陰謀主義で目的達成のためには手段は何を選んでもかまわないということ(逆に言うと、そのような組織はスパイの暗躍を許すことになり、ますます中央集権の独裁制が強くなる。戦前の日本共産党がその轍を踏んだなあ。)。これらの悪いところを、ボリシェヴィキは継承していて、レーニンといえどもその問題を克服できなかった。というか強化する方向の運動を行ってしまった。トロツキー、スターリンも同罪、というのが著者の考え。ここは同意。寒村の心情を忖度すると、感情や情熱で人民の海に漕ぎ出したナロードニキの成果を陰謀集団のボリシェヴィキが簒奪したという憤りもあったのかしら。
ソヴェト連邦も解体してから批判するという立場でみると、革命ははた迷惑なものでないに越したことはなく(@林達夫)、人生を賭けるまでの決意を持たなくとも政治の方向や仕組みを変えられるほうがはるかによい、という平凡な感想を持った。もちろん現在のこの国の制度や仕組みがよいとはまったく思わない。また制度や仕組みを変える権利と義務を持っていながら、その行使を躊躇したり、放棄したりする「人民」が是であるともまったく思わない。
荒畑寒村「ロシア革命運動の曙」(岩波新書)→ https://amzn.to/4cep6DJ
荒畑寒村「寒村自伝 上」(岩波文庫)→ https://amzn.to/4c9IxOJ https://amzn.to/4eeNdnH
荒畑寒村「寒村自伝 下」(岩波文庫)→ https://amzn.to/3RlAYvO
立花隆「日本共産党の研究 1」(講談社文庫) - odd_hatchの読書ノート
ネクラーソフ「デカプリストの妻」(岩波文庫) 1820年代シベリア送りになった貴族の将校についていった妻たちをたたえる劇詩。 - odd_hatchの読書ノート