このブログからわかるように、自分は小説と西洋古典音楽には一家言を持つようなマニアであるのだが、それ以外の芸術にはうとい。本書を読むまで、ロダンが1840年生まれ1917年没ということすら知らなかった。作品も有名な一つしか知らない。なので、ロダンについてはここではなにも語らない。著者のリルケもほとんど知らない。過去に「若い詩人への手紙」を読んだはずが、全く記憶から失せている。
そこで、ドイツの詩人ライナー・マリア・リルケ(1875年生1926年没)がどうロダンを見たかだけに関心を向ける。20代後半のリルケはロダンの作品にほれ込み、妻子を故郷に残してロダンを訪問し、数年間ロダンの秘書のような仕事をして、数年後に喧嘩別れした(のちに和解したが再会できず、ロダンが先に没した)。親子ほども年の離れた二人なので、独立心の強そうなリルケをロダンが支配しようとしてうまくいかなったらしい(これらの経緯は解説で詳述される)。
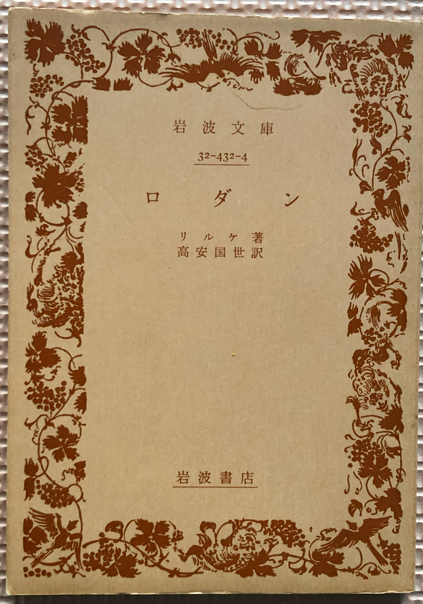
本書の書き方がユニークなのは、ロダンの生涯も、ロダンのエピソードも、ロダンのインタビューもないこと。およそロダンその人を知るための手がかりがほぼないのだ。本書にあるのは作品の解説とリルケの考えだけ。(同じように対象に関わる事実を一切書かない評論として、ジャンケレヴィチの「ドビュッシー」を思い出す。記憶から失せているが、ニーチェのワーグナー論もそうだったような。「反時代的考察」「ワーグナーの場合」)
さて、リルケによると造形(とくに彫刻)は絵画やことばよりも芸術の抽象性が高いのだという。そのなかでロダンが行ったのは過去の彫刻の超克。すなわち過去の彫刻はモデルがあり、ポーズを取っていて、比喩の機能があるからだ。人体を彫刻するとき、神話や歴史のどの人物で、どの場面かがわかるような演劇的身振りをしていて、観客に何を訴えているかがわかるように作られている。鑑賞者は彫刻を通して物語を読む能力を持っていなければならない。これは古典派の規範そのものだね。それに対しロダンの彫刻は無名の生きた人間を題材にし、運動の一瞬を切り取り、偉大さを示すものであった。すなわち具体的な名前を持つ、誰もが知っている人物ではなく、名無しもしくは抽象的な人間であるが、誰もに当てはまるような普遍性をもっていて、内的な欲求から生まれる運動を行っている。そこには誰もがわかる物語はないので、鑑賞者は彫刻そのものを感じる(共感する、感応する)のである。以上はロマン主義の芸術観だね。本人がどう思っているかはわからないが、リルケはロマン主義でロダンを擁護したのだった。(なので、読書中にロマン・ロランの「ベートーヴェンの生涯」やハンスリック「音楽美論」に似ているなあと何度も思った。)
19世紀末から20世紀初頭にかけての論(第1部の評論は1903年、第2部の講演は1905年)なので、当時の流行も反映しているのがわかる。ロダンの作品をほめる言葉に、生・若々しい・力強い・内的必然・有機体・神秘・統一・運動などを使う。そこからニーチェやベルクソンなどの「生の哲学」を聞き取れる。彫刻は永続する一段高いもので、手仕事(handwerk)で作られるところに価値があるとする。のちのハイデガーのテクネ―論の先駆けのようだが、やはりドイツの学生運動(ワンダーフォーゲルなど)にあった反資本主義や自然讃歌などを読み取りたい。
またリルケがロダンという人間を称賛するのは、孤独で無口な性格・生活、勤勉、富や名声を拒否する脱俗性、集団制作ではなく個人の創作など。以上は、ドイツのプロテスタンティズムに則った職業倫理に合致する。そのような近代宗教人が黙々と内省に基づいて人間の真実に触れる精神的な作品を金銭ずくではない動機で創作する。それが天才。このような「天才」概念の最初の対象になったのはベートーヴェンあたりと思うが(宮城音弥「天才」岩波新書を読んだのは40年以上前なので覚えていない)、これらの規範や節制を芸術家に求めるようになった。それは創作活動をする人を呪縛した。資本主義に巻き込まれていないことが創作者の要件になってしまった。禁欲や貧困であることが称賛され、金儲けや名声を求めるものを一段低く見る。ことにこの国では、創作活動をするものをけなし止めさせる呪文として広く流通した。プロテスタントのような禁欲節制を他人に求めるのは他者に介入しすぎ。(ロダンにしても発注する受け取り手がいたから、長年創作して生計を立てることができたのだ。超俗的で貧困にあえぐ生活をしていたわけではない。リルケがそこを低く見ているのはよろしくない。)
以上の芸術観は同時期にでたトーマス・マンの「トニオ・クレーゲル」1903年に近しい。このドイツ人の二人が似ているというより、当時の芸術思想や美学がこういう水準にあったのだと考えたい。
低評価だったロダンの作品をリルケ他のディレッタントやスノッブが称賛したことでロダンは20世紀初頭には巨匠・名人になっていた。おそらくリルケによる個々の作品評価はいまとなっては凡庸だろうが、そのことよりもロマン主義芸術観のわかりやすい(?)解説になっているところが、21世紀に読む意味があるのだろう。