同じ著者の「ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる」は中世からWW1までを一気に通観したが、本書では近世から近代までをみる。その歴史のメルクマールになるのは、フランス革命。この時代を音楽家を通してみるので、フランスやプロシャのような一国内の歴史とみることはできない。視点は西ヨーロッパを縦横に行き来し、同じ出来事を複数の立場でみることになる。なのでフランス革命も、王侯貴族vs市民だけでみるのではなく、周辺国の思惑と政策からみることになる。さらには、「自由・平等・友愛」のスローガンを思想史としてみるし、市民・民衆の精神の現れとしてもみる。読者には、ここに書いてあることを飲み込むにはたくさんの知識を求められる。
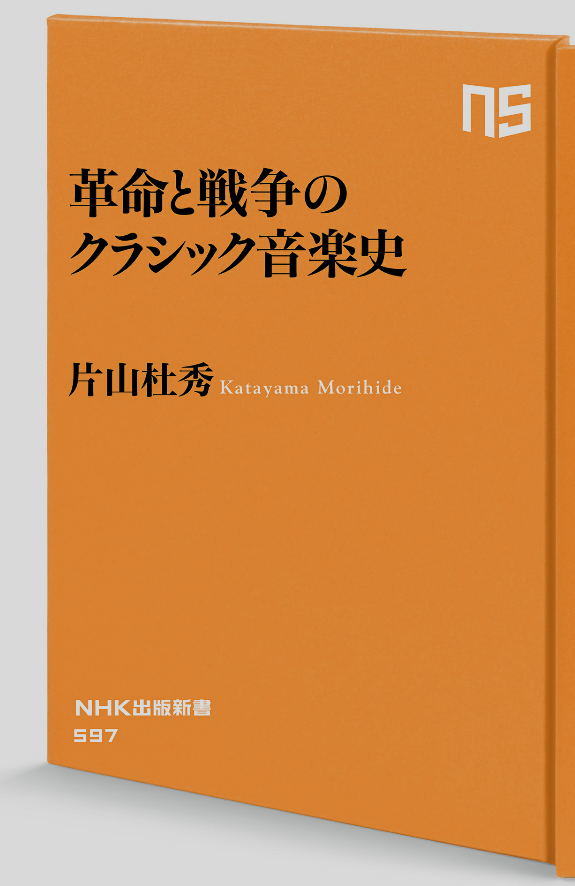
序章 暴力・リズム・音楽 ・・・ 音楽(ことにクラシック)は暴力的。近世・近代になってからは、戦争が音楽を変えてきた。戦争を描写し、新たな表現形式を生み出した。音楽のリズムは、人を同時に同じように動かし、強調した行動をさせるのに適しているから。例はベートーヴェンの「ウェリントンの勝利」、チャイコフスキーの「1812年」、ショスタコーヴィチの「レニングラード」。
(WW1のあと、戦争の描写は映画が担い、音楽はもっぱら新しい表現形式を磨くのにむかった。)
第一章 ハプスブルク軍国主義とモーツァルト ・・・ この章は「ドイツ」を対象にする。ハプスブルグ帝国については菊池良生「神聖ローマ帝国」講談社現代新書を参照。もう一つの話題のトルコ音楽について。16世紀になるとオスマン・トルコは東欧から中央にかけて侵略を開始。黒海からバルカン半島に入り、ウィーンを包囲する(1683年)。撃退されるが、18世紀までなんども進出を図る。それはプロシャやハプスブルク帝国などの軍国化を促進化することになる。1787年からの露土戦争では、ハプスブルク帝国も参戦し、ヨーゼフ二世はクリミア半島まで出征する。これらの経験でヨーロッパはトルコに関心をもった。音楽では、トルコ音楽の影響があって、管楽器と打楽器を使って大音響をだし威圧する風になった。ちょうどそのころ、モーツァルトは第1楽章が軍隊行進曲になっているジュピター交響曲を書いた。これはヨーロッパ諸国の軍国化の影響がある。
第二章 フランス革命とベルリオーズ ・・・ この章はフランスを対象にする。フランス革命では、自由・平等・友愛のスローガンが作られたが、自由と友愛は本来矛盾するけど、革命では自由を求める人は他人との協力・協調を求める(それが自発的に政治共同体に作られた)。このスローガンに基づく政治は土地や歴史に関係なく普遍的なので、革命は輸出できると思った。周囲の君主国は革命の輸出に恐れをなし、同盟を結んで対抗しようとしたが、緒戦では国民軍のフランスに負ける。恐怖政治を終えて復古になったが、1830年にはふたたび革命が起きて国王は逃亡する(こういうまとめのフランス革命史を読みたいがいいのはないか?)。革命と戦争の時代には、行進と野外イベントがつきもの。群衆は刺激を求める。そこで大オーケストラ(野外では吹奏楽)と大合唱による祭典・式典が頻繁に行われた。ゴセックやケルビーニなど。1830年に作られたベルリオーズの幻想交響曲には、このようなうるさくて刺激的で新しい革命の音楽が反映している(この交響曲の解説も片山風に書き換えられるべき)。
第三章 反革命とハイドン ・・・ ふたたび18世紀ドイツ。トルコのウイーン包囲があるなど、ハンガリー以西はトルコの領土。そこでハプスブルク帝国は西方に対する備えが必要。でも資本主義によって地代と年貢に依存する貴族は経済状況が悪化する。18世紀後半になると余裕がなくなって、雇っていた音楽家を解雇しなければならない。そこで音楽家は音楽教育を受けた貴族相手から、貴族趣味にあこがれる新興ブルジョア市民向けに作曲するようになる。典型例はハイドン。貴族向けに書いていた時は繊細で趣向を凝らしたものだったが、出稼ぎに出た倫敦で市民向けに書くと刺激的でうるさくてわかりやすいメロディの作品になった。ディッタースドルフが「バスティーユ襲撃」交響曲を書く際には革命歌「ラ・マルセイエーズ」を引用して、市民の関心を募る。
第四章 ナポレオン戦争とベートーヴェン ・・・ 革命とナポレオン戦争は大量死をもたらした(それまでの歩兵戦をフランスが砲兵戦に変えたのが大きな理由)。産業革命と都市化は貧困と騒音をもたらした。これらの野蛮を経験することで、市民の趣味が変わった(うるさい、上品、単純、行進向き、熱狂、共感、押し付けがましい、非洗練)。フランス革命の標語「自由・平等・友愛」をみると、自由は基本的人権の尊重を、平等は身分制廃止を、友愛は平和主義を政策とした。その先にあるのは、自由で平等な市民が集まり、マスの力を示すこと。その手段が手を取り合って歌うことだった。
(民主主義が成立すると、合唱運動が盛んになる理由。18世紀末のイギリス、19世紀半ばのフランスがそう。全体主義運動で人が集まると歌うようになるから民主主義だけに理由を求めるのはまずい)。
それをもっともよく現わしているのが、ベートーヴェン。とくに「フィデリオ」、ミサ・ソレムニス、第9。いずれも合唱が重要であり、個性をもった個人が妙技を披露するのではなく、集団で同じ歌を歌って高揚する作品だった。でも友愛によって集まる「みんな」は分割されたみんなであって、別のみんなに対抗する「みんな」でもあった。ナショナリズムが分断線=国境を引く理由であり、国内のマイノリティ差別を生み出す原因。
(第9を見ると、シラーの詩にカントの理想を仮託し、終楽章の二重フーガはヘンデルのオラトリオ風になり、第1楽章と終楽章にはハイドンの「天地創造」の影響があるとのこと。ベートーヴェンがひとりでこれらを発想したわけではなく、先人の技術を巧みに使っている。こういう編集能力のある人でもあった。20世紀前半にあったベートーヴェンを「努力の天才」とする評価は変えないといけないね。)
(イギリスはヨーロッパの周辺だったが、いち早く金融と貿易で資本主義化が進んで民主政治になった。とくに「自由・平等・友愛」のスローガンを掲げなくとも、政治体制で実現した。でもそれは奴隷貿易、中南米とインドのプランテーションから砂糖と綿を格安で輸入して高く販売する利益を前提にしていた。)
2024/06/04 川北稔「世界システム論講義」(ちくま学芸文庫)-1 世界システム論は、近代世界を一つの生き物のように考え、象徴としての「コロンブス」以降の世界はヨーロッパ世界システムの展開である 2016年
2024/06/03 川北稔「世界システム論講義」(ちくま学芸文庫)-2 ヨーロッパは政治的統合体を作らなかったから世界システムを作れた 2016年
革命と戦争が音楽を変えた、という認識で、1800年の前後60年の社会を通観する。音楽の変化を見ることはまことに革命と戦争をみることであったし、社会の変化に気づくことであった。あいにくほとんど「西洋音楽史」はこの変化をとらえることができない。作曲者個人のこととするか、せいぜい就職状況のせいにするか。
2016/10/20 パウル・ベッカー「西洋音楽史」(新潮文庫) 1924年
笠原潔「改訂版 西洋音楽の歴史」(放送大学教材)
笠原潔「西洋音楽の諸問題」(放送大学教材)
高橋浩子/中村孝義編「西洋音楽の歴史」(東京書籍)
2018/05/11 岡田暁生「西洋音楽史」(中公新書) 2005年
これはわずかに社会の変化に触れている。
2023/03/24 石井宏「反音楽史 さらば、ベートーヴェン」(新潮社)-1 2004年
2023/03/23 石井宏「反音楽史 さらば、ベートーヴェン」(新潮社)-2 2004年
音楽史の専門ではない著者(ではなにが専門家というとよくわからない)なので、学問への忖度なし。なので、ほとんどの「西洋音楽史」がふれない政治史、社会思想史、風俗などの膨大な情報を持ち込む。記述はむしろこちらのほうが多いので、俺は政治哲学の副読本みたいなつもりで読んだ。なので、本書の隣にあるとよいのはハンナ・アーレント「革命について」。ついでにフランス革命史と同時代の啓蒙主義の資料もあったほうがよいし、ウォーラーステインの世界システム論も参照できるようにしておきましょう。
革命と戦争が音楽を変えたという見方は、他の時代にも通用するか。その疑問の答えはたぶんNO。なるほどWW1のあと貧乏になった社会では大規模管弦楽の作曲はなくなり、室内楽程度の小規模曲になった(そうでないと上演できない)とか、WW2では戦意高揚の音楽が枢軸国・連合国でたくさん書かれたとかのトリビアをあげることができる。でもそれは音楽の分野のなかのできごとで、社会や政治とのかかわりをみたり、観客などの音楽のステークホルダーの影響をみることはできない。俺の見方では、革命と戦争が音楽を変えたのは、フランス革命の前後にのみ起きたのだ。
それはこの時代が近世から近代への大転換をおこしたこと。重要なのは、王侯貴族と聖職者階級とそれ以外の身分制が壊れた。人びとが階層と土地を離れて、上下左右に行き来するようになった。資本主義と国民国家が世界にあまねく広がり、富が集まる場所が変わった。王侯貴族と聖職者は没落した(といわれるけど、抜け目のよい貴族は土地を所有する資産家に変貌して、資本主義のプレーヤーになった)ので、かわりに市民(というが20世紀のような国籍と参政権保持者ではなく、資産家と職業組合構成員に限られる)が貴族趣味を持つようになった。こういう社会構成が変化し、身分制が消えて、資本主義のプレーヤーが変わったのだった。
もうひとつ重要なのは、貴族趣味にあこがれる市民にとって、芸術は世界観を構成する重要な項目であり、存在意義に関わる哲学的な問いであること。なので、市民は芸術を求め、解釈し、語った。芸術運動に聴衆も加わり、その影響を作曲者もすぐに受けた。こういう〈幸せな〉時代は1830年以降もあったが、資本主義が帝国主義になり、大衆化と都市化が進むにつれてなくなった(それを悲しいと主張するのがトーマス・マンとアドルノ)。
まことに「革命と戦争が音楽を変えた」のはこのとき一回限り。この観点で「ヨーロッパ」を見るのは面白い。
一応注意喚起すると、「革命と戦争が音楽を変えた」のはフランスとドイツとその周辺のごく限られた地域のできごと。すでに市民革命が終わり国民国家になったイギリスではそういう運動はなかったし、フランス革命と同時期に民主国家を作ったアメリカには芸術運動をする市民はいなかった(すでに大衆化していた)。フランス革命の影響はしだいにヨーロッパの周辺に伝搬していった。そこからナショナリズムの音楽運動もおきたが、先に変化を体験していたフランスとドイツの音楽を消化して、民族風にするものだったので(日本も同じ)、「音楽を変えた」 は起きなかった。それくらいに、稀有な出来事がある時代のある地域で起きたのだ。
片山杜秀「ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる」(文春新書) → https://amzn.to/4dWYCJ7
片山杜秀「革命と戦争のクラシック音楽史」(NHK出版新書) → https://amzn.to/45BSJz5
樺山紘一「《英雄》の世紀 ベートーヴェンと近代の創成者たち」(講談社学術文庫) → https://amzn.to/4kYacWu
かげはら史帆「ベートーヴェン捏造」(柏書房) → https://amzn.to/45WJQQq
小宮正安「ベートーヴェン《第九》の世界」(岩波新書) → https://amzn.to/3ZYoGh2