2025/08/27 テア・フォン・ハルボウ「メトロポリス」(中公文庫)-3 反資本主義と反機械で殺気立つモッブは民族中心の全体主義運動に絡めとられる。 1926年の続き
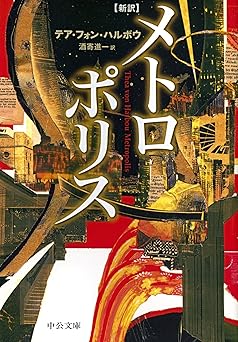
映画で最も印象的だったのは、機械人間のマリアでも、大げさなだけで無能なフリーダーの稚拙な恋愛でも、当時の未来イメージのメトロポリスでもない。同じ褐色の労働服と帽子をかぶり、猫背で下を向き力なく同じリズムでゆっくり隊列を組んで歩く労働者だった。

彼らは上部のエリート層の支配を受け入れている。労働は厳しいが(映画だと円形に配置された電球がひかったところに巨大な時計の針を合わせる作業なので、ブルシットジョブなのがとてもよくわかる。旋盤や溶接のような熟練を必要としないし、他人のスピードに合わせなければならず、自主的なところがまったくない)、

彼らは解放されるすべを知らない。いつか現れる救世主を待つだけ。受け身で愚痴をたれるばかり。工場長にはときに文句をいうが、パネル越しの命令に逆らうことはない。根無し草で、住んでいるところ(はこの映画には全く登場しない)は生まれた所ではないので愛着はないし、労働に疲弊して死んでしまえば廃棄させられるからその地に魂や霊が留まることはない。

そういう労働者は、架空の存在なのではなく、この国でも見られるものだなあ。初めてこの映画をみたのは20代前半だったが、自分の人生を暗示しているようで、共同トイレで風呂がない自分のアパートを眺めて慄然としたものだったよ。
さて映画はワイマール共和国の時代の1927年に発表。ジョージ・スタイナーは「ハイデガー」(岩波現代文庫)の序文で、1920年代ドイツで黙示的な大作があいついで書かれたことに注目する。ブロッホ「ユートピアの精神」1918年、シュペングラー「西洋の没落」1918年、バルト「ローマ人への手紙注解」1919年、ローゼンツヴァイク「救済の星」1921年、ハイデガー「存在と時間」1927年、ヒトラー「我が闘争」1925年。以上は「全体」志向で予言的でユートピア的という共通性をもつ。自分はこれにトーマス・マン「魔の山」1924年も追加したい。そこにラング-ハルボウの「メトロポリス」も加えるのだ。
「メトロポリス」の暗さ、憂鬱、破壊衝動、機械による支配の嫌悪、正体を見せない命令への服従はまさに黙示的(もちろんそこにはワイマール共和国が置かれている国際情勢も反映しているだろう)。そして閉鎖空間の中で複数の階層が分離しながら統一国家を作っているのは「全体」志向だし、最後に至っても脱出や解放が訪れないのもユートピアにふさわしい。ラング-ハルボウの創作は上記のテキスト群の映像化と俺は見る。それは次の10年代に起きた全体主義運動、ファシズム運動を予言しているのだ。
テア・フォン・ハルボウ「メトロポリス」(中公文庫) → https://amzn.to/40XEmBF https://amzn.to/3IAQSAY