2022/08/18 堀田善衛「ミシェル 城館の人2」(集英社文庫)-2 1992年の続き
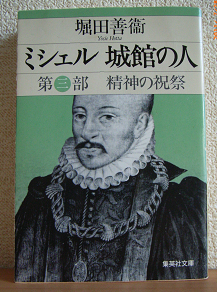
率直に言えば、堀田善衛の著作は敬愛するところ多々とはいえ、通読するのに困難が時に起こる。「ゴヤ」がそうで、この「ミシェル 城館の人」でも2巻の中ほどで半年以上放置していたのであった。その理由が、本書第3巻でわかる。すなわち堀田善衛自身がモンテーニュのような現在進行形で人間を見直す試みをしていて、体系的であろうとはけっしてせず、人間の行いを観察することに徹底し、日常の実践に資するように仕立てているからである。これらの語句は堀田がモンテーニュに向けたものであるが、読み返すとそれは堀田善衛自身の方法を示したことにほかならない(事実、堀田は戦時中にモンテーニュの「随想録」を「方丈記」などと一緒に繰り返し読み、深甚とした影響を受けていることを本書に記している)。俺のように安易にものごとを解決し、白黒をつけたがり、思考の過程を重視しないものには、モンテーニュも堀田善衛も難解になるのであった。
では思考を体系化しなかったモンテーニュの重要性はどこにあるかであるが、堀田がエレガントにまとめている。40代(第2巻のころ)は懐疑主義を旨とするのであるが、相対主義や判断停止に陥りかねない。
「相対主義が最終的に到達するのは、現実においては、せいぜいのところで社会的価値、あるいは判断を停止することによって、結局はまわりに合わせる、という程度のことであった。しかし、それだけでは思想の名に価しないのである。」(P419)
1980年代以降に相対主義がリベラルにも保守にもシニシズムにも蔓延して、人権尊重や社会的弱者救済などの活動に相対主義で水を注しているのを見ると、この指摘はもっと知られなければならない。どっちもどっちの行く末が現状肯定・変化の嫌悪になるのをみると。で、モンテーニュは相対主義の罠に落ち込まないためには、他人と話し合えという(実際、モンテーニュは貴族なのに農民・家人と、カトリックなのに異教徒と話し合いをするのであった。結論をだすのではなく、考えを押し付けるのでもなく。モンテーニュは自尊心を振り回すな、地位や見せかけに惑わされるななどの話し合う際の諸注意をしている。これができないから俺には堀田善衛もモンテーニュも難解になるんだな)。理性を懐疑したとしても、これらの個人的体験は疑いようもないから、そこにあった人間そのものとしてものを言えという。一般法則をたてるのではなく、日常の実践に資するように仕立てて。
「彼の思想、道徳の要諦は、人間性を、たとえば大きな樹木――深く根を張りつめ、天空を蔽わんばかりに枝葉茂らせた大きな樹木のように、精蹄神的にも肉体的にも、理性的にも感覚的にも十全に発展させ、かつ平均のとれた伸ばし方をすることにあった。そして大きな樹木がそうであるように、つねに地上に立っていることにあった。天上や地獄は、彼にとっては無縁のものであった。(P416)」
「人生という大樹をして十全に、根をはり、幹を整え、枝葉をして天まで伸ばさせよ。(P418)」
「天上や地獄」というのは当時影響のあったスコラ哲学のこと。彼にって重要なのは自分自身であり、そこから敷衍される人間という存在。エラスムスなどの同時代のユマニスト(人文学者)と違うのは、キリスト教をベースに考えていないところ。
「ヨーロッパのほとんどすべての人々が、カトリックかプロテスタントかということでかたみに殺裁し合っていたときに、目を大きくひらいて外にも向うことの出来る、自由闘達な精神がモンテーニュの城館の中にいた。しかも、この外に向けられた目もまた内省の一部であった。/こういう人をこそ、世界人、あるいは世界市民と呼ぶのであろう。(P430)」
モンテーニュにとってのモラルは、生きること、「人間の生活をその自然の性状にふさわしく営むこと」、精神、肉体、感覚、理性などを十全に伸ばす、宇宙的に展開することであった(ここで自分のぼんくらを披露してしまうと、こういう「人間性」「ユマニティ」などはよくわからない概念であるのだ)。通常、西洋にかぎらず世の哲学思想宗教は自然の性状にふさわしく営むにはやっかいな欲望や情念を抑えつけたり克服したりしようとするが(ワーグナー「パルジファル」のクリングゾルのように去勢までするのもいる)、モンテーニュは無理はせず、避けることを奨励する。モンテーニュは肉体を嫌悪しない。実際若いころのモンテーニュは多くの女性と艶聞をもったのだし(このあたりの記述はのちのローマ教会が問題にして、発刊から約100年後の1676年に「エセー」は禁書目録に加えられた)。
堀田善衛はこのようなモンテーニュの考え方ややり方に新しさを見出す。なるほど、堀田の手引きでみると、モンテーニュは200年後のフランス革命に書かれたものと遜色ない。最後の肉体賛美や欲望の肯定などはミラボー伯の「肉体の扉」やサドの著作に引き継がれるのだろうとさえ思う。
この感想では、モンテーニュの生活をあまりみなかったが、著者はうまくまとめている。あれかこれかの二項であるのではなく、対立するものが混在するのが近代だなあ。
「法官貴族でありながらも、若き日のミシェルは可成りな遊び人でもあった。/田園への引退者でありながら、王の側近であり、公人であり王臣であった。/貴族でありながら、庭師や農民たちと話すことを好んだ。/シャルル九世、アンリ三世の侍従武官でありながら、ナヴァール公の側近でありかつ助言者でもあった。(P436)」
堀田善衛「歯車・至福千年」(講談社文芸文庫)→ https://amzn.to/3TzIzHm
堀田善衛「広場の孤独」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3TyWLk4 https://amzn.to/3vunHt2
堀田善衛「歴史」(新潮文庫)→ https://amzn.to/4aukzfv
堀田善衛「記念碑」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3vwOipy
堀田善衛「時間」(新潮文庫)→ https://amzn.to/43EXW6a
堀田善衛「奇妙な青春」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3vvIBbi
堀田善衛「インドで考えたこと」(岩波新書)→ https://amzn.to/4cwhiOP
堀田善衛「鬼無鬼島」(新潮日本文学47)→ https://amzn.to/3xoefrC https://amzn.to/3TDmlnO
堀田善衛「上海にて」(筑摩書房)→ https://amzn.to/3PJCGWX
堀田善衛「海鳴りの底から」(新潮文庫)→ https://amzn.to/4axgGX8 https://amzn.to/3TVq5Th https://amzn.to/3TVEq1G
堀田善衛「審判 上」(集英社文庫)→ https://amzn.to/43ANAUB
堀田善衛「審判 下」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IWDkN5
堀田善衛「スフィンクス」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3TUfg3G
堀田善衛「キューバ紀行」(岩波新書)→ https://amzn.to/4cwhvBB
堀田善衛「若き日の詩人たちの肖像 上」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3vwEPOW
堀田善衛「若き日の詩人たちの肖像 下」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3TCxbKR
堀田善衛「美しきもの見し人は」(新潮文庫)→ https://amzn.to/4cvGTat
堀田善衛「橋上幻像」(集英社文庫)→ https://amzn.to/49jslYK
堀田善衛「方丈記私記」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3IUqfDR
堀田善衛「19階日本横町」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3TB9PoT
堀田善衛「ゴヤ 1」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3TzknEX
堀田善衛「ゴヤ 2」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3TTnXLs
堀田善衛「ゴヤ 3」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3IRZj7U
堀田善衛「ゴヤ 4」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3vwOogU
堀田善衛「ゴヤ」全巻セット(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3vwPNE1
堀田善衛「スペイン断章〈上〉歴史の感興 」(岩波新書)→ https://amzn.to/49k7RPr https://amzn.to/3xlcrzG
堀田善衛「スペインの沈黙」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/3J0K508
堀田善衛「スペイン断章〈下〉情熱の行方」(岩波新書)→ https://amzn.to/4ar4JD7
堀田善衛「路上の人」(新潮文庫)→ https://amzn.to/49e9vlJ
堀田善衛/加藤周一「ヨーロッパ二つの窓」(朝日文庫)→ https://amzn.to/3IRZCzA https://amzn.to/43xqSwR
堀田善衛「歴史の長い影」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/4ae0ydy
堀田善衛「定家明月記私抄」(ちくま学芸文庫)→ https://amzn.to/3PE2vaW https://amzn.to/3VU2Muv
堀田善衛「定家明月記私抄 続編」(ちくま学芸文庫)→ https://amzn.to/3PGKWHn
堀田善衛「バルセローナにて」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3PEoI8Q
堀田善衛「誰も不思議に思わない」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/4ai7hDu
堀田善衛「ミシェル 城館の人1」(集英社文庫)→ https://amzn.to/4cBgKHc
堀田善衛/司馬遼太郎/宮崎駿「時代の風音」(朝日文庫)→ https://amzn.to/3IYDbsx
堀田善衛「ミシェル 城館の人2」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IVZ9w5
堀田善衛「めぐりあいし人びと」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IREiKB
堀田善衛「ミシェル 城館の人3」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3PH4tat
堀田善衛「ミシェル 城館の人」全巻セット(集英社文庫)→ https://amzn.to/4acvVVZ
堀田善衛「ラ・ロシュフーコー公爵傳説」(集英社文庫)→ https://amzn.to/49k7DYB
2022/08/04 堀田善衛「ミシェル 城館の人3」(集英社文庫)-2 1994年に続く