2022/09/01 堀田善衛「ゴヤ 3」(朝日学芸文庫)-2 1975年の続き
「彼ら(民衆)が立ち上って戦ったのは、ナポレオンの新しい軍事雫専制主義に対してであって、フランス革命の精神に対してではなかったのであることが社会的に次第にはっきりしてきていた(P10)」
アーレント「革命について」を援用すれば、スペイン人は憲法を作る体験をしたのであった。
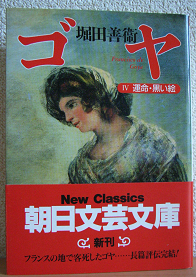
反動・弾圧・迫害 ・・・ 戦争終結。フェルナンド7世が帰還し、憲法を保護にし、「超反動絶対専制君主政治」に戻す。密告が奨励され、弾圧・迫害が続く。経済が停滞し、植民地が愛想をつかして独立する。6年後に反乱が起きる。
フェルナンド七世・査問・粛清 ・・・ ゴヤは親仏派とみなされ調査されたが、一方王その他の肖像画注文が多数入る。豪華絢爛で不愉快な肖像。
″国家悪により追放さる″ ・・・ 政権の右往左往は肖像画の制作にも影響がある。大物政治家の肖像画の完成直前に、政治家が国外追放になったので、タイトルの文字が書き加えられた。次は俺の晩かもしれない。
『王立フィリピン会社総会』 ・・・ フランス革命は激烈な価値の転換、転倒をもたらした(貴族と聖職者の時代から退屈なブルジョアジーの時代へ)。タイトルの巨大な絵のような空無な政治空間が生まれる。フランス革命自体は文化の革命を行さなったが、革命の周辺では影響を受けた。それをみるに、
「新古典主義者諸氏もまた、大革命、恐怖政治、ナポレオン独裁、ルイ十八世復活などの、諸価値の転倒、再逆転などの思想的辛酸を経て来ているのである。/しかし彼らは(略)その長きにわたる危機状況を、美あるいは理性の定立ということを先に立て、そこで、美、あるいは完壁性というものを法則的な古典、古代に見るという迂廻路を経ることによって切り抜けて来ていたのである。/ゴヤが断乎として拒否したものは、その迂廻路そのものであった(P80-81)」
(18世紀後半、モーツァルトも入る新古典主義の説明では瞠目すべき見解!)
「空無の大空間のような思想的空白時には、人は、これも前記総会図中の人物たちのように無駄なお喋りで時を過すか、それともスペインをも含む多くのロマンティクのように「宇宙は夜の闇のなかに沈んだ」(ネルヴァル)として絶望するか、どちらかになりやすいものであったが、われわれの精力的な老人は、耳が聞えないせいがあって前者にはなりえず、またアラゴンの岩沙漠の真の闇の怖しさを知る者としてロマンティクではありえなかった(P79)」
(駄弁にふけらず、ロマンティックにもならない芸術家は他にベートーヴェンくらいという指摘も瞠目すべきもの。ともに聾者であるということも。)
「「血みどろの戦争」の、もろもろの宿命的結果のなかでも、もっとも「宿命的」であったのは、もっとも勇敢に戦った者たちが、戦争が終った後に、もっとも非道い目に遭わされたことであった(P84)」。
それを想起させるための空無を描いた巨大な絵。このように読み取る堀田善衛の見ることのすさまじさ。圧巻。(思い返せば、作家もまた1945年の東京と上海で同じ光景をみたのであった)
版画集『闘牛技』 ・・・ 過酷な政治状況ではあっても人が娯楽を求めるのは自然。ゴヤもタイトルの版画集をだす。注目するのは民衆、平民を登場していること。当時の新古典主義ではありえない異常なこと、だそう(そうするとモーツァルトのダ・ポンテ三部作オペラも民衆が登場する異常なものであった)。もうひとつは、動・瞬間の写し取り、光と影の対比、物語がないこと。これらは当時としては絵画ではなく、印象主義やその後の芸術の先取りになる。
地下画帳 観察・記述・批評 ・・・ ゴヤが描いたデッサンを見る。半島戦争、その後の反動政治での弾圧などで起きた残虐行為、拷問など。
「人間がもつもっとも本質的な悪の一つは、人間が人間に対して犯す悪を直視し、これを表現しきる勇気と技術を欠いていることである(P208)」
第4巻の前半は引用ばかりになってしまった。作家の指摘は目からうろこばかりなので、血肉にするためにメモを残さなければならない。自分の関心が歴史にあるので、「地下画帳 観察・記述・批評」に書かれたゴヤの心情に関する指摘には無頓着になってしまった。
世の中は暗い。反動により民衆は隠れなければならない。密告に怯え、逮捕されれば拷問される。経済はしっちゃかめっちゃかで、体制側といえどもまともに給与を払えない。イギリスは支援名目で高い値段で売り、国内の物流は滞る。酒で憂さを晴らそうにも、酒がない(たらふく飲む経験をスペイン人はしていないのだって)。ゴヤはとりあえず宮廷画家の称号を持っていて、ブルジョアや高給軍人、政治家等の依頼があるので生活には困らない。ゴヤのしたたかで冷徹なのは、売る見込みがなく、見つかれば逮捕・投獄される社会批判、政治批判、体制批判の絵を描き続けたこと。
堀田善衛「歯車・至福千年」(講談社文芸文庫)→ https://amzn.to/3TzIzHm
堀田善衛「広場の孤独」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3TyWLk4 https://amzn.to/3vunHt2
堀田善衛「歴史」(新潮文庫)→ https://amzn.to/4aukzfv
堀田善衛「記念碑」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3vwOipy
堀田善衛「時間」(新潮文庫)→ https://amzn.to/43EXW6a
堀田善衛「奇妙な青春」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3vvIBbi
堀田善衛「インドで考えたこと」(岩波新書)→ https://amzn.to/4cwhiOP
堀田善衛「鬼無鬼島」(新潮日本文学47)→ https://amzn.to/3xoefrC https://amzn.to/3TDmlnO
堀田善衛「上海にて」(筑摩書房)→ https://amzn.to/3PJCGWX
堀田善衛「海鳴りの底から」(新潮文庫)→ https://amzn.to/4axgGX8 https://amzn.to/3TVq5Th https://amzn.to/3TVEq1G
堀田善衛「審判 上」(集英社文庫)→ https://amzn.to/43ANAUB
堀田善衛「審判 下」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IWDkN5
堀田善衛「スフィンクス」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3TUfg3G
堀田善衛「キューバ紀行」(岩波新書)→ https://amzn.to/4cwhvBB
堀田善衛「若き日の詩人たちの肖像 上」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3vwEPOW
堀田善衛「若き日の詩人たちの肖像 下」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3TCxbKR
堀田善衛「美しきもの見し人は」(新潮文庫)→ https://amzn.to/4cvGTat
堀田善衛「橋上幻像」(集英社文庫)→ https://amzn.to/49jslYK
堀田善衛「方丈記私記」(新潮文庫)→ https://amzn.to/3IUqfDR
堀田善衛「19階日本横町」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3TB9PoT
堀田善衛「ゴヤ 1」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3TzknEX
堀田善衛「ゴヤ 2」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3TTnXLs
堀田善衛「ゴヤ 3」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3IRZj7U
堀田善衛「ゴヤ 4」(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3vwOogU
堀田善衛「ゴヤ」全巻セット(朝日学芸文庫)→ https://amzn.to/3vwPNE1
堀田善衛「スペイン断章〈上〉歴史の感興 」(岩波新書)→ https://amzn.to/49k7RPr https://amzn.to/3xlcrzG
堀田善衛「スペインの沈黙」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/3J0K508
堀田善衛「スペイン断章〈下〉情熱の行方」(岩波新書)→ https://amzn.to/4ar4JD7
堀田善衛「路上の人」(新潮文庫)→ https://amzn.to/49e9vlJ
堀田善衛/加藤周一「ヨーロッパ二つの窓」(朝日文庫)→ https://amzn.to/3IRZCzA https://amzn.to/43xqSwR
堀田善衛「歴史の長い影」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/4ae0ydy
堀田善衛「定家明月記私抄」(ちくま学芸文庫)→ https://amzn.to/3PE2vaW https://amzn.to/3VU2Muv
堀田善衛「定家明月記私抄 続編」(ちくま学芸文庫)→ https://amzn.to/3PGKWHn
堀田善衛「バルセローナにて」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3PEoI8Q
堀田善衛「誰も不思議に思わない」(ちくま文庫)→ https://amzn.to/4ai7hDu
堀田善衛「ミシェル 城館の人1」(集英社文庫)→ https://amzn.to/4cBgKHc
堀田善衛/司馬遼太郎/宮崎駿「時代の風音」(朝日文庫)→ https://amzn.to/3IYDbsx
堀田善衛「ミシェル 城館の人2」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IVZ9w5
堀田善衛「めぐりあいし人びと」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3IREiKB
堀田善衛「ミシェル 城館の人3」(集英社文庫)→ https://amzn.to/3PH4tat
堀田善衛「ミシェル 城館の人」全巻セット(集英社文庫)→ https://amzn.to/4acvVVZ
堀田善衛「ラ・ロシュフーコー公爵傳説」(集英社文庫)→ https://amzn.to/49k7DYB
2022/08/29 堀田善衛「ゴヤ 4」(朝日学芸文庫)-2 1977年に続く