福音書の成立に関する知識(共観福音書とかQ資料とか)はあった。新約聖書27篇が選ばれたのはイエスの死後300年もたってから。その間に、たくさんの文書が作られたのは知っている。邦訳にも、 聖書「新約聖書外伝」(講談社文芸文庫)がある。そういうのを読んで、多少はイメージをもっていた。初期キリスト教のことは知らないのがわかって、本書を入手。自分の無知を反省。ページごとに教えられることが多数あって、メモするだけで大変な分量になってしまう。それでも頑張って要約を作ろう。
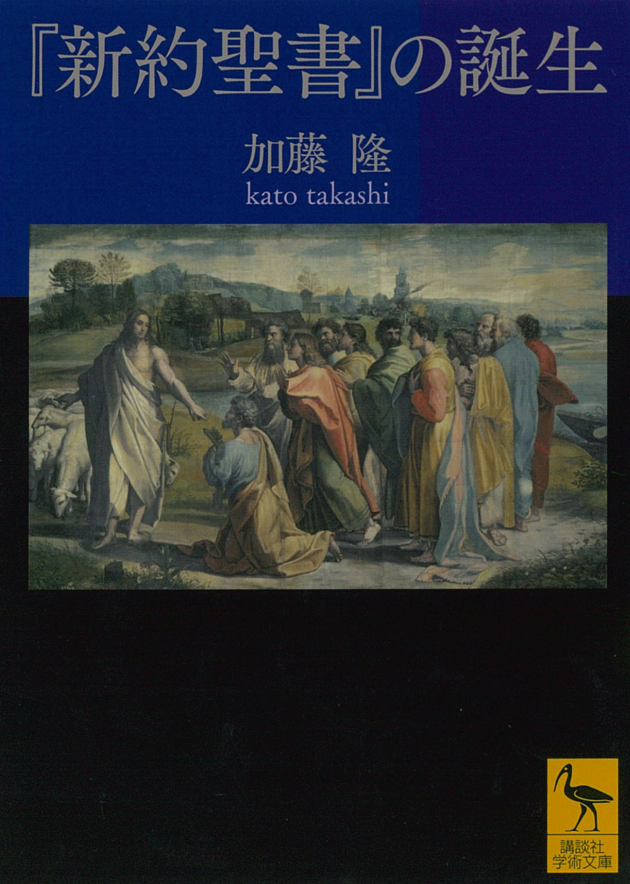
・イエスの時代、ユダヤ人の王国は、ペルシャ、ギリシャ、ローマ帝国の支配下にあること600年。ユダヤの神ヤーヴェは創造神で救済神であるが、ずっと沈黙しているのでユダヤの民は神に見捨てられていると思うものも出てくる。そこでユダヤ教は神は民を見捨てることはなく「救い主」を遣わし介入すると考えた。この前のころからギリシャ語圏になり、ユダヤ教典がギリシャ語に翻訳されだす。
・ローマ帝国はユダヤ人(全人口の1割くらい)に統治させていたので、利害関係ができて、ユダヤ人は一枚岩にはならない。ローマの傀儡から独立派まで。エリート主義の閉じこもりから無関心まで。ユダヤ教も民族主義が強いと差別的になり、普遍主義が強いと開放的になる。アラム語とギリシャ語話者が混在。
・イエスの時代のユダヤ教では、いくつかのグループができていた。1.サドカイ派:現状維持、富裕層、政治的には日和見。2.エッセネ派:現状維持、儀式の厳格化、修行者のコミューン、エリート主義。3.ファリサイ派:立法主義、中流以上の知識人層、ユダヤ人内の差別拡大。4.ゼロテ(熱心)派:独立運動志向の国粋主義者、テロ、セクト化。5.ヘロデ派:ローマの傀儡。6.一般ユダヤ人層:被差別当事者。とくに宗教的であったわけではない。(以上は福音書に登場するので、違いを知っておいた方がよい。イエスたちはそのグループにも喧嘩を売っていたね)。
・ユダヤ教とユダヤ人の改革者が生まれる。ヨハネとイエス。ヨハネは荒野で人を待っていたが、イエスは民のなかに積極的に入り、ユダヤ人社会の差別撤廃に動く。罪人(刑法犯のことではない。被差別者や貧困者などユダヤ教のルールを守れないので神の救済から漏れてしまう人たち)とのかかわりを重視。活動は教えと癒し、そして弟子集め。イエス運動がユダヤ人社会で問題視され、最高処罰である十字架刑となった。問題になったのはユダヤ教の指導者の権威を認めないこと、神殿の権威を認めないこと。それだけ敵視、危険視されていたのだね。
(福音書や使徒行伝などのテキストから入ると、イエスが語ったことばにばかり関心をもって、イエスが何を語ったかを考えるのだが、こういう活動@アーレントに気づかない。活動@アーレントを小さいことに思い込んでしまう。それじゃダメじゃん。これらのテキストからイエスがなにをしたかを見ることは大事。テキストから入ると、ユダヤ人社会の差別撤廃に動き、罪人の中に入っていったことが見えなくなる。)
・直系の弟子を含む少人数がイエス運動を再開。エルサレムに共有財産制の共同体(エルサレム共同体と便宜上呼ぶ)を作る。定着するもものもいれば、巡回布教にでるものも。そのさいに十字架刑と復活は、神がイエスの権威を認めたことであるとした。イエスを知らない人のために、超自然的な出来事を納得させるために、ユダヤ教聖書の権威を利用した。その際に知識人が作業した。ユダヤ人の指導者の権威は認めないが、聖書の権威は(便宜的に)認めた。
(復活は神がイエスの権威を認めたことは、溝田悟士「「福音書」解読」講談社選書メチエでも強調されていたので参照しよう。)
・ギリシャ語を話す人が加わるにつれて、神殿の権威を認めるものとそうでないもの(ヘレニスト)のグループができ、エルサレム共同体は分裂する。おりからユダヤ人やローマ帝国の迫害が強化。AD30年前半。分裂でエルサレム教会を率いたのは「主の兄弟」ヤコブ。分裂したグループで大きかったのは回心者パウロのグループ。このグループは異邦人がキリスト教徒になることを容認し、律法を守ることは不必要とし、代わりにピスティス(信仰とか忠義とかに訳される)を求める。この考えを打ち立てるために、パウロは聖書の権威を利用したが、聖書のテキストの一部を無視しているし、倫理基準などを提示しなかったので、彼の組織は無秩序に陥りやすかった(なので、パウロは各地の宗教共同体を回って直接働きかけたが、行けないところには手紙を書いた:なお本書の著者はパウロの手紙は宛先限定で問題限定で書いているので、神学論文ではないという。なので、パウロの手紙に彼の神学論があると読むのは危ないという。)
(パウロの考えを本書は批判している。ポイントは「信じる者は救われる」には欺瞞があり、「十字架における罪の許し」は罪に矛盾が生じるというもの。神学の議論はここではスルー。俺が重要だと思うのは、神を信じるを宗教共同体を信じるに転化して、教会への忠義(というか服従)を要求するようになったというところ。ああなるほどと思うし、ドスト氏の「大審問官」はパウロ批判であったのだという発見にもなった。)
(トリビア。コスモポリタンはさまざまな民族が混ぜ合わさった状態をいい、帝国支配のような広大な地域で平和が維持されている、とくに都市で実現するという。俺はコスモポリタニズムに帝国主義や全体主義などがあるようであまり賛同できなかったが、そのわけがわかった。たとえばアニメ「宇宙戦艦ヤマト」でガミラス帝国を撃退した後にできた「地球連邦」は地球ひとつを支配する帝国そのものだ、とか。)
イエスが十字架刑で亡くなるまでの概要を本書からあげると
・紀元前6世紀ころからパレスチナは周辺の帝国の支配下にあって、ユダヤ人は政治的な自由を失っていた。独立の試みも失敗続きだったので、イエスが生まれるころには政治的には支配を受けいれ現状維持を図る保守化していた。ユダヤ教も律法を守ることを要求する保守化になっていた。
・イエスはユダヤ教の改革運動者の一人。口承で教えを伝え、テキストを作ることはなかった。
・イエスの死後、改革運動は分裂する。ユダヤ教からの迫害も起きる。非ユダヤ人にキリスト教信者が増える。
イエスの神の王国をつくる運動は、もともと積極的な布教と共同体創設にあった。イエスの存命中は自分でいけるところに限られていたが、没後は積極的にパレスチナの外に出ていった。ペテロとパウロの二人がよく知られている。なので、どこに行ってどこに拠点を作ったのかは重要だが、このサマリーでは割愛。
イエスや福音書の解説本を読んでいると、テキストの異同にばかり目がいって、地域のひろがり・信者の民族や使用言語の差異などに関心をもたなくなる。本書で補完することは大事。
溝田悟士「「福音書」解読」(講談社選書メチエ) → https://amzn.to/43EqHjQ
土岐健治「死海写本 『最古の聖書』を読む」(講談社学術文庫) → https://amzn.to/3SRdH5b
山形孝夫「聖書の起源」(ちくま学芸文庫) → https://amzn.to/3FjvyyE
加藤隆「『新約聖書』の誕生」(講談社学術文庫) → https://amzn.to/4mvsGPZ
加藤隆「一神教の誕生」(講談社現代新書) → https://amzn.to/3H6qKgr
加藤隆「キリスト教の本質 「不在の神」はいかにして生まれたか」(NHK出版新書 → https://amzn.to/3H940wu
2025/06/19 加藤隆「『新約聖書』の誕生」(講談社学術文庫)-2 キリスト教の拡大は無秩序をもたらしたので、テキストを作り平準化を図る。統一的理解が困難な聖書の権威をささえるのは教会の権威。 1999年に続く