この30年間の生命科学の発展がよくわかる本。1980年代にヒトのゲノム解析をするのが国家プロジェクトになったのだが、数十年がかりで多数の研究者を必要とすると思われていた。それがシーケンサーの発明によって塩基配列決定が短時間でできるようになった。おかげで数十年どころか21世紀が始まる前に終了してしまった。微量のDNAでも複製できるので、微量物質の挙動がわかるようになった。この「革命」が起きたのは1990年代だが、それ以前に生物学の専門教育を受けた自分は、まったく浦島太郎になってしまったと思ったよ。
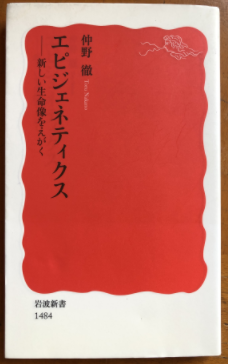
ふるい生物学ではDNA→RNA→タンパク質のセントラルドグマは強固であり、生物の形質はこれで説明できると思っていた。しかし、遺伝子の突然変異がなくても、形質(表現型)は変わるのであり、安定的に受け継がれる(相貌分裂によって消滅しないで同一個体に残るという意味。次世代に受け継がれるかは議論がある)ことがある。それをエピジェネティクスという。まずここで目からうろこ。たとえばヒトには数万個の遺伝子があるが、それがすべて稼働していると、個体間の差異はないことになる。でも個体間の差異はあるわけで、それをふるいセントラルドグマでは説明できない。でも、エピジェネティクスの事例がみつかることで、遺伝子の変異はなくても、DNAがメチル化(-CHが-CH3に置き換わる)ことで、その遺伝子は発現が制御される。あるいはDNAを三次元的に巻き取っているヒストンの一部が化学的に修飾されると、その遺伝子は発現が制御される。このメチル化とヒストン修飾は個体の状態によってさまざまである。すると、ほぼ似たような個体であっても、表現型が様々になる。メチル化とヒストン修飾は遺伝子の変異や染色体異常のようにまれなことではないで、誰にでも起きている。たとえば、春化処理をすると秋に発芽する麦を春に発芽させることができる。受精卵はどのような器官にも分化できる可能性を持っているが、一度分化した細胞は特定の機能しか持たない(特定の遺伝子しか発現しない)。あるいは、低栄養状態にさらされた胎児や十分に成長できないで出産された未熟児などは、長期的には特定疾患に罹患した割合が有意に増えている。これらは環境のせいとか成長のせいとかあいまいな説明しかできなかったが、メチル化とヒストン修飾という科学的な厳密さで説明できるようになる。ということは、特定疾患の治療にエピジェネティクスを利用したり、出産や子育てを支援する政策に取り上げることが可能になっている。
(エピジェネティクスの遺伝は今のところ否定的。獲得形質をひろくとっても「ラマルク説」は復活しそうにないみたい。)
2016/09/15 ジャン・ラマルク「動物哲学」(岩波文庫)-1 1809年
2016/09/14 ジャン・ラマルク「動物哲学」(岩波文庫)-2 1809年
でも著者は未来像を描くにあたっては慎重。つまり、エピジェネティクスは生命現象全体からすると小さい影響しかないし、産業化できる規模や範囲もそれほど大きくはないのではないかと主張する。未知の現象を科学者が説明するときには、大風呂敷を広げるものだが(そのほうが政府の支援や企業の商業研究が期待できるから)、ちゃんとみきわめる。科学者が大風呂敷を広げると、専門教育を受けていないものはよしあしを判断しないで、流されてしまうから(STAP細胞とかほかいろいろ)。
もうひとつ好感なのは、科学史や科学論をきちんと調べているところ。教養をもって上品さ(ディーセンシー)を保とうとする。その謙虚さは、むやみに「新しい生命観」を振りかざすような元研究者のエッセイストにはみられない。エピジェネティクスの詳細な説明は大学の専門課程レベルになるし、専門外にはトリビアになるので、正偽を区別することはできないが、記述から見えてくる姿勢で信頼できるのがわかる。
仲野徹「エピジェネティクス」(岩波新書) → https://amzn.to/4pzzv4k